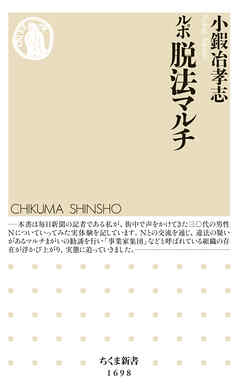あらすじ
2021年春。高円寺の駅前で、道行くひとに「いい居酒屋知らない?」と声をかけまくる男二人がいた。東京に異動してきたばかりの著者は、誘いに応じてついていく。そこから浮かび上がったのは、マルチまがいの手法で金を巻き上げる「事業家集団」と呼ばれる組織の存在だった。毎日新聞記者が、被害の実例や組織内部の資料から、脱法マルチの実態に迫るルポルタージュ。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
痛いなぁ、、、イタイじゃなくて、心が痛くなる一冊。
やっぱり若い人が狙われてしまうんだよね、こういうマルチは。
はるか30年前、自分が新入社員だった時に、新入社員研修中にアムウェイ勧誘してる奴がいた。未来への不安、新たな環境への不安、そういったところに 容易につけこまれるんだよね。
僕はたまたま、マルチに関する本とかを呼んでいたから無視したけど、純真無垢な、真面目な人ほどのめり込んでしまうと思う。
手っ取り早く金を稼げるように見えてしまうし、何よりも自分が否定されない、プラスなことしか言わない、輝く未来が約束されてるような、バラ色の未来をすり込んでしまうんだよね。
その頃と比べて今のマルチは、法律的な問題を潜り抜け、より、たちが悪いと思う。
この書籍は、高校教育の副読本として採用されるべきじゃないだろうか?
Posted by ブクログ
学生、新社会人への副読本として推奨すべき本。
繋がりに間を噛ませて責任の所在は無くす集金システムを開発したトップの方(書面回答もある)の知能の高さが窺える。
居酒屋聞かれたら「ググれ!」の一言だけど、いつの間にか師匠に紹介されているところからもシステム化されているのだろう。
恐ろしいのは集団の時に居た方が精神的苦痛はまだ少ないところ。これも始めは利害抜きの心地良い人間関係を構築させているところで上手いと思う。
ある意味金持ちになるノウハウ本ともいえる。
Posted by ブクログ
カルトとマルチのハイブリッド型。
人の心のスキマに入り込む巧妙さ。
そして全ては「自己決定した」で片付けられる。
茹でガエル状態。正にこの世の地獄だと思い身震いした。
正しい情報が正しい場所に届いて一人でも多くの人が救われることを願ってやまない。
Posted by ブクログ
「ルポ」というと「潜入ルポ」のイメージが強いためなのか、どこかでそのような宣伝のされかたがなされているためなのか、本書に対して、「潜入度が弱い」という批判を見かけたことがある。しかし、私自身の感想としては、新聞記者として、できる限りの地道な取材をして書き上げられたルポルタージュであり、そのような批判は的外れなのではないか、という印象だ。
もちろん「潜入度」を求める読者にとって、期待外れな感じがあるのは否めない。
「いい居酒屋知らない?」と言われてついていって、「いいカモ」として認定されたであろうところまでは「潜入」しているけれど、そこから先に誘われたであろう全国大会やセミナーには「潜入」できていないからだ。
しかし、新聞社の調査報道として、法律に抵触しかねない組織活動、そうでなくても、どこかにいる誰かの苦しみや悲しみにつながっている組織活動に、一銭たりとも金銭を流すべきではない、という考え方は、ジャーナリストの倫理のありかたとしては、認められるべきものだろうと思う。(もちろん異論もあるだろうが)
本人の潜入取材に代わって、本書には、新聞社が独自に入手した、全国大会の音声データの文字起こしが経済されており、これがなかなか衝撃的だった。
「ネットからの情報はダメ。自分で見た情報こそが確か」「ネットはダメ。自分で本を読んだり、自分で情報をとってこないと」というようなフレーズで、脱法マルチのカルト的な世界への囲い込みがなされている姿を見ると、これまでなんとなく行われてきた、情報リテラシー教育のありかたを、根本から見直し、考え直さなければ、と強く思わざるを得ない。
「ネットの情報はダメ。自分で調べましょう」
「ネットの情報はダメ。本の情報はオッケー」
それは、これまで長年、学校現場で聞き続け、わたし自身が批判してきた言葉そのものだ。
その長年聞き続けた当の言葉、その理屈によって、脱法マルチが支えられてしまっているのだとしたら…わたしにとって、こんなに苦しく、悔しいこもはない。
Posted by ブクログ
■被害にあわないためにはどうすればいいか。
マルチ商法や詐欺を企てる組織は巧みに近づいてくる。「見知らぬ人と安易に連絡先を交換しない」「不審に感じたら、すぐに連絡を絶つ」という二つが大切。
こういった組織は報告、連絡、相談の「報連相」を徹底させる。何気ない連絡かあ始まったやり取りは安心感を生むのと同時に、依存性を高める。気づくのが遅くなれば洗脳状態となってしまい、自分ではなかなか抜け出せなくなってしまう。
■組織で使われる用語
・チューニング
師匠の考えと自らの思考を同一化させること。成功者である師匠の考えを一緒にすることで自らも成功できると教えられる。
・ティーアップ
「持ち上げる」という意味。勧誘段階でこれから紹介する師匠について事前に経歴や実績を誇張して伝えておく。実際に師匠にあったとき関心や興味が勝り、心理的に疑うことができなくなる。ネットワークビジネスでよく使われる言葉。
・スロープ
目的を告げずに徐々に組織の理念に染めていくこと。当初は勧誘目的を告げずに近づき、バーベキューやフットサル、飲み会を通じて徐々に仲良くなる「段階」を踏む。
・エンロール
もともとは登録や入会という意味。組織内では自己決断させることを意味する。15万円分の商品購入や勧誘活動を「エンロール」させることで、あくまで自己責任と位置づけ、組織への批判をかわしている。
・師匠
小売店を営みIの商品を扱っている経営者。ストアオーナーなどとも呼ばれている。
・弟子入り
師匠の下で学ぶこと。セミナーへのフル参加や報連相が強く推奨される。最終的には師匠の店で15万円分の商品の購入を求められる。
・リーダー
活動しているグル-プの中で師匠の下に位置する人間。数系列を達成しており管轄によっては師匠の店で働いている人間も少なくない。
・基準
組織内で定められた目標。師匠の基準に合わせることを目標とされる。
・現場
勧誘活動、友達作りをする場所。街中や、街コン、バーベキュー、フットサル、マッチングアプリなど勧誘現場を指す。
・本流
弟子入り後、本格的に参加するセミナー
・管轄
各師匠が率いるグループ、チーム。師匠の店や家がある場所で勧誘の活動場所も変わってくる。
・自己投資
商品を毎月15万円分購入すること。経営者になるためには「月10~20%の投資が必要」などと説明を受ける。
・つるみ
師匠と一緒にいること。勧誘活動後の深夜遅くに師匠との飲み会が開催されることもある。
・職住近接(接近)
一般的には職場と生活拠点が近い方がいいという教え。シェアハウスへの入居が勧められることもある。共同住宅は殆どの場合、師匠の家と近い。
・パートナー
自らが勧誘して入会させた人間。
・紹介者
組織に加入するきっかけとなった人物。自らを勧誘してきた人物。
・ハードワーク
24時間、寝る間も惜しんで勧誘活動に邁進すること。
・SUHW
スーパーウルトラハードワークの略称。ハードワークの強調語。とにかく働く(勧誘)すること。
・チームビルディング
一連の勧誘活動の工程。
・アンチ
SNS上で組織の注意喚起をする元構成員やユーチューバーを指す。組織に批判的な報道をしたマスコミも含まれる。組織のセミナーでは登壇者がアンチのモノマネをしたショートコントが催され、会場から大笑いが起きる一幕もあった。
・ドリームキラー
恋人や友人、両親など。組織に加入する前に築いていた人間関係。組織から見て夢を邪魔する人々。勧誘活動の理解が得られにくいので「ドリームキラー」と呼び、一気にその人たちとの人間関係を引き離す。
・環境
組織の呼び方の一つ。組織内の誰かが「トレーナーとMさん(最高幹部)が作ったこの環境をもっとより良いモノにしよう」などと発言したのが由来。
・事業家集団
組織の名称の一つ。トレーナーが全国会議で発した「俺たちはマルチをやっているのではなく事業をやっている。俺たちは事業家の集まりなんだ」が由来。
・PJ(プロジェクト)
組織内で各種のプロジェクトチームが存在している。SNS上で商品や組織関係者のブランディングを行う舞台もいればアンチに対し、誹謗中傷を行う舞台も存在している。
・親友作り
新しい友達を作るということ。街中などでの勧誘行為を指す。新規開拓とも呼ばれる。
・便所の落書き
SNS上で組織への注意を呼び掛ける書き込み。組織に対するマスコミの報道は「情報統制されており、切り取られている」などと教え込まれている。
Posted by ブクログ
子どもに読ませたい1冊。こういう系統のビジネスって手を変え品を変え世の中にうまいこと隠れて好機を伺っているんだろうと思うけれど、情報として全ての若者に叩き込んでおいてもらいたい。
Posted by ブクログ
「事業家集団」と呼ばれるマルチ組織への侵入…はしてないな。構成員とのちょっとした交流と、被害や組織の実態などをまとめたルポ。なんというか、カルト教団化させたマルチというようなおぞましい形態をしていて、これ実在するんか、と恐ろしくなった。調べてみたらまだ活動しているらしい。引っかからないように注意しないと。
Posted by ブクログ
怖い。
シェアハウスも悪用されているんですね。
せっかく、最近?一般的になったいい形態の家だと思っていたのに。
世の中、悪いことを考える人は頭がいいんでしょうね。
その能力を別のことに使えばいいのに。
もうそれを抑える力が日本にはないのかな。
でも、こういう本がちゃんと発売されているということはまだ大丈夫?なのかなと考えさせられました。
Posted by ブクログ
リーマンショック後の2009年から2010年の20代の時、私の高校時代の同級生(地方出身、東京の難関国立大学の卒業生)が本書に出てくる事業家集団と思われる団体の活動にハマっていた。その同級生の手法は以下のとおりである。
・本書にも出てくるシリーズ本を勧められる
・不労所得を学ぶボードゲームの会に誘われる
・立食パーティーに誘われる
・丸ビルの休憩スペースで同級生の師匠筋にあたる容姿
端麗な女性と会うことを勧められる
その時から13年から14年ぐらい経過し、DX化も進んできているため、事業家集団の手法がどれくらい変化したのか興味があったため本書を手に取った。しかし、事業家集団の手法は驚くほど変わっていなかった。
本書は事業家集団が使う用語・組織の仕組みを解説している点は評価できる。他方、本書は、この事業家集団の手法が確立した時期の分析や、事業家集団の歴史的・社会経済な分析が不足しているので、読後に物足りなさを感じる。そのため、3点と評価した。著者には、経験を積んでより良いジャーナリストになっていただきたい。