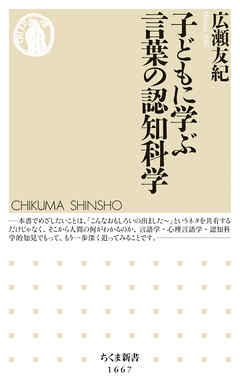あらすじ
小学生になった息子の珍解答は続く。さらに巷の記事・絵本さらにTシャツのロゴ・町の看板まで、題材はあらゆるところに広がっていくことに。「これ食べたら死む?」「のび太vs.のび犬」「ニンジンは、ヤギ・ヒツジも食べてくれるよ♪」ヘンテコな答えや言葉遣いの背後にある、子どもの、あるいは人間一般の心の働き、認知のしくみ、言葉の法則や性質について、楽しく学べる一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
言語学に関する内容です。タイトルにもあるように、著者の子どもの言い間違いや書き間違いの事例から、人間がどのように言葉を認識しているのかを紐解こうとするものです。
言語学に関する本は何冊か読んだことがありますが、ダントツで読みやすいと感じました。この手の本ですが、事例説明→実際の例の提示がひたすらに続き、読んでいて情報量がパンクしてしまうことが多々あります。(こういったことがあります→実際の例がこちらです の流れが延々と続く)
この本はそれが適切なスピード感で行われていますし、実際に子供の間違いをベースにして説明がなされるので、こういったこと確かにあったよねとイメージがとてもしやすいと思います。著者の語り方が親しみやすいのも良いです。
書かれていることで興味深かった内容の一つが、「メンタルレキシコン(頭の中の辞書)への検索のかけ方」です。私たちが何かを話そうとするときに、当たり前のように行われている言葉や助詞のチョイスがどのように行われているのかについて説明がされています。こういった日常的に行われる言葉の認知に興味がある人であればオススメできる本です。
Posted by ブクログ
『「超常現象」を本気で科学する』(石川幹人)を読んでいた時に【認知科学】の文字が出現。
何だこれはと思って関連書探しヒットした『子どもに学ぶ言葉の認知科学 』(広瀬友紀)。
ホラー&オカルトとは一切関係がないものをチョイスしました。
【認知科学】とは「人間の知覚・記憶・思考などの知的機能を司るしくみに迫る研究分野」で、
心理学、言語学、計算機科学、芸術学などさまざまな視点からのアプローチが含まれるそうです。
「科学」と聞くとフラスコと試験管使って薬品グツグツ…とイメージしてしまうのですが、
調べてみたら「一定の目的・方法の下でさまざまな事象を研究する認識活動、およびそこからの体系的知識」とあり、
薬品だけに限らないんですねアホですいません。(恥ずかしい話、【化学】との違いもわかっておりません)
今回読んだこの本で、
【認知科学】を、というより、【母国語である日本語を子どもや外国の方に教える事の難しさ】をメチャクチャ感じました。
「日本語と英語は文の構造や発音が違う」というお話はよく耳にしますが、ちゃんと知ろうとしたのは今回が初めてです…笑
頭で理解はしました。が。
私からは「聞いて言って繰り返して慣れて」としか言えない…。
そして…
日本語に慣れぬ外国の方に「警察官が中学生をカツアゲしたヤンキーに説教した」的な、日本人でもわかりにくい事は言っちゃアカン事は理解しました。
そして…
「ぶぶ漬けでもあがっていかはりますか」を久々に目にして、
【語用論】もっと知りたくなり、こちらも関連書探しております。
Posted by ブクログ
非常に興味深く読みました。
子どもの成長過程に応じた言い間違いから何が読み取れるのか。面白い研究をされている方がいるのですね。
私は昔から、子どもが抽象的な言語を体得するのはいつか? どういういきさつで? と疑問に感じていました。子どもを注視していると、2歳くらいまでは"今"しかないように見受けられます。これが少し成長すると、"昨日"とか、"明日"を理解するようになる。どうやって?
自分の子どもを気をつけて見ていたのですが、残念ながら判らずじまいです。この問いに答えてくれるような本に出会いたいです。
Posted by ブクログ
子どもの言語習得過程を実際に観察して、言葉を使いこなせるようになるステップを考察しているが、学者と実際の学校での指導方法の考え方が微妙に食い違っているのが面白かった.英語を含めた考察も楽しめた.学生時代、国語の学習は嫌いだったが、本を読むことは好きだったことを振り返ると、国語自体の指導方法の見直しが必要な感じがした.
Posted by ブクログ
子育てママ研究者が分析する言葉の発達
主に音について
語彙、音韻、意味、統語等の観点から、子どもの言い間違い・小学校のテストの間違いを学術的に分析する構成。個人的には日本語学に疎いため、第4章の日本語の関係節、第6章語用論は勉強になった。私も日々子どもとの関わりの中で、生徒の間違いを著者のように楽しんで分析できるようになれればいいなと思った。決して理不尽に不機嫌になるのではなく。
また、一文が長く(ときには5行以上)になることもあり、主語述語が掴みづらくなる箇所が多々あった。
Posted by ブクログ
子供の言い間違いや書き間違いから、人間の言葉に対する姿勢が見えてくるという話。
今まで子供は大人の模倣をしてお喋りをしていると思っていたのですが、そうすると「来ない(きない)」などの説明がつかないな…!?と気がつけたのが一番大きかったかもしれないです。
外国の言葉と日本語を比べてみる章では、やっぱりこれだけ音節や文法が違かったら取得するのも難しいよな〜と改めて思いました。
Posted by ブクログ
子どものテストの珍答案を経て、言語の認知科学へ……面白い。
「のび太とのび犬問題」!
@以下、コピペ
小学生になった息子の珍解答は続く。さらに巷の記事・絵本さらにTシャツのロゴ・町の看板まで、題材はあらゆるところに広がっていくことに。「これ食べたら死む?」「のび太vs.のび犬」「ニンジンは、ヤギ・ヒツジも食べてくれるよ♪」ヘンテコな答えや言葉遣いの背後にある、子どもの、あるいは人間一般の心の働き、認知のしくみ、言葉の法則や性質について、楽しく学べる一冊。
目次
第1章 習わないのにわかっていることば―言語習得とその先
第2章 逆さま文字、何が逆さま?―文字の認知
第3章 英語にあって日本語にないもの?―目的語と関係節、そして主語?
第4章 日本語って難しいの?―文理解と曖昧性
第5章 小さい「っ」の正体―特殊モーラと音声知覚
第6章 なぜ会話が通じるのか―語用論
第7章 頭の中の辞書をひく―メンタル・レキシコン
@
目次
まえがき
第一章 習わないのにわかっていることば──言語習得とその先
「死む」は言い間違いではない
大人の模倣ではない証拠
過剰一般化
いつごろまで「死む」って言うのか
ちゃんとやすらないと手を切ります
大人よりも複雑な構文?
言語を観察する力 ツッコミ能力?
構造的多義性
小学校英語教育の現場に平野レミ先生を!
第二章 逆さま文字、何が逆さま?──文字の認知
鏡の中は逆さまなのか
鏡文字の謎
文字の分解と組み立て
のび太とのび犬問題
パーツ認定とその構成
文字同士の配列──ターャジスとケブンッリジだがいく
第三章 英語にあって日本語にないもの?──目的語と関係節、そして主語?
修飾戦線異状あり?
目的語ってないの?
日本語のほうが自由だ?
子どもがわかるように
人食いニンジンの恐怖
あなたはウナギなんですか
関係節って英語で出てくるやつですよね?
これ本当に関係節なの?
第四章 日本語って難しいの?──文理解と曖昧性
ガーデンパスでどんでん返し
英語に直してみる
大事なことをなぜあとに?
自由とひきかえに……
全部読んでも結局曖昧なとき
こじらせた曖昧性
略しても、好きな人
主語関係節vs.目的語関係節はホットな話題
曖昧性が明らかにしてくれること
第五章 小さい「っ」の正体──特殊モーラと音声知覚
小さい文字はちょとむずかしい
小さい「っ」の正体は?
イタリア語にも小さい「っ」ってあるんですか
イタリア語話者と日本語話者は似て非なるものを聞いている?
失ったのではない。手放したのだ
聞いてる時点でカタカナ英語?
ここも特殊だ日本語は
小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」(ねじる音・拗音)
しりとりでわかること──音節を使う子どもたち
第六章 なぜ会話が通じるのか──語用論
「語用論」ってなんだ
文字通りじゃないよ、のサイン
言葉通りの意味と語用論的な意味
2は3に含まれる?
象のなかには哺乳類であるものもいる……マルかバツか?
言葉の上級者コースへようこそ
第七章 頭の中の辞書をひく──メンタル・レキシコン
メンタル・レキシコンの検索
意味のネットワーク
意味つながりが検索を速める
意味情報で混乱
音つながり「ご近所さん」の競争
音つながりのメリット──言いたい語を検索する場合
概念に対応した語を捜すときと、入力から語を割り出すとき
正真正銘言い間違いについて
言い間違いの単位
アクセントの情報は?
統語や意味
あとがき
文献案内
@@@@@
Posted by ブクログ
以下、引用
人間が文を読んでいる際の視線を計測してわかることのひとつとして、我々の眼は一文字ずつ律儀に注視するわけではなく、ある程度の区間ごとに視線の停留、次の地点(文字システムによって異なるが、少なくとも数文字以上先で、単語を超えることも)まで瞬間移動、また停留、瞬間移動、を繰り返しているという事実があります。なのでやはり「逆さスジャータ」は普通の人間には難しいと思われます。