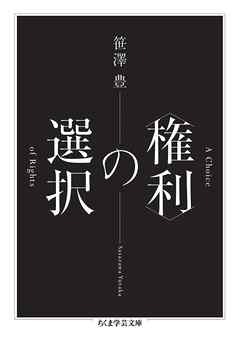あらすじ
“right”に「権利」という訳語があてられたとき、そこには特殊日本的な背景が作用し、それ自体が一つの独自な解釈を表すものとなった。「力と利益」の意味を含む日本の“権利”の思想は、「正しいこと」を意味する西洋の“ライト”の思想とどの程度異なり、また、どの点で共通しているのか。この問いを考察の糸口として、我々が「権利」と呼ぶ思考装置の問題点と限界を明かし、その核心に迫る。福沢諭吉、西周、加藤弘之ら日本の思想家をはじめ、ロック、ドゥオーキン、ロールズ、セン、ニーチェらを導き手とし、理念と力の錯綜した関係を解きほぐした著。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
"権利は尊重されなければならない"。
今日では自明視されているが、そもそも「権利」の思想とはどのような思想であろうか。そしてこの思想の根拠はどのようなものであろうか。この問いこそが、本書全体を貫く問題意識である。
一見迂遠のように見えるが、本書は先ず予備作業として、〈ライト〉の訳語に当てられた「権利」という語についての考察から始まる。〈ライト〉は「正しさ」や「正当性」を意味の中核に持つ語である。これに対し、「権利」の「権」は「力」、「利」は「利益」を意味しているが、このズレは何なのだろうか。幕末明治初期に西洋思想に邂逅し、その中で〈ライト〉の思想を導入することに与った人物たちの理解をたどっていく。
福澤諭吉の『西洋事情』では「通義」という語が当てられたが、『学問のすゝめ』では「権理」、「権義」が用いられた。遡って幕末期、西周は〈ライト〉に相当するオランダ語regtに"権"の語を当てている。これらについて、当時の国際情勢、〈力〉によって支えられている国際公法の世界に関するリアルな認識に因るものではないか、とする。また「利」については、人民の「利を保護する力」と理解されたことが、津田真道や加藤弘之の用法を通して論じられる。
このような〈ライト〉に関する日本的受容に対し、〈ライト〉の思想の本質とはどのようなものなのか。
以下、ロールズ、ドゥオーキン、セン、プラトン、アリストテレス、ヘーゲル、ニーチェを参照しつつ、どこまでもどこまでも著者の考察は、根源に迫っていく。
その結論をどのように考えるか。〈ライト〉、権利が全ての人間にとって無縁なものではない以上、それは本書全体を読んだ読み手一人ひとりが考えるべきことであろう。始めのうちこそ、著者の考察が何処に行こうとしているのか少し取っ付きにくいかもしれないが、決して難しい言葉を使っている訳ではないし、論理の展開も丁寧に行われている。自ら考えるに当たって、良き導きの書になると思う。
Posted by ブクログ
武力闘争によって勝ち取られた「権利」が力を背後に持たざるを得ないという矛盾から考察を始め、「権利」あるいはこの日本語のもととなっているrightという言葉が担ってきた意味を歴史的・哲学的に解き明かしていく著作。著者の結論は、<ライト>の思想はその正当性の根拠を提示できない思想であって、これを絶対的な真理として受け取ることはできない、けれども、これは我々にとって絶対に必要な思想である、というものである。この結論を導き出す過程において、ロックからロールズまで、古典的な政治哲学・法哲学、さらにはそうした思想を日本に導入しつつ独自の解釈を加えていった福澤諭吉や加藤弘之らの議論とその限界が明快に論じられており、きわめて示唆に富んでいる。