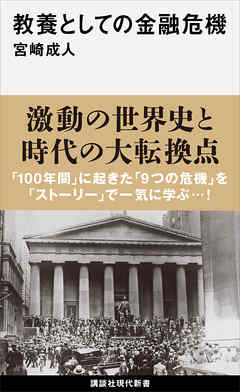あらすじ
激動の世界史と時代の大転換点――。
「100年間」に起きた「9つの危機」を「ストーリー」で一気に学ぶ…!
世界的な金融危機はなぜ起きたのか? なぜ金融危機は10年に1度起こるのか? 新型コロナショックは新たな金融危機を引き起こすのか? 危機を何度も乗り越えたこの世界は、いったいどこに向かうのだろうか?
【目次】
序――国の黒字・赤字とはどういう意味か?
――国際金融危機の仕組み
コラム 日本はこれからも経常収支黒字ですか?
第1の危機 なぜ史上最悪の危機は起きたのか?
――金本位制、大恐慌、ドイツを巡る資金の流れ
コラム あなたの国の経済的トラウマは何?
第2の危機 なぜブレトンウッズ体制は崩壊したのか?
――固定相場制、ドルの垂れ流し、ニクソンショック
コラム 人民元がドルに代わって基軸通貨になるのですか?
第3の危機 なぜドルは大暴落したのか?
――変動相場制、オイルショック、インフレ
コラム 経常収支の赤字や黒字は国内政策で是正できますか?
第4の危機 日米・米独貿易摩擦は乗り越えられたのか?
――プラザ合意、円高パニック、バブル発生
コラム 為替市場介入に意味はあるのですか?
第5の危機 発展途上国の債務危機はなぜ同時多発したのか?
――ラテンアメリカ大混乱、IMFプログラム、ブレイディープラン
コラム 発展途上国の貧困問題は解決できますか?
第6の危機 アジア通貨危機とは一体何だったのか?
――サドンストップ、パニックの伝播、アジア通貨基金
コラム 固定相場制が守れないのはなぜですか?
第7の危機 米国発金融危機はなぜ起こらなかったのか?
――ヘッジファンド、質への逃避、FRBの介入
コラム ハゲタカファンドに勝つにはどうしたらいいですか?
第8の危機 世界金融危機を引き起こした複合的要因とは?
――リーマンショック、金融工学過信、群集心理
コラム 国際金融は誰が運営しているのですか?
第9の危機 絶体絶命のユーロを救った「一言」とは?
――単一通貨導入、ギリシャ危機、ドラギマジック
コラム EUは連邦国家に向かっているのですか?
第10の危機? 次の危機はどこで起こるのか?
――新型コロナ、債務累積、資産価格高騰
感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
過去100年にあった九つの金融危機を振り返り、その原因と問題点を探っている。
近年はコロナ禍の不況への対策として、各国の政府と中央銀行は未曾有の金融緩和政策を実施してきた。しかし今年からは経済を正常化するために金融引き締め政策が段階的に進められる運びとなる。今この時にこの本が世に出たのは、タイムリーであったという他はない。初心者でも理解しやすいように、国際収支の基本を確認し、第一次世界大戦後の国際金融危機から話を進めていて、金融政策や為替など国際金融の全体像を理解するための良書であると思う。
時の首相は「新しい資本主義」を唱えている。資本主義が古くても新しくても金融危機はやってくる。資本はより利益となる投資対象へと集まり膨れ上がり、やがて行き場を失うと市場は暴落する。
金融危機を未然に防止するのは難しい。「残念ながら、未然に防いだ危機は国民の目には見えません。危機予防のため、事前に財政・金融政策を引き締めたり、規制を強化したりすることは、おそらく不人気でしょう」と著者がいうのは、まさにその通りだと思う。
飽くなき成長を求めて、資本の移動の自由をどこまでも認めるのか、規律ある経済活動を促し、金融危機を未然に防ぐ(あるいは抑制する)のか。本の最後は、規律と成長が二律背反ではないこと、規律重視か成長重視かは選択の問題であると結んでいる。
最終章では今後の金融危機の可能性を予想しているが、「より大きな「危機」は、米国が「調整」をしてしまったときに来る」と予想している。米国の膨大な需要にとって代われる国はどこにもないからだ。まさに今、米国から金融引き締め政策が始まっている。これに追随するかしないか、各国で対応が分かれているが、その結果がどうなるかは、間もなくわかってくるだろう。