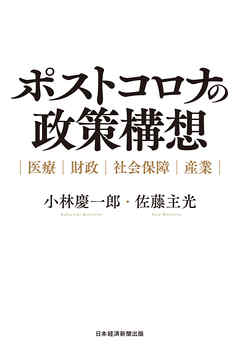あらすじ
■オリ・パラ開催・観客論争、後手に回った感染拡大防止対策、PCR検査体制・医療体制の不備、ワクチン接種をめぐる縦割り行政、中央・地方政府間の連携の悪さ、医療専門家と経済専門家との不協和音、露呈したデジタル化の遅れ。さらに日本は、生産性・経済の低迷のために、長期衰退も、もはや絵空事ではなくなった。
■日本はコロナ対応において、どこで、何を、どう間違ったのか。危機を突破する道はどこにあるのか。カギはガバナンス(統治構造)とリスクシェアのあり方を変えることにある。
■経済学の知見をもとに、コロナ危機に対する数々の政策を早くから提言し続けてきた経済学者が、日本社会を立て直すための包括的な政策ビジョンを提示。コロナ対策をめぐる意思決定過程を間近で見てきた著者だけにしかなしえない観察、洞察にもとづき、豊かな構想力で描き出す。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
日本のコロナ対応について、経済学者の視点から問題点とその解決策を述べたもの。前半の医療体制に関する考察は素晴らしく、とても参考となった。ただし、財政についてや税制については、コロナとはかけ離れた内容も多く、参考にならなかった。また、後半の解決策もそれぞれの章をまとめた内容でくどく感じた。
「医療エリートによる判断は、医療システムを平時と同じ状態に保つことと医療機関の経営が成り立つことを優先し、そのために国民の様々な経済社会的な活動は大幅に制限する、という判断に傾きがちなのだ。コロナ危機は社会全体に大きなコストをもたらしたが、非医療の活動が受けた制限とコストがあまりのも大きかったことに比べて、医療提供体制の改革の度合いや医療提供者が分担するコストはあまりにも小さかった」p46
「(スイッチOTCが進まない)「医薬品の安全性は医療の専門家が判断しなければならない」という意識が専門家には強すぎて、消費者の自己判断への信頼がまったく欠けている。医療専門家は「自分自身の健康について判断する一般国民の知的能力」をまったく信用していない、ということである。エリートが一般市民を自分と対等な思考力を持たない愚民とみなすような歪んだ状況である。専門家にこういう認識が広がっていること自体が、成熟した民主主義社会としてきわめて不健全ではないだろうか」p47
「水際対策をめぐる議論でも同様に、国民全体が被る膨大なコストに想像力が及ばず、きわめて内輪の業界コストばかり重視する議論が厚生労働省の医系技官の官僚集団などから繰り返された。水際対策を強化しない隠れた大きな理由は、ひとことで言えば、「水際対策を行う検疫所の職員の仕事が増えすぎて大変だ」ということだ。2020年のコロナ禍が勃発した時点で、国境を閉鎖し、政府のあらゆる政策資源を水際対策に投入しておけば、日本の感染はオーストラリアなどと同じようにかなり抑え込めたはずである」p50
「現実の政策当局者は、検疫所の「仲間」の業務が増えすぎて耐えられないから、という理由で、国民が巨大なコストを支払うことになると分かっていながら不作為を選んだのだ」p51
「日本の医療エリートがコロナ危機という非常時に見せたのは、医療側の変革はできる限り後回しにして、一般企業の営業の停止や個人の外出の自粛など、国民の基本的人権を極端に制限することには何のためらいも見せない、というお家大事のご都合主義的な姿であった」p52
「(ダイヤモンドプリンセス)自衛隊が管理した区域では管理者側に感染者は出なかったが、それ以外の区域では、管理者側に船内感染者が続出した。危機管理の徹底している自衛隊と、一般の行政職員との間で、感染者側の徹底度合いが違うことが如実に表れている」p54
「誰が感染者かわからないという「情報の不完全性」は、経済活動を大きく悪化させる。PCR検査などの感染症検査は、この情報の不完全性を是正する機能を持つ。本来は診断と治療という医療行為のための感染症検査が、社会の「情報の不完全性」を是正するという経済政策としての機能を有してしまった」p56
「公衆衛生の専門家にとっては「感染症を見つけること」が検査の目的なので、一般市民に無作為に検査をして陰性の結果が大量に出れば、それは「無駄な検査をした」ということになる。一般市民への無駄な検査をなるべく減らして、感染していそうな対象者を選んで検査をすべきだ、という考えになる。一方、経済学的な視点からは「情報の不完全性」を是正することが善なので、一般市民に検査をして、陰性の結果が出れば、その結果は「感染していない確率が低い」という有益な情報をもたらし、経済を活性化させるので、「無駄な検査ではない」ということになる」p57
「(ワクチンがどこにいくらあるのか把握できなかった)医療機関・接種会場におけるワクチンの過在庫状況を迅速に把握するシステムを欠いた結果といえる」p65
「(閉鎖的・独善的になりやすい医療政策の決定プロセス)この背景には政策決定を担う、あるいは影響力を及ぼす厚労省の各委員会・審議会のメンバーの多数を医療関係者が占めていることがある。そこには同じ分野の専門家がサークルを作って物事を決めて、経済学を含めて他の意見が入り込む余地のない「ムラ社会」がある。癒着や既得権益を擁護する温床になるだけではなく、政策決定が閉鎖的・独善的になりやすい。利用者の利便性や医療費の適正化といった目線を欠く。そもそも、先述のセルフメディケーションを含めて医療政策で「最も重視」されてきた安全性と有効性は医師によって担保されるべきという「家父長主義」的風潮、つまり医師の判断が絶対的で患者・国民の選択を尊重しない姿勢があることが否めない。その姿勢は平時の医療に限らず、コロナワクチンの接種が医師(および医師の指導の下での看護師など)に限られるなど非常時においても変わらなかった(結果、ワクチン接種の担い手の確保を困難にした)。総じて厚労省の意思決定は、医系技官という医師免許・歯科医師免許を持った官僚と医師の団体である日本医師会を軸に回ってきた。これは医療政策のガバナンス問題といっても過言ではない。しかし、医療は医療従事者に限らず、健康やコストなど患者、自治体、保険者、企業を含めて多くのステークホルダーの利益に関わる。感染症対策を含む「医療のように重大なことを、医師にすべて任せるわけにはいかない」。エビデンスに基づきつつ、安全性や有効性にとどまらず、利便性や経済性など多様な視点による政策決定が求められているのではないか」p68
「(コロナ禍の医療従事者の多忙感)新型コロナに対応する一部の医療従事者に負担が集中する一方、医療従事者全体としては、必ずしも労働時間が増大していない実情が窺われる(財政制度等審議会建議)」p76
「(過大な病床数)わが国の病床は人口1000人当たり13.0床でアメリカ(2.9床)やドイツ(8.0床)を上回るなど諸外国に比べても多いにもかかわらず、コロナ病床数確保は遅々として進まなかった。感染者数が欧米より少ないにもかかわらず医療が逼迫する要因になっている」p98
「(過度な個人情報管理)個人情報は漏洩がないようにと、きわめて神経質に扱われてきた。セキュリティを理由に個人情報の利活用が進まないケースも少なくない。情報漏洩が起きるたびにメディアなどでも大々的に取り上げられることから現場が委縮している面も否めない」p106
「全国的にわが国は病床が過剰気味である。多すぎる病床は入院の頻度や期間を増やし医療費を高めてきた」p118
「わが国では病床数と入院医療費との間には高いプラスの相関があることが知られている。つまり、医療機関は病床を埋めるように入院の頻度や日数を増やす誘因を持つ」p122
「わが国の環境税は国際的に見ていまだに低い水準にとどまる。(CO2 1トンの排出に対して日本は2万4241円(2017年3月)、イギリス4万2193円、ドイツ3万7128円)」p162
「わが国の行政は「申請主義」を旨としてきた。国民一律10万円を支給した特別定額給付金でさえ、世帯ごとに申請しなければならなかった。持続化給付金を含む中小企業への支援も同様である。しかし、この申請主義の弊害が近年目立っている」p208