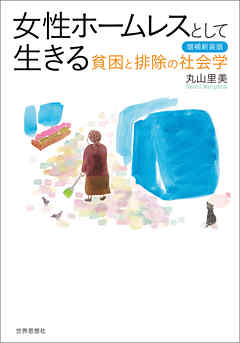あらすじ
女性ホームレスの生活史から、女性が貧困に陥る過程を浮き彫りにし、福祉制度や研究が前提にしてきた人間像を問い直す。2013年刊行の第33回山川菊栄賞受賞作に、著者による付録「貧困女性はどこにいるのか」と岸政彦氏による解説「出会わされてしまう、ということ」を収録した増補新装版
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
女性差別は差別と認識されず社会の中で長年に渡って根付いてきた。
女性というマイノリティグループの中でももっとも弱い立場にある、貧困や障害、病気や高齢などのいくつもの不利な条件を抱える人がどのように生きる術を奪われてきたか、そしてその上でどのように自分に備わるものを生きるために生かしてきたかが描かれている。
正直言って、読んでいて恐ろしかった。生きるとはなんと恐ろしく、手に負えないものなんだろう。この本はままならない生をせめて理解しようというひとつの抵抗の形だ。
Posted by ブクログ
社会学における「質的調査」の代表例として挙げられていたので読んでみた。
エスノグラフィ、フィールドワークという観点から読んでも興味深かったし、貧困問題、ジェンダーという観点からも読むことができる。
ホームレスという対象に、「女性ホームレス」という視点を持ち込む。
ちなみにこの本では
ホームレス:住居喪失者
野宿者:路上生活者
と定義している。
はじめに、において3つの目的が掲げられている。
「これまでほとんど研究されることのなかった女性ホームレスについて、その存在様態と生活世界をとらえること
男性を前提にして成立してきたホームレス研究全体をジェンダーを分析視覚として持ち込むことによって再検討し、男性だけではなく女性をも扱うことができるものにまでその枠組みを鍛え上げていく。
女性ホームレスたちの日常的な実践に焦点化することを通じて、男性を中心にとらえられてきた人間の主体性について、どのような別様の可能性が見出されるのかを検討する。」
今までのホームレス論は、
ホームレスを改良すべき客体としてみなす見方から、自立した主体としてみなすという考え方を作った。
しかしその一方で、さらに周辺化された人を排除する可能性も孕んでいる。
そして、その周辺化された人として、「女性ホームレス」を対象にする。
女性の野宿生活者は少なく、定まった住居がなく不安定であったり、施設に入らざるを得ない人が多い。
なぜか?
→女性は家事育児などの再生産労働に従事しがち。それが女性の経済的自立を妨げる。性別役割分業を前提としたモデルは、女性を社会保険よりも社会福祉や公的扶助に結びつけてきた。保険は働くもののためにあり、資力調査をしない。社会福祉や公的扶助は貧困に陥るまえに最低限の生活を保障するもにであり、資力調査をする。男性よりも女性が社会福祉や公的扶助を受けやすく、路上生活に陥りにくい。
ではなぜこうした傾向が見られるのか?
→福祉制度の歴史による。女性において福祉制度を利用する際に重要視されたのが、社会通念として支配的な女性役割にかなうか否か。主要な稼ぎ手となる男性パートナーを持たない女性の中で最も早い時期から保護が行われていたのが子供をもつ母親であった。(軍人遺族→離別母子→未婚の母)さらに単身女性に対しては売春婦に対する救済措置として人権を守ることより治安維持や性モラルの維持という点から福祉制度が発展してきた。
貧困女性が福祉をりようするとき主要には子供を養育する母として保護されるか、売春婦として処罰と保護更生の対象となるか、歴史的にはそのどちらかの位置しか用意されていなかった。
そして、論は女性ホームレス、野宿生活者の生活に切り込む。
この部分は、実際に筆者が無料低額宿泊所の利用者や野宿生活者へのヒアリング、女性ホームレスへの支援活動を通してヒアリングした内容を事細かに記載している。
(自分の言葉で書いてしまうが)これをとおして読み取れるのは、女性ホームレスの一貫性のなさ。なぜ路上生活を選択しているのかが、自らの意思で決定しているわけではなく、周りから示された選択肢や、夫との関係性、同じ生活を送る周囲の人々との関係性で、その場で選び取っているということである。
当初、ホームレス論は、意志を持って「一般社会生活から逃避している」としていたが、実はそうではない。むしろ複数ある選択肢の間で迷い、半ば偶然のような形であったとしても決断した選択を、その後長い時間をかけて失敗しながらも他者との関わりのなかで維持して、実現していっているのである。
これはまさに、ジェンダーの在り方と同じ。セックスがジェンダーを規定するのではなく、ジェンダーがセックスを規定するとした。そして、規定は絶えず意味づけされる。構造に規定されながら構造に働きかけていくのである。
だからこそ、選び取れるような環境を作ることが重要である、と筆者は締めくくっている。
ということで、非常に示唆に富んでいた。
確かにある集団を一概に捉えることで、ある程度「スッキリ」はすると思うが、実際はそうではない。でも逆に、極端に言えば「人それぞれだよね」と言ってしまえばそれまでとなってしまう。じゃあ質的調査ってなんの意味があるんだろう、と思ってしまったが、その答えは解説の文章に書いてあった。それは「一概に言えなくしていく」ということ。それと同時に、「理由を書くこと」であるということ。人々の暮らしに対して、必ず理由がある、それを捉えて文章化することこそ、目的なのだろうと思う。
とは言いつつも、私は研究者でもなんでもないので、ここまでの域には達しないと思うが、少なくとも、他者の営みへの想像力は忘れないでおきたいと思う。
ジェンダーや貧困の観点からも非常に示唆に富んでいる本だった。
Posted by ブクログ
大好きな岸政彦さんが、本書に寄せた解説でこんなことを言っていた。
---
社会学は何をしているのか。質的調査は何をしているのか。私はそれを、ひとことで乱暴に言えば、「一概に言えなくしている」ということだと思う。(p.311)
そしてさらに、もうひとつの目的がある。(中略)社会学の、質的調査のもうひとつの目的とは、「理由を書くこと」である。たくましいでもかわいそうでもなくただ、人びとの行為には、そして人生には「理由がある」のだ。(p.319-320)
---
女性ホームレスが安定した住居生活を送れるようにするため、福祉団体や個人が何度手を差し伸べても、いつのまにか野宿生活に戻っていってしまう女性たち。理由を聞いてもどれもみなちぐはぐで、要領を得ない。長年一緒に暮らしていた男性ホームレスを見捨てられないとか、野宿生活の方が他人との触れ合いがあって孤独を感じずに済むとか。女性ホームレスの数が少ないことから夜間などに身の危険があったり、高齢だったり知的障害を抱えていたり、側から見ればどう考えても野宿生活をこのまま続けていく方がリスクが大きいのに、彼女たちは用意されたアパートや施設を抜け出して、元いた公園へ何度も、何度も、舞い戻っていく。
本書の第五章以降に収録された、数名の女性ホームレスたちとの会話の記録を読んで、わたしはやっと、ほんの少しだけ、彼女たちの行動の理由が理解できたような気がした。というより、彼女たちが置かれた状況下なら、きっとそうせざるを得なかったのだろう、と納得させられた。私が生きてきた世界線では、野宿生活なんてありえない。でも、彼女たちが生きてきた世界線では、少なくとも今この瞬間においては、野宿生活が一番理にかなった生活スタイルなのかもしれない、と読者に思わせるだけの説得力があった。
支援っていったいなんだろう。女性ホームレスのために良かれと思って差し伸べた手が実は全然的外れで、彼女たちははなからそんなことは求めていなかったとしたら。
駅や公園にホームレスがたくさんいたら、近隣住民は嫌だと感じるかもしれない。少なくとも私は、自宅の最寄駅や目の前の公園にホームレスが住むようになったら、申し訳ないけれど、嫌だ。どこかに通報したりするかもしれない。でもホームレスって、そもそも住宅街の公園にはいない。新宿とかそういう繁華街。だからそもそも「近隣住民」というのがほとんど存在しないのかも。いやいるか。代々木公園の周りに住んでいる人だっているか。でも、だとしても、近隣住民と同じ人権がホームレスたちにもある。であれば近隣住民の声だけを拾って、ホームレスたちを一掃するという動きもまた違うのかもしれない。でもホームレスは住民税を払わずに公園に「住んで」いるわけだから、そういうところに行政的な問題があるのかもしれない。そもそも公園って何?、、、
NetflixのDark Touristというドキュメンタリー番組で見たんだけど、アメリカには、麻薬常習者が合法的に麻薬をやれる公園というのがあって、そこのテントの中であれば、どんな違法な、どんな強いドラッグでもやっていい、ということになっているらしい。だからあちこちから薬物依存の人たちが言い方は悪いけどゾンビみたいにゾロゾロ集まってきて、医療スタッフが常駐しているテントの中でクスリをやってぐでんぐでんのどろんどろんになっていた。恐ろしい光景ではあった。でも、薬物依存者をゼロにするのは無理だからせめて死人が出ないように、他の人に迷惑をかけないように、そういう手段を取ったというのは斬新すぎて、ああ、アメリカだなあ、と思った。だから何っていう話。でもこれ倣えば、ホームレスも、ホームレスがホームレスのまま、今の状態がいいならそのまま、生活し続けられる公園みたいなのをどっかに作っちゃってもいいのかなあとは思う。棲み分け的な感じで。家に住みたいホームレスは救済したらいい。でもやっぱ野宿生活がいいわっていう人もやっぱり一定数いるみたいだし、じゃあそういう人たちがそのまま生きられる場所を作る、というのも一つの手のような気がした。
そういえば先日、小2の息子が学校の宿題でSDGsの貧困問題について調べていて、ホームレス支援についてまとめた最後に「でも好きでホームレスをやっている人もいると思う」と書いていた。なかなかやるよね。