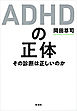岡田尊司のレビュー一覧
-
この類の本を読む時私は、
字面を追いながら、自分の深層心理が求めている言葉をひたすら探しているような気がする。
自分の意志薄弱の原点を探るのに役立ったと思う。
Posted by ブクログ -
特に「大人のADHD」と呼ばれるものは、その9割が本来の"発達"障害ではないと言う。
※だからといって当事者の苦しみ自体が偽りであるということではない
この本では、ADHDの診断の現状や、ADHDの原因について詳しく解説されている。
未診断だが疑いのある状態の人も含めたADHD当事者はもちろん、そう...続きを読むPosted by ブクログ -
■社会性やコミュニケーションの最も原初的な段階は、母親と目を見つめ合わせ、表情でコミュニケーションするということ。母親が笑いかけると笑いだす。いないいないばーに反応して面白がるといった反応は情緒的応答というコミュニケーションの第一歩が踏み出されていることを示している。
■社会性の発達がうまく進んでい...続きを読むPosted by ブクログ -
母がスマホ、アニメ依存で家庭が崩壊しつつあるのでこの本を読んだ。
しかし分かったことは、家族全員が依存症だったことだ。
まずは自分の依存を治さなければいけない。
YouTubeがないと寝られない体質になってしまった私。無音が怖かったのだ。
さらにYouTube依存を加速させる思考として、月々のモ...続きを読むPosted by ブクログ -
この世界に溢れる少年犯罪の原因を探ることから始まった。「誇大自己症候群」と聞いて、「ただ自分を大きく見せたい痛い奴のことなのかな」くらいにしか思えなかったが、読み進めていくうちに、「これはそんな簡単な問題ではないぞ」と思うようになった。
自分が学生だった時のことを振り返ってみると、自分を大きく見せよ...続きを読むPosted by ブクログ -
すごく勉強になった。
病気や治療の特徴を、薬だけでなく患者を理解するという側から説明するのがよかった。いろんなパターンが説明されており分かりやすい。
特に最後の方で周りの人の接し方や、資本主義的な考えへの提議など、とても参考になった。10年前と思えない。重版されるわけだなあと思う。いい本でした。Posted by ブクログ -
回避型という物を知り自分に思い当たる点がいくつかあったので読みました。
色んな参考例や実験の結果など具体的に書いていて分かりやすかったです。
こんな自分の性質はおかしいという自覚はあったものの、とても人に気軽に相談できるような内容でもないのでずっと抱えていましたが読んでかなりスッキリしました。Posted by ブクログ -
自分に当てはまることが多かったです。ただ、治そうとするのではなく受け入れることが重要とのこと。本の帯にあるようなことを思ったことがある方は読んで損は無いと思います。Posted by ブクログ
-
■「数学不安」という専門用語がある。数学ができるかどうかには数量処理や作動記憶といった認知的能力のほかに問題を解く際の不安が関わっている。この不安が「数学不安」。
・数学不安が強いと解けないのではという不安や恐怖に圧倒され、肝心の問題に集中することができず実力以下の成績しか取れない
・数学不安は単に...続きを読むPosted by ブクログ -
新聞の書評で関心を持って読んだのですが、タイトル、オビで書かれていることは確かに本文中の重要な内容なのですが、最終章の第9章へと読み進むに連れて、この本が本当に伝えたかったことがなんだったのかが分かってきました。それがなんであるのかは、どうぞ、自ら読んで確かめていただければと思います。198ページに...続きを読むPosted by ブクログ
-
回避型人間 ⇔共感型人間
幼少期に親からの愛着(応答性や共感性)が乏しいことが原因
成人の3割(引きこもりは1%)、日本人の若者の過半数?
自閉スペクトラム症
回避型より強い障害レベル、遺伝要因のほか環境要因も。晩婚化。
成人の4~5%
アスペルガー症候群
自閉スペクトラム症の中でも知...続きを読むPosted by ブクログ -
仕事、私生活においてどうも普通ではない、という人に時々出会ってきた。距離をおける人であれば、とにかく近寄らない、関わらないというスタンスで対応してきたが、顧客担当者となるとそうもいかない。そう言った人の思考、特徴などを知りたく、何となく手にとって読んでみた。パーソナリティ障害なるものを初めて知ったが...続きを読むPosted by ブクログ
-
・”愛着障害(不安型)の人は、両価的な傾向を抱えやすいです。ここでいう両価的とは、求める気持ちと拒絶する気持ちの両方が併存している状態を指します。”
・”愛着障害(回避型)の人は、距離を置いた対人関係を好みます。親密さを重荷とし回避して、心理的にも物理的にも距離を置こうとします。”
・”愛着障...続きを読むPosted by ブクログ -
私が機能不全家族の介護に関わる中で、ずっと「おかしい」とモヤモヤ感じていたことを明確にしてくれた本です。
きっかけは、要介護者のために行政や包括支援センター、介護事業者や家族が集まった会議の中で、家族以外の人(他人)が「(要介護者の言動について)絶対におかしいわ~」と発言されたこと。ずっと私は「おか...続きを読むPosted by ブクログ -
この著者の本はたくさん読みました(精神科医が書いていることもあり、機能不全家族をどのように捉えたらよいのか、私なりに大変参考になりました)が、特に本の後半で精神保健福祉法第22条について書かれていたことが目からうろこでした。
私なりに法律には詳しいつもりでいましたが、これまで精神的に大変な人と関わる...続きを読むPosted by ブクログ -
同著者『愛着障害 子ども時代を引きずる人々』同様、愛着障害の概要について具体例を挙げながら解説しており、さらに最新の知見を踏まえている。特に、近年パーソナリティ障害、摂食障害、子どもの気分障害、大人のADHDなどが急増しているが、それらの根底には愛着の問題があり、酷い場合「死に至る」ことが強調されて...続きを読むPosted by ブクログ
-
愛着を重視する共感型人類が多くを占める中で、愛着を重視しない回避型人類の発生を論じている一冊。
小さな進化となるのか、共感力の欠如が目立つ現代への一時的適応の形となるのか。
回避型は障害ではなく、環境に合わせた生物の反応に思えてなりません。
社会と技術によって愛着を不要とする回避型人類の生存と繁殖は...続きを読むPosted by ブクログ -
自分の過敏性は、発達障害と愛着障害の両方が背景にあるのかなと本書を読んで感じた。また、愛着障害のタイプは、親密な感情や心を通わす関係を持ちたいと思わない「回避型」であるともわかった。Posted by ブクログ