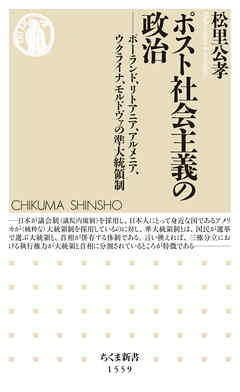あらすじ
約三〇年前、ソ連・東欧の社会主義政治体制は崩壊した。議会制=ソヴェト制の外観の下、一党制または事実上の単一政党制を採用していた国々は、複数政党制を前提とする新しい政治体制への転換を迫られた。以来現在まで、これらの国々では幾度となく政治体制の変更が行われ、それは時に暴力を伴う。この政治体制のダイナミックな変化を理解する鍵となるのが、ポスト社会主義圏に多く見られる「準大統領制」というシステムである。地政学的対立とポピュリズムに翻弄されたソ連崩壊後の三〇年を、大統領・議会・首相の関係から読み解く。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
題名の「ポスト社会主義」という表現に強く惹かれて手にした一冊で、大変に興味深く拝読した。
本書では「社会主義」を標榜していた経過が在り、その限りでもない体制に切り替えて、以降に様々な経過を辿った国々の情況を取上げて論じている。数在るそうした国々の中から、本書で取上げられているのは、ポーランド、リトアニア、アルメニア、ウクライナ、モルドヴァである。殊にウクライナに関して興味深く拝読した。
公選の“大統領”が在って、同時に選任と任命の方法等は様々でも“首相”が在る体制を「準大統領制」と本書ではしている。米国のような「大統領制」と、日本のような「議会制」との中間のようで、そのニュアンスが色々と在るので各国毎に色々な様子は見受けられる。
「社会主義」を標榜していた国々が、その限りでもないということになったのは、上述の国々の中ではポーランドがやや早く、ソ連の中の共和国であった経過の国々としてはリトアニアが少し早いが、概ね「ソ連後」なので、30年間余りを経たことになる。30年間余りの中、ポーランドやリトアニアは欧州連合にも入っている「西側」になっていて、アルメニアはロシアとの関係が深く、ウクライナやモルドヴァは西側とロシアとの間での争いの舞台のような様子とも見受けられる。既に各々の様々な変遷の経過が在る。
本書は、その概ね30年間の経過に関して、「巷で思い込まれている?」ということを排し、「歴史」として変遷や課題と見受けられる事柄を述べている。こういうような内容の類書は余り思い浮かばないので、なかなかに貴重だと思う。
本書は2021年3月に登場している。内容は概ね2020年頃迄の状況ということになる。が、現在時点で読んで、些かも古過ぎるということはない。「今年」や「去年」という次元の極最近の状況にこそ言及は無いが、十分に「現在時点の状況へ至る、少し前の経過」が判り易く纏まっている。
本書で取上げられている国々では、「社会主義」の体制の後に、著者が「準大統領制」としている体制を色々と変えている。現在に至って、或る程度落ち着いているように見える例も、未だこれから色々と在りそうな感じの例も交っていると思う。
ウクライナに関しては、目下の戦争のことも在って、「そこへ至る迄の変遷」に関心が在ったので、殊に興味深く拝読した。そしてその内容には少し驚かされた面も在った。
ウクライナでは、大統領の権限や議会議員の選挙、その他色々なことが何回も変わっている。憲法も何度も変わっているが、中には「憲法の規定に鑑みて疑問?」という例迄交っている。そういうような中、言語、宗教、歴史認識というセンシティヴな問題に、政局的な思惑で手を付けて、後の社会的な混乱の遠因になっているというような出来事も起こってしまっているようだ。
自身は「ソ連の後」という国々には高い関心を寄せて来た。そうした意味で本書は大変に興味深かった。「30年間程で体制を大きく変えて」というのは「何となく停滞?」という日本国内では解り悪いと思う。故に本書の内容は、その「大きく変えて」のあらましが掴み易い。広く御薦めしたい。
Posted by ブクログ
新書とはいえ400ページ弱。戦争前のウクライナ政治をより理解したくて1年前に読み始めたのだが、間隔を空けてしまったら内容についていけなくなり途中で一度挫折。改めて最初から読み始めたが、なんともユニークで面白い本である。扱っている5か国も、本書で主題となっている「準大統領制」も、普段なかなか理解する機会がない。
頭の整理も兼ねて書くなら、大統領制、議会制でもない「準大統領制」においては、大統領は選挙によって選ばれる(議会が選出するのではなく公選であることが条件である)。一方で、首相も併存しており、そこに3つの小分類がある。
- 大統領が自由に首相を任命できる「高度大統領制化 準大統領制」。首相は単なる助手であり、抑制は存在しない。日本人にとっては台湾がイメージしやすい。
- 大統領が議会の承認を得て首相を任命する「大統領議会制」。議会にはたいてい拒否権がある一方、議会が何度も拒否権を行使した場合は大統領による議会解散によって膠着状態が打破される(これが大統領にとっての強いカードとなる)。ロシアがこの制度の代表例だが、事実上形骸化している。
- 議会が首相を選ぶ「首相大統領制」。議会多数派が大統領の意にそぐわない首相を選ぶCohabitationになりやすい。
そのどれにおいても大統領・首相・議会の間で絶妙なパワーバランスがあり、お互いを牽制しつつも政治的膠着に陥るリスクや、自身の権力を増大させようと憲法改正を働きかける動機を常にはらんでいる。
面白いのは、旧ソ連の国家(非承認国家を含む)は35あるのに、そのうち27が準大統領制を採用していることである(!)
その理由も本書にて紹介されるが、それと併せて、
・ソ連崩壊後、そもそもまともな民主主義も政党もない中で、どのように憲法によって政治体制が規定され、現実の政治が進展した(あるいはしなかった)か
・政治の行き詰まりやスキャンダルによって、どのように政治体制のチェンジが起こったか(この多くは憲法改正を含む)
が5か国について詳述される。内容はかなり詳しく、固有名詞も多いのでその全てを理解するのは正直言って難しい。
しかし日本やイギリスという政治権力と衆議院第一党が多くの場合一致するような政治体制(細川内閣のような例外はあるし、連立政権を組む場合もあるが)に慣れ親しんでいる身からすると、本書で描かれている多様な政治体制は自分の理解を大きく広げてくれたし、各国の歴史的要因、社会的要因、地政学的要因が複雑に絡んだ政治史はとても興味深かった。
建設的内閣不信任案、第一党以外へのボーナス議席制度など、こんなアイデアもあるのかと勉強になる部分も多かった。
Posted by ブクログ
準大統領制 国民が公選する大統領が首相を任命する体制
②高度大統領化準大統領制:任命に議会承認不要:台湾、スリランカ
③大統領議会制:議会承認必要:ロシア、カザフスタン、ベラルーシ、議会解散権
④首相大統領制:議会が首相候補を指名し大統領が任命または事前協議:ポーランド、リトアニア ウクライナ モルドヴァ アルメニア
準大統領制以外
①大統領制 :首相は存在しない:米国
⑤議会大統領制:大統領が議会により選ばれる:ドイツ、イタリア
ソヴェト制=議会制 実質単一政党
→ 体制崩壊により複数政党の体制転換
憲法改正を繰り返し、首相大統領制へ
ポーランド
共産主義打倒「連帯」の分裂、大統領制 カトリック教会
リベラリズム「市民プラットフォーム」とポピュリズム「法と正義」との闘争
象徴機能しか果たさない大統領
リトアニア
14世紀 リトアニア大公国
16世紀 ポーランド士族共和国へ合同しポーランド化カトリック化
憲法制定後の大統領選挙 期待が拡大 大統領権限を抑制均衡メカニズムで縛る
政府活動が活発だと大統領の仕事が増える=ポピュリスト的パフォーマンス
EU加盟後16%居住人口減少
アルメニア
聖書に登場、ユダヤ、ギリシャ、アルメニア人 諸帝国の分割統治の歴史
カラバフ紛争
ウクライナ
大統領を決めてから新憲法制定へ 独立是非と大統領選挙を同時実施
理念の大統領、実務の首相
軍需産業はロシア内製化へ、ベラルーシは民需が継続
現在2004年改正憲法
2019年 ゼレンスキー大統領73%支持「人民の僕」党56%議席
モルドヴァ
ルーマニア人とモルドヴァ人
ラテン文字化されたモルドヴァ語=ルーマニア語が国語
フランス憲法を修正したルーマニア憲法をさらに議会主義的に
大統領公選廃止 議員の3/5の支持が大統領選出条件