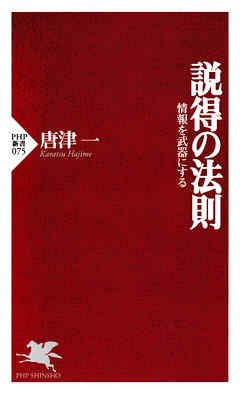あらすじ
力ずくでも、情でもない。情報の威力で武装した〈最強の説得〉とは!? 無理強い、詭弁では人を動かせない。説得の成否を分かつのは、押しの強さでも情でもなく、「情報」の使い方である。相手の翻意をうながす決定的な情報とは何か? 困難な状況を乗り切り、一つの目的を貫徹させる交渉術とは? 欧米との丁丁発止、歴史に残る究極の説得など、数々の具体例から説得の「法則」が明らかになる。本書の構成は、●序章 「実践的説得の技術」 ●第1章 「説得とは何か」 ●第2章 「科学的説得の技術」 ●第3章 「説得の達人たち」 ●第4章 「説得の現場」 ●第5章 「デジタル時代の説得術」である。著者が実際に、技術分野の日米交渉でかけひきをした経験のほか、松下幸之助の巧みな説得術や南極研究家・西堀栄三郎の破天荒な体当たり説得術など、説得の成功例を豊富に取り上げる。データと情報の威力を知り尽くした著者が解き明かす、成功する説得の〈実践法〉。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
筆者は日本の産業界・経済界の発展にも大きな影響を与えてきたシステム工学者、評論家だ。残念ながら私は知らなかったがパナソニックの松下幸之助やソニーの井深大などとも関係があり、品質管理の手法を生産現場に取り入れるなど活躍された方だ。そうした日本経済を作ってきた歴史的な人物達と行動を共にする事で学んだ、人を説得するという技術を惜しみなく紹介していく。人だけでなく生物全般が外部からの情報をもとに活動していると捉え、であるなら、人と人との接触、コミュニケーションの中に人間活動は成り立つとする。だから相手に何かをやってもらったり、自身が何かするたもの同意を得る事、即ち説得こそが成果を生み出すきっかけとなる。
前述した偉人達は説得の技術に長けていたわけであるが、何故その様な技術を持っていたのか。勿論相手が納得するだけの正確かつ事実にもとづくデータ量は重要だ。それを用いて相手に伝えるロジカルな思考も外せない。だが一つ大きな要素としては、相手を説得して何かを成し遂げたいという強い気持ち、信念がそこには欠かせない。また絶対にそれは実現できるという確信がなければ、自信や信念は生まれない。
大きな事を成し遂げるには何より信念に基づく説得が重要である事を一貫して紹介していく。その上で現代社会においては、コンピュータ処理による正確性や表現力の強化にも適応し、それを使いこなす事が重要となる。本書が書かれた1999年という年を考えれば、Windows95が出て間も無く、プレゼンツールもそんなに大した事が出来なかった時代にも、そうした先見性の高さに舌を巻く。
中々時代が進んでも人間同士が協調して仕事が完成することは変わらないから、今読んでも古さを感じず納得感を持てる。
Posted by ブクログ
説得の実例が面白く参考になる。それ以外にも興味深いトピックあり。
以下注目点
・ドイツ原発廃止も簡単でなはい様子。フランスにならって35時間労働にすることをぶちあげているようだが、実行できる策は無い模様。一方、自動化の進んだ日本の半導体工場では週36時間勤務を実現しているところもあるとのこと。24時間フル操業のシフト性の話なので、単純な話ではないが、フランスの役人にその話をしたら絶句したとのことで、フランスでも35時間労働の実現はさすがに難しいことが分かった。
・マニュアル主義の問題点に触れているところが、面白い。日本はかつてその解決にQCサークルを使っていた。
・あなたと私は意見なり考え方が一致していると思わせることが説得に重要。ねじ伏せては、相手に悔しさが残るだけ。
・同じ話題を持っていることが、話の分かる奴になるコツ。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
どうすれば説得の達人になれるのか?
いかにも「説得された」と相手に思わせずに事を運ぶ方法とは?
情報を武器にする「説得の法則」。
力ずくでも、情でもない。
情報の威力で武装した<最強の説得>とは!?
無理強い、詭弁では人を動かせない。
説得の成否を分かつのは、押しの強さでも情でもなく、「情報」の使い方である。
相手の翻意をうながす決定的な情報とは何か?
困難な状況を乗り切り、一つの目的を貫徹させる交渉術とは?
欧米との丁丁発止、歴史に残る究極の説得など、数々の具体例から説得の「法則」が明らかになる。
[ 目次 ]
序章「実践的説得の技術」
第1章「説得とは何か」
第2章「科学的説得の技術」
第3章「説得の達人たち」
第4章「説得の現場」
第5章「デジタル時代の説得術」
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
説得においては、感情の古い脳に認知させる事が大切と説明されている箇所が大変納得して読めた。
論理的な大脳新皮質で納得しても、その奥にある感情のが支配する古い脳が邪魔をして、「理屈では納得できるが、オマエのいう事は聞きたくない!」という気持ちは周りの人々を見ていてよくある出来事で実感した。
Posted by ブクログ
唐津一著「説得の法則」PHP新書(1999)
*説得というのは作業を始める前に、これから説得する相手はどんな人なのか、どんな過去があり、現在何をしているのか、何に興味があるのか、そして将来についてはどういう青写真を描いているのかを良く研究することが大切である。海外とのやりとりの場合で苦労するのは、言葉の壁以上に精神風土の違いに起因するものが大きくなるのである。つまり説得の技術の鉄則は、、まず相手との共通項を多くしろということである、と著者は説いている。個人的に海外ビジネスでの交渉を多くするが、肌で実感しているのはやはり相手の文化を知ることが言葉以上に重要であるということ。確かに言葉は意思疎通という観点で重要だが、様々な意味合いの言葉を使うよりかはストレートに伝え、それ以上に数値などで客観的な事実を示す方が海外での交渉はうまく進む。言葉はあくまでツールとして利用している。ただし、外国人が片言の日本語で「こんにちは」と言ってくれるのは言葉を伝えるという表現以上に、我々の感情に響くものがある。自分では同じような外国語の使い方をしている。各国の駐在経験から、タイ語、マレーシア語、インドネシア語、広東語で日常会話程度は理解できる。やはりこれらの言語を理解する海外の方々と仕事をするときは、相手も、そしてこちらも初対面で一気に関係が深まる。それは言葉でのコミュニケーション以上に、言葉を通じて相手の文化を少しでも理解しようとしているこちらの気持ちが伝わるからだと個人的には考えている。説得の法則、つまりそれは相手をどれだけ理解する気持ちがあるかどうか、ということが本質的に一番大切な法則になっている。