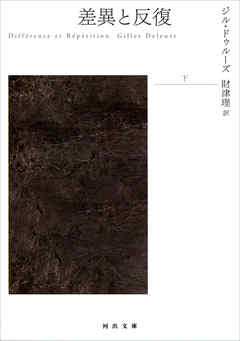あらすじ
自ら「哲学すること」を試みた最初の書物と語る、ドゥルーズ哲学のすべての起点となった名著。下巻では“理念”、そして強度、潜在性などの核心的主題があきらかにされるとともに、差異の極限における「すべては等しい」「すべては還帰する」の声が鳴り響く。それまでの思考/哲学を根底から転換させる未来の哲学がここにはじまる。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
凄く面白い。
シンプルでありながら物凄く重い荷物を背負い込んだ本だ。
言及範囲、取り扱い射程が長大である。ギリシャ哲学、ベルクソン、ニーチェ、カント、ヘーゲル、ハイデガー、ダーウィン、フロイト … …。万物を縦断し、横断し、掘り上げ、そして掘り下げる。
次から次へと諸事象が繰り出される。
それゆえに私のような凡人にはあまりに突飛な論脈だと感じる箇所もしばしばであった。
何かと何かが違うということ。
同じことを繰り返すということ。
差異と反復は共存し得ない対立概念でありながら、それと同時に、両立するものでもあると汲み取った。その霊妙さが本書全体を覆っていた。
下巻の前半、微分、積分の話題で数式が幾度も飛び出してきた。自分にとっての険しい峠であった。
印象的な節は数知れず。
強いということ、強度についての数的、数学的説明。物理的、物理学的解釈。
生きるというのは墓場へ向かうことではない。
「パラドクスが哲学におけるパトスである」、胸の内側に深く浸透してきた。
根拠づけることは、何によって成立するのか? 何に対して行使されるのか?
分からないことを分かるために読む。
分かろうとしないわけではない。
もちろん分かろうとしているがそれでも分からないことがある。
分からないことがあるということから人は目を背けがちであるが、そこに抗ってみてはどうか? という、メッセージにもならないメッセージを勝手ながらに嗅ぎ取ったりもした。
Posted by ブクログ
p307
或るひとつの差異がおのれをそこから抜き取るその表面的な反復に、その差異が(深さにおいて)必然的に所属している場合、そうした差異の本質はどこにあるのかを知ることが問題になる。そうした差異は縮約であるが、しかしこの縮約の本質はどこにあるのだろうか。そうした縮約はそれ自身、弛緩のすべての水準とすべての度においてそれ自体と共存する或るひとつの過去のもっとも縮約された度、もっとも緊張した水準ではないだろうか。各瞬間、過去全体が、ただし、様々な度と様々な水準において[それ自体と共存する]。現在の度と水準は、それらのうちのもっとも縮約されたもの、もっとも緊張したものでしかない。それが、ベルクソンの輝かしき仮定であった。その場合、現在の[現前する]差異はもはや、先ほどのようには、諸瞬間の表面的な反復から抜き取られて、その反復が存在するのに必要不可欠な或る深さを素描するような差異ではない。