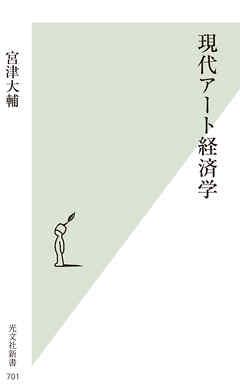あらすじ
「経済的な都市おこし」を目的としたヴェネツィア・ビエンナーレに代表される大規模国際展、経済動向を色濃く映し出す「アートフェア」やアジアのオークション事情、さらにはギャラリストやキュレーターといった「時代を動かすキー・プレイヤー」の動きから、美学や美術史の観点では語られることのない、「現在進行形・アートの見方」を包括的に示すとともに、日本の文化的プレゼンス向上に向けたヒントを探る。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
マネーゲームに翻弄されるアート、などという図式はできれば目にしたくない、というのが本音ながら、残念ながらグローバル資本主義があまねく支配するこの世界でアートもまたそのシステムを駆動するエンジンの一つである。それを渋々でも認めるのなら本書が怒涛のごとく紹介する絢爛たるアート・マネジメントの世界が今まさに熾烈な覇権競争を繰り広げているさまに瞠目ししかと知らなければならない。100年前とは全く様相を異にするアート界のプレイヤー達の配置図は複雑に絡み合い、その中でアーティストが今後美術史に名を残していくことは極めて難しい、と著者は認める。しかしその上で美しいものを一人の一生以上の時を超えて受け継いでいくことの重要性をも一プレイヤーとして熱心に説く。アートの有り様の現在を知る上で有用な書。
Posted by ブクログ
ルーブル美術館の入場料だけでも 16ユーロ*年間1000万人=220億円。
現代美術ではニューヨーク。年間200億ドルを超える経済効果。
アートによる都市おこしは、イタリア共和国に編入したてのヴェネチアから始まった。これが後にヴェネチアヴィエンナーレになる。
横浜トリエンナーレは当初は赤字。
2011年から横浜美術館をメイン会場にし、場所と人のリソースの効率化で黒字化。経済波及効果は50億円。
Posted by ブクログ
広告代理店等に務める会社員でありながら現代アート作品の収集を続け、日本を代表するアートコレクターの一人として知られる著者が、これまであまり語られてこなかった現代アートと経済に関する論考集。先日訪問したロサンゼルスの現代アートのみを収めた私設美術館「The Broad」(ジェフ・クーンズ、草間彌生、ダミアン・ハーストなど超一流n作家の作品が多い)で、改めて現代アートの持つ価値を実感し、その経済的インパクトを知りたいと思ってセレクト。
ここでの経済は2つの意味がある。一つは作品そのものを巡る経済圏であり、アーティスト・ギャラリー・コレクターというステークホルダーと、その売買が行われるオークション会社や世界各国で開催されるアートフェアが中心となる。もう一つはヴェネツィア・ビエンナーレや、ドイツのドクメンタ、日本における横浜トリエンナーレ等、地域を巻き込んだ大規模国際アートイベントによる地域経済へのインパクトがある。
この現代アートを巡る経済圏においても、中国がアーティストの質と取引される金額の高さ、アートフェアの規模等で活況を誇っているというのはやはり興味深い。
Posted by ブクログ
コレクター歴20年。アートフェアやオークションに代表される経済活動や、大規模国際展を始めとする地域の文化振興策といった様々な事象を通して、アートの存在意義や社会に対する影響力を、経済的、政治的な視点で紐解く。
美術館で観るだけの一般人に対して、コレクターの見る目はちょっとちがうな、とわかります。
Posted by ブクログ
アートを取り巻く状況がわかり、勉強になった。
印象的だったのは、ベネッセ福武總一郎氏のメッセージ「経済は文化の僕である」。
ベネッセアートサイト直島に行ってみたくなった。