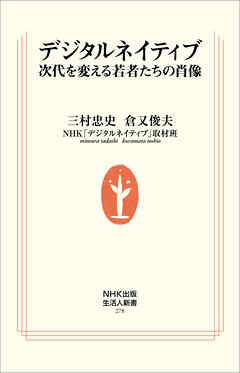あらすじ
ネット・コミュニティを自由自在に使い、不特定多数の人々と瞬時につながることで、新たな事業や組織を次々と創り出す「デジタルネイティブ」と呼ばれる若者たち。従来の常識や価値観にとらわれない考え方や行動力によって、世界を変えていく可能性を秘めた彼ら新世代の今を追う。NHKスペシャル同名番組の出版化。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
NHKで08年11月に放送された「デジタルネイティブ」をまとめた本。世界に存在する“電脳世界育ち”の感性をできるだけ掬ってみよう、表現してみようと試みた番組記録。
あとがきにも触れてあるように、kizashiでは放送後300件以上の反応を示したブログが存在し、それらの意見を「放送前に知っていれば」と制作班が痛感している感想で終わる。インタラクティブ性が出版からも滲み出ており、制作チームもそれに十分気づいている。「構成をああすればよかった」とか「このブロックをこちらにすれば」とか。
放送コンテンツとWebコンテンツ。あれもこれもと欲張れば伝われない部分なども、このチームは気づいている。次作は何を繰り出してくるのだろう。09年期待大のチーム。
Posted by ブクログ
以下Evernotoより転記
集合知は単なる知識の足し算ではない
今までの大人の視点で世界を見ることの危うさ 変化の可能性を潰してしまう危惧
それとともにそれは避けようもないだろうという感覚もある
P43 「インターネットは僕にとって情報そのもの」
「僕は人間のコミュニケーションのあり方や、つながり方に関して、ほかの世代よりも多くのバリエーションを持つのが「デジタルネイティブ」なのではないかと考えた」
コミュニケーションという概念がより広いモノになっている
通人としてのデジタルネイティブ
P72「デジタルネイティブたちは総じて物質的な欲が少なく、自分が好きな道を追及する傾向が強い様に思う」
人生の道はいつでも未知
拝金主義からの退却
拝金主義は生産性を高めない。想像力を育まない。
人は体の中に、頭の中に取り入れるものによって変化する
ハンバーガーを食べまくる人の話 カーボーイビバップ
P80「平均的な大学の卒業生は、これまで人生で5000時間以下しか読書していないかわりに、1万時間もビデオゲームをしている。そうなると、もうそれまでの人類とは違うものになっている」
1万時間の効果は果てしなく強い
デジタルネイティブの持つ価値観を日本社会は受け入れることができるのか。出来たとすればどのような社会が拡がるのか。できないとすればどのような社会が待っているのか。
P97 デジタルネイティブの特徴
・インターネットの世界と現実の世界を区別しない。
・情報は、無料だと考えている
・インターネットのフラットな関係になじんでいるため、相手の地位や年齢、所属などにこだわらない
いじめとインターネット
悪意が暴走してしまう可能性はある。そもそもこの場合のネットいじめの被害者は「いけにえ」なのだろうか。
たしかにネットそのものへの関与を無くしたところで心の奥底に眠る問題を解決できたわけではない。むしろ闇は押し込められ拡がっていく可能性もある。しかも大人の目に見えないとkろで。それこそもっとも恐れるべき事なのかもしれない。
他の国の感覚、価値観を輸入する。あるいはそうった感覚自体が地球規模で平衡化しつつある家庭なのかも知れない。
P146 「世界を今まで以上にフラットにできると思います」
インターネットの機能ををベースにした世界を持つ人々
P157 「デジタルネイティブは世界の風景を変えていけると思っています」
これこそが一番大きなテーマであろう。過程は非常に困難かも知れない。押さえつける力は強いかも知れない。しかしネットワークで繋がった若者、何かを共有できている若者は既存の組織の中で凝り固まっている人々よりもある意味で緩やかでかつ緊密なつながりを持っている。それは今までの人類というか20年程度前の社会からではまったく想像できない力を持つ可能性がある。それは既存の社会構成員からすればまさしく「ブラック・スワン」と言えるかも知れない。
P158 「彼らにとってインターネットは意識的に使う「武器」ではなく、あらかじめ備わった「言語」のようなものなのだ」
呼吸をしている様にネットを使う。
もちろんそういったインフラが整っているからこそ、と考えることは必要だ。インフラ投資をしてきた社会が存在しなければ今の様な状況は生まれてこなかった。
しかし、それは人類的な後押しがあったのかも知れない。この変化は密かに要求されたいたものなのかもしれない。それをプログラミングされたロボットのように機械的にこなしてきただけなのかも知れない。
チャプター4までは基本的にポジティブなインパクトのお話になっている。
チャプター5はそんなに単純なものではない、という影の部分も一応描きながらもネットが持つパワーとそれを当たり前の様に使う世代のインパクトを伝えている。
一人の人間の人生のダイナミズムの幅が拡がってきている
P186 「デジタルネイティブというブログとかSNSとかメッセンジャーとかそこらへんに精通しているというバックグラウンドがあって、更にその上にチャレンジスピリットが乗っかっている感じ」
基本的に社会を大きく動かすのは志を持った一部の人。今の世界ではそれに引っ張られる人の数とその伝播のスピードが今までとは比べものにならないぐらいアップしている。情報に反応し、行動に移せる人。情報浸透圧が圧倒的に低い世代。それがデジタルネイティブたちなのかもしれない
なぜネットの世界はこんなにポジティブに語ることができるのだろうか。梅田氏の書籍もそうだ。驚くほど、人によってちょっと引いてしまうぐらいのポジティブさで書かれている。今の日本社会を同じくらいのレベルでポジティブに語ることができるだろうか。もしやったとしてもただ現実認識が甘いだけのものになってしまうだろう。この根本的な差はいったい何なのか。日本が日本語、日本文化、日本市場で閉じてしまっている、ということもあるかもしれない。そこから脱出する人々は増えてきているが、それでも多くの人はその中にとどまり続けている。
おそらく変化への期待値というのがあるのかも知れない。すくなくとも今の日本において、世界を変えられるかも知れないというインパクトはほとんど感じられない。そういう意味では日本は衰退しているわけではない。経済で世界のトップに立ったときですら世界を変えるインパクトは持っていなかったのだ。世界を少し買えるだけのお金はあったかも知れない。でもただそれだけだ。
今のアメリカは経済で痛手を負っている。
しかしツイッターという新しいサービスがもつ可能性は今参加しているユーザーですら計り知れないだろう。それはブラック・スワン的なものかもしれない。つまりまったく予想外のインパクトがそこから出てくるかも知れない。すくなくともその可能性は感じられるサービスである。
世界を変えるというのは世界のあり方を変えるだけではない、そこに存在する人々の意識すら変えてしまう、ということだ。
そんな世界においてデジタルネイティブはどのように動き、そしてデジタルネイティブと調和できない人々はどこに行ってしまうのだろうか。
Posted by ブクログ
とてもライトな体裁で、あっさり読めるけど内容は充実。 NHKで制作された番組のまとめで、取材者が主観を交えながら 再編集をしているような体裁でつづられています。 僕は放送を見ていないのですが、とてもわかりやすかった。 デジタルネイティブという概念と、 もう台頭しつつある実例は、僕みたいにWebの中の人にも新鮮。 武器として習得したわけではなく、「ネイティブ」な感じで Webに接して活動している人が普通にいるのは事実。 しかも+の方向に積極的な姿勢がすごくいい。 この本にもありましたが、たしかに日本だとWebのもつ 負の側面ばかりがピックアップされがちなんだよね。 けどWebのもつ本来の力と正しい活用法を自然体で体得した世代が もう前線で活躍していることを認めなきゃいけないんでしょうな。 すごくまっとうなWebの力と未来を予見させる内容でした。
Posted by ブクログ
私は社会人になってから初めてパソコン(インターネット)や携帯電話を持った世代です。小学生のときからそういった情報ツールに触れている世代が社会に出てくるとどうなるのだろうというのは、問題意識として持っていないといけないのかなと思っています。
"デジタルネイティブ"という言葉はうまくそういった世代を象徴的に表していると思います。本書はデジタルネイティブをテーマとしたNHKの番組の担当ディレクターが番組製作の過程も含めてまとめたものです。取材されたデジタルネイティブとされる個人が何人か紹介されていますが、違いますね。
途中にデジタルネイティブ度を測るテストがありますが、私は15点/100点。デジタルネイティブは100点に近いのだとすると結構まずいかもしれません...
小学3年生の息子は携帯メールもするし、少し教えてやると何だかネットサーフィン的なことをしています。がんばれよ。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
ネット・コミュニティを自由自在に使い、不特定多数の人々と瞬時につながることで、新たな事業や組織を次々と創り出していく「デジタルネイティブ」と呼ばれる若者たち。
従来の常識や価値観にとらわれない考え方や行動力によって、世界を一変させる可能性を秘めた彼ら新世代の今を追った最新ドキュメント。
NHKスペシャル番組の出版化。
[ 目次 ]
プロローグ 大人たちの知らない「デジタルネイティブ」の世界
1 全米を驚かせたデジタルネイティブ
2 「情報の私物化」を禁止せよ―ネットの向こうの不特定多数を信じる
3 デジタルネイティブが世界を支配する―解明が進む若者たちの世界
4 ネット上に「国連」をつくりだせ―デジタルネイティブの「フラット革命」
5 デジタルネイティブの「能力」のゆくえ
エピローグ 次代の扉を開けるデジタルネイティブ
ネットユーザーとテレビ制作者の新しい関係―あとがきにかえて
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
+++ ヒットしたフレーズ +++++++++++++++
・大きな組織にいることの方がリスク
・ネットの向こうの不特定多数を信じる(はてな:近藤淳也)
・日本初の世界標準をつくり、世界の人々の暮らしに影響を与える(はてな:近藤淳也)
●デジタルネイティブを雇うということは、その人だけを雇うということではなく、コミュニティー全体を雇う気持ちでいなくてはならない (→facebookへのアクセスを禁じる企業はナンセンス)
●伝統的な企業や政府組織は、組織に属する人間が個人として情報を発信することを警戒するが、デジタルネイティブは自身が情報を提供することに価値を見出す
・インターネットは弱者に力を与える
Posted by ブクログ
NHKの、同名の番組の書籍化。
番組は以前見たのだけど、本だとじっくり味わえて面白かった。
この本に登場している「デジタルネイティブ」は活力がすごいと思った。
『日本では若者が何か事件を起こすたびに、ネットにその責任を「ネット悪者論」がまかり通っているが、その空気がデジタルネイティブの可能性を発芽する機会を奪っているのではないか』ということがエピローグで述べられている。これには同意。
ネットの正の部分にスポットライトを当てた報道が増えていけばいいと思う。ネットに触れたことのない人には、なかなか理解されにくいことかもしれないけれど。
◆ メモ
・ネットベンチャー企業「アルカーナ」を経営する原田和英氏
・「はてな」の近藤淳也氏
・若くしてカードゲームを開発する会社を経営するアンシュール・サマー氏
・「ティグ」社会貢献活動を行う人々を支援するSNS機能のあるサイト。
・スティーブン・カソマ氏。ティグでエイズ対策活動を行い、エイズの国際会議にも参加した。
・『ネクスト』読みたい。
・ジャスティン・ベリー氏。19歳のとき、ポルノサイトを運営していたとして検挙された。
・モハメド・シドベイ氏。かつては少年兵だったが、逃走したところを他国の軍に保護される。「チャイルドソルジャー・ドットコム(現在は閉鎖)」というサイトを立ち上げて子どもの人権保護を訴え始める。
Posted by ブクログ
インターネットで知り合いになってあったことがある人が5人以上いる
定期的にチェックするブログが5つ以上ある
インスタントメッセージで友人と日常的にチャットする
等がデジタルネイティブ。恐るべし
Posted by ブクログ
- 番組の作り方とデジタルコンテンツの作られ方の対比
- デジタルネイティブだから何かを変えられるわけではない
- デジタルネイティブは実行力を加速している。
- ネットの向こうを信じる
- 世代間の距離が大きくなる事によるゆがみの可能性