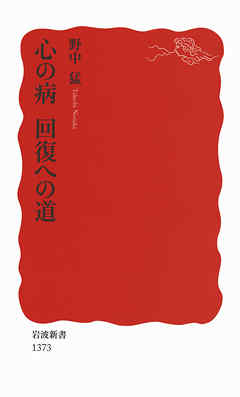あらすじ
職場で学校で、大きな問題となっている心の病。なぜ人は心を病むのか? どのような対処が適切で、回復には何が必要なのか? チームケアに取り組む精神科医が、身近な具体例と共に、精神障害者のおかれた歴史、精神医学の最新知見や、日本・世界の新たな潮流を紹介する。ハウツーにとどまらず、心にしっかり効く一冊。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
精神科の抱える患者の疾患の本質、それを扱ってきた医療や地域、回復に向けての試み。
新書という啓蒙書の形で、総合的に触れているので非常に読みやすいとともに全体像を理解するには良い本だと感じた。
内容は6章に分かれておりまとめると、
1章 精神疾患とは何かについての概論
2章 日本での精神病院などの対応の歴史
3章 精神疾患の仕組みと付き合い方
4章 リハビリの現在と取り組み
5章 世界での取り組み
6章 今後の取り組み(リカバリーすること)
のような内容になっている。ここから興味のもっているところを巻末の主な引用文献で読むこともよいと思う。
個人的にはいつも手元に1冊おいておきたい良書だと思った。
Posted by ブクログ
尊敬する野中先生の新書です。御自身の体験から、精神医療、保健、福祉についての歴史も含めて、わかりやすく解説され、特にリハビリテーションの部分は詳しく、最近のリカバリーな流れまで非常にわかりやすく述べられています。最後にチームワークで締められた部分も、チームワークをいかに作り維持するかが非常に重要であるとの訴えかと思います。特に初学者にお勧めしたい一冊です。
Posted by ブクログ
精神科医による、一般向けの解説書。
心の病を疑うべきはどのようなときか?
初期対応としてどのようなことが考えられる?
身体的な症状、主観的な体験、行動上の変化に異変が現れる。
不眠、食欲不振。幻聴などの声が聞こえること。仕事などに集中できず、それまでと行動が違うこと。
そして、重点的にページが割かれていると思ったのが、ある程度回復してからの社会生活支援。
たしかに、陽性症状などがおさまっても、社会生活に戻れなければ、結局生活は大変なまま。
先進国のほうが社会生活復帰が大変だというのが興味深かった。
たしかに、社会がシステム化されているので、戻るのが難しいのかもしれない。
正常と異常の区別も、シビアなものかもしれない。
長期的に考えていく必要がある問題なのだと思う。
問題提起として、わかりやすく読みやすい本だった。
Posted by ブクログ
心の病とは、脳の病である。
改めてそう言ってもらえると、少しほっとする。
世界と日本の精神保健システムについても最新情報で比較されてたり。
精神疾患のなかでも統合失調症など重いものが中心。リハビリについてとても詳しく書かれている。
アメリカや発展途上国における対処方法はすごいなーと。
Posted by ブクログ
「生活が不便であるのは、多数派に合わせた社会環境になっているから・・」という言葉はなるほどと思いました。
精神病理だけでなく、あらゆる障害もまた、治療の後に社会復帰するのではなく、障害と共に自らの人生を歩み出し、生涯に渡り「障害と付き合って」生きていく決断をしなければならないのだということなのでしょう。
それにしても、日本の行政が「友人の結婚式出席」は遊戯の範疇に入るということで、障害者年金と生活保護で暮らす人々に遠方に住む友人の結婚式に出席できなくさせているのは、なんて国なんやろう・・・・と思う。QOLということが福祉の現場で言われるだけでなく、国として、憲法の基本条項として、行政として・・・・、もっと考えてほしいものだ。