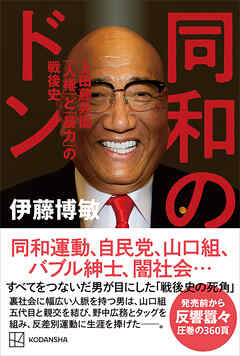あらすじ
政界でもメディアでも知らぬ者はいない「京都のドン」が初めて語った。没落と反抗、暴力と抗争の修羅場を経て、自民党系同和団体のトップとなった上田藤兵衞は、あらゆる差別と闘ってきた。その人生は、そのまま戦後の暴力団・同和・経済事件史そのものでもある。山口組五代目と親交を結び、野中広務とタッグを組み、部落解放同盟と拮抗した上田が見たもう一つの戦後史とは何か? 発売前から業界を賑わせている本格ノンフィクション。
...続きを読む感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「近刊」ということで一部の内容が紹介されていたのが偶々眼に留まり、興味を覚えて入手し、紐解いてみた一冊で。大変に興味深く、出逢えて善かった一冊となった。
非常に幅広い内容の「鎹」(かすがい)として上田藤兵衛という人物を取上げ、その伝記、関わった事案や事件に関する事を軸にしながら、前史等も含めて昭和、平成、一部は令和という時代の表や裏を語る感である。概ね、1980年代前半から極近年の2010年代末頃までの出来事や動向、そして昨年辺りの世の中の動きを踏まえたコメントも在る。
世の中の色々なモノを動かしている存在として、様々なモノが在る。政治、経済、官庁や自治体というようなモノに対し、暴力団のようなモノも在ったのであろうが、同和運動はそれらの結節点のような面も在ったのかもしれないという感を、本書の読後には抱かないでもない。或いは、少し独特な立ち位置のようなモノを、意図してか意図せずかで確立した上田藤兵衛という人物が、諸要素の結節点的な途を歩んだということなのかもしれない。
日本では古くから「穢れ」(ケガレ)という概念が在る。“死”に纏わる事柄がその「穢れ」(ケガレ)の最たるモノとされている。が、遺体や陵墓に関する事柄、処刑に関連する事柄、動物性の材料―皮革、骨、肉等―を扱う事柄というような仕事は存在し、それに携わることになる人達は登場する。そうした人達の「穢れ」(ケガレ)は「拭い悪いモノ」と認識され、被差別階層というようなモノが形成された経過が在る。
その被差別階層の経過は永い訳だが、江戸時代の身分制度の中でそれが固定的になって来た。そして明治期に身分制度が廃されたのだが、差別は残ってしまった。そういうことの解消を目指さなければならないとする動きが、所謂「同和運動」の流れを作って行くこととなる。
被差別に関係する人達にも色々と在るということが本書には在る。上田藤兵衛に関しては、「被差別」に該当する場所の出身ではあるというが、別段に貧しい生い立ちとも言い悪い。「夙」(しゅく)と呼ばれるそうだが、京都市山科区に在る天智天皇の陵墓を護るというような活動に従事した一族の後裔に相当するそうだ。上田藤兵衛の何代か前から事業を手掛けている<若藤>という号の商家で、立派な家に暮らしていた彼は「若藤のぼん」と近所で呼ばれていたという。因みに上田藤兵衛の「藤兵衛」は家の後継者が代々名乗っている名で、母親の意向を受けて「高雄」という青年期迄の名を改名したそうだ。
その後、上田藤兵衛の家では事業が傾いてしまう。そして無頼な青春時代に入る。一時は暴力団の組員に組み込まれそうになったが、それを断る。そして自身の様々な仕事の他方で「同和運動」に関与することとなる。1980年代初め頃のことになる。
こういう「前置き」的内容が提示されながら、1980年代最初の頃の「同和」は既に「利権」が在って、それが暴力団をも誘引するような状態になっていたということが説かれ、その後の展開が綴られるのである。
本書では非常に幅広い内容の「鎹」(かすがい)として上田藤兵衛という人物が在るのだが、もう一人の鍵となる人物も登場する。野中広務である。
野中広務は京都府出身の政治家だった。京都駅の近くに構えた事務所が「八条口」と呼ばれて、昭和の頃の自民党の有力な代議士の典型的な活動も展開した。が、野中広務は「同和」に関することでも知られている。
野中広務は園部の出身だ。江戸時代に移封して陣屋を構えた大名に従った、武具等の皮革製品を扱う職人だった一族の後裔に相当するらしい。実家は農家だったのだが、「皮革製品を扱う職人だった一族」が在った場所は「被差別」ということになる。野中広務は青年時代に国鉄に勤務していたが「あの人は…」と言われていたことに衝撃を受け、それを解消すべく政治を志し、町政、府政を経て国政に進んだという経過も本書に詳しい。
「同和運動」を巡って、野中広務は「利権」を廃することに心を砕き続けたのだという。そして上田藤兵衛はその考え方に共鳴する。「同和対策」や、改称した「地域対策」という「利権」の余地が残る考え方ではなく、差別を廃して必要な場合には人々を護り救うという「人権擁護」という考え方を推し進めようとしたのだ。
大雑把な本書の流れを振り返った。現在、その「人権擁護」というのは、社会のあらゆる人々を受容れる、あらゆる少数派を排除しないというような「社会的包摂」という概念になって来ている。上田藤兵衛の携わる運動は、その「社会的包摂」という考え方に傾倒しているのだという。
こういう大雑把な流れに加え、政界と財界との癒着の経過、暴力団の抗争や離合集散や“対策”を受けた変容の経過等、興味深い内容が満載の本書だ。
ハッキリ言うと、「自身が生きて来た時代」がスッポリと入った時間経過の中での、表も裏も、功も罪も織り交じった「歴史」が巧みに説かれている一冊だと思った。そしてそれを紐解くことは「モノを考える重要な素材」を得ることでもあると思う。幅広く御薦めしたい一冊だ。
Posted by ブクログ
全国水平社宣言がなされて100年を迎えるものの、今なお残る穢多非人への差別的思想・言動・制作に困る人たちも多いと聞く。そうした現状に、シンプルに正義を持って立ち向かう人もいれば、同和政策を逆手に取りその制度を悪用するエセ同和の出現や暴力団の関わりなど、多くの人が蠢き複雑に絡み合う過去から現在を一冊でなぞることができる。
なかなか学校では学ばない暴力団のシノギや団同士の抗争、企業舎弟の実情などみずから知りにいかないと知れないことが多々書かれており、かなり衝撃的。
二度読むことでさらに理解が深まりそうだ。
Posted by ブクログ
1冊の中で知れる範囲と人物が多くて自分程度の知識ではその全てを深く理解するというより文字が通りすぎていく状態の部分も幾つもあり、詳しい方ならとんでもなく楽しめたんだろうと思ってしまうのが悔しくもある
Posted by ブクログ
小学生の時に教科書で「部落差別」というのを知って衝撃受けたのを思い出した。沖縄にいると(時代かもしれんが)実感としてまったくリアリティがない部落差別問題(むしろこの本でも言及されてるように「部落」という言葉を母親は単に「集落」という意味で使ってたと思う)。
同和利権というフレーズや、なんだかヤクザっぽい団体が絡んでるのも大人になってなんとなく知ってたけど、その歴史が端緒から知れたのは良かった。複雑な組織構造というか組織の歴史があまり頭に入ってこなかったところはあったけどそこはそこはご愛嬌。あと主人公の上田さんがどう「ドン」なのかもよくわからなったけど、今も戦いを続けていて、かつそれは部落から今はもっと普遍的な”包摂”を求めているところは、ステキ。
まだ決して終わっていないし忘れてはいけない日本の闇。闇で終わらせてもいけないし。
もっと敏感でいたい。