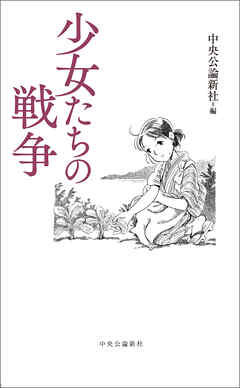あらすじ
「サヨナラ」も言えぬまま別れた若き兵士との一瞬の邂逅、防空壕で友と感想を語り合った吉屋信子の少女小説、東京大空襲の翌日に食べたヤケッパチの〈最後の昼餐〉……戦時にも疎開や空襲以外の日々の営みがあり、青春があった。
太平洋戦争開戦時20歳未満、妻でも母でもなく〈少女〉だった27人の女性たちが見つめた、戦時下の日常。すぐれた書き手による随筆を精選したオリジナル・アンソロジー。
〈目次〉
若い日の私●瀬戸内寂聴
美しい五月になって●石井好子
私を変えた戦時下の修学旅行/十五日正午、緊迫のNHK放送室●近藤富枝
「サヨナラ」がいえなかった●佐藤愛子
空襲・終戦・いさぎよく死のう●橋田壽賀子
海苔巻きと土佐日記●杉本苑子
続 牛乳●武田百合子
半年だけの恩師●河野多惠子
はたちが敗戦●茨木のり子
人間が懐しい●石牟礼道子
親へ詫びる●森崎和江
戦争/敗戦の夜●馬場あき子
「田辺写真館」焼失 母は強し●田辺聖子
めぐり来る八月●津村節子
葦の中の声●須賀敦子
被爆前後/一個●竹西寛子
にがく、酸い青春●新川和江
ごはん●向田邦子
か細い声●青木 玉
国旗/終戦の日●林 京子
よみがえる歌●澤地久枝
夏の太陽●大庭みな子
子供の愛国心●有吉佐和子
スルメ●黒柳徹子
サハリン時代●吉田知子
戦争の〈おかげ〉●中村メイコ
青い空、白い歯●佐野洋子
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
例え戦時中でも、流されず確固たる自分を持っている少女達。だから彼女達は、自己を成長させ、その後の人生が輝くのだ。迎合せず感性の赴くままに生きる事は、何と素晴らしい事か!
Posted by ブクログ
女性著名人27人が戦時中の思いを綴った本。
サヨナラと言って別れることが出来る別れは倖せ。
人は生まれてくるのに十か月もかかったんだ、死ぬのにもそのくらい必要だ
さようなら→「そうならねばならぬのなら」という意味
この3つが印象に残った。
名前も知らない人を、ひと目見て恋したり
人間魚雷を作ってるとも知らずに作業したり
スルメをもらうために、何も分からず兵隊さんも見送るのに万歳と言ったり
そんな、子どもの頃の日常の出来事が書かれてた。
Posted by ブクログ
昨年の2021年は、対米英を中心とした1941年12月8日の太平洋戦争開戦から80年の節目の年にあたり、中央公論社新書編集で女性27名のエッセイが発行された。最年長は、開戦時19歳だった故・瀬戸内寂聴氏、最年少は3歳の故・佐野洋子氏。非日常が中心となった戦局の日々の中で、幼少期・青春期を戦時下で送った日常生活が切々と綴られる。ある少女は空襲を逃げ惑い、ある少女は満州、樺太、ジャワ島などで終戦を迎える。戦場で繰り広げられる生死を彷徨った戦争の対極に、銃後の守りを強要された非戦闘員、少女たちがどのように考え、生きたか。そして、戦後には執筆・分筆活動で戦争の愚かさを訴えた27名の著者、中央公論新社の編集者に敬意を表したい。
Posted by ブクログ
この本は、1941年(昭和16年)12月8日の太平洋戦争開戦時に、満20歳未満だった女性によるエッセイを著者の生年順に収録したということ。
最年長、1922年生まれの瀬戸内寂聴さんと、最年少1938年生まれの佐野洋子さんの年齢差は16年。
この時代、男性は生年がたった一年違うことで生死を分けられた。
女性たちも、年齢によりまたは住んだ場所、環境により、さまざまに違った体験をしたことだった。
瀬戸内寂聴さんは、その青春の中で、運よく「良き時代」の最後を味わうことができたと書かれている。
軟弱、と当局ににらまれながらもまだ音楽を勉強することができた石井好子さんは、
優れたユダヤ人の先生方が弾圧から逃れてきていたお陰で日本の音楽界は発展したと書かれている。
終戦の年の1年間、NHKのアナウンサーだった近藤富枝さんは、玉音放送の緊迫の現場を目撃する。
軍艦マーチの前奏付きで大本営発表を読むのがそれまでの仕事だった。特攻隊の戦果、戦死者名と二階級特進の発表は一番辛い仕事だった。
「やらされた」戦争という感が大きい。
まだいかなる思想も持たない、少年少女たちのまっさらな頭の中は、軍国教育で黒く塗りつぶされていった。
力を持った軍部には、政治家も、天皇陛下さえも抑止力を持たなかった。
ましてや弱い女子供には。
しかし、自分には戦争責任はなかったのかと振り返る人も多い。
学徒動員で、挺身隊で、工場で作らされていたものが人間魚雷や特攻機の部品だったと知った時、自分の手は若者の命を奪ったのだと愕然とする。
無邪気に日の丸を振ってお見送りをした兵隊さんたちの、一体何人が帰ってきたのか。
原爆の光を隣の町で見て、被爆した人たちを見て、もう夏の太陽は自分には違ったものになってしまったという人。
一瞬で奪われた友達に、今の文明を見せてあげたかったと偲ぶ人。
戦争は、誰も幸せにしない。
Posted by ブクログ
太平洋戦争開戦時に20歳未満(3歳〜19歳)だった作家・女優ら27人の“すずさん”。「この世界の片隅に」のエッセイ版といった趣の本です。こうの史代さんのカバー・扉イラストも良い。今は亡き瀬戸内寂聴さん、今なお健在の黒柳徹子さんらが綴った少女目線による戦時下の日常が胸に迫ります。どこまで理解できるか分かりませんが、戦争ものとしての敷居は低いので、今の子たちにこそ読んでもらいたいですね。
Posted by ブクログ
有吉佐和子、大庭みな子などの女流作家により描かれた太平洋戦争のさなかの少女たちの非日常的風景。
その頃「ああ、私はいま、はたちなのね」と、しみじみ自分の年齢を意識したことがある。眼が黒々と光を放ち、青葉の照りかえしのせいか鏡の中の顔が、わりあいきれいに見えたことがあって……。けれどその若さは誰からも一顧だに与えられず、みんな生きるか死するかの土壇場で、自分のことにせい一杯なのだった。十年も経てから「わたしが一番きれいだったとき」という詩を書いたのも、その時の残念さが残 ったのかもしれない。(はたちが敗戦 茨木のり子)
おかずは、きれいに殻をむいた茹で卵一個であった。
他人のお弁当のことを書くなど、われながらはしたないと思う。けれども、未だにあの時の友達の、首をすくめた姿が忘れられないのである。 他の友達のお弁当など思い出しもしない。あの茹で卵一個は、彼女にとってはまさにものすごい贅沢であり、私も彼女のよろこびを素直に自分のよろこびとすることが出来た。そういう時代だった。
三十八年前の夏に、彼女は広島で被爆して亡くなったと聞く。 (一個 竹西寛子)
Posted by ブクログ
日米開戦時(昭和16年)二十歳未満だった女性によるエッセイを、著者の生年順にまとめた本。当時19歳だった瀬戸内寂聴さんを筆頭に、3歳だった佐野洋子さんまで、27人の名文が載っている。
書いた時期、目的とも、50年以上前から15年ほど前までそれぞれ。それぞれに、少女たちの戦争があり、日常があった。文は簡潔で素晴らしくとも、書いていることは、私たちとは変わらない「小さきもの」たちの見た世界。
瀬戸内寂聴さんは、太平洋戦争開始の報を受けても、女子大のクリスマスでは七面鳥を食べたし、鮮満旅行にも参加している。音楽学校に通っていた石井好子さんたちは鶯谷のおしるこ屋で目当ての美青年に「紫」と名前をつけていた。最後ののんびりとした時代だった。
茨木のり子さんの開戦時は女学校の三年生だった。「暗雲はいちどきに拡ったのではなく、徐々に徐々に、しかし確実に拡がっていって、気がついたときには息苦しいまでの気圧と暗さで覆いかぶさるようになっていった」石牟礼道子さんは敗戦の頃代用教員をしていた。その頃、年齢不詳の骨と皮だけの少女を拾った。復調したあと復員兵に出身という加古川へ送って貰ったけど、のちのことは一切わかっていない。「それでも、生あるものたちや、人間が懐かしいから、在るがままに視ているよりかしかたない」
敗戦の年、大庭みな子さんは広島の本川小学校の収容所で、被爆者の介護をしていた。朝に生きていた人が昼には亡くなる。白骨は方々に散らばっている。14歳の夏ことだった。小学生だった黒柳徹子さんは、スルメ欲しさに出征する兵隊さんの集まりを探しては、旗を持って「万歳」を叫んでいた。後に「私も戦争に加担したんじゃないか」と発言した。
本書を読んでいる時に、偶然、戦時少女だった方の聴き取りをした。それを末尾に、支障がない程度でこっそり紛らわせてみたい。
1945年6月22日、倉敷市水島三菱飛行工場を破壊する目的で水島空襲が起きた時に、Mさんは幼稚園年長組だった。工場の川を挟んで数十メートル先の農家の8人家族だった。ずっと空襲警報が鳴って怖いのでよく眠れていなかった。朝8時過ぎ、警報が鳴って防空壕に入る。とは言っても穴を掘ったものではなくて、目標になる家を避けて、田んぼの中に稲藁で屋根を作った小屋のようなモノ。そのすぐ2-3メートルほど先に爆弾は落ちた。砂を被った。後で直径10mほどの穴が開いていた。幸い家族は全員無事だった。空襲が終わって海軍さん10人ほどがやってきて、たくさんの牛が死んでいたので、腹を割って川で洗って、肉を持って帰った。あの赤色は鮮明覚えている。8月15日、近所のおじさんが「戦争が終わったよ」と言った。終わっても2日ぐらいは眠れなかった。3日ぐらいから眠れ出した。爆弾が落ちて戦争が終わった。
Posted by ブクログ
色んな年齢の方の戦争体験を色んな表現で読めるのがとても新鮮やった。
同じ時期に生きておられても、場所や年齢が違うことによって体験や思想に違いが出るのが凄いと思った。
今のコロナの時代も、場所や年齢や立場の違いによってみんなの体験や思想に違いがある。
そういう事なんやろな。
昔を学んで、今に繋げる。
もっともっと沢山の事を勉強せなあかんなぁとまたしみじみ感じた。
Posted by ブクログ
最年長 瀬戸内寂聴さん
最年少 佐野洋子さん
向田邦子さん、黒柳徹子さんなど戦時中少女であった27人の著名な少女たちのエッセイ。
軍国主義教育を受けて育った彼女達は、ロシアの少女達の環境に近いのかもしれないと思った。
Posted by ブクログ
開戦時に少女だった著名な文化人の戦争についてのエッセイ。同じ世界線に生きてるものの、そこにはそれぞれの戦争があった。中村メイコさんの「戦争のおかげ」がとても印象に残った。社会が沈んだ状況での生き方の参考になったかな。
Posted by ブクログ
『戦争は女の顔をしていない』(スヴェトラーナ・アレクシエーヴィッチ著)の日本版?
銃後の暮らしぶりが、自然体に描かれている。
開戦時に、はたち未満の〈少女〉だった日本の女性著名人を、年齢順に並べてある編集がよい。
一番最後の絵本作家佐野洋子氏をして、うちのおふくろの2つ上、死んだオヤジと同い年か・・・。先の大戦を語れる人が少なくなっていく中、貴重なアンソロジー。
銃後の、なにげない暮らしぶりが綴られているものが多いが、死にゆく人に言えなかった「サヨナラ」につての佐藤愛子の考察、いさぎよく死のうとしていた橋田壽賀子の覚悟など、やはり、迫りくる戦火を身近に感じていた二十歳に近い年齢の女性のエッセイは、印象深い。
とびら絵の、こうの史代も良いね。