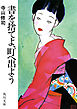寺山修司のレビュー一覧
-
寺山修司氏の1967年の著作を、1975年に文庫化したもの。
同じ寺山氏の1963年の著書『家出のすすめ』と何となくタイトルが似ていて、混乱します。
まあ、どちらも寺山氏らしい、とっ散らかったエッセイ集ですが、印象としては、寺山氏20代の著書である『家出のすすめ』よりも、寺山氏30代の著書である『...続きを読むPosted by ブクログ -
1976年に角川文庫から発売された寺山修司戯曲集。
内容紹介には、初期戯曲集とありますが、演劇実験室天井桟敷の初期の2編の台本と、天井桟敷以前の戯曲3編が収録されています。
自分、寺山氏の演劇作品は全く観賞したことがないんですが、寺山修司監督映画『書を捨てよ町へ出よう』と『田園に死す』は、なぜか好...続きを読むPosted by ブクログ -
原作のエッセイを読んで、いまいち分かりにくかったのだが、年配の友人に寺山修司ってどういう人?って尋ねたら、映画の方が面白いよと言われて読後に鑑賞もしてみた。
確かに面白かった。原作で読んだ言葉たちが繋がった。「書を捨てよ町へ出よう」とは「町そのものを書物のように読むべし」ことだそうだ。町とはそこに...続きを読むPosted by ブクログ -
短歌、俳句、詩、エッセイ、評論、演劇…。芸術のジャンルを軽々と飛び越え、その鬼才ぶりを発揮した寺山修司。言葉の錬金術師は歌う。故郷を、愛を、青春を、父を、そして祖国を。短歌の黄金律を、泥臭く、汗臭く、血腥い呪文へと変貌させる圧倒的な言語魔術に酔いしれる。Posted by ブクログ
-
《ノック(30時間市街劇)》という演劇の存在を知り、興味が湧いたので読んでみた。寺山修司という人が、天井桟敷や、映画や、詩などを通して何をやりたかったのか少しだけ分かった気がした。当時はあらゆる人間が、とにかく何か動かしてみること、行為を起こすこと、を求めていたのかも。私は今、あした何が起こるかわか...続きを読むPosted by ブクログ
-
戯曲も寺山修二も初体験。想像していたより、エンタメ色のある楽しい戯曲だった。
「毛皮のマリーになんて、なるんじゃなかった!」醜女のマリーを演じてみたい。
---------------------------------
他の方のレビューを読んで、「さらば、映画よ」がサイコパスにて引用されていたこと...続きを読むPosted by ブクログ -
どきりとさせられる言葉が随所にみられ、瑞々しい感性にも触れられた。「そう 恋のまたの名はおばけだよ」などなど思春期に読んでいたらもっともっと心にきたであろう。でも読めて良かった。次は音読したい。Posted by ブクログ
-
愛や恋、海などを題材にした詩が多いのが印象的である。他にも短い物語なども見られる。
詩人の表現力の高さには驚かされるばかりである。身近な題材であるが、それをとことん追究する様子は一種の哲学のように思える。Posted by ブクログ -
『本を読むということは「人生をおりている時の愉しみ」か、あるいは「人生を何かによって閉ざされている状態の代償行為である。』
『「正義」の最大の敵は「悪」ではなく「べつの正義」なのだ、というのが確信犯の倫理である。』
『想像力があれば存在することができる』Posted by ブクログ -
思わず一気読み。今でいう中二病的視点と俗っぽくて場末のスナックで一人呻いているおっさんのような人間臭いユーモアが同居していて、寺山修司の人間としての深みがアンバランスな文章に浮き出ていて面白い。笑うに笑えない、または笑えないのに笑えてしまう、というか。真面目に競走馬のセックスについて綴られている場面...続きを読むPosted by ブクログ