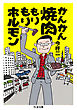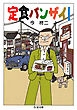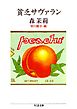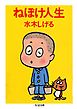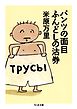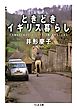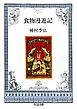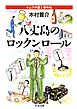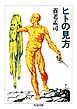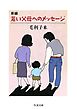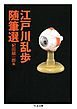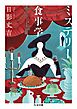エッセイ - 筑摩書房 - ちくま文庫作品一覧
-
3.0
-
4.0
-
3.7
-
5.0
-
4.2
-
3.7
-
-
-
4.1
-
4.3
-
-
-
4.3
-
5.0
-
3.4
-
-
-
5.0
-
-