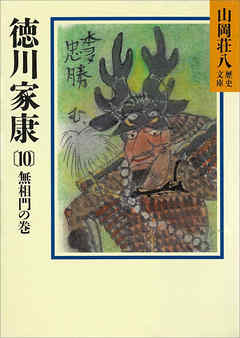感情タグBEST3
Posted by ブクログ
小牧・長久手の戦いをメインにした巻。
家康と秀吉の読み合い、駆け引きが面白い。その間に石川数正の苦悩が絡む。
最後は於義丸(家康の次男)の養子の話が出て、どうなるか?
Posted by ブクログ
賤ヶ岳の戦勝祝いに秀吉のもとへ使者を派遣するのに誰かという問題と石川数正の煩悶、織田信雄に頼られ小牧長久手の戦い、榊原康政や本多忠勝の活躍に池田恒興や森可成の戦死、戦後の秀吉との人質や大坂伺候などの駆け引きなど。
Posted by ブクログ
いつか読もうと思っていた作品。「豊臣秀吉」、「織田信長」はある程度知った気でいたので、戦国時代の三大英雄、最後の一人を知るためにと思い読み始める。
結果、非常に感動した。司馬遼太郎作品や池波正太郎作品、世の中の一般的な「家康像」を覆す作品であった。家康がなぜ天下を取り、そして江戸幕府260年の平和な時代を築けたのか、おぼろげながら理解できた気がした。
また、著者の目を通して描かれた「家康の思考法」に強く感銘を受け、自己統制の本としても傍に置きたいと思った。
Posted by ブクログ
この巻は小牧長久手の戦い。戦いに至るまでの経緯が詳しくて、信雄の無能ぶりが目につきました。前の巻辺りから感じましたが、流石に家康を主人公にしている作品だけに、ここまで読んで感じたのは、秀吉をどちらかと言うと悪者とまではいいませんが、好意的には書かれていないところ。この辺りは司馬遼太郎作品や、池波さんの作品とは全く違うところ。肝心の戦いは、誰がどこに行ってこうしてああしてと、あっち行ったりこっち行ったりで、分かりにくかったです。でも今まで漠然としか知らなかった石川数正のことがよく分かり、へぇーこんな可哀想な人だったんだとちょっと勉強になりました!
Posted by ブクログ
ほぼ小牧・長久手の戦いに割かれている。
それと、家康の重臣である石川数正の登場場面が際立って多い。
その後に起こるある重大事件を予期していると思われる。
Posted by ブクログ
小牧・長久手の戦い。
天下を狙う者たちとの死闘。
今川義元とのときは膝を屈し、武田信玄には壊滅的打撃を受け、織田信長には正室と嫡子を差し出した家康。秀吉とは互角以上の戦いをやってのけた。
軍事的にはやっと日本の頂点に達しつつあるようだ。
駿遠三甲信五カ国の太守になっても麦飯喰らいの家康。
堺商人を取り込み、商業から富を得る秀吉に対抗するにはそれ以外に手はない。
外交下手の三河武士たちは素朴朴訥に命を捨てる最強の野戦集団であった。
家康はついに強みを生かして日本最強の軍事国家を作った。
堪忍・内政・農業資本の家康。
知略・外交・商業資本の秀吉。
さて、天下はどこに行く。
Posted by ブクログ
小牧・長久手の戦いがメイン。
家康、秀吉、双方譲らず。
知能戦が繰り広げられる。
ただ、突進していくだけが戦ではない。
勝つためには、退く勇気も大切。
大局を見て、時にはわざと負けることも大切なのだ。
Posted by ブクログ
大権現様が時勢を味方に付けた者との戦いを堪え忍ぶ10巻。
何もかも思い通りにしてきた秀吉だったが、
全てをお見通しの大権現様は思い通りにはならなかった。
だが、平和のために今秀吉を潰すのは得策では無いと考え、
兵を引き、講和を決意する大権現様。まさに神である。
そして苦しい立場に置かれる石川数正。
秀吉派の作家は冷たい徳川より温かい羽柴を選んだとし、
家康派の作家は徳川のために汚れ役を引き受けたとしている。
どちらがより史実に近いのかはもはや誰にも分からないが、
三方原や伊賀越など苦難を一緒に乗り越えて来た
主君や仲間たちをそう簡単に捨てられるかと考えると、
願望もあるが、後者の方がより事実に近いのではと思う。