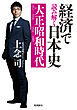上念司のレビュー一覧
-
丁度去年(令和元年)の今頃、この本の著者である上念氏の「経済で日本史シリーズ」を読んでいました、最近近くの本屋さんで似た様な装丁の本が並んでいたので手に取ってみました。勿論タイトルも気になったからですが。。
今では既得権という言葉が使われてマイナスのイメージがありますが、できた時には必要とされた規...続きを読むPosted by ブクログ -
日本史の教科書には足りない歴史的な出来事を
起こした人々の「意図」「背景」まで踏み込んで
語っている。また歴史的な出来事の羅列ではなく、テンポよく文章化されているので、読んでいても時間の経過を感じない。室町時代の貨幣経済の仕組みなどの解説でサラリと経済学の知識が使われており、このシリーズを読むと同時...続きを読むPosted by ブクログ -
なぜ前職がホトホト大嫌いになって”謀叛”を起こしてやろう、という気持ちになったのか。
自分でもうまく説明できなかったけど、この本に説明してもらった感じ。Posted by ブクログ -
上念氏と同年代なので、卒業・就職・結婚・子育てと社会を意識しながら生活してきた平成。ニュースもそれなりに見ていたはずなのに、何も見えてなかった事に愕然としました。無知は罪。反省しました。Posted by ブクログ
-
地位財と非地位財の話はなるほどなと思った。少し前まで自分もブランド物が欲しい!といった物欲があったが、今はそういったものにほとんど興味がなく、自分が成長するために読みたい本や観たい映画などに投資しているので、非地位財へお金を使うことにシフト出来ているのかな?笑
株などの話は専門的知識もないしよく...続きを読むPosted by ブクログ -
たかだか250ページの本に一ヶ月半も掛かってしまった…今年はほんと読書に回す時間が取れない…と言い訳
やっぱり歴史は繋がっているので大東亜戦争へたどり着くまでに一次大戦辺りからの世界情勢を踏まえておかないと訳分からんになりますわな〜金本位制への復帰後の世界経済の流れやブロック経済の影響など日本国内に...続きを読むPosted by ブクログ -
上念さんが言われる様に「自分教」を確立することが大事なんだと思います。じゃんけんで100回勝ちたければ、最低300回勝負すればいい。お金にまつわる見方が変わります。でも、住宅ローンで家を買った人にはやや厳しい内容かもです。Posted by ブクログ
-
上念さんの本は、とりあえず、飽きるまで全て購入してますので読もうと思っている。
彼の人となりが良く感じられる本。YouTubeでアップさせるたびに見ているので既読感は否めず、ただ、それを承知で読んでいる。
人生の長期計画を始めたばかりで、なかなかこれから先は見えないが、とにかく、こっちは工場広げて稼...続きを読むPosted by ブクログ -
1.何をもって日本の経済を1位と言っているのかを知る
なぜ借金説が蔓延しているのかを知る
2.日本政府の資産は約700兆円にのぼり、このような国は珍しいとされている。日本の財政に対してのイメージは、「財政赤字なので増税して税収を増やす」「財政縮小をして赤字を削減する」といったイメージが強いと思われ...続きを読むPosted by ブクログ -
室町時代の宗教は何をしていたのか?が面白い。
今の宗教観とは全然違った。
お金は銅銭が流通
銅銭は国内で鋳造されたものでなく、隣国、明から輸入していた。
明と貿易をしていたのは僧侶だった。
僧侶は仏教を持ち込んだのと同時に貿易商人でもあった。
国内のものを持ち込んで銅銭を手に入れていた。
お金持ち...続きを読むPosted by ブクログ -
一部ご紹介します。
・デフレ:モノとお金のバランスがお金不足により崩れること。2年以上連続して物価が下がり続けること。
・デフレ継続→物価下落→財布の紐固くなる→支出の先延ばし→モノ売れなくなる→給料安くなる→デフレ継続
・デフレ→就職難、中高年のリストラ、心の病、自殺
・デフレ→サービス残...続きを読む -
学校で学ぶ機会が少ない歴史の『意図』の部分を埋めるのによい本。当時の政治基盤を支えたのは、現代で言うところの巨大商社であり、日銀であり、金融組織であり、軍事力(これは主に応仁の乱以降だが)であった寺社の勢力。寺社の発展が幕府の財政基盤を満たし持ちつ持たれつの関係が構成された。また時代によって、その主...続きを読むPosted by ブクログ
-
諸外国との関わりが一層意味を持ってきた大正・昭和時代。戦争や内政の混乱などの原因の一つに当時の金融システムの脆弱性があった。それが本シリーズを通して議論されている金本位制。当時はグローバルスタンダードだったこの制度をどうして当時は積極的に採用していたのか。貨幣の天井が決まっているから、生産性の向上に...続きを読むPosted by ブクログ
-
江戸時代は歴史の授業で習うほど、庶民が抑圧され中央幕府がやりたい放題をするような社会体系ではなかった。歴史の見方を変えてくれる本です。庶民と言われる約9割が主役となり、産業を発達させ、新たな需要と共有を生み出した。また、石高制と貨幣制度が同時に現れ、バックにあるゴールドの有無によってインフレとデフレ...続きを読むPosted by ブクログ
-
シリーズ4冊目。
明治維新から日露戦争までの経済の流れだけでなく、なぜ清やロシアと戦争に進んだのかも分かりやすく説明してくれている。
お隣の国もこの頃からクレーマー体質だったことも書かれていたりと非常に興味深い内容でした。
遼東半島をめぐり、ロシアとの緊張が高まり、そこで日英同盟、そしてバルチック...続きを読むPosted by ブクログ -
高校の時、世界史を選択していたせいか、この本により勉強させられた。
特に、江戸時代の百姓(農民とは限らない)は思ったより豊かな生活をしていたという点だ。歴史についてさらに学びたいと思うようになった。Posted by ブクログ -
勝間和代さんらの「反デフレ」キャンペーンの第一弾。
ただ、後に「リフレ派」と呼ばれる「反デフレ」の本は、
多く出ていることも知る。
複数読んで理解を深めるのがいいと思います。Posted by ブクログ -
最近では「ニュース女子」の司会者としても活躍している筆者は、保守論客というより怒れるご意見番といった立ち位置になるのでしょうか。説得力がある断定的な発言は気持ちいい。本書が書かれた2018年11月時点で、政府の増税政策は間違っていると警告していますが、ご存知のように2019年10月に10%に引き上げ...続きを読むPosted by ブクログ
-
上念司の経済論的な主張を正しいと思っているので、多少荒さはあるものの、会社論的な中身も素直に腹落ち。というよりも、大企業勤務経験がある人なら、あるあると共感できるような事例が満載。調整が上手い人が評価されるのは分からないでもないが、調整上手だけだと、結局、事業の体をなさなくなる。テスト対策でもするよ...続きを読むPosted by ブクログ