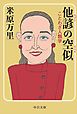米原万里のレビュー一覧
-
ハンガリーに住むなかで、中東欧に関する本を読みたくなり手に取った本。
3つの物語は歴史の話としても面白いが、根本的には子供や家族の人生の話である。
2000年前後に生まれた人間としては、フィクションのようにしか感じられない社会主義や民族紛争の世界で、実際に生きていた人々がいて、それぞれの考えや思いが...続きを読むPosted by ブクログ -
【305冊目】著名な日露通訳者による通訳、ひいては言語に関するエッセイ。知人に薦められて読んだが、興味深いだけでなく、笑える!裏表紙に「通訳を徹底的に分析し、言語そのものの本質にも迫る、爆笑の大研究」との紹介は、この手の紹介文にしては正確!
タイトルは、通訳をめぐるジレンマをたとえたもの。原文に忠...続きを読むPosted by ブクログ -
通訳の方って、
キャラの濃い方、結構いらっしゃるけど、
ここまで面白い方はそうそういらっしゃらない。
今の時代、
コンピュータが通訳も翻訳も
お上手になってしまったから
なかなかこういう方は表に出てこないのかしらん。Posted by ブクログ -
世界各地に、同じ意味の諺があるんですね。
世界のいろんな地域のいろんな国の人々の、長い時間をかけて作られ語り継がれてきた諺が、同じ意味で存在するとは、、人間が生きている間に起こるいろんな出来事、それに対する思い、そこから学ぶ教訓などが同じように存在するんだなぁ。すごい。
舌鋒鋭いのが持ち味と思います...続きを読むPosted by ブクログ -
宗教が根付いていない日本人の私には、海外の宗教紛争はいまいちピンとこない感覚なので、今回すすめられなかったら一生読む事はなかったでしょう。
故郷から遠く離れた子供たちが当然のように抱く「愛国心」。その表現は様々で、矛盾を抱えながら必死に生き延びる姿が胸をうちましたPosted by ブクログ -
読書会参加二回目、課題図書
いい本を挙げて頂いた
米原真理さんは「犬猫好き」で有名でエッセイも楽しませてもらった
有能なロシア語の同時通訳者だったそうで、ゴルバチャフさんのお気に入りだったとか
プラハの「ソビエト学校」の個性的過ぎる同級生三人
両親の生きざま、時代背景、国家まで背にして生きざるを得...続きを読むPosted by ブクログ -
作者の実体験を描いた本に「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」があるが、本書はこの実体験を下敷きに書いた作者唯一の(!)小説。
相当に衝撃的内容であるし文章構成も巧みである。ラーゲリについてこの本しか読んでいなかったら間違いなく星五つ。
が、同じラーゲリが舞台なのでどうしてもソルジェニーツィンの「イワ...続きを読む -
通訳という知らない世界と職業の方々の仕事ぶりや頭の中を垣間見ることができる一冊。
原文に忠実かどうかを貞淑と不実、訳した文の整いぶりを美女と醜女にたとえていて、ああ確かに不実な美女と貞淑な醜女のどちらがよいかはケース・バイ・ケースなのだろうなと思った。Posted by ブクログ -
1960年代、当時のチェコスロバキアのソビエト学校で学んでいた日本人、シーマ力が主人公である。通っていたプラハ・ソビエト学校にいた、オリガ・モリソヴナを中心とした各登場人物の謎を、ソ連崩壊直後のロシアにて次々に究明していく物語。なによりも時代考証が凄まじい。謎解き要素だけでなく、スターリン主義に巻き...続きを読むPosted by ブクログ
-
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」に次ぐ同著者の二冊目の本。
副題が「正義と常識に水を浴びせる13章」。文化の差異が異なる価値観を産み、異なる文化が異なる言語を産み、美味の評価も変わったり、異文化の交差でそれぞれの文化が際立ったり、また、それが異文化の排斥に繋がったり、文化と言語の違い等で愛国心が芽生...続きを読むPosted by ブクログ -
私は天邪鬼である。こんなご時世だからこそ、ロシア人やロシア文化を知りたいと、数年ぶりに手に取った米原さんのエッセイ集。
ボリス・エリツィンもミハイル・ゴルバチョフも、歴史の教科書で勉強した存在と、通訳という究極の身内から見た存在とはずいぶん異なっる印象を受け、興味深かった。
また、米原節ともいえ...続きを読むPosted by ブクログ -
●積読書だったが、やっと読めた。読み出したら止まらない。土日を費やした。
●今の国際情勢の時にソビエトの本を読むのは皮肉なものだけれど、本当に独特な国だと思う。
●今の屈折した結果も過去のしがらみが要因とも言えるし…
●一時期に、米原さんの本を集中的に買って読んだが、これがその最後となる。
●疾走感...続きを読むPosted by ブクログ -
以下、好きなエピソード。
* ナポレオンの愛した料理人
* 言い換えの美学
* 曖昧の効用
* 心臓に毛が生えている理由
* あけおめ&ことよろ
* 読書にもTPO
* 何て呼びかけてますか?
* 記憶力と年賀状Posted by ブクログ -
「薔薇の名前」で知ったアリストテレス「詩学」の第二部が現代に伝わっていたら、この本のような内容だったのではないかと思わせてくれる。小噺を通じて「笑い」が生じる普遍的な構造を探究した本。各章の最後に例題があって楽しめた。
著者の相変わらずの教養の深さテーマと読者への誠実な姿勢。本当の意味で真面目な...続きを読むPosted by ブクログ -
ロシア語の同時通訳の米原万里が、通訳にまつわるエピソードなどを紹介するとともに、同時通訳とは何か、ひいては、コミュニケーションとは何か等の深いテーマについても語った本。
題名が面白い。「不実な美女か 貞淑な醜女か」。同時通訳の現場には通訳のスタイルを決める2軸がある。ひとつは、原語、すなわち発話者...続きを読むPosted by ブクログ -
「嘘つきアーニャの真っ赤な真実」が好きすぎて、この本を読みました。作品の中で描かれる歴史が残酷すぎて衝撃でしたが、オリガ・モリソヴナが何者か解明していくのが気になって最後まで読みました。作品を通して、酷い歴史は繰り返されてはならないというメッセージも感じられました。Posted by ブクログ