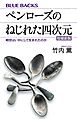世界的ベストセラーとなったユヴァル・ノア・ハラリ著「サピエンス全史」「ホモ・デウス」を思い出す。
何かのサイトで紹介されていた本書、気になり購入し、台風14号の影響による大雨で外出も出来ない休日を利用して読んでみました。
地球に生命が誕生してから38億年の歴史が約300Pに集約されていました。
...続きを読む
地球が誕生してからの過酷な歴史、絶滅と進化を繰り返してきた生命の歴史。
知らないことばかりで非常に興味深く読み終えることが出来ました。
レビュー
【目次】
1章 炎と氷の歌
太陽が生まれた瞬間
生まれたころの地球
コンロで煮えたぎる鍋のように
生命の誕生
三〇億年の支配者
宇宙でもっとも危険な物質
終末論的な災害
驚異のバクテリア
スペシャリストと分業制
もっと奇妙なこと
地球上の生命は……
2章 生物、大集合
超大陸の分裂
海綿のたゆまぬはたらき
肛門の発達がもたらしたもの
逆境の時代の回復力
奇妙な美しさを持つ生き物
食べられない方法を探す
「内側がない」動物
三葉虫はすごい
風変わりな生き物たちの動物園
頭足類の化石の歴史
カンブリア紀の生命の開花
化石記録に名を記した最初の魚
3章 背骨のはじまり
小さな生き物ののぞみ
「鎧」で防御する
逃げろ!
オズの魔法使い
体のほとんどが尻尾
脊椎動物の進化
人間はとても大きい動物
悪夢のような生物
「鎧をまとったヤツメウナギ」のように
全く新しい動物
最強の捕食者
最古の脊椎動物の微笑み!?
議論の余地
4章 渚に打ち上げられて
魚でごったがえした海
最初の樹木
緑に覆われる大地
葉っぱの下の小さなドラマ
ちょっと変わった魚類
保守的なシーラカンス
捕食者たち
四肢動物の足跡
絶滅の危機
足のある奇妙な総鰭類
パンゲア大陸の暗くて蒸し暑い森
彼らは、いつの日か……
5章 羊膜類あらわる
陸地の奪還
西部戦線のように
ヒカゲノカズラと石炭
両生類の繁栄
新世界に移住するための「宇宙服」
水の支配からの脱却
負債を返すとき
草食動物の奮闘
ディメトロドンの背中の帆
地球上を闊歩した樽型の生物
競争が激化した世界
追い詰められる陸上生物
絶滅、絶滅、絶滅
三葉虫の旅立ち
ほとんど生き残らず
生命は戻ってくる
6章 トライアシック・パーク
数千万年の復興
勝ち残ったものたち
は虫類のカーニバル
脚を失うトカゲ
五メートルの怪物
ワニのような「ハイウォーク」
空への進出
最古の恐竜たち
超大陸の分裂・生命の宝くじ
7章 空飛ぶ恐竜
五トンの怪物
恐竜の呼吸はすごい
史上最大の陸上動物
恐竜が成功したもう一つの鍵
恐竜、空へ飛びたつ
離陸する二つの方法
オルドビス紀のそよ風
小型ほ乳類のパラシュート飛行
始祖鳥の翼
命の灯火
飛べない鳥たち
無数の鳥たちのさえずり
菜食主義のワニ
花を咲かせる植物の登場
たった一撃で……
大絶滅、姿をあらわすほ乳類
8章 素晴らしきほ乳類たち
むかしむかし……
鼓膜の誕生
人間は耳が悪い
逃げ出した魚の顎関節
小さく、毛深く
カモノハシやハリモグラの祖先
代謝の速い活動的な動物
体重に匹敵する昆虫を食べよ!
ほ乳類は夜に遊ぶ
脂肪とタンパク質が豊富な「乳」
恐竜がニッチを埋める
ほ乳類の進化と拡張
有袋類の長く輝かしい歴史
とっちらかった世界
バスくらいの大きさがあるヘビ
クジラは海へ……!
急速に変わりゆく世界
9章 猿の惑星
南極の長い冬の夜
奇妙な新しい贈り物
類人猿の鳴き声
直立歩行のはじまり
腰痛が大きな悩みの種
動物界のエリート戦闘機
未解決の問題
樹上も、地上も
新鮮な肉と優れた石器
10章 世界を股にかける
終わりを告げる鐘
時には近く、時には遠く
地軸の傾き
ポラリスはやがて……
一〇万年ごとの寒波
深層海流の循環システム
ホモ・エレクトゥス
火を使う
「つがいの絆」と不倫
死後の世界はない
もっとも美しい道具の製作者
私たちが本当に世界を見ることができたなら
各地に進出するホモ・エレクトゥス
サイを狩る
数奇な運命
脳を維持するためのコスト
地球には巨人がいた
ネアンデルタール人の繁栄
アフリカからやってきた種
11章 先史時代の終わり
生命の繁栄
脂肪を蓄える目的
生殖と寿命のあいだ
長老たちの知恵
悲痛な叫び
ホモ・サピエンスの進出
ある場所では死に絶え……
熱帯気候化したヨーロッパ
道具の開発、高度な技術
壊滅的な噴火
移動する人類
ネアンデルタール人との交配
ネアンデルタール人の絶滅
洞窟壁画と儀式
12章 未来の歴史
絶滅の形
ホモ・サピエンスの絶滅の可能性
たった一発の銃弾
到来する氷河時代
独り占めする人類
「絶滅の負債」を返済するとき
大氷河時代
次々と死に絶える
地球の歴史と二酸化炭素
ゆっくりと着実に
分業と効率的な生産
もっと大きく、もっと速く、もっと遠くへ
生命の進化と多細胞生物
大地に広がる菌類
花の進化と昆虫の進化
「コロニー」は超生物
植物の未来
生命は深海や地中に集中する
約八億年後の未来
エピローグ
ホモ・サピエンスが特別な理由
「第六の絶滅」か?
私たちの惑星
人類の課題
地球の「外」へ
生命は……
年表1 宇宙のなかの地球
年表2 地球上の生命
年表3 複雑な生命
年表4 ほ乳類の時代
年表5 人類があらわれる
年表6 ホモ・サピエンス
参考文献
謝辞
注釈
訳者あとがき
索引
著者について
ヘンリー・ジー【著】
『ネイチャー』シニアエディター。元カリフォルニア大学指導教授。1962年ロンドン生まれ。ケンブリッジ大学にて博士号取得。専門は古生物学および進化生物学。1987年より科学雑誌『ネイチャー』の編集に参加し、現在は生物学シニアエディター。ただし、仕事のスタイルは監督というより参加者の立場に近く、羽毛恐竜や最初期の魚類など多数の古生物学的発見に貢献している。テレビやラジオなどに専門家として登場、BBC World Science Serviceという番組も製作。
竹内薫 【訳】
(たけうち・かおる)。1960年東京生まれ。理学博士、サイエンス作家。東京大学教養学部、理学部卒業、カナダ・マギル大学大学院博士課程修了。小説、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍している。主な訳書に『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』(ロジャー・ペンローズ著、新潮社)、『奇跡の脳』(ジル・ボルト・テイラー著、新潮文庫)、『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』(ポール・ナース著、ダイヤモンド社)などがある。
☆発売たちまち1万部の大重版!!
ジャレド・ダイアモンド(『銃・病原菌・鉄』著者)超絶賛!!
「著者は万華鏡のように変化する生命のあり方をエキサイティングに描きだす。全人類が楽しめる本だ!」
「地球の誕生」から「サピエンスの終末」まで。全歴史を一冊に凝縮!
地球誕生から何十億年もの間、この星はあまりにも過酷だった。激しく波立つ海、火山の噴火、大気の絶えまない変化。生命はあらゆる困難に直面しながら絶滅と進化を繰り返した。ホモ・サピエンスの拡散に至るまで生命はしぶとく生き続けてきた。本書はその奇跡の物語を描き出す。生命38億年の歴史を超圧縮したサイエンス書!