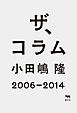小田嶋隆のレビュー一覧
-
面白い!東日本大震災からコロナ禍までのコラムを集めた、4年前発行の本。表紙の通り、当時の政権を斬り捨てていますが、ただ罵倒するのではなくユーモアや自戒を加える語り口はさすが稀代のコラムニスト。もっと長生きして欲しかった…Posted by ブクログ
-
この、安倍さんやその政権の諸々の担当者が作った無意味な日本語を垂れ流す事態は、その後の首相やその政権の担当者たちが変革し、日本語を取り戻すことができたのだろうか?
いやいや、そんなことは決して無いのだろう。
願わくば、この著者の遺志を継いだ人が同じテーマでこの本の続編を出してもらえないものだろうか。...続きを読むPosted by ブクログ -
読み手の世代を選ぶ本。アラ還の僕にはどの節の内容も響きました。その中でも、
「同窓会に出席してみた。」
「麻雀を打ってみた。」
が面白かったし、刺さりました。
”老い”というのは自分が思っている以上にきちんとやってくるもんなんだろうなあ、と思わせます。Posted by ブクログ -
小田嶋隆(1956~2022年)氏は、早大教育学部卒、味の素ゼネラルフーズ勤務後、TBSラジオのアシスタント・ディレクター、作詞家等を経て、コンピューター関連ほか、様々なテーマを論じるテクニカル・ライター、コラムニストとなる。
本書は、集英社のPR誌「青春と読書」に2018年7月~2019年10月に...続きを読むPosted by ブクログ -
著名コラムニストの過去の作品を再編集したもの。好みはあると思うが、本質をつき、議論を恐れない舌鋒にある種の爽快感と快感を得ていた読書は多いと思われ、あまりにも早い逝去が悔やまれます。著者のメッセージはいつ読んでも時代のギャップを感じないと改めて感じた。Posted by ブクログ
-
コラムニストであった小田嶋隆氏が複数の雑誌に掲載してきたらし短編小説をまとめたもの。鋭いキレがある訳ではないが著者ならではの切り口や著者の実体験に基づくと想像される内容もあり楽しめるPosted by ブクログ
-
もう、氏の知見を新たに拝見することは叶わない訳で、そんな中、新刊としてこういう書に触れられるのは僥倖。友達っていう、確かに考えてみれば曖昧な存在について、改めて立ち止まって考えてみるきっかけになりました。Posted by ブクログ
-
いろいろな試作的短編を集めたもの。断片集とでも言えるかも。残念ながら著者が死んでしまったため、このあとどういう方向に向かうことになるのか知ることはできない。Posted by ブクログ
-
はじめて著者のコラムを読んだのはバグニュースというパソコン雑誌だった。80年代半ばで高校生の頃だった。独特の語り口と考え方にすぐ夢中になったが、就職してからは疎遠のままであった。
訃報を受け、久々に著者の作品を手に取った。題材は社会的なニュースになり、より広範な人たちに向け警鐘を鳴らすような内容に変...続きを読むPosted by ブクログ -
人間が感情生物であるからこそ
「社会的な障壁を貫く本音」なるものが、判官贔屓とはまた違った意味で下駄を履き、SNSで闊歩する羽目になっているのかもしれない。Posted by ブクログ -
小田嶋さんの、軽妙だけどしっかりとした日本語で書かれた文章は読みやすくて、とても面白かったけど、扱われている事象がどうにも腹が立って読むのに中々に力が入りました。
なんでこんな愚かな人達に国の運営なんて任せなきゃならんのだ。
それを許してきたのが自分も含む有権者の怠惰だということが更に腹が立つ。
...続きを読むPosted by ブクログ