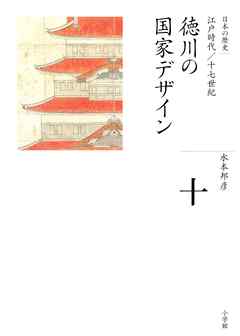感情タグBEST3
Posted by ブクログ
装丁の美しさと、タイトルの良さに惹かれて手に取りました。
よくよく見たら、歴史大全ものの1冊だときづいたものの、出版社の売る気満々的な雰囲気が伝わり読む事に。
ちなみにアートディレクションは、原研哉。
内容的には、戦国末から江戸初期(四代家綱)までの国政・地方の城下町・村・臣民などに分けて解説しています。
今までの歴史大全ものと違うのは、屏風絵の解説から入るあたり。
「洛中洛外図屏風」・「築城図屏風」といった屏風絵から、当時の風俗や政治状況などを読み解く。
ただ、屏風絵自体のレイアウト面積が小さいのと、解説と屏風絵のポイントのリンクが丁寧ではないため、分かりにくかったりします。
このへん強化したら、クオリティメチャメチャ上がると思うのですが・・・・。
特に1607年からはじまる、駿府城普請を描いた「築城屏風」絵図は解説と供にじっくり楽しみたかった。
また、為になったのは、日光東照宮に関する記述。
家康の神号については、吉田神道にもとづく明神号賜与となるはずだったのが、天海僧正の反対で山王一実神道になったということ。
天海が山王権現を推薦した理由としては、「自分は三界すべてに存在し、衆生はことごとく自分の子供である」と宣託されたあたりであるとか。
本書では、この山王權現こそが、キリスト教の一神教的な考え方と対決できる、日本の唯一の神であったのではないかとの説を唱えている。
農と自然に関する記述も面白く、徳川時代における農村の山野は、草柴山と木山が半々であったということだ。
山といえば、樹木が生い茂ったイメージしかもっていなかった私には新鮮であった。
特に里山のかなりの部分は草柴であったという。
理由は牛馬の飼い葉と農作物の肥料として、草柴が重宝されたからであるという。
ただ、そこには自然破壊という問題も含んでおり、大雨や台風の場合、草柴の山は地滑りを起こし、土砂が川へ流れ込むために洪水などを引き起こす原因となったらしい。
この、徳川時代の農民が自然との共生に苦心するあたりの記述が、眼の覚める思いでした。
また、細かい記述ですが、1701年に調べた中村藩15000軒の住民に対して、馬が17000弱いたというあたりであったり(さすが馬追の町!)、雨乞いの祈りが、能・踊り・相撲・競馬・火灯し・千度参り・絵馬など多彩であったことなど、この本を読まなかったら分からない部分は結構補足されました。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
戦国時代に終わりを告げた徳川の治世。
徳川社会の成立には政権づくりの巧みな手腕があった。
[ 目次 ]
はじめに 徳川の日本人
第1章 京都と天下人
第2章 首都と城下町の建設
第3章 村づくりの諸相
第4章 神国日本と「国民」
第5章 農と自然の風景
第6章 内国のネットワーク
第7章 徳川の「自治」と「権力」
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]