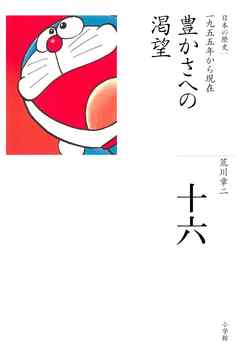感情タグBEST3
Posted by ブクログ
小学館創立85周年記念出版のシリーズの最終章。表紙にドラえもんっていうのがたまりません(これ決め手)。1955年から現在までの日本の歴史を政治や経済、人々の暮らしなどの側面で描かれています。1955年といえばまだ生まれる20年前、とはいえ親世代がリアルに生きてきた時代。両親のアルバムに載ってた白黒写真を思い出しながら読んでみたいと思います。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
物質的繁栄を求めた私たちが得たものとは。
高度経済成長からバブルを経て混迷と閉塞の時代へ。
[ 目次 ]
はじめに 私たちが選んだ道
第1章 「戦後社会」をめぐる対抗―一九五五年(豊かさへの離陸;戦後憲法的世界の広がり;沖縄と安保体制)
第2章 戦後大衆社会の成立―一九六〇年代(都市化と消費社会;欲望達成を支えた社会構造;欲望への異議申し立てと豊かさの質の提起;占領下沖縄と日本復帰;旧植民地・民衆と日本の戦後)
第3章 豊かさの成熟とゆらぎ―一九七五年頃(経済大国と過労働社会;総中流の時代と深部の変動;「戦後日本」への問い)
第4章 「戦後」からの転換―一九九五年頃(国内外の転換と新秩序;再編のしわ寄せ)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
14巻同様、多分に一面的・主観的なところや錯誤があるが、戦後の社会問題・社会運動史をまとめたような一冊。
一斉就職と終身雇用、性別役割分担はどのように誕生したか。セーフティネットへの関心の低さや競争主義、自力解決主義がなぜ浸透したか。公共政策より経済政策重視のあり方が生んだのは何か。戦争や公害などにおける被害受忍論の背景には何があるのか、日本国籍非保有者はどのように扱われたか。巨大与党体制に対し野党はどう動いたか……などなど、戦後の影の部分に焦点を当てて現在の日本社会がどのように成立したのかに迫っていく。
Posted by ブクログ
環境庁時代の頭を下げる石原さんが印象的。戦後社会運動についての広く浅い概説かんはぬぐえない。中卒業人口の大量就職は徴兵がないことからもいままでにないものだというのはなるほどと思った。また産児制限でベビーブームが終息していた。
Posted by ブクログ
自分が生きてきた時代の歴史というのは
案外、灯台下暗しである。
中学校、高校の日本史でもたいがい現代史のところは
ほとんど時間が足りなくなって、はしょられることが多い。
同時代の価値を定義することは、なかなか難しい。
小学館の「全集 日本の歴史 全16巻」は
小学館創立85周年記念出版。
新視点で日本の歴史をとらえた企画であると聞いていた。
原研哉アートディレクションの
どらえもんの表紙(さすがは小学館!)に誘われて
最終の第16巻「1955年から現在 豊かさへの渇望」(荒川章二)を
読んだ。
目次は以下の通りである。
第一章 「戦後社会」をめぐる対抗 ー1955年~
第二章 戦後大衆社会の成立 -1960年代~
第三章 豊かさの成熟とゆらぎ -1975年~
第四章 「戦後」からの転換 ー1995年頃~
歴史を勉強していていつも知るのは、
普段は日々の暮らしの中に僕たちの意識があるが、
俯瞰的、時系列的に社会を眺めると
そこには抗い難い力が働いていることだ。
大河の激流の中で、個人の存在、役割とはなんだろう。
一方で歴史書に書かれない市井の人々、
つまり大多数の僕たちの暮らしは厳然といま、ここにある。
その尊さを踏みにじられてなるものか、の思いは日ごと強くなる。
個人、家族、組織、社会、国家。
物事はいくつかのレンズで複合的に観察し、
同時に自ら思考し、判断し、行動することが大切なのだろう。
この本がキーワードにした「豊かさ」が戦後どう変化してきたか。
国家の求めた「豊かさ」と、
僕たちひとりひとりが求めた「豊かさ」は、
どこで一致し、どこで相反してきたのか。
そのことを考えてみる。
ゴールデンウィークは、
日頃虫の目で観ることが多い日々を
鳥の目で観直す絶好の時間であるように思う。
この本は、戦後から現代までの時間と、
そこに拮抗していた力の存在を
鳥の目で観察するのに役立つ本である。
世田谷美術館で開催中の写真展
「日本の自画像 写真が描く戦後 1945-1964]」を
この本と合わせてご覧になってはどうだろう。
自分たちの暮らしと国家の輪郭が見えてくる気が僕はした。