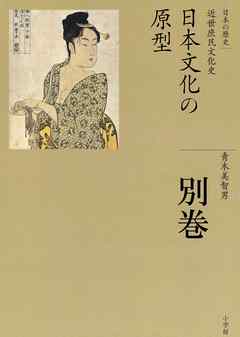感情タグBEST3
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
歌舞伎に旅にと庶民はいかに文化を楽しんだのか。
江戸の文化をひもとけば今の暮らしが見える。
歴史が未来を切り拓く。
[ 目次 ]
はじめに 江戸時代における庶民の生活文化
プロローグ 無事と士農工商の世
第1章 ねぐらから住まいへ
第2章 暮らしを潤す
第3章 学ぶ、知る
第4章 文具をつくる、文を書く
第5章 知と美を広める
第6章 食べる、着る
第7章 浮世の楽しみ
第8章 旅への誘い
エピローグ 『ごんぎつね』と環境歴史学
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
全16巻の「日本の歴史」シリーズの別巻として刊行されたもの。「近世庶民文化史」という副題が付いている。戦国後期から江戸にかけての庶民の衣食住に関してある程度網羅的に概観した意欲作。帯には、「江戸の文化をひもとけば今の暮らしが見える」とあるが、近世から現代にかけての庶民史の大きなストーリーが述べられている訳はなく、分かっている限りの事実の整理に徹している印象。全体通して感じるのは、庶民の「快適さに対する欲」かな。
個別的には情報量が物足りないという部分もあった。一冊の本にまとめているというページの制約上の問題と、筆者が何度も書いているように、庶民史に関しては研究が殆ど進んでいず、不明なことが多いのだろう。
最近、江戸時代の農家屋敷や、民俗資料館にあるような道具類(文房具や漆器類など)にかなり興味があるので、私には、全般的に面白かったかな。
例えば、第1章で農家民家の江戸自体を通しての細かい変遷が触れられているが、それを読むと江戸時代初期の普通の家は相当に質素で、そもそも板間などが存在しないのが普通だったようだ(土間にゴザなどを引いて寝る)。それが、江戸中・後期以降の養蚕や商品作物などの生産の拡大に伴って、急速に家が豪華になっていき、現在各地に保存されているような農家屋敷も登場してくる。また、書画などにも凝りだし、都市部から流入してくる「有名書家・画家」の品を集めたりし始める。テレビ「お宝探偵団」では、堂々と有名画家の銘の入れてある、一見して真っ赤な偽物と分かるような品物が旧家の倉などから出てくるが、この時代くらいから盛んに偽造され出されたのだろうなと思う。そういう色々な連想をつらつらしながら読んだ。