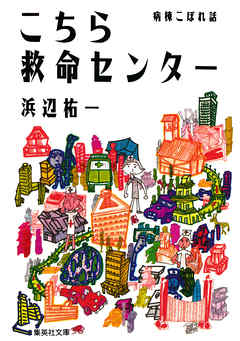感情タグBEST3
Posted by ブクログ
医療従事者によるユーモアたっぷりな現場ルポ。人生の教訓的アドバイスも散りばめられている。もし自分が緊急救命センターにお世話になることがあるとしたら、浜辺先生に診ていただきたい。
Posted by ブクログ
これは必読の書。プロ意識を持って仕事をしつつも自分を追い込まず、周りに温かい目を向けられるか。救命センターという過酷な職場で情熱を持ちつつ冷静に対処する外科医師の姿から得るものは多い。
Posted by ブクログ
看護や医療に興味があった。
常に生死に関わっていること。すごいストレスの世界だろうな。介護のことも考える。
看護師に対する考え方に共感した。こんな上司がいるといいな。
Posted by ブクログ
この本の何が面白いって、読み手としているのが一般人じゃないところ。
なんと相手は医療の専門関係者で、特にナース達。これって結構珍しいよなあ。だから心臓マッサージのABCDなんて
『今更だから説明は止めよう』
なんてすっ飛ばされる。会話も婦長さんや麻酔医等、救命センターで腕をふるう人たちとのやり取り。
お医者さんのエッセイに多い、患者さんたちとのやり取りはあくまでも医療関係者に伝えようとするエッセンスの手助けでしかない。
病院での主役は患者さんで、自分たちは脇役と言い切る作者の強い気持ちが伝わってくる。
ナースのたまごたちに向けたエールも清々しい。
重苦しさも少しはあるが、手にとって損はない一冊。
Posted by ブクログ
このシリーズ面白いです。
著者先生の前向きで素直で誠実な気持ちが盛り込まれていて、
読んでいてとても気持ちが良いです。
本来、しんどい内容のものなのですが、語り口調が軽やかで、
それを感じさせません。
人間が作る生の人間のドラマは、台本が無くて本当に面白いです。
Posted by ブクログ
浜辺祐一(1957年~)氏は、東大医学部卒、東大病院救急部、国立水戸病院外科勤務等を経て、1985年に救命救急センター開設と同時に都立墨東病院へ移り、現在、救命救急センター部長。
本書は、医療従事者向けの月刊誌「ナースコール」に連載されたエッセイをまとめて出版された『Dr.HAMABEの病棟こぼれ話 第一部』(1990年)、『同 第二部』(1991年)を一冊にして、1992年に改題の上文庫化されたもの。次作の『救命センターからの手紙』で日本エッセイスト・クラブ賞(1999年)を受賞し、その後も発表を続ける「救命センター」シリーズは累計で100万部を超えている。
内容は、浜辺医師の救命救急センターでの日々(前半には水戸病院の外科医だったときのものが含まれている)について、同僚の看護師や、患者とその家族らとのやり取りを中心に綴ったエッセイ(1篇は4~8ページ)であるが、「ナースコール」誌の主たる読者と思われる看護学校の学生や新人・若手看護師に向けたトーンで書かれている。
私はノンフィクション物が好きで、様々なノンフィクションやエッセイを物色している中で「救命センター」シリーズを知り、本書を手に取った。
そして、読み始めた当初は、浜辺医師の強い個性、ストレートな言動や記述に少々面食らったのだが、徐々に、それらが浜辺医師の実直さ、更には優しさなのだと感じられてきて、最後まで読み切った。
我々、医療を受ける側の人間は、医療従事者と接する場面の多くが、自分の健康を損ねているときであるため、彼らに身体的かつ精神的に支えて欲しいと思い、往々にして「聖人」のようなイメージを期待してしまうものである。そして、多くの医療従事者も、患者の期待にできる限り応えてくれようとする。
しかし、少し冷静になればわかる通り、医療従事者にしても、身体的にも精神的にも患者側と同じ人間であるし(稀には「聖人」もいるかもしれないが)、本書の中で敢えて浜辺医師が見せようとするのは、そうした表面的なものを取り払った生身の医師の姿である。読み始めた当初に私が抱いた違和感は、その生身の姿にあったのだが、読み進めるうちに、浜辺医師がこのエッセイを書いた目的が、看護学生や新人看護師へのアドバイスであるなら、これほど役に立つものはないだろうと感じるようになったし、それは医療を受ける側にとっても、知っておいてよいというか、寧ろ知っておくべきことであるように思われた。(私が現在幸いなことに健康だということもあろうが)
「贈る言葉」という一篇には次のような一節がある。
「そんなに肩に力を入れることはない。いい看護婦になろう、立派な看護婦になろうなんて目をつりあげることはない。力むことは何にもない。生身の人間の傍らにいることのできる条件、それはいつも自分らしく、生き生きとしていることだけだから。周りの人間に、自分らしさを生き生きと表現すればするほど、より多くのものが与えられ、より豊かなものを得ることができるのだから。自分らしくということ―これほどわかりにくいことはないかもしれない。でも本当の自分というものを一番よく知っているのは、ほかの誰でもない、自分自身である。看護学校を卒業し、臨床にたつ前の、この時にこそ、今までの自分を振りかえってほしい。君だけにしかわからない君だけの正解がきっとあるはずだから。」
救命センターの内側と医療従事者の生身の姿を垣間見られ、医療を受ける側としても役に立つエッセイ集である。
(2022年11月了)
Posted by ブクログ
救命センターで働くお医者さんの独り言みたいなコラムが看護師が読む月刊誌に載っていたようなところをまとめたものです。歯に衣着せぬ物言いが過激なので月刊紙にはかなりクレームが届いたようですがとっても面白いです。考えさせられる内容もあり読み応えがあります。
Posted by ブクログ
一編、一文が短くて読みやすい
時間も都合も問わず救命センターに運ばれてくる
多様な患者に対応するのは、精神的にも肉体的にも
きつい仕事だが、語り口は飄々として軽やか
その中でも、患者やその家族、医療スタッフ
との関わりを持ち、気持ちに寄り添う余裕を
持っている
忙しさにかまけて省いても、
仕事の上で急に問題になることは少ないが
本当は大事にすべきことだと再認識させられた
読んでよかった
Posted by ブクログ
1時間ほどで読める短さ、軽妙な語り口。でも扱っている内容は重い。心に残ったのは、「おじいちゃん子」と「堂々巡り」。おじいちゃんが起こした奇跡だと信じたい。「自殺」と言っても末期がんの78歳のおじいちゃん、看取る家族もなく、痛みに耐えながらの闘病は辛い。
Posted by ブクログ
「ハイ、救命センターの当直です」「24歳の女性なんですが、眠剤を多量に飲んで意識がないんです」「わかりました。すぐ搬送してください」消防署からの依頼である。救命救急センターの電話は、途切れることがない。死ぬか生きるか24時間態勢で取り組む救命救急センターの若き青年医師と、看護婦、そして患者が織りなす、心温まるドキュメンタリー。(背表紙)
Posted by ブクログ
よく医療ドラマで、瀕死の患者を救う天才医師、みたいなのがあるけど、現実はそれがいつも当たり前に起きて、(慣れは怖い、と著者も言ってる)サクサク対応しちゃってることに、少なからずびっくり。
また命は救ったけれど植物人間、といった時は「本当に良かったのか?」と悩む。
医療に携わる皆さんに敬礼。
Posted by ブクログ
先日本棚を整理していたら出てきた一冊、、何故か積読状態でした。
救命救急センターに勤めるお医者さんの、エッセイ集となります。
読み手としては、新人に近い看護婦さんを想定しているようで、
身近なネタを非常に読みやすく、それだけに不思議な生々しさとなって、
医療関係にはあまりなじみのない私にも、スルッと入ってきました。
登場する人々も、どこか海堂さんの小説にも出てきそうで、面白く。
決して聖人君子ではない方々であればこそ、むしろ安心してお付き合いできそうです。
ん、続編も何冊か出ているとのことですので、ぜひ手に取ってみようと思います。
Posted by ブクログ
現役の救命医が日常を書いてるから、医者や看護師など医療者の気持ちがわかる。東大病院救急部から都立濹東病院へ、救命救急センター医長。
末期癌患者の運命を何度説明しても家族に理解してもらえない、自殺願望があって運ばれてきた患者、痛い思いをさせてこの世にひきとめておかなければいけない、徹夜つづきで治療しても死んでしまうことも、命を助けようとして植物人間を生み出してしまうことも、家族や本人に感謝されるどころか、ののしられることも、バイクをぶっとばして怪我した人間を、なんでおれたちが真夜中にヘトヘトやなりながら手術しなきゃいけないのかなど(笑)
Posted by ブクログ
この先生のご著書は他にも読んでいます。臨床の現場で起こる様々なことと、医療に携わる方々の姿勢に感銘を受けるだけでなく、本書では、人生についてのアドバイスもたくさんいただけたように思います。看護師さんを目指す方々に向けて書かれた文章だからでしょうか。
Posted by ブクログ
目に入ってなんとなく借りた一冊。読みやすく面白かった。ドラマみたいでもなく、普段診てもらうお医者様ではなく、医者になった知人たちの仕事ぶりを想像してしまいそうになる。
Posted by ブクログ
看護婦(現・看護士)さん向けの月刊誌の連載をまとめたものなので、著者も看護婦さん向けに書いているけれど、医療現場を知らない人が読んでもオモシロイ。歯に衣着せぬ発言と言うのか、看護婦さんとのかけあいがオモシロクもあり、温かくもある。
Posted by ブクログ
「ジェネラルルージュ〜」読んで、ちょっと救命救急の現場に興味が出たので手にとってみました。
中身は救命医の著者から看護師、看護学生向けのエッセイというかメッセージというか…です。
実際に救命で命を救って、植物人間になっても患者は幸せなのか。という問いや、「何で自分がプライベートを犠牲にしてまでこいつら(患者)の命を繋がなきゃいけないんだ。という正直な悩みまで色々あって、お医者さんだって人間だもんね…と思ういいきっかけになる作品。
ただ著者が結構好きに書いているので、嫌な人は読んでて心底いらいらするかも知れませんが。
Posted by ブクログ
医療事務の関係で読みだした救急医療に関する本。
なかなか日常では関わらない世界。
しかし、命の危機にひんした際には、自身の命をつないでくれる最後の砦。
そんな現場の状況を映し出している作品です。
医療問題が騒がれている中、読んでみるのもいいのではないでしょうか。
Posted by ブクログ
【対象】
誰でも
【感想】
墨東病院に入院中、売店でたまたま見かけて購入した。
墨東病院の救急救命センターでの話なのだが、人生において示唆に富むメッセージが「さらり」と書いてある。
(自分も墨東病院の救急救命センターに入院し、救急病棟に2泊したが戦場のような感じだった)
患者・家族・看護婦・医者 の織り成す現実は、ドキュメンタリーとは思えないぐらい。
事実は小説よりも奇なり。
この本を読むと、そう感じざるを得ない。
Posted by ブクログ
まだ看護師のことを看護婦と
言っている時代の話で違和感があった。
患者の悪口言ったりしててなんだか
受付してた時を思い出して懐かしくなった。
Posted by ブクログ
医者の、毎日お仕事エッセイ。
患者の立場から考えれば当然の要求だけれども
先生や看護師の立場なら? が何となくわかります。
とはいえ、先生の指示だけに従うわけにもいかず…。
かといって、先生が何を考えてどう指示を出しているのか
仕事に対してどう思っているのか、が理解できました。
人が死んだからと、悲しんでいる場合じゃない、というのは
非常によくわかります。
その時間があったら次に走らねば間に合わない。
しかしそれを見た患者さんは? 見舞客は??
読みやすく、分かりやすく、で面白かったです。
Posted by ブクログ
救命センターの外科医が、看護師向けの雑誌に書いたエッセイの文庫化。
「先生、・・・」と会話形式で始まり、現場の実態をユーモアたっぷりに、そして第3者にもわかりやすく解説されている。
生きるか死ぬかの24時間態勢の救命救急センターのドキュメンタリーだが、コロナ禍の今から見ると、まだ牧歌的・・・
Posted by ブクログ
おじいちゃん子の話は涙がでた。偶然で奇跡の話(滅多にありえない話)だと思うが、きっとおじいちゃんの願いを神様が聞いたとしか思えない。
そこまでひどい話(重症)や奇跡的なエピソードがなく、本当に看護士(未来のを含め)にむけた本。医療関係者からの目線は新鮮だった。
普段仕事しててミスや判断が命に直結しない仕事って楽だよなぁと思った。
Posted by ブクログ
救命センターの医師のエッセイ集。
特筆すべきことは無いが、それなりに面白い。
医療ドラマが受けている今なら、もう少し脚色して映像化すれば面白いかも。
Posted by ブクログ
本書は看護婦さん向けの月刊誌に連載されたもの。
重体患者を扱う救命センターでの小さな人間ドラマが普遍的な生き様を考えさせ、そして心を温めてくれる。
生死に直面すると人間の本音がでるもの。それを主治医、看護婦の目線で捉えることによって、どう心に収めていくのか、どう教訓としていくのか、著されている。
以下引用~
・おもしろいものだ。相談するとは言っても、人は他人の意見に従うことはない。自分で既に結論を持っているから相談する。その結論が正しいことを確認したくて人に相談する。だが、その結論が正しいのか、間違っているのか、誰にもわかりはしない。自分自身にすらわからない。だからこそ、自分の思っていることを支持してくれる人があらわれるまで、人は相談相手を次々に求め続ける。そして結論を、ではなく、安心を手に入れるに過ぎない。
ただ忘れないで欲しい。その結論を出したのは他の誰でもない、自分自身なのだということを、責任は全て自分が負わなければならないということを。だって、自分の人生は自分で決めるのだから。
Posted by ブクログ
「ハイ、救命センターの当直です」「24歳の女性なんですが、眠剤を多量に飲んで意識がないんです」「わかりました。すぐ搬送してください」消防署からの依頼である。救命救急センターの電話は、途切れることがない。死ぬか生きるか24時間態勢で取り組む救命救急センターの若き青年医師と、看護婦、そして患者が織りなす、心温まるドキュメンタリー。
(裏表紙紹介文より)
***
約20年前の話ということで古さを感じる部分はあったけれど、医療や看護の精神は変わってないんだろうと感じました。
不謹慎な部分もあったけれど、常に“他人の生死や人生”に関わらなければならない医療従事者からすれば、軽口や愚痴を吐き出さなければやっていけないというのは理解できる。
でも自分や身近な人のことでそんな風に言われてたらやっぱりやめて欲しいなとも思ってしまう。
勝手だけど、立場が違えば感じ方も変わってきてしまうんだな。
Posted by ブクログ
救命センターであったであろう医師と看護師、患者のやりとり。たまに看護学生。小話3ページくらいのが集まった文庫本。
看護師新人の時に理解できなかった諦めるまたは死を待つという決断が少し腑に落ちた。
時々出会う、この著者のような医師は人間味にあふれて熱いけど冷静だと思う。冷静な判断が時に冷たく感じてしまっていた昔の自分の思いと重ねながら読め、まだ若かったあの頃いた現場を思い出した。
医師も看護師も人間で患者も人間。当たり前のことなのに忙しい毎日でそれを忘れていってしまってる、または疲れ果てて仕事の魅力を失いかけてる医師看護師さんに読んでもらいたい。
あと看護学生。リアルだけどさらっと書かれてる文章は現場の空気、グロさはあまり感じ取れないがきれいごとばかりの仕事ではないことがよくわかると思う。
医師や看護師は高給取りでいいよね、偽善、と思ってる人にも読んでもらいたい。
ぶっ通しで読むとちょっと飽きたので、★3つにしました。
この方の文庫ほかのは小話ではないようで、お手軽に読みたい方にオススメだと思います。
Posted by ブクログ
元々看護師向けの月刊誌に連載されていただけに、専門的な言葉は分からないけれど、全体的に読みやすい。
心暖まるお話が多く、ドラマやドキュメンタリーで見るような緊迫したものではない。
文章が上手いわけではないけれど、お医者さんの心境だとか、本当はこんな風に思ってるのかな、等と内側を垣間見た感じがする。