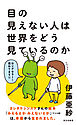伊藤亜紗のレビュー一覧
-
2020年中学入試では栄光学園、中大附、東京都市大附で出題、高校入試では東京学大附で出題された。
先日、目の見えない人に道を聞かれて、説明にとても苦慮したことがあって読んでみた。
実は足の裏から多くの情報を得ているとか、美術館で絵画鑑賞するとか、驚きの世界であった。
大切なのは、見えている人が...続きを読む -
スポーツは、目の見えない人にとっては、安全な場所。という感覚に驚いた。
ルールがあるからこそ、自由に出来る。それは、フィールドやコートといった仕切られた空間も同様。
ルールがあるから自由、安全という感覚は、一般的な社会においても、示唆を与える。
とにかく、特殊な状況を理解することは、物事を理解...続きを読むPosted by ブクログ -
前著「目の見えない人は世界をどう見ているのか」の一流アスリート編。興味深い世界が開かれていく。視覚障害に対して、かわいそうではない、平等な地平がスポーツを通して見えてくる。Posted by ブクログ
-
リオデジャネイロでのパラリンピックが盛り上がりは2020年に向けて障がい者スポーツへの関心のギアを一段階上げると思います。NHKの放送もソチの時は教育テレビの福祉番組が中心にあったように覚えていますが今回は総合テレビでスポーツとしての中継が存在感を増していました。本書も社会福祉的な論点ではなく身体論...続きを読むPosted by ブクログ
-
小学生の頃位から目が悪いことを自覚するようになり、近視、遠視、乱視、斜視の全部アリ状態なので
いつか見えなくなるのではという不安は予てより持ち合わせていた。
売れているらしいことと書名が気になり読んでみた。
発見も多かったがほとんどが中途失明者の話で先天的に視力のない人はどのように見ているのか気にな...続きを読むPosted by ブクログ -
こういう本は、インタビュー→その内容を消化→既存の研究内容とすり合わせて昇華、という構造だと思うのだが、昇華の部分が特に物足りなかった。
インタビューの内容はかなり良い題材だと思う。しかしそれで辿り着く考察が「はぁ普通やな」みたいな話で、イマイチ感動がなかった。
筆者の考察が面白くなくて、インタビュ...続きを読むPosted by ブクログ -
冒頭の伊藤さんの話は分かりやすく読めたが段々、理解が追いつけず、最毒が必要と感じた。
全体を通しての印象は「利他」も含め、一見、善い言葉も使うときには正しく理解しなくてはならないということ。特に利他はその最たるものの一つ、と思った。Posted by ブクログ -
ルネサンス前後の絵画を中心に解説をしてくれる本。
昔の絵画についてあまり知らなかったので、ためになりました。
他の比較しながら説明をしてくれるので結構わかりやすいです。Posted by ブクログ -
盲目の人と接することがあり、何か得られないかなと読んでみたが、易し過ぎて特に新しい発見はなかったかな。これが初見ならばいい入門書なるのかもしれない。
読むのならば、目の見えない白鳥さんと~でいいと思う。追加でコテンラジオの障害の歴史やヘラルボニーの活動を知ると、より理解が深まると思う。
Posted by ブクログ -
目の見えない人に、何を聞いてみたいだろうか。
そこは暗闇の世界なのか。
聾唖の人をどのように区別し、愛するのか。
寡黙な優しさを感じられるのか。
盲目の世界において、美しさとは。
価値観はどのように変わるのか。
残念ながら、本著はそういう観点では、インタビューをしない。また、登場する「目の見えない...続きを読むPosted by ブクログ -
★★★
今月1冊目
科学的な本。ピアニストにエクソスケルトンをつけて物理的に動かすとできないからできるイメージがわいてジストニアがなくなる。
このマシーンいくらするんだ?Posted by ブクログ -
目の見えない人の世界が少しだけ想像できた本。
何か足りないことに嘆くのではなく、今の状況を受け入れて前へ進むことの大切さを改めて感じた。目が見えない状況でのスポーツに関して興味がもてた。Posted by ブクログ -
目が見えない人の世界の見方が面白かった。
目が見える人は見えているようで、意外と見えていない。例えば、目が見える人は風景を見る時、立体的ではなく、平面的に見ている。目が見えない人は頭の中で想像して見るので、物を立体的に捉えている。
また、見えない人は想像力や推理力が優れているので、人の話を聞いた時に...続きを読むPosted by ブクログ -
小中学生に本を紹介するにあたって、新しく出ている「ちくまQブックス」から選んで読んでみた。やさしく書かれてはいるけれど、中身は深いと思う。著者は吃音があるから大学の教員になるなんて思ってもいなかったようだ。僕も体について悩みがある。中3のときだったと思う。ものすごくトイレを我慢したことがあった。それ...続きを読むPosted by ブクログ