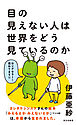伊藤亜紗のレビュー一覧
-
今日の世の中を覆っている合理性や生産性という価値観は違う、ふれることを通じて得られる非合理で生々しい感覚に価値を見出そうとしている。今日に必要な思想だと思った。Posted by ブクログ
-
中学生、高校生を対象にしたシリーズだが、大人が読んでも考えさせられる1冊。
「自分の身体は思い通りにならない」ということを考える内容。前半では著者自身の経験を中心に、吃音について説明されている。同じ音を繰り返す「連発」、言葉が出てこない「難発」の状態について語りながら、そんな身体とどう付き合うのかと...続きを読むPosted by ブクログ -
近代的な「主体」を前提とした「利他」は利己の変奏に過ぎない。では、利他がたちあがる場とはどのようなものか。そのことを5人の論者がそれぞれのフィールドに引きつけて読者にわかりやすく説いてくれている。5人話はどれも本当に面白い。Posted by ブクログ
-
今までは、心には個性があった方がいいけど、体は平均値に近い方がよいと思っていた。
“きみの体はきみの「こうありたい」には応えてくれない” p.62
体には、どうがんばったって平均値にはなれない部分がある。それをネガティブに捉えるのではなく、あるいは白々しい前向きな言葉で語るのではなく、自分にぴっ...続きを読むPosted by ブクログ -
医師は患者さんのために働くし、産業医は働く人のために働くので、利他的な職業でありそうですが、そこで利己的な利他を発動しがちなのもまた真だと思うので、メタな視点ってやっぱ重要なんだなあ、と思いました。Posted by ブクログ
-
親鸞会などのいう難度海よりも、小舟にすがる生き方のほうがいいと思っていた。つまり、道徳で安らぎを得るよりも、その場その場を悩み、オロオロする倫理がいいと改めて思わせてくれた。
それから、する対されるの関係でなく、お互いにあるというのも、J哲学を超えて、西田幾多郎の主客不分離を思わせた。Posted by ブクログ -
I really loved each stories in this book. I have a father who has been blind for long time and this noted me that how "I" should see his vision and hi...続きを読む
-
目が見えないということがどういうことか少し理解したように思う。
聞かされて「そうだったのか」と思うこともあれば「やっぱりそうなんだな」と思うこともあった。
例えば触覚に関して、点字を読むのは触覚ではないと言われていて、それは想像するとすぐに納得できた。
ただ、目が見えない方の点字の識字率が13%...続きを読むPosted by ブクログ -
読みやすかったし面白かった。
できないことができるようになる瞬間の「あ、こういうことか」をサポートするテクノロジーが書かれていた。
ニューラリンクのように脳にインプラントを埋め込んで考えるだけで色々できる、みたいなのは正直言って少し怖い。
でも、装着することでプロと同じ指の動きでピアノが弾ける器具だ...続きを読むPosted by ブクログ -
「目の見えない白鳥さんと…」の白鳥健二さんも登場します。あっちは感性鋭いノンフィクション作家、こっちは美学(芸術や感性的な認識について哲学的に探究する学問)の専門家による本。きっと違った視点で語られているのだろうなと手に取りました。
不勉強で美学という学問分野そのものを全く知らなかったけれど、なか...続きを読むPosted by ブクログ -
複数の理系研究者を現代アートの研究者がインタビューし、気づきを横展開しつつ「できるようになる」意義や醍醐味を取り戻す文脈に整理するPosted by ブクログ