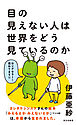「はじめに」からグイグイ引き込まれる内容だ
バーチャルリアリティを使ってけん玉の技をトレーニングする
球の動く速度はかなり遅い
このトレーニングにより、96.4%が技を習得したという
(TVでもこういうの見たぞ!ご高齢の方のリハビリだ
負荷をかけたトレーニングをさせたいが、故障してしまう
...続きを読む可能性も高い
よって編み出された方法とは…
負荷の少ない器具を使うのだが、バーチャルでは実際より負荷の高い器具を使っているという設定にし、
そのバーチャル映像を見ながらリハビリトレーニングするのだ
これにより身体を痛めることはなくなり、かつ効果があったという)
「自分の体を完全にコントロールできないからこそ、新しいことができるようになる」という
どういうことかというと、逆に「体が完全に意識の支配下だったらどうか」
うまくやったことがないことをそもそも人は意識できないし、
うまくやろうと思ってもできない事は、意識の仕方が間違っていることになる
できなかったことができるようになるとは、「意識が体に先を越されるという経験」だという
意識がお手上げでもテクノロジーがあれば介入できると嬉しいことがたくさん書いてある
五名の科学者と考えるのだが、自分自身がピアノを習っていたのでピアノ関連でざっとご紹介
ピアニストの演奏技術を助ける方法を研究している科学者
「練習と本番は、仮説と検証の関係」だという
「ふだん降りてこない演奏を降ろすため」の探索
(何かが「降りる」という感覚は芸術だけではなくスポーツでも起こりますね)
楽器の個体差、場所、時間、その日の気温湿度、本人のコンディション…
すべてがそろったとき
そんな奇跡を待つの?いいえ違います
かつては…
筋トレ的なピアノ教育が盛んであった
これは全体を部分へと分解してしまい、かつ身体を壊してしまう
本末転倒なこの方法(根性で何とかする時代ありましたねぇ 「スポコン」流行りましたもん
私も幼少時に手を広げる器具を装着しタオルを巻いて固定させられた覚えがある 今なら虐待になるんじゃないのかしらん?)
芸術、スポーツ、そして労働や仕事までもが当てはまる面白い表現で言えば…
~職人の総合的な技を解体し工場労働的な分業と単純作業への反復及び分解にしてしまう
大量生産や弱肉強食といった近代資本主義社会の論理だ~
ではどうするか
プロの動きを体験できる自動で動く指のマシーンを生み出す
正しい指の動きを直感的に理解することができ、鍵盤を押す深さや押し方も再生できる
実際使用された科学者の息子さんのひとこと「あ、こういうことか」
(これめちゃめちゃよくわかりますね 結局私はピアノに関して「アハ」体験を全くすることもなく
ただひたすら親の目を盗み練習をサボることばかり考えていた思い出しかない…トホホ)
意識と関係なく指を動かすことよって、意識することのできない動作、つまりイメージすることのできない領域へと私たちの体を連れ出してくれる
未知の可能性へと誘い出す(ぜひとも味わってみたいこの体感!)
もう1個だけ事例を…
元巨人の桑田真澄
(何を隠そうファンだから取り上げたい(笑))
制球力のあれほど良い桑田の投球フォームは毎回違う
フォームは毎回違うのに結果はほぼ同じ
そしてご本人も知らなかったそうなのだ
環境の変動に対する応答可能性
それは「体のゆらぎ」だという
まさにこれが無意識レベルで体が意識を追い越している現象だという
(高校時代からしっかり存じ上げており大変尊敬しているのだ
そう大変な努力家であるから
が、それだけじゃない何かがあるはず
センス?
ん?もしかしてセンスってこういうことなのか?
無意識レベルで体が意識を追い越している現象=センス?)
■「報酬」と「罰」は使い分けが大事
非常に興味深い内容があったので紹介したい
「褒められると伸びるタイプです」と豪語するゆとり世代ちゃんたちに教えてあげたい!
異なるタイプの学習で使い分けが大切のようだ
◇報酬系
ドーパミンがバーっと出る
脳の深いところがつかさどる
うまくいったときの運動の仕方をフラッシュで焼き付けるようなもの
強化学習に最適だが、時間を置くと忘れてしまう
◇罰系
小脳で働く
誤差やエラーと認識し、その運動を抑制したり計画をチューニングし直す作用となる
小脳は記憶もつかさどる
よって罰系で学習すると学習したことが長い間定着しやすい
長い間やっていない水泳や久しぶりの自転車がこれにあたるという
興味深い内容は尽きないのだが…
~体という謎めいた物体を前に試行錯誤する人の営みは科学者よりその人その人が真理を求めて彷徨う
その営みは過去、未来に向かう体の歴史をつくり、身体的なアイデンティティとそこにうまれる唯一無二の物語は文学だという
「科学」と「文学」はいずれもテクノロジーとの付き合いに試行錯誤しながらも進んでいく~
「文理共創」著者の目指したいところはここなのだろう
なぜこの本を読みたかったか
それは私が芸術+スポーツである踊りを長年やっており、行き詰っているからである(トホホ)
むかしむかしはスポコンで「10回やってできないなら100回やりなさい」とご指導をうけておりましたが、
そんなことやったところで、できないことが全てできるわけがない(と気づくまでに約10年)
もう20年も続けているのにこのザマは一体…
プロの方や、上手い踊り手と一体何が違うのだろうか
数年前からいろいろ検証かつ試行錯誤の模索をしている最中なのである
この本で少しだけわかったことは
あらゆる環境に置いての再現性(変動の中の再現性)の重要性だ
このために出来ることはたくさんあるだろう
練習場所を変える、服装を変える、道具を変える…
そして修行は続くのである…
人の可能性を秘めた非常に興味深い内容なのだが、
ただ素人がどこまでできるかという虚しさも残るんだよなぁ
そんなことより、お身体の不自由な方や障害のある方に役立ちそうな内容がたくさんあった
今後、テクノロジーのさらなる開発により不自由な方に少しでも役立つことが増えるといいと思うし、
研究されておられる方を応援したいものだ
※Kazuさんのレビューで興味を引き読むことができました
ありがとうございます!