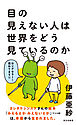伊藤亜紗のレビュー一覧
-
目が見えない人がどのように世界を捉えているのか、目の見える人がいかに視覚の情報に頼っているのかという本 目が見えない人全員が点字が読めるわけではないPosted by ブクログ
-
文系の著者が5人の理系の研究者に話を聞いてそれぞれの章を書かれた本。
素人には理解するのが大変であろうお話もわかりやすいように噛み砕かれていて、面白く興味深く読むことができた。
何かが出来ない状態はどうやったら出来るかのイメージが上手くできていないから、という話、逆上がり出来ない子供だった私に刺さ...続きを読むPosted by ブクログ -
道徳の倫理の違いについて初めて考えたし本書を通して理解できた、パンチラインは沢山あったけど1番最後の章「不埒な手」でそれまで論じてきたことの根本をもう一度問い直そうとしているのが構造として面白かった、伴走ランナーや身体で感じるスポーツ観戦を実際に体験(体感?)してみたいPosted by ブクログ
-
著者は、意識で体はコントロールしていない、体は先にゆく、と言っているけれど、ちょっと違うんじゃないかな。それは要するに、脳の仕組みのせいだ。予測で判断して司令を出す、ミラーニューロンで見たものを経験したように取り込む、可塑性汎用性が高い、簡単に言うと騙されやすい、錯覚しやすい、だからそのようなことが...続きを読むPosted by ブクログ
-
リレーエッセイという手法、面白いな。手紙のやりとりをこういう形でやってみたいかも。
御三方それぞれの視点が交差する様、少しずつズレて発展していく様など非常に楽しい。Posted by ブクログ -
読まないで聴くはじめてのオーディオブック。東工大リベラルアーツ伊藤亜紗教授著。目の見えない人との絵画鑑賞法とは?健常者の優しさ押し付けではなくその人になった想像力こそが大事なのかも、いろんなことが目に入りすぎて五感の衰えを日々感じる今日この頃。Posted by ブクログ
-
視覚に制限があることから見える人から引き算的な世界を生きていると想像しがちだけど、実態は全然違う。
健常者は見えるが故に、物の見方が拘束させていることがある。
視覚障がい者は見えないが故に、物事の見方に自由度がある、身体・器官の使い方に自由度がある。
見ると観るは違う。
そういう人たちと接するこ...続きを読むPosted by ブクログ -
自分の頭をぐいっと働かせて視点の変更を促すのにとても役立つ内容ばかり。面白い。
環世界、情報と意味、大岡「山」駅、
点字は「読む」こと(使っている器官は違うけどやってる仕事は「読む」、つまり触って「読める」し聞いて「眺める」こともできる。器官と能力を切り離す)、
ソーシャル・ビュー(美術館鑑賞方法...続きを読むPosted by ブクログ -
「器」のような人に自分はなれるだろうか?
人間は意志の保有者ではなく、思考が留まる「場所」なのだということ。自分が人生に対して抱いている不可抗力的な恐ろしさの断片を言語化してくれているように感じた。Posted by ブクログ