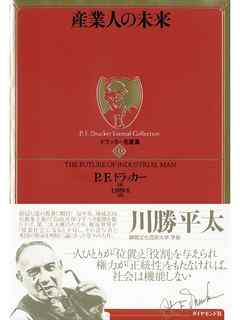感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ドラッカーの2作目。1942年、第2次世界大戦のさなかに、戦後の社会を構想している。
ドラッカーによると「識者と友人の多くが本書をわたしの最も優れた著作としている」らしい。
訳者の上田さんによると「本書は、ドラッカーの著作の中でも、最も面白く最も知的興奮をおぼえさせられるものである」とのこと。
1作目の「経済人の終わり」も驚いたが、こちらはさらにスゴい。
ドラッカーは、まだ経営学者ではなくて、社会経済政治の評論家(?)みたいな感じ。
近代の啓蒙主義、理性主義は、全体主義になる。つまり、「これが正しい」とすると、違う意見の人は間違っていることになる。ここには、自由はなく、善意から始まった活動は、最終的には恐怖政治につながる。
全体主義、世界大戦は、商業社会が産業社会に移行する道が分かっていないから。経済利益を中心とする社会から人間中心の社会に構造転換をしなければならない。それは戦後にやるのではなく、戦争中から始めないといけない。
みたいな本かな?
32才の人が書いたとは思えない、深い洞察。圧倒的な教養の厚み。
これは天才ということも超えているな。
個人的には、全体主義と個人の関係みたいなことを最近考えていて、それと関係してハンナ・アーレントを読んでいるのだけど、ドラッカーとアーレント、思考プロセスは違いそうなんだけど、たどり着く結論部分はかなり似ている。
この本は、アーレントの「革命について」(1963)の議論を先取りするような中身になっているな。
理性中心の啓蒙主義、これが正しいというものがあるという思想は、既存の社会を破壊すれば、歴史の必然(?)や人間の本質(?)から、自ずから正しい社会がでてくるだろう、と善意で考えて、革命を起こす。が、結果、うまくいかず、恐怖政治になっていく。
一方、人間の社会には単一の正解はないと考えれば、人間の自由が尊重された社会となる。(違う意見には、ちょっとイライラすることもあるでしょうけど)
ちょっと単純化しすぎているかもだけど、ドラッカーもアーレントも、アメリカ革命とフランス革命を比較することを通じて、こんな感じの結論にたどり着いている。
あと、フランス革命やロシア革命が、理性主義、啓蒙主義から生じて、恐怖政治になったという流れは分かり易すく、アーレントも同様の理解をしているところ。が、ナチも理性主義から出てきているというドラッカーの見解は、かなり驚き。
ナチといえば、大衆のプロパガンダがイメージされて、反理性主義という感じなんだけど、これは、心理学とか、生物学とか、つまり、身体や心を科学的に取り扱うところからでてきているということ。このへんのところは、なるほどと思うところと「?」が残ることなのだけど、いずれにせよ思考を活性化させる本ですね。
強引にまとめると、
・社会経済が産業化して、生産の自動化、大量化、効率化が進むことによって、人間の仕事の単純化や失業の増加が生じる。これらによって、いわゆる「疎外」が生じて、人間は社会における位置づけを失う。(ここまで、マルクス、アーレント、ドラッカーは同じ見解)
・しかしながら、この状態を一つの正しい理論で合理的に解決することはできない。それは全体主義、恐怖政治につながる。社会の基盤は、人間の不完全性、多数性にもとづくことが必要である。(ここまで、アーレントとドラッカーは同じ見解)
・すでに生じている産業化から昔に後戻りすることはできない。全体主義社会は、産業化の問題を、戦争という目的にむかって、統合、解決したが、これは普遍的な解決にはなりえない。産業社会を運営するポジティブな目的が必要である。そして、その解決策は、今、存在するものを活用してやっていくしかない。(これから全く新しいツールをつくることはできない)経済的利益中心の世界から人間中心の世界に変革し、人間に社会的な目的とポジションを与えていく鍵は、企業である。つまり、企業のコミュニティ化が必要である。(ドラッカーの見解)
お〜、これは「学習する組織」の考えと一緒ではないか。そして、「強み」にフォーカスするポジティブアプローチにも通じるかも。
あと、ドラッカーがマネジメント関係の本で、利益は企業存続の条件であるが、目的ではない。企業は社会、顧客に価値を提供する、貢献する存在である、という考えをよく書いているけど、その背景の思想がクリアになった感じ。
つまり、ドラッカーは、その後の経営学を先取る概念を次々と出しているのだけど、その目的は、企業が競争優位を築くことではなく、企業が人間的な社会に貢献できることだったんだ!!!
自分のやっていることが、なんか壮大な歴史的なパースペクティブのなかで、意味が通じた感じ。
Posted by ブクログ
正直ショックだった。
今の日本に読み替えられると教えられて読んでみた。
確かに民主党政権がダメな理由が述べられているし、ニートやフリーターの問題についても読み取れる部分がある。1942年の著作に現代に通じることが書いてある。
次は「傍観者の時代」だ。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
一人ひとりが「位置」と「役割」を与えられ権力が「正統性」をもたなければ、社会は機能しない。
反中央、地域志向、反教条主義の「自由」を保守すべき根拠を掘り下げ、第二次大戦のただ中、戦後世界が「産業社会」になると予見し、その青写真と、米国の使命を明快に論じきった堂々の力作。
生涯を貫く問題意識と方法論を知る社会改革への野心作。
[ 目次 ]
第1章 産業社会の行方
第2章 機能する社会とは何か
第3章 一九世紀の商業社会
第4章 産業社会における権力の正統性
第5章 ナチズムの試みと失敗
第6章 自由な社会と自由な政府
第7章 ルソーからヒトラーにいたる道
第8章 一七七六年の保守反革命
第9章 改革の原理
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
第二次大戦中に書かれた本で、前著『経済人の終わり』の続編とも言える本かと思います。戦中であることの影響を大きく受けて書かれつつも、戦後の世界の規範を「自由」に求めた大きなスケールの内容です。
本の帯では、社会における位置と役割と正統性がメインテーマのように書かれていますが(確かにそれもテーマですが)、それよりもまずは「自由」についての本だと思います。ここでドラッカーの言う「自由」は楽しく自由気ままというものではなく、「自由とは解放ではない。責任である...意思決定と責任が伴わなければ自由ではない」と定義される「自由」になります。この「自由」の概念の元、「自由」を伴わない、もしくは「自由」を自ら放棄した全体主義や社会主義を根本的に否定します。そして、その「自由」が成立するための土壌となる歴史やシステムを持つアメリカを戦後の中心とならないといけないとしています。そして自由な産業社会を築くために、「われわれは分析においては革新的、理念においては理想的、方法においては保守的、行動においては現実的でなければならない」と鼓舞します。そのために、この戦争を建設的な政治行動にとって絶好の機会としなければならないとしています。また、その中心となる企業を重要なコミュニティとして捉えていますが、この辺りは後の日本びいきにつながるところが見えるのかなと思います。
今日的な価値は当時と比べて薄まっているかもしれませんし、「自由」の基盤にキリスト教を布置しているところも個人的には共感しずらいところがありますが、よい本かと思います。
Posted by ブクログ
産業社会の特殊理論と社会についての一般理論について、若かりしドラッカーが著した名著である。
第二次世界大戦期、アメリカの参戦直前に上梓された本著は、当時の状況からして戦争とともに自由社会と自由経済が終わるだろうと一般に思われていた時代に、「戦後社会に何を期待するか、そのためにいま何をなすべきか」という問題を提起し、戦後は輝かしい産業社会が到来すること、そして経済発展があることを予見していた。
現在本著に掲げられている産業社会とわれる時代を通り越し、さらに次にポスト産業社会さえ抜け出している。なおかつ資本主義社会を通り越し、ポスト資本主義社会とドラッカーが名付けた時代にいる。
だが個々の人間と社会との関わり方はポスト資本主義社会特有の問題ではないし、ここの人間の位置と役割に関わる問題は社会の一般理論に関わるので70年前の本著の見通す社会理論は意義深い。
Posted by ブクログ
経済人の終わりと同様に社会学の内容。産業社会では、個々人が責任を持ち、正当な権力を持つべきという産業社会の姿を述べている。正当な保守主義の変遷を踏まえながらの記述で、勉強になる。こういうの勉強したことないので。
Posted by ブクログ
経済人は終わりだけど、産業人には未来があるということか。当時の経済人と産業人の違いを理解したうえで挑戦したい本だけど、あまり読みたいとも思わない本でもあります(^^;
読んでいてチャップリンのモダンタイムスの一幕を思い出しました。資本主義社会の中で会社では人間の尊厳が失われ機械の一部の歯車のように働くようになっていることを笑いで風刺していますが、最後は自由な生活を求め旅立っていきます。そんな映画が流行っていた時代、人々に魅力的な生き方、働き方を提示できるかいなか、つまり、個人がその社会の中で「位置と役割」を持てる社会かどうか、と述べています。
たぶん(と言うのは本書から明確には読み取れなかった)そのためには個人にも自由と責任が伴うということだろう(正確にはドラッカーの言う自由には責任が含まれているので、併記するのはよくないのかな)。
自由とは解放でもなければ、幸福でも安定でも平和や進歩のことでもなく、「責任を伴う選択である」と説いています。つまり単なる選択の自由は自由とは言わず、選択することにより責任が伴うことを自由と言うということです。
そのために戦後社会において、自由で機能する産業社会を構築しなければならないわけで、ひとりひとりの人間が明確極まりない社会的地位と重要な社会的役割を持つという現実を産業社会の形成に役立てなければならないということらしい。
だから何なんだ(笑)って叫びたくなります。
自分なりにいいように解釈するなら、経営者は社員に、その会社での本人にとっての意味ある位置と役割を与えることが重要だということだろう。そしてそれは自由で保障されていると。自由と言うのは選択の自由であり、選択するということは間違った選択もするということだろう。間違った選択をしてもよりよくする「責任」が伴うということなんだろう。その自由のもとで働く意味を見出していくことが産業人の未来と言うことなんだろうなあ。