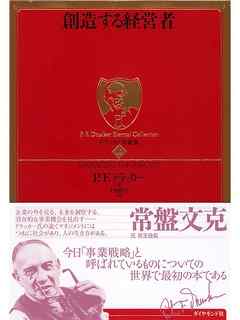感情タグBEST3
Posted by ブクログ
●ドラッカーは、経営に関して、日本企業に多大な影響を与えた一人です。たくさんある著書の中でも本書は代表的一冊。マーケティングの基本となる「顧客あっての企業(お客様第一)、知識あっての企業、目標管理の考え方・・等」について、独自の理論を提案。
●会社に入った頃に読んだ本。今でも大切にしている一冊です。上司に、「製品に問題が発生した時に、お客様なら、どう考えるだろうか?を常に考えて仕事をしろ」と口酸っぱく言われました。時代が進歩しても、問題解決の基本だと思います。
Posted by ブクログ
ドラッカー名著作選第六巻
今回は、現在では一般的に普及されている企業・経営戦略を主に取り上げています。この著書の事例は、主に大企業を取りあげている為、中小企業に対してはそぐわないという方もいますが、基礎的な概念に大も小もないと思います。どなたでも読んでいただきたい名著です。
Posted by ブクログ
友人よりプレゼントして貰った大事な本。
自身初ドラッガー。
ゴーイングコンサーンの元、企業が成長を続けるためにある事業戦略。
その戦略のあるべき姿について、様々な角度から記述されている。
実に多くの示唆が得られる本だった。
大まかに行って、前半が分析手法や分析のポイント、
後半は分析を踏まえての方向性という構成になっている。
本書冒頭に出てくる
企業にとって行うべき仕事として挙げられている3つの仕事。
・今日の事業の成果を上げる
・潜在的な機会を発見する
・明日のために新しい事業を開拓する
この基本を押さえずに、今日の事業の成果を上げるどころか、
なんとか維持することに終始してはいないか?
・・・などなど、ドラッガーの言うことが全て正しいとは思わないが、
自社の問題点を色々と感じた。
ビジネスパーソンは、自身の勤務する企業を創造しながら読むと、
大変理解が進むと思う。
少し期間を空けて、再読したいと思う。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
経営者を魅了し続けた世界最初の事業戦略書。
[ 目次 ]
第1部 事業の何たるかを理解する(企業の現実;業績をもたらす領域;利益と資源、その見通し;製品とライフサイクル;コストセンターとコスト構造;顧客が事業である;知識が事業である;これがわが社の事業である)
第2部 機会に焦点を合わせる(強みを基礎とする;事業機会の発見;未来を今日築く)
第3部 事業の業績をあげる(意思決定;事業戦略と経営計画;業績をあげる)
コミットメント
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
ドラッガー3冊目ということで、事業の定義等幾つか被るところもあるが、製品の概念(昨日の主力製品とか)は、GE等のコングロマリット企業に通ずるものであり感動!!ドラッガー勉強の最後に、3大古典の残り【現代の経営】を読みます・
Posted by ブクログ
ドラッカーエターナルコレクションの第6弾。世界最初の事業戦略書と呼ばれる著作です。
確かに例えば、製品とライフサイクルについての章では、後にボストンコンサルティングによってあまりにも有名になるPPM(プロダクトポートフォリオ管理)にも繋がる成長戦略に基づくポートフォリオ理論が展開されています。
「機会を優先する」、「顧客を理解する」などドラッカーの著作ではおなじみのテーマが出てきますが、この本ではより網羅的に分析されています。事業戦略については、この本が書かれた1960年代以降、かなりの研究がなされ、多くの本が出版され、この本で書かれていることの一部は陳腐化され、一部は時代に合わなくなっているものもあるように思いますが、それでも光って見えるのは、やはり巨人とも評される著者の凄みか、単に私が著者の威光に目がくらんでいるからでしょうか。
原題は『Managing for Results』。ちょっと邦題がずれているんではないのかな、と思いますが、許しましょう。やっぱりよいのではないでしょうか。
Posted by ブクログ
ドラッカー三大古典は「現代の経営」「経営者の条件」そして本著「創造する経営者」といわれています。
事業戦略という言葉を最初に使った著作でもあるといわれています。
当時から考えると戦略とは一般語になっていますが、なりすぎて戦略の意味がぼけてきてしまっている気がします。なんでもかんでも戦略って使っていて、「それって戦略というより戦術じゃないの?」っていう場合にも使われています。
言葉を分解すると「戦いを略す」ということで、いかに無駄なく焦点を合わせて「戦わず勝つ」ことで、戦う術の戦術の上位に位置する考え方だと思います。
この本では「何をなすべきか」について書かれています。上記古典のうちでは最も実践的といか実際的なことが書かれています。
翻訳者さんは「哲学者としてのドラッカーとマネジメントの父としてのドラッカー」がいるとあとがきに書いておられまして、本著はマネジメントの父としての側面が強いと思います。
書かれていることの多くは現在では多く知られていることですので、すっと理解できました。経営の再確認にもってこいの書物です。
以下印象に残った文章
・物事は、予想したとおりには起こらない。未来は常に違う。しかし、将軍たちが昔の戦争に対して備えたがるように、企業人も昨日のブームや昨日の不況に対処しようとする。
・「いかなる状況が、わが社の製品やサービスなしですむようにしてしまうか、あるいはわが社の製品やサービスなしにすまさざるをえなくしてしまうか」
・「学殖として意識しているようなものは、学問ではなくて衒学にすぎない」
・脂肪と筋肉を混同し、多忙と成果を混同する。
・イノベーションとは古いものに新しい次元を与える。
Posted by ブクログ
1964年、ドラッカーが55歳ころの作品と言うことは、今の私くらいの年齢だ。しかも、50年後にも通用する内容の本を書けるというのがすごい。なぜ、大阪万博前に「顧客は満足を買う」って宣言できているのか不思議です。今のビジネス本の多くが2年くらいで陳腐化しちゃうのとは大違いって思うけど、今はもっと時代が速いのかな?
この本は、結構、実践的と言うか数字的なアプローチも多く、今まで読んだ本とはちょっと雰囲気が違うが、この実践的な話も面白い。むしろ、この方が新鮮だし、これまで読んだ本より集中できた。洗濯機の白さを競う話も面白かった(^^)。
本書の中で本業は3種類と言っている。これは社員一人一人の仕事の本業は何かと言うことにもつながっている。経営者はもちろんのこと社員も自らの仕事を以下の3つととらえる必要がある。
(1)今日の事業の成果を上げる
(2)潜在的な機会を発見する
(3)明日のために新しい事業を開拓する
社員は毎日この3つの仕事をやっているかどうかチェックすべきだろう。社員で新しい事業の開拓などと言うと戸惑うかもしれないが、小さな改善も新しいステップになる。
そもそも、企業の歴史とか伝統とかいうが、それは「過去の意思決定や行動や業績によってもたらされたものが今日の事業」と言うだけのこと。それをなどるだけでいいのか?それは(1)のみの仕事をしているに過ぎない。
明日のための意思決定や行動をしなくていいのか?作られた過去の歴史ではなく明日の歴史を作れ!と言うことだろう。
選択と集中は重要なことだけど
5万ドルの取引も500ドルの取引もかかるコストはほとんどかわらないからといって、コストだけを意識した選択ではいけないと感じる。なぜなら私は零細企業の経営者だから。事業仕分けのように、ある部分だけを見て、「不要じゃないか」「2番ではいけないのか」と言う判断では割り切れないものを持っているのが零細企業なんだろう。
(だから生き残れないのか?しかし、それでも生き残れて何が楽しいのか?)
事業分析と言う点では、なかなか零細企業にはハードルが高い面もあるが、この本の基本を理解したうえで自社向けにアレンジをして分析する必要性は高いと感じた。
(以下は個人的なメモ)
商品の仕分けも必要なこと。
(1)今日の主力製品
(2)明日の主力製品
(3)生産的特殊製品(限定的な特殊市場を持つ製品)
(3)開発製品
(4)失敗製品
(5)昨日の主力製品
(6)手直し用製品(欠陥が明白であり、その手直しが容易であり、現実に大きな利益と成長が奪われているもの)
(7)仮の特殊製品(主力製品になるかもしれないにも関わらず特殊製品として扱っている製品)
(8)非生産的特殊製品(この製品がなければ量産品の注文が来ないと言い訳されるような製品)
(9)独善的製品(成功してないければならないのにまだ(もう?)成功しない製品)
(10)シンデレラ製品(チャンスを与えれば成功するかもしれない製品)
ノンカスタマー 自社の商品を買っていない人は誰か、なぜ顧客になっていないのか?
金と時間の使い方 顧客は何を買うか、金と時間をどう使っているのか
価値選好 他社から何を購入しているのか、その満足はどんな価値があるのか、それは潜在的に競合するのか
提供しうる価値
存在価値
商品群 顧客の考え方や経済的な事情から意味ある商品群は?
潜在的な競争相手
潜在機会 わが社の事業の一部と考えていないために見えていなくて試みてもいない機会はどこにあるのか
顧客の現実 顧客の現実であって、わが社に見えないものは何か
強みを基礎とするアプローチ
(1)理想企業のモデルからスタート
・・・・理想的な味噌屋の姿とはどんなものか考え構想を練る
(2)最大の成果を上げるべく機会の最大を図る
・・・・理想企業実現とその最大の成果の実現に向けて一歩を踏み出す
(3)最大の成果を上げるべく人材の最大利用を図る
・・・・そのために人材配置の意思決定が重要
気になった言葉
知識は本の中にはない。本の中には情報のみ。情報を仕事や成果に結びつけるのが知識。
4つのリスクがある(負うべきリスク、負えるリスク、負えないリスク、負わないことによるリスク)
Posted by ブクログ
ドラッカーの1964年の著作、世界で初めて「事業戦略」を扱った著作と言われている。今日の戦略に関する書物が扱っているものの本質はほとんど網羅されているように思う。
Posted by ブクログ
ドラッカー名著集の第六弾。ドラッカーの書籍の中では会計の要素がかなり強調された書籍。ちなみに原題は「managing for results」とのことで、こちらの方が書籍の内容をイメージし易く、よりふさわしい気がするのは私だけであろうか。
前半の第一部において事業戦略について記述されており、この第一部が本書の最も重要な箇所。後半の第二部以降は、意思決定や機会に焦点をあてること等、本書以外のドラッカーの書籍で述べられていることとやや重複する。
日本におけるドラッカーの分身と言われる訳者の上田惇生氏が「経営者の条件」、「原題の経営」と並ぶドラッカー三大古典と本書を位置づけていることが、本書の素晴らしさを表している。
Posted by ブクログ
ドラッカー、最初の事業戦略の本。
ドラッカーにしては珍しいと思ったのが、顧客ではなくまず製品の分析からすすめている点。(収益性やプロダクト11のカテゴリなどは参考になる)
また、強みにフォーカスするドラッカー氏が今回は弱みを克服することで機会を発見することを説いている。
1960年代の段階で、様々な業界が持つ独特の弱みについて氏は鋭く突っ込みを入れ、改善を促しているが、リーマンショック以降、急激な変化を目の当たりにしているなか、それらの産業は変化を受け入れざるをえない状況になっているし、変化への対応を先延ばしにしてきた産業は危機的な状況に晒されている。
事業戦略とは経営の舵取りにかかわることだが、だからこそこれを読み、ひとりひとりが経営の担い手としてそれぞれの立場で次の一手を考えなければならないと思った。
Posted by ブクログ
タイトルは原題「managing for results」のほうがわかりやすいかも・・・。組織や外部環境を含めた事業を、どんな風に見て、どのように対応していけば成果をだしていくことができるのか?について書いてあります。
的確に人材と資金をピンポイントであてて、事業の目指すべき方向に持っていくことが大事!ということでした。その的確なポイントをどう見つけるか?また、そうすることがどれだけ大事か?についてほとんどのページが割かれています。会社全体だけでなく、関わっているプロジェクト単位でみても、自分はどこに労力をさいて仕事をするべきか?(あるいは部下にしてもらうか?)やめるべきことはなにか?など考えさせられるところが満載です。
Posted by ブクログ
第?部 事業の何たるかを理解する
第1章 企業のの現実
・企業にとって今日行うべき仕事は三つであり、それぞれ異なるアプローチが必要で異なる問題定期が必要。
?今日の事業の成果をあげる。
?潜在的な機会を発見する
?明日のために新しい事業を開拓する。
・企業の現実についての仮説
?成果と資源は企業の内部にはない。いずれも外部にある。
企業とは、外部にある資源−知識を外部における成果すなわち経済的は価値に転換するプロセスであると定義できる。
?成果は問題の解決ではなく、機会の開拓によって得られる。
問題の解決によって得られるものは通常の状態に戻すことだけ。成果は、機会の開拓によってのみ得ることができる。
?成果をあげるには、資源を問題にではなく、機会に投じなければならない。
問題を全くなくす事はできないが最小限にすることは可能。その上でいかになすべき仕事を見つけ、いかに資源と活動を集中するかが重要。
?成果は、有能さではなく、市場におけるリーダーシップによってもたらされる。
価値あるものとは、リーダ的な地位によってのみ実現される。多くの業界において、最大手でありながら利益率は最高ではないという企業は多い。
?いかなるリーダーシップも、移ろいやすく短命である。
企業はリーダー的地位からその他大勢の地位に簡単に落ち込む。そのような地位から脱却するため、事業の焦点を問題の解決ではなく、機会に合わせなければならない。
?既存のものは古くなる
経営者の仕事は企業とその行動、姿勢、期待、製品、市場、流通チャネルを新しい現実に合わせて変化させること。
?既存のものは、資源を誤って配分されている。
(1)業績の90%が業績上位10%からもたらされ、コストの90%は業績を生まない90%から発生している。
(2)資源と活動のほとんどは、業績にほとんど貢献しない90%の作業に使われる。即ち資源と活動は作業の量に応じて割り当てられる。
(3)利益とコストの流れは同量ではない。利益を生み出す活動に意識的に力を入れないならば、コストは何も生まない活動、単に多忙な活動に向かっていく。
?業績の鍵は集中である。
業績のあげるには大きな利益を生む少数の製品や製品ライン、サービス、顧客、市場、流通、用途に集中しなければならない。
人材は少数の大きな機会に集中しなければならない。得に成果をあげる知識をもつ高度の人材。
企業家的な三つの活動を行う上で必要な分析の基礎
(1)今日の事業の業績をあげること
(2)潜在的な機会を発見すること
(3)明日の事業を開拓すること
第2章 業績をもたらす領域
・事業の分析の基本は、現在の事業、すなわち過去の意思決定、行動、業績によってもたらされた今日の事業の骨格、経済的な構造を調べる事から始まる。
・白熱した議論と意見の対立を招くような分析においては、分析の手法と道具を簡単なものにしなければならない。
第3章 利益と資源、その見通し
・いかなる種類の作業がコストの計算に適切であるかを決定することこそ、事業についての分析の一部であり、それにより選択肢とそれぞれの帰結を示すことができる。しかし、選択肢の最終の意思決定はマネジメントの責任。
・独占者がリーダーシップを失うのは、顧客に選択肢が与えられていないからである。独占の顧客は第二の供給者を待望する。出現すればそこに群がる。
・小さな特化した企業だけが時として自らのあらゆる製品とサービス、あらゆる市場と最終用途、顧客と流通チャネルに関して、リーダーシップを握ることができる。
・資源配分に関する分析は企業を理解し、診断し、行動に関わる意思決定を行う上で必要にして不可欠なステップ。
第4章 製品とライフサイクル
・予期したものと違う結果がでうようならば、類型変化の前兆と考えられ、少なくとも分析が必要。
・あらゆる製品、市場、最終用途、流通チャネルにはライフサイクルがあり、成長のために要する追加コストを分析すればライフサイクルのどの段階にあり、どれだけの余命があるかが明らかになる。
第5章 コストセンターとコスト構造
・コスト、およびその定義、測定、管理は、企業活動に関わる問題のうt、研究のし過ぎとまではいかなうとも最も徹底的に研究されてきた分野。
・問題はコストの絶対値ではなく、対業績費で、いかにコストが安く効率的であっても業績をあげなおならばコストでさえない。浪費。
・コスト管理の効率をあげるにはいくつかの原則がある。
?コスト管理は最大のコストに集中しなければならない。コストもまた社会的現象であって、その90%は10%の活動から発生する。
?コストはその種類よって管理されなければならない。
?コスト削減の最も効率的な方法は、活動そのものをやめること。コストの一部削減が効果的であることは希。
?コスト管理の成果をあげるには、事業の全体を視野に入れなければならない。
?コストとは経済の概念。分析の対象たるコスト構造は、経済的価値を生むための全経済活動。
・コスト管理のためには以下のコスト分析が必要。
?大きなコストが発生しており、効果的なコスト削減が大きな成果をあげるコストセンターを見つける。
?主たるコストセンターにおける重要なコストポイントを見つける。
?事業全体をコストの流れとしてみる。
?コストを法律上あるいは税制上の主体別に発生するのではなく、顧客が支払うものとして定義する。
?コストを基本的な特性によって分類し分析する。
・生産費はコスト管理の体系的な努力が昔から行われてきた唯一といってよい領域である。しかしほとんどの産業において、既に純粋の生産費は総コストのごくわずかな部分となっている。これ以上の大幅なコスト削減は本格的な技術革新が必要なほど。
・コストポイントのそれぞれを独立した問題として扱うのは適切でない。分析からもコストは一つの体系であるということが明らかになっている。
・コストポイントに対する対策についても「他のコストにいかなる影響を与えるか」を問わなければならない。
・コストポイントの種類
?生産的コスト:顧客が必要として喜んで代価を支払ってくれる価値を提供するための活動コスト。生産や販促のためのコスト。
機会にしけ源を集中することこそ生産的コストの管理のための唯一の効果的な方法
?補助的コスト:経済価値は生み出さないが、経済活動の一環として不可避なコスト。運送、事務、製品検査、人事、経理など。
それらが必要かを明らかにしなければならない。したがって「この仕事をやめたならば、どれだけの損失を受けるか」を問わなければならない。
?監視的コスト:何かを生み出すためではなく、何か悪いことがおこらないようにするための活動コスト。
最善の管理はそのものをやめること。「やめるとコスト以上の損失を受けるか」を問わなければならない。
?浪費的コスト:いかなる成果も生むことのない活動のためのコスト。最も高くつくのは無為のコスト。待ち状態にある機械、スケジュール変更による待機人員など。
浪費的コストは分析の必要がない。巨額であり、つまるところ人間はあまり効率的ではない。だが浪費的コストの発見には特別の努力が必要。
浪費的コストを発見する最良の方法は、それを意識的に探すこと。「何もせず、いかなる成果もあげずに、時間や資金や人間を使っているのはどこか」と問う。
第6章 顧客が事業である
・事業とは市場において知識という資源を経済価値に転換するプロセスであり、事業の目的は顧客の創造。買わない事を選択できる第三者が喜んで自らの購買力をと交換してくれるものを供給すること。
・マーケティング分析から明らかになっているもの
?顧客と市場を知るのは、顧客のみ。
顧客に聞き、顧客を見、顧客の行動を理解して初めて、顧客とは誰であり、彼らが何を行い、いかに買い、いかに使い、何を期待し、何に価値を見だしているかを知る事ができる。
?顧客は満足を買う。
顧客は製品を買っているのではなく、満足を買っている。満足を得るための手段をつくって引き渡せるにすぎない。
?競争相手は同業他社にとどまらない。
顧客が買う物が満足であるという事実から、あらゆる製品とサービスが突然全く異なる生産、流通、販売のされ方をしている他産業の製品やサービスと競争関係に置かれる。
?質を決めるのは企業ではない。
メーカーの考える製品の質とは単に生産が難しくコストがかかっているだけという場合がある。顧客の関心は「この製品が自分のために何をしてくれるのか」だけ。
?顧客は合理的である。
顧客は合理的である。メーカーや供給者はなぜ顧客が不合理に見える行動をするのかを知らなければならない。顧客の合理性に適応すること、あるいは合理性を変えようとすることがメーカーや供給者の仕事。そのためにはまずそれを理解し、尊重しなければならない。
?顧客の企業に対する関心は些細なものである。
顧客が自社の製品のことを少しなりと考えてくれていたとしても、それはまことに些細な関心に過ぎない。誰しも自分が行う事や作るものは重要であるが、顧客は通常それらのものを見ていない。
?決定権をもつ者、拒否権をもつ者
マーケティング的アプローチによる分析では誰が顧客かはわからないという前提に立たなければならない。顧客とは支払うものではなく買う事を決定する者。
?市場や用途から顧客を特定する。
企業や業界が顧客を識別できない場合にもマーケティング分析を行えないと事ではない。顧客ではなく市場や用途から始めればいい。
・外部からの事業の見方には三つの側面。「誰が買うか」「どこで買うか」「何のために買うか」という視点。それらの三つの視点のうちどれが適切であるかは事業によって異なる。
・マーケティング分析は市場調査や顧客調査をはるかに超えるものであり、第一に事業全体を見るもの。第二にわが社の市場、顧客、製品ではなく、顧客の購入、満足、価値、購買、消費、合理性を見ようとするもの。
第7章 知識が事業である
・顧客が事業であるのと同時に知識が事業である。本の中にあるのは知識ではなく情報であり、知識とはそれらの情報を仕事や成果に結びつける能力。そして知識は人間の頭脳と技能のうちにのみ存在する。
・知識の現実
?事業に特有の知識についての意味ある定義は極めて簡単、呆れるほど簡単である。
?知識の分析には訓練を要する。
?知識は滅しやすい。それは常に再確認し、再学習し、再訓練しなければならない。
?いかなる企業も多くの知識において同時に卓越することはできない。
・わが社の知識は卓越しているか?
?わが社は適切な知識をもっているか。わが社の知識は成果があがる領域に集中しているか。
?わが社は貢献している知識に対して報酬を受けているか。
?わが社の知識は、わが社の製品やサービスに十分組み込まれているか。
?いかにして知識の利用法を改善できるか、そこにおいて欠けているものは何か。欠けている知識はいかにして手に入れるか。
第8章 これがわが社の事業である
・現在行っている事よりも重要なのは当然行っているべき事であるにも関わらずまだ行っていないものの発見。
?全盛期を過ぎたものに代わるべきものを開発する努力
?機会と成功の追求。自らの目を養うための体系的な努力がなければ、最も明白なことを見落とす。
?知識
(1)本当に重要な新しい知識として何を取得する必要があるか
(2)現在の中核的な知識の何を向上させ、最新のものとし、進歩を図る必要があるか
(3)わが社の知識のどこに再定義の必要があるか
・自らの企業について分析の終点まで到達したからには、自社の事業が何であり、何をしており、何をできるかを理解できるはず。
?製品やサービスが提供しようとする顧客の満足。自社の製品やサービスが満たすべき顧客のニーズ。事業が対価を期待しうる顧客への貢献。
?望ましい貢献を果たす為に卓越性をもたなければならない知識の領域。事業の存続と繁栄のために必要な卓越性の領域。必要とする人材。
?際立った価値を提供すべき顧客、市場、最終用途。そして、それらの顧客、市場、最終用途に到達するために開拓し、かつ顧客として満足させるべき流通チャネル。
?これらの目標を具体化すべき技術、プロセス、製品、サービス。
?成果をもたらす領域におけるリーダーシップ。
第?部 機会に焦点を合わせる
第9章 強みを基礎とする
・事業を成功させる三つの保証済みのアプローチ
?利用しうる市場と知識から最大限の成果をあげるべく、あるいは、少なくとも、長期的に見て最も有利な成果をあげるべき、「理想企業」のモデルからスタートする。
?最大の成果をあげるべく、「機会」の最大化を図る。
?最大の成果をあげるべく、「人材」の最大利用を図る。
・自社や産業にとっての「現在」という期間の決定が、いかなる活動を行うのかを決定する。理想企業の実現の最善の方法は大きな輪郭を描いてその実現に着手したあと、順次に修正と改善を行っていく事。
・平凡なものに関する原則は、機会の領域を犠牲にしてまで人材を使ってはならないこと。余剰があったときのみ平凡なものに考慮すべき。
・わずかな変更を施すことによって、製品と活動を理想企業の設計に適合するものに替えることこそ、極めて高い優先度に値する。
・リプレイスメントは技術的な困難が大きくてはならない。これに対しイノベーションとは既存のものから新しい種類の経済を生み出す未知のものを作り出すこと。
・イノベーションは発明や発見そのものではない。焦点は知識そのものではなく、成果に合わせられる。したがって規模が大きいほどよいのではなく、小さいほどよい。
・第一級の人材は常に最も大きな機会、最も大きな見返りのある領域に割り当てなければならない。
第10章 事業機会の発見
・事業機会は三つの問いによって明らかにされる。
?事業を脆弱なものにし、成果を阻害し、業績を抑えている弱みは何か。
?事業内においてアンバランスになっているものは何か。
?事業に対する脅威として恐れられているものは何か。いかにすればそれを機会として利用できるか。
・事業においてアンバランスは組織図にしかない。生きた事業はあちらで成長しこちらで縮小する。
・潜在機会の発見とその実現には心理的な困難が伴う。確立された慣習の破壊を意味するが故に内部の抵抗を受ける。それはしばしば組織が最も誇りにしてきた能力の放棄を意味する。
第11章 未来を今日築く
・我々は未来について、?未来は知りえない、?未来は今日存在するものとも今日予測するものとも違う、ということしかしらない。
・未来を築くためにまず初めになすべきことは、明日何をするかを決めることではなく、明日をつくるために今日何をなすかを決めること。
・最後に発すべき問いは「我々自身は、社会と経済、市場と顧客、知識と技術をどう見ているか。それは、今も有効か」である。
・未来において何かを起こすということは、新しい事業を作り出すということ。ビジョンを事業として実現するということ。
・未来において何かを起こすには進んで新しいことを行わなければならない。
・未来において何かを起こすための人材は少しでいい。しかし最高の人材でなければ結局何も起こらない。
第?部 事業の業績をあげる
第12章 意思決定
・最大の成果をあげるには、全ての仕事を一つの大きな統合された成果のための計画としてまとめなければならない。
・あらゆる事業について中核となる意思決定。それは「事業の定義」「卓越性の定義」「優先順位の設定」。
?事業の定義
(1)わが社の事業は何か
(2)わが社の事業は何でなければならないか
(3)わが社の事業は何にならなければならないか
?卓越性の定義
卓越性の定義の適切さを判定できるのは経験だけ。
?優先順位の設定
事業をいかに組織化し単純化したとしてもなすべきことは常に利用しうる資源に比してはるかに多く残る。従って優先順位を決定しなければ何事も行えない。
第13章 事業戦略と経営計画
・経営計画は次ぎの事を決定しなければならない。
?追求すう機会、進んで受け入れるリスク、受け入れることのできるリスク
?事業の範囲と構造、得に専門化、多角化、統合のバランス。
?目標を達成するための時間と資金。新事業の設立と、買収、合併、合併とのバランス。
?経済情勢、機会、成果達成のための計画に適合した組織構造。
・四つのリスク
?負うべきリスク:ほとんどあらゆる産業に負うべきリスク。それはほかの産業の企業にとっては耐えられないリスク。
?負えるリスク:機会の追求に失敗して多少の資金と労力を失うというリスクは負えるリスク。
?負えないリスク:負えるリスクの反対のもの。但しそれ以外に新事業の開発に成功しても資金繰りができない場合などは、それは元々負えないリスクとなる。
?負わない事によるリスク:典型は革新的な機会に伴うものなど。
・事業をマネジメントせずに財務的な操作だけに頼るならば、必ず失敗する。
・正しい組織が必ず成果をあげるわけではないが、間違った構造は成果を生まず、最高の努力を無駄にする。
・組織構造は、いかにそれが今日の事業の要求に応えるものになっていたとしても、事業の変化に応じて再検討していかなければならない。
第14章 業績をあげる
・企業家的な計画を実現し、業績をあげるには、次ぎのようなマネジメントの能力が必要。
?企業家的な計画を、特定の人間が責任をもつべき仕事に具体化する。
?企業家的な計画を、日常の仕事に具体化する。
?一人一人の人間の職務と組織の精神をの中心に、業績を捉える。
・知識労働については特別の注意が必要で、分析や方向付け、焦点のはっきりした行動計画が必要。
・とりわけ研究活動においては生産的でなくなったものを廃棄し、成果をあげられるものに稀少な人材を集中することが必要。
・新しい事業のための提案は、必ずいかなる資源、得にいかなる人材が必要であり、どこからそれらの資源をもってくるかを明らかにしなければならない。
・期待と実績を見直す。「もし、この製品、活動、部門が今日なかったとしたら同じ事をするか」を問わなければならない。
・組織の中の人材を創造的たらしめることを望むなら、彼らの仕事や職務を古色蒼然とした仕事の維持ではなく、将来性のある新しい仕事に結び付け、定型化したものではなく成果をあげるものに結びつけるような事業をマネジメントしなければならない。
・知識労働者を監督することはできない。知識労働者は自ら方向付けを行い、自ら管理し、自らを動機づける。しかし彼らも自らの知識と仕事がいかに企業全体に貢献するかを知らなければ行う事ができない。
・つまるところ企業の精神は、どのような人たちを高い地位につけるかによって決まる。
・経済的な課題についての能力と意欲だけが、経営幹部としての唯一の要件ではない。経営幹部以外の場合には、例えば団結した効率的なチームをつくってそれを率いる能力のほうが重要。
終章 コミットメント
・もし企業が現代経済における企業化活動の中心であるならば、そこに働く知識労働者は、すべての企業家として行動しなければならない。
・今日、組織に働く知識労働者は三つのコミットメントを果たさなければならない。
?自らの知識と努力をして経済的な成果に貢献させるコミットメント。知識労働者たる者は、仕事や技能や技術ではなく貢献に焦点を合わせなければならない。
?集中するコミットメント。知識労働者たる者は、企業の経営幹部として、自らの管理下にある唯一最大の資源、すなわち自分自身を機会と成果に割り当てる責任を果たさなければならない。
?自らの職務と仕事、および企業全体としての経済的課題を、体系的、目的的、組織的に遂行するコミットメント。