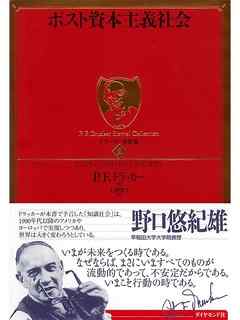感情タグBEST3
Posted by ブクログ
2017年に本書を初めて読みましたが、とても感銘を受けました。1993年に発刊された本とは思えませんでした。ドラッカーは本書の中でポスト資本主義の世界は知識人と組織人の時代だと述べていますが、本書で度々登場する「組織」を「ネットワーク」に置き換えて広義に解釈すると、2017年でも十分に説得力があると思います。ドラッカー自身が「日本語版への序文」で述べているように、本書を通じで日本びいきの表現がかなり多いのは気になりましたが、まだバブル崩壊直後で、日本がそれなりに評価されていた時期だったということでしょう。
逆に言えば、2017年の日本の状況をもとに本書を読むと、日本がドラッカー氏の主張する知識社会に移行しているのかは大きな疑問を感じました。つまりドラッカー氏の期待に日本は応えられていないということです。そしてその大きな理由は社会人教育がうまくいっていないことだと思うのですが、これは教える方(教育機関)が悪いわけではなく、むしろ我々日本人(社会人)がスマホゲームやSNSなど教養を蓄積するのとは程遠い生活を日々送っていること、読書などよりよっぽど楽しいアクティビティに満ち溢れているということで、しかしドラッカー氏の言うようにそんな誘惑に囲まれていても教養を蓄積し、現実社会に生かす人物がこれからの知識社会での中心人物になるのだとは思います。本書とても興味深く読みました。
Posted by ブクログ
もし時間を遡れるなら17歳の私に読ませたい。
受験勉強の中では得ることのできなかった「世の中はこれからも変わっていく」「それに自分も関わることができる」という認識を、10代の私に与えたい。
まあでも、今でも十分だったけど。
大量に引用。
それにしても日本を褒めすぎ。
Posted by ブクログ
現在の資本主義社会のその先について書かれた本です。これからの社会を生き抜くために必読の本であると思います。
20年以上前に出版された本にもかかわらず、現代社会に見事に当てはまっています。資本主義社会の次に来る知識社会への転換を予言しており、知識社会によって会社、政治、教育等がどのように変貌するかを説明しています。
著書での知識社会は、簡単に言えば専門知識を所有するプロフェッショナルが中心となって動かす社会と表現できると思います。そこには、資本主義社会の資本家と労働者という図式はありません。専門知識、情報という武器を持って、自由に社会を飛び回るプロフェッショナルが中心となるのです。
少し前に紹介した神田昌典の著書2022でもドラッカーの考えが引用されていました。2022を読んで、ドラッカーを再読しようと思い、まずは手始めにポスト資本主義社会を読んでいます。ポスト資本主義社会は、まさに2022で指摘する歴史の大転換を予想した本です。著書では、2010〜2020年頃に知識社会へ移行すると予測しています。20年以上も前からドラッカーは、予測していたことに驚きです。
数年前に著書を読んでも正直ピンと来なかったのですが、2022を読んだ後にもう一度再読してみると、身に迫る思いを感じました。2冊セットで読むといいのかもしれません。これからの時代を生き抜くために、2冊とも読む価値は絶対にあるはずです。
目次
序章 歴史の転換期
われわれが経験しつつあるものは何か
ポスト資本主義社会の姿
知識社会への移行
国民国家を超えて
第三世界の行方
ポスト資本主義社会における社会、政治、知識
第1部 社会
第1章 資本主義社会から知識社会へ
何が産業革命をもたらしたか
技術革新と文明
知識の意味が変わった
産業革命
生産性革命
テイラーの悲劇
教育訓練が生産性を爆発的に向上させた
マネジメント革命
マネジメントとは何か
一般知識から専門知識へ
第2章 組織社会の到来
組織の機能
企業も病院も組織
組織の特性
変革機関としての組織
組織の論理
従業員社会
第3章 資本と労働の未来
資本と労働の役割の変化
資本家なき資本主義
コーポレート・ガバナンス
マネジメントの責任
第4章 生産性
知識労働とサービス労働の生産性
チーム
集中
仕事の改善
アウトソーシングの理由
第5章 組織の社会的責任
ポスト資本主義社会の原則
社会的責任とは何か
組織と権力
責任型組織
第2部 政治
第6章 国民国家からメガステイトへ
国民国家の誕生
福祉国家としてのメガステイト
経済国家としてのメガステイト
租税国家としてのメガステイト
冷戦国家の登場
メガステイトは機能したか
ばらまき国家という民主主義の否定
袋小路に入ったメガステイト
第7章 グローバリズム、リージョナリズム、トライバリズム
ゆるぐ国民国家の基盤
環境問題、テロ、軍備管理
新しい現実としてのリージョナリズム
トライバリズムへの回帰
第8章 政府の再建
政党の基盤の消失
反行政の流行
軍事援助の不毛
経済政策において廃棄すべきもの
行うべきこと
第9章 社会セクターによる市民性の回復
二つの社会的ニーズの高まり
NPOによる市民性の回復
コミュニティは欠かせない
市民としてのボランティア
第3部 知識
第10章 知識の経済学
知識が主役
知識の経済学
知識の生産性
中央計画と集中化の失敗
マネジメント上の処方
結合せよ
第11章 教育の経済学
一変する学び方と教え方
高度の基礎教育を与える
強みに焦点を合わせる
学校へ戻る
学校の責任
第12章 教養ある人間
知識社会の中心は何か
求心力となるべき存在
知識社会と組織社会
教養ある人間の条件
専門知識を一般知識とする
Posted by ブクログ
1993年作と著者の著作の中では比較的最近のものになります。その頃はといえば、自分はまだ学生時代でバブルの時代を経て、バブルの崩壊もぴんとこないまま、ぼんやりと無自覚に楽しく生きていた時代です。世界では、共産圏が崩壊して少し後ですね。
そこで『ポスト資本主義社会 (Post-capitalist Society)』です。
この前後数十年を歴史の転換期と位置づけ、様々な視点で時代を論述しています。構成は大きく、I部:社会、II部:政治、III部:知識、と整理しています。その中で、年金や社会格差など最近でも大きな話題になっている問題も取り上げられています。かなり以前から強調していた、新しい形の"コミュニティ"の重要性や、"知識社会"の到来とその意義を論じられています。相変わらず面白いですね。
日本についても多くの言葉を裂き、バブル崩壊後にも関わらず基本的には日本に対して高い評価を与えています。それに応えるだけのものを実現しているか、失望させてはいないか、気にかかるところです。
Posted by ブクログ
またしても自分には難しすぎたわけだが。
90年代までが労働者と資本家に分かれた資本主義で、現代がポスト資本主義で知識社会、って感じの話だった。
今が資本主義で、その後何が起こるかの話だと思ってたけど違った。
知識あるいは知力それ自体が労働力そのものとなることは今日極めて常識的だが、90年代でさえ一般的ではなかったとのこと。
Posted by ブクログ
数世紀続いた資本主義が終わりつつあるのではないか、という気分の今日この頃、冷戦終結後、つまり「共産主義」後の93年に書かれたドラッカーの「資本主義」後の社会論を読んでみる。
が、驚くべきことが書いてある訳ではなく、これからの社会では、「資本」ではなく「知識」が中心となる、という、今となっては、常識に属する事かな?
といっても、93年にこれが常識であったかというと、そうではないわけで、ドラッカーの慧眼に改めて感服する、ということなのだろう。
だけど、今読んでも面白いなと思ったポイントは、
・ブローデルの見解などを踏まえつつ、数世紀にわたる資本主義の歴史的なパースペクティブのなかで議論されていること
・資本主義だけでなく、国民国家という政治体制についても、議論がおよび、ポスト国民国家というパースペクティブがあること
・そのなかで、マルクスやケインズ、そしてテイラー(ドラッカーによれば近代を作った人間の一人)などの思想家の位置づけがなされていること
・そして、社会論だけでなく、個人としてのあり方、教養のあり方について論じてあること
などである。
知識社会においては、当然、知識が中心なので、知識人、教養が大切。今日における教養とは、古典に関する知識ではない。専門的知識を除外しての教養とはありえない。なぜなら、社会において価値ある知識とは専門知識だから。
が、専門知識それ自体は、教養ではない。教養とは、自分の専門知識以外の専門知識を理解する能力のことである。
そして、そうした能力なしには、自分の専門知識それ自体もほとんど意味がなくなる。なぜなら、他の分野での新しい知識によって、自分の分野で革命的な変化が起こるということが、今日では、常態であるからだ。
これまた、当たり前のことだが、そのとおりだと思う。
Posted by ブクログ
ドラッカー名著作集8巻
資本主義社会と言われている世の中から、社会がどのように変わっていくかを、明確に提示している本著作。それだけでなく、働く上のでの取り組みから、教育機関が今後どうあるべきか提唱している。
言うまでもなく名作です。
Posted by ブクログ
1993年と比較的近年の著書で、ソ連崩壊もあり、比較的日本が高く評価されていた時期に当たる。社会が知識社会・組織社会に代わって行き、求められることが高度化すること。政治がグローバル化する中で、統合・分化すること。そして、何より知識の重要性が説かれている。知識中心の世の中になり、そのための教育の在り方まで述べられている。ドラッカーは常に知識の重要性に触れており、それは社会としても、会社としても常に課題である。
Posted by ブクログ
またまたドラッカーの時代シリーズ。
社会、政治、知識とこれだけテーマの広がりを持ちつつも、どこか一本の筋が通っており、必ずドラッカーの掲げるいくつかの原理原則に集約される。
1.問題は、技術ではなく、技術を何のためにつかうかである。
2.知識は、富の創造過程の中心である。(=教養のある人間になるべし)
3.学校の目的は、継続学習である。(=日本の弱みである社会人の継続学習の場を何とかしなくてはいけない)
4.政治も、企業も、大事なことはいかに不要なものを廃棄するか。(=新しいことを始めるには、まずは棄てること)
いずれにしても、ドラッカーの本は、いつも答えがシンプルかつハッとさせられるので、いつの時代にも色あせないのだと思う。
Posted by ブクログ
[ 内容 ]
[ 目次 ]
歴史の転換期
第1部 社会(資本主義社会から知識社会へ;組織社会の到来;資本と労働の未来;生産性;組織の社会的責任)
第2部 政治(国民国家からメガステイトへ;グローバリズム、リージョナリズム、トライバリズム;政府の再建;社会セクターによる市民性の回復)
第3部 知識(知識の経済学;教育の経済学;教養ある人間)
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度
☆☆☆☆☆☆☆ 文章
☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー
☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性
☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性
☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度
共感度(空振り三振・一部・参った!)
読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ)
[ 関連図書 ]
[ 参考となる書評 ]
Posted by ブクログ
社会の転換点である今日。資本主義の次はどうなるのか書いた本。もう10以上前の本なので取り立てて発見したことはなかったけど体系的に書いてあって読みやすくて勉強になった。ドラッカーのいうとおり社会は本に書いているように動いているのは驚くべきことである。ただまだ変化してないところもあり意外と社会って変化するのは遅いかもと思った
Posted by ブクログ
『LIFESHIFT』に書かれてたことも、『ホモデウス』に書かれていたことも『ティール組織』に書かれていたことも『学習する組織』に書かれていたことも既に、この一冊に書かれていた。圧倒的先見性。必読です。
一方で
ポスト、といえるのだろうか。資本主義社会の資本の中身が変わってきたよね、レベルの話?? 広井良典さんの定常型社会、緑の福祉国家や『資本主義の終焉』のほうがよっぽどしっかり論じられているような、、、
とも感じました。
また、『マネジメント』、『非営利組織の経営』、『プロフェッショナルの原点』を読んでいたら、新しく得られるものが少ないかもしれません。
Posted by ブクログ
1993年初版のポスト資本主義を考察した著作。
前書きに著者は「本著はいかなる国の読者よりも日本人にとって大きな意味がある」とし、バブル絶頂から転落しつつある日本に未来を示唆したい思いがあったようだ。
著者最晩年に書かれた本のひとつであり、それまでの著者の総決算的な内容である。ドラッカーを読み込んでいる読者には今までの振り返りにちょどよい本で、初見の人にはドラッカーの考え方がよく分かるのではないか。
ただ、本著を「預言書」だと勘違いしては肩透かしをくい、本質を見失う。
この本は近代から現代史をその意味するところを解き明かし、足元を見据えることに主眼を置いている。そこから見えるポスト資本主義の社会や政治体制、知識そのものに関わる新しい課題を扱っている。
著者は国民国家が揺らぎケインズ理論が破綻すると慧眼にも見据えていた。そしてグローバリズムが政治社会の趨勢になる一方で同進行的にリージョナリズムやトライバリズムが国民国家の基盤を揺るがしているとしている。
時代をよく示唆した名著である。
以下印象に残った文章。
・今日では、土地、労働、資本は主に制約条件として重要である。それらのものがなければ、知識といえども何も生み出せないし、経営管理者がマネジメントの仕事をすることもできない。だがすでに今日では、効果的なマネジメント、すなわち知識の知識への応用がなされれば、他の資源はいつでも手に入れられるようになっている。
・社会やコミュニティや家族は「存在」する。組織は「行動」する。
・成功する組織は、自らの内に、自らが行っていることすべてについて体系的廃棄を組み込んでいる。数年ごとに、あらゆる工程、製品、手続き、方針について検討することをみにつけている。
・先進国は、知識労働者とサービス労働者の生産性を向上させない限り、しかも急速に向上させない限り、経済の賃貸と社会の緊張に直面する。
・今日のトップマネジメントは、テニスのダブルス型チームである。これは情報化時代において必要となり、あるいは少なくとも可能になった試みである。
・生産性向上のための最善の方法は、人に教えさせることである。知識社会のいて生産性の工場を図るには、組織そのものが学ぶ組織、かつ教える組織とならなければならない。
・組織の中のあらゆるものが、「組織と組織の目的に対して、自らにできる最大の貢献は何か」を問い続けなければならないことを意味する。換言するならば、全員が責任ある意思決定者として行動しなければならない。全員が自らをエグゼクティブと見なければならない。