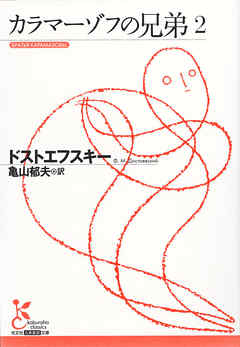感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ゾシマ長老がいよいよ最後の懺悔をし、聖体を受けたいと言う朝から始まる。
アリョーシャはゾシマ長老から修道院を出るように言われているけれど、何故なのかというのがこの朝のパーイーシー神父からの言葉に現れていた。
神父がアリョーシャにかけた言葉「さあ、お行きなさい、みなし児よ」って今思うと含みあるなぁ。
小学生たちの喧嘩騒ぎに巻き込まれるアリョーシャは、カラマーゾフ家に恨みのある少年に指を噛まれる。こういう少年たちとアリョーシャのやりとりがYA文学っぽさがあって好き。
リーズちゃんとアリョーシャの恋もしかり。リーズのめんどくさい女心がとぉっても可愛く?いやエキセントリックに描かれててたまりません。
それに比べてその後のカテリーナの執着心といったら…ドストエフスキー様の女性の描写力にただただおののきます。
2巻はこの後のイワンによる叙情詩、『大審問官』に悩まされる。。これは、教養あるイワンによる、無神論思想の言い訳的物語ですかね、それとも天使アリョーシャへのあてつけ?
正直読んだだけで、まったく理解出来てませんのでいつか解説書的なものと共にもう一度読みたい。
あとは、我が推しスメルジャコフちゃんのあのセリフ「つまり、賢い人とはちょっと話すだけでも面白い…最高❤︎
そして、ゾシマ長老は大地に口づけて、神に魂をあずけました。。
Posted by ブクログ
難しい。「大審問官」に至るまで随分と時間がかかってしまった。
でも、「大審問官」を読んだときには、自分の内側にあった問に対する答えのヒントがありそうで、とても惹きつけられた。
Posted by ブクログ
みんなすごい作品だと言い、自分が同じ物を感じ取ってるのか確かめられないけど、しいていえば、脳みそをがんがん揺さぶられて、思考や価値観の方向性を強制的に軌道修正させられる2巻目。抵抗しようにも論破され納得せざるを得ない。信じるしか道は無いのか。
Posted by ブクログ
圧巻の読み応えの2巻。
めちゃくちゃひきこまれました!
有名な大審問官のパートはつきささったし、それ以外にも印象的なくだりが盛りだくさん。
スネギリョフとイリューシャの、貧しさと闘うなかでの鬱屈とプライド、それから親子愛。
若かりし日のゾシマ長老を訪ねる謎の訪問者も面白かったなあ。
あと意外だったのが、若いアリョーシャとリーズが想いをかよわせる場面!
うそ……これ……60近いドストエフスキーが書いているんだよね?
読んでいるこちらがムズムズしてしまうくらい、甘酸っぱいんですよ。
文豪の知らない顔を垣間見た気がして、なにげに好きなところでした。
ところで、今回、読んでいる途中でちょっと失敗してしまったのですよね。
「あれ? これ前の部分でどうなってたっけ?」と気になったところがあって、軽くネット検索で調べたら、偶然、できれば本を読んでいくなかで知りたかった先の展開を見てしまい。
うわああ、やってもうたああ(泣)。
でも、横着した、自分が悪いんだよなあ。
今度からは、気になったところが出てきても、作品を読んでいる途中は楽だからと検索せず、前に戻って探すか、潔くあきらめて先へ進むことを決意した次第でした。
Posted by ブクログ
さらに泥沼化するかに思える複雑な人間模様のなか、兄イワンと高僧ゾシマ長老がそれぞれに神学的テーマを展開。
キリストにケンカをふっかけるイワンの創作叙事詩『大審問官』の衝撃と、ゾシマ長老の愛に満ちた談話・説教のコントラストが印象深い。いずれも難解で普遍的なテーマを含んでいるため、ざっと一読では消化不良に終わってしまった。とりあえずネット上にある解説や考察などを調べてみているが、ここは宗教に疎い人はつらいところかも。
とはいえ、主人公アレクセイを中心に起こるトラブルの数々は筋書きとして面白いし、各人物の魅力や思想的な深みも相まってものすごく重層的な世界が出来上がっているなぁと圧倒された。
Posted by ブクログ
キリスト教に馴染みのない(クリスマス程度でしか関わらないからね)大多数の日本人にとっては読み進めるにあたって鬼門となる2巻。だけれどもイワンとゾシマ、どちらのエピソードもこの物語の核、芯となる重要部材なので絶対に外せない。
「カラマーゾフの兄弟の感想を聞かせて?」と頼まれたら、8割くらいの人間がこの巻の話をするんじゃねえかな?
かくいう私も一読で理解しきれたとは言えないのでこれから何度も読み返すと思う。
Posted by ブクログ
イワンとアリョーシャの会話が難しくて頭に入らず、なかなか読むのが苦痛な巻だった。読み方のおススメとしては、とりあえず本編を頑張って読んだ後に亀山さんの後書きを読むこと。普段、後書きや解説は読まないクセがあり、さらにこの長編を読んだ後では早く本を閉じたいと思っていた。だが、後書きで噛み砕いて当時の貨幣価値から宗教的背景まで説明してもらうことで、頭の中にガタガタに構築されていた話の筋を見事に整理してもらえた。
Posted by ブクログ
まぁ圧巻でしたわ。
大審問官における「自由とパンとは両立しえない」と、人間に選ぶ自由を与えた神を責める巧みさには舌を巻く。
これはもう人間の弱さにつけ込んでくる悪魔そのものの思考だと思ったね。
ひとはパンだけで生きるものじゃないと聖書に書いてあるのは、それがどれほど難しいことか神ご自身が良くご存知だからなんだよね。
ああ神についてゆける数万の強者と
悪魔について行ってしまう数百万の弱者。
門は常に狭い。
狭き門から入れ、入りたいねぇ。入れてください。
ゾシマ長老の兄さんについてのところ、前回10年程前に読んで、かなり共感共鳴したのだけれども、今回はふんふんそうだね、と当然の如く通り過ぎた感がある。
でも本当はここもとっても大事なところで、こういう兄さんみたいな人こそが狭い門を通っていけるんだと思うわけさ。
Posted by ブクログ
第二部第四篇〜第六篇を収録。カテリーナとグルーシェニカの口論、イワンによる物語詩「大審問官」、ゾシマ長老の回心の物語。アリョーシャを狂言廻し役としながら、「信仰」と「秩序」との関わりという物語の中心的な主題が姿をあらわす巻。
こうして見ていると、「民衆」をめぐる思考という点で、「昭和10年代」の青年たちがドストエフスキーに惹かれた理由がよくわかる。イワンのシニカルさも、ゾシマ長老のナイーブなまでの「民衆」への信頼も、双方ともにマルクス主義以後の青年たちの心性に近しいものだろう。日本の近現代文学とドストエフスキーとの関係は、時代の精神史という観点から再考の必要あり、と思わずにはいられない。
Posted by ブクログ
イワンの物語詩「大審問官」とアリョーシャの「ゾシマ長老の談話と説教」が対を成し、神は存在するのかしないのか大きな命題を突きつけられたような壮大な第2巻。
壮大な宗教の経典を読んでるような重苦しさもあったが、巻末の読者ガイドが親切で理解も深まった。
「自分の苦しみは他人にはわからない」「人間誰しも全ての人に対して罪がある」など突き詰めて考えればそういうことだなと双方納得させられるものがあった。
ゾシマ長老の少年時代の逸話がなんとも微笑ましい。さてここから物語はどう展開してゆくのか?
Posted by ブクログ
ヒットワード連発の巻でした!
「いかがなもんです、いかがなもんです!」
“さくらんぼのジャム”
「一粒の・・・」
後はゾシマさんの話が染み入ります。
Posted by ブクログ
大審問官とゾシマ長老の伝記的内容が「対」になっているようにも見えたが、訳者の解題の通り、イワン陣営VSアリョーシャ陣営で見るととても構造が理解しやすかった。
キリスト教が15世紀間の間に前提とした条件などが変わることで、既に実用に耐えうることができなくなっているという投げかけや、キリスト教が課した要望の高さ(自由など)についていけない多数派と乗り越えうる少数派を対比させ、かつ、当時とは数が違うことも引き合いに出し、内在する選民的側面を炙り出したりするなど、イワンの持つ、神の創った世界=キリストが悪魔から退けた世界、への疑念が詰まっているパート。
そこから始まるゾシマ長老の伝記的パートが、イワンの問いへの回答のようにも見える。過去に殺人を犯した訪問者の精神や行動の遷移に則り、個人の内面での葛藤=罰の持つ影響などが語られている。無神論や世界の否定を述べたとして、この内省に「神」は介在しているのだろうか。つまるところ、イワンの言う個々人に課された要求の例としての貧しさの面などは、結局物的なものが多く占めており、この葛藤は精神的な活動であり、望まずとも訪れてしまう活動だと思われる。自由な精神活動を送ることに大半の人間は耐えきれない、と言う内容が議論対象。その際に、どう心を持つか、どう内面を取り扱うか、その参照事例としてのキリスト教、神、という事例に過ぎないのではないだろうか。罪を明らかにしたことで、ゾシマ長老にその矛先が向き、ある意味で「救われた」状態になった、これをキリスト教的に解釈するか、無神論または自然崇拝的に解釈するか。個人が個人と内省的に向き合い続けた結果の、自立した個人、というものがキリスト教的な理想像として提示されているように思える。そこに至れるかどうかはさておき、指針として基準を設けておくことは、社会的な安定において重要だと考えられる。そのため、その基準が適切でない、なくなったことでのイワン的な問いかけもまた意義があり、多様であればあるほど、その議論はどの論へも還元されていき、また一つ変化をもたらすことになる。無神論的であっても訪れることが想定される「内省」にどう対処していくか、無神論的処方が提示されていく必要がある。
次巻以降で本格的に、ドストエフスキーが「ロシア」というものをどう捉えたか、「父殺し」「民衆」「父と神がかりの子供」「無神論」など壮大なテーマを登場人物の属性に落とし込んで表現されていき、かつ、多面的に表現することで(イワン陣営VSアリョーシャ陣営のように)論に厚みを出していることで、傑作たらしめているというか、時間の評価にも耐え続けているというか、そういった側面を感じ取ることができた。
Posted by ブクログ
読書ガイドから抜粋
僧侶は、妻帯を禁じられた黒僧、妻帯を許可された白僧の2種類に分かれ、19世紀半ばではだいたい2対5の割合で存在し、どちらの種類の僧侶も、僧衣の色はほぼ黒と定められていた。教会で地位を築くには黒僧になるのが必須だったため、アリョーシャが婚約したのはかなり攻めていだとも言える。
第1部で父フョードルがイワンとアリョーシャを相手に投げかけた問い、つまり神の存在と不在をめぐる問いが第5編「プロとコントラ」と第6編「ロシアの修道僧」に結実する。
Posted by ブクログ
1巻を読んでいる時は、分からない宗教の話が続いて挫折しそうになったが、個人的には面白いと感じる事がようやく出来た2巻目だった。
主人公達を取り巻く主要なサブキャラ達がしっかり出てきて特徴を掴めてきたから面白さを感じられたのかもしれない。
キリスト教ではないし、ロシアの歴史はほとんど知らないが、読み進めるうちにとても興味が湧いた。知りたくなった。
「自分を振り返ったときに恥ずかしくない振る舞いをしなさい」というようなフレーズがあった。(うろ覚えだが)できる限りそうしたいなと改めて気付かされた。
Posted by ブクログ
この本について知りたかったら、訳者の亀山先生のNHK100de名著、または本書の後書きの「読書ガイド」を読めば十分だと思うけど。
今まで読んだドストエフスキーと違い、構成がしっかりしている。勿論、嫌になるほど饒舌で長いけれど。この第2巻はまだ2日目のことなんだよ。驚いたことに。
長男ドミトリーと美人カテリーナのアレヤコレヤは前日譚として語られるのみ。チョッと物足りなさを感じる処。勿論、其処から説き起こしたらトンデモナイ大長編になるのは判っているけれど。
登場人物が後の時点から、この時のことを思い返す表現が何度かある。こんなのも他のドストエフスキー作品には無かったと思う。
カテリーナの「自分の一生を犠牲にしても妹としてドミトリーを愛する」という宣言。唐突とは思わないけれど、舞台での戯曲の台詞のように感じる。その後の三男アリョーシャの台詞も同じく。
二男イワンの語る子供たちへの虐待と「大審問官」の物語。教会がキリストが去ったあと、悪魔と手を結び、人々の自由を奪い、権力を奮い、パンを与えたという内容に納得した。ロシア教会のことは良く知らないが、カトリックには当て嵌まることが多いと思う。しかし、イワンは無神論というのとは違うように思うんだけど。
終盤はゾシマ長老の遺言ともいうべき半世紀。イワンの非難とぶつかる部分はない純朴な信仰のあり方。アリョーシャは何を思っただろう。
3巻に移りつつ、100分de名著を読み返そうかと思う。
Posted by ブクログ
かなりキリスト教の宗教色の強い一巻だと思う。神の存在、聖職者フリーメーソン(秘密結社)、ヨハネの福音書、修道僧ゾシマ長老、黙示録。イワンとドミートリーとのやり取りが少なくアリョーシャの行動、心理が多く描かれていて兄弟の不仲が伝わってくる。兄弟同士、女性とどう絡んでいくのだろうか?
Posted by ブクログ
巻末に付された、訳者による読み方ガイドが秀逸。これがなかったら、途中で挫折してたと思われる。とはいえ、それでも尚、読まされてる感が少なくない。第1部に引き続き、ここでもちょくちょく、宗教論というか宗教史みたいなのが、色んな人の会話の中に盛り沢山。目で追っているうち、思考がどこか他のところへ飛んでいってしまったり、あるいは寝てしまったり(苦笑)。でもそれを除くと、ただの親子間のいさかいというか、横恋慕というか、そんな物語になってしまうから、本作を孤高たらしめているポイントは、小難しい会話の中にあるんだろうけど。個人的には正直、しんどい気持ちの方が大。
Posted by ブクログ
1巻に比べ、人間の本質を突くような内容がちりばめられていて、ぎくりとする。
印象深かったのは、第6編の2-d謎の訪問客 『私はあなたを殺しに来たんですよ。あなたを殺しても、後々その罪を背負うことも考えずに、その時はそんなことも考えずにあなたを殺そうとしました。』結果この人は殺さなかったのだが、殺されそうになった人は大きなわだかまりを持つ。
私もある事件で人が憎くて、人を殺したいと行動しそうになったことがある。本人の前で「それ以上しゃべるな!殺したくなる」と言ったことがあり、「殺せるものなら殺してくれ」と返されたことがある。その時私は思った。「(空白何も考えられなかった後)こいつはずるいやつだ!!わたしの今の苦しみを解消させようとさせながら、後で殺したことを後悔させることで、私を苦しめようとしている。どの道を選んでも、こいつに縛られるんだ!!!その時は殺さなかったが、私が壊れることで、その衝動はなくなった。苦しみからは解放されたが、壊れる前のあの生活はもうできないんだと思うと、何とも言えない空白がよぎる。
自分のような経験は過去の本に書かれており、そんなに珍しい事ではないんだと思わさられ、知らされる。ドストエフスキーに尊敬と共に感謝の気持ちを持った2巻目だった。
また1巻でさらされた多くの伏線が引っかかる点が面白かった。
解説で書いてある、『ファウスト』にも挑戦したいと思った。
Posted by ブクログ
ゾシマ長老の衰弱を気にしつつもアリョーシャはカラマーゾフの問題を解決するために奮闘する。カテリーナとグルーシェニカ、ドミートリーの間で生じている生々しい問題はイワンやヒョードルなどの人物をも巻き込み、より複雑怪奇な物語へと導いている。その問題について追究していくうちに我々読者はドミートリーの人物像を築き上げている。この第2部の謎めいた箇所といえばやはりイワンの話す大審問官の章。人間の姿として現れたその人に対して大審問官は、あなたが自由を与えたから人々は苦しんだとして批判した。これは聖書を読んでいないと分からないなと思った。そもそもこのカラマーゾフの兄弟を読むにあたって聖書の基礎知識が無ければ理解は不十分に終わる気がした。この物語は宗教面、ロシア情勢、階級社会、金銭面など様々な背景を含んでおり、重層的で多義的な物語であることがこの第2部で分かる。つまり様々な視点で見つめなければならないと感じた。また、第1部では説明的な文章が多く、物語の流れをいまいち掴めなかったが第2部でドミートリーの不穏な動きなどが目立つのを認めると我々読者も少しずつ何かしらの予期が生まれてきたではないだろうか。この予期がどんな形で生まれるのか第3部を読んで確認したい。
Posted by ブクログ
だいぶ飛ばし飛ばし読んでしまった。
第一部よりは面白いが、まだもどかしい。
イワンとアリョーシャの有名なやり取りはまた時間があったらゆっくり読み直したい。
Posted by ブクログ
1巻目で、人物が分かってようやく物語に入り込めた感じ。アリョーシャと貧しい子供との出会い、イワンの大審問官の物語、そしてゾシマ長老の物語。
一つ一つが、濃い。
ただ、キリスト教への造詣が深いとまではいかなくとも、何かしら神について考えるところがないと、登場人物達が語る内容への感情移入がしにくい。
Posted by ブクログ
1巻目よりかはスラスラ読めました 笑
個々のストーリーが散りばめられており、
アリョーシャとリーズの関係性が1番面白かった。
ただ大審問官やロシア修道僧あたりの宗教色が強い場面は難しく感じました。
いざ、3巻目へ
Posted by ブクログ
カラマーゾフ新訳、第二巻。ちょうど、NHKラジオの文学の世界で、ドストエフスキーの特集をしていて、彼が本書を書いた背景や時代を理解しながら読んだが、それでも難解。
Posted by ブクログ
ロシアの文学の天才が残した文学史上最高と言われる作品。当時のロシアの歴史的背景や宗教等が重なり合い、主人公たちの物語を描く。
世の理や恋物語についても述べており、宗教観についても触れている作品。長いが人生で一度は読んでもいいと考える。
登場人物が多く、複雑であるため、あらかじめ簡単に予習してから読むべし。
Posted by ブクログ
宗教に関連したやりとりの場面はつらい。素養がないため理解できないし、興味もわかない。親子や兄弟、男女や子弟、友人などの複雑な人間関係を描写する部分は見事で、面白く読めた。
「女の涙なんて、真に受けちゃだめですよ」p98
「ロシアでは酔っ払いどもがいちばん善良なんです。いちばん善良なやつらが、いちばんの酔っ払いということなんでして」p131
「傷ついた人間からすると、みんなから恩着せがましい目でみられるのって、ほんとうにつらいことなんですよ」p162
「人生という大きな杯にいったん唇をつけた以上、最後までこれを飲み干さないかぎり、ぜったいに手から杯をはなさない」p202
「賢い人とはちょっと話すだけでも面白いと世間で申しますのは、ほんとうなんですね」p341
「キリストをしりぞけてしまえば、結局のところ、世界中が血の海となるよりほかはない。なぜなら、血は血を呼び、剣を抜いた者は剣によって滅びるからだ」p449
Posted by ブクログ
登場人物のキャラクターや魅力も多彩で、セリフがやたら長いところや、心身ともに病的な様子が多く見られる点など、ドストエフスキーらしさがたくさん見受けられる
Posted by ブクログ
やっと第2巻を読破。2巻から面白くなるという何かを見て期待を込めて読み進めていく。噂に名高い大審問官のところを楽しみにして読んでいったが、なんとなく理解できたような出来ないような。きっと読解力が自分に足りないのだろう、この部分の素晴らしさ、示唆的な所までは理解できなかった。最後の長老の言葉も、罪の告白のところまではよかったのだが、そのあとがなんだか難解で、だーっと読み飛ばしてしまった。後に大事な内容だったらどうしよう…とにかく話が進みそうな第3巻にいってみる。