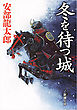安部龍太郎のレビュー一覧
-
予てから私も著者と同じく、戦国~安土桃山時代の捉え方が、江戸時代に真逆に書き換えられていると感じていたので、本作品内で引用されている例示は至極納得でき、爽快な気分になった。キリシタンや南蛮貿易を主として捉えると人物も事件も違った様相を呈して非常に面白い。蛇足だが、景教の影響からの厩戸皇子や蘇我馬子の...続きを読むPosted by ブクログ
-
事実としたら、秀吉のイメージは大きく変わる。秀吉は「本能寺の変」を事前に知っていた、ということだから。
光秀も一人責任を負わされ、長生きしていたら、「事実」がどれくらい公になったのだろうか。
信長の天才性や人を人とも思わぬ所業がやっぱり強烈だった。Posted by ブクログ -
明智光秀の謀叛とされている本能寺の変は、実は明智光秀ひとりに悪役が押し付けられたもので、裏では色んな動きがあった、というものですが、これが歴史の真実なのかよくできたフィクションなのかよくわからないながらも、おもしろく読めました。Posted by ブクログ
-
本能寺の変の背景を大胆に推測した一冊。
信長は、ポルトガルとの南蛮貿易で富を得て、それが権力の源泉になっていた。このころ、宣教師たちの日本での活動が最も盛んとなる。ポルトガルがスペインに併合されると、スペインとの交渉に入ったが、決裂。貿易で得ていた信長の力に陰りが生じる。それをみた足利義昭は、公家勢...続きを読むPosted by ブクログ -
話題になり、人からもおすすめされたので手に取りました。
本能寺の変の謎を解く、といった作品は、おそらくこれまで多数あったと思いますが、国内の政治状況に加え、大航海時代という世界の歴史の中でとらえたこの作品は、かなり興味をそそる一冊となりました。
その観点からとらえ、その後の秀吉の天下統一、朝鮮出兵...続きを読むPosted by ブクログ -
あまり知られていないものを含む、多数の資料による、力強さを持った言葉。感情を抑えない優しく温かい言葉。
二つの言葉を、心地よく感じながら読むことができた。まだどこかに謎を紐解く資料が残っているのだろうか。残っていないのだろうか。歴史浪漫に胸が熱くなった。Posted by ブクログ -
明治維新時に、旧幕府側の藩士として多難な目にあった父と、藩閥を嫌い日本を飛び出してボストンで教職にある息子との、行きつ戻りつで近代日本のやりきれない部分を描こうとしたものか。Posted by ブクログ
-
戦国時代の事柄の中で自分が知らなかった戦いを扱っていてとても興味を持った。
九戸兄弟の四男、政則の視点から描かれておりストーリー展開もテンポ良く引き込まれていく。
様々な出来事に対して九戸の長男、政実の思慮深く緻密な策略を建て挑んでいく姿は凄いと思わされる。
多少神秘的な箇所があまりしっくりこない感...続きを読むPosted by ブクログ -
以前買った雑誌サライに「半島に行く」の連載を見付けた。二度行ったことのある丹後半島だったので、興味を持った。
さて、その連載が一冊の本となって上梓されたのを新聞広告で知り、購入、
気楽な歴史紀行と思ってたら、どうしてどうして、面白くて、久しぶりにページを捲る手が止まらない読書となった。
歴史作家と歴...続きを読むPosted by ブクログ