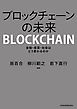検索結果
-
-「本書で皆さんにお伝えしたいのは、いくつになっても、どんな状況になっても、新しい扉を開くための方法です」。著者は、独学ブームの元祖・柳川教授。『独学という道もある』に、いま注目のリスキリング(学び直し)論を増補した決定版。年齢、世代を問わず一生モノの本質だけを集めました。 会社や世間から嫌々やらされるのではなく、自分で自分の新しい可能性を切り開くために学ぶこと。それは自分の未来をマネジメントすることにもつながります。 そして独学のコツの一つは、頑張りすぎないこと。三日坊主に終わった自分にがっかりしてムリだなんて決めつけはもったいありません。「ふまじめ」なほうがいいのです。 異色のキャリア(大検→慶應通信部→東大院)を歩んだ著者ならではの「非常識」な学びのすすめ。 まえがき――誰でもやり直せます、いつでも学び直せます 第一部 働くみんなの「リスキリング」入門 1章 「なぜいまリスキリング?」の疑問に答えます 2章 これからの人事と経営はこう変わります 第二部 独学で人生を切り拓く 3章 オフロードだって道のひとつ 4章 私はこんなふうに独学してきました 5章 大学院を使った学び直しのススメ 第三部 大人のためのマイペース独習法 6章 「キャリアの振り返り」から始めましょう 7章 独学は「ふまじめ」なほうがいいのです
-
3.8過去の学びや蓄積を最大限に活かす 新しい成長の技術 アンラーンとは、「学ばない」ことではありません。 過去の学びから、クセやパターン、思い込みをなくすことで、 新たに成長し続けられる状態に自分を整える技術です。 以下の項目に1つでも当てはまる人は、 アンラーンで「学びの効率」が上がります。 □何かをしない言い訳に「(仕事が)忙しくて」とつい言ってしまう □自己紹介では会社名や肩書を入れるのが当たり前 □最近、ワクワクすることが減った □「疲れた」などの、ネガティブな口グセがある □周囲の人との会話が、毎日同じような話題ばかり □仕事とは別の分野の「学び」をしていない □この1か月で、仕事関係者以外の人と会った人数が3人以下 □「以前はこうだった」「こういうときはこうするものだよ」と前例で説明したくなる 「新しいインプット」の前に絶対不可欠な 「学び、成長し続けられる自分」の整え方
-
4.38万部のベストセラー『ダークサイド・スキル』木村尚敬氏と 「40歳定年説」柳川範之東大教授による最新作! 先の見えない時代、「管理職」に求められる役割も変わりつつある。 従来からある「マネジャー」としての仕事に加えて 「リーダー」としてリスクをとった意思決定を自ら行い、 ときには一級の「プレイヤー」として最前線に立つことも要求される。 旧来型の管理職として時代に取り残されるか、 新時代のリーダーとして道を切り開くか。 本書では、その2つを対比しつつ、新しい時代の「管理職に求められる条件」を描き出す。 ○時代に取り残される「旧来型」オッサン管理職 -情報がないから判断できない -自部門に不利な決断ができない -意思決定を自分の仕事だと思っていない。責任をとらない -「リスクを減らす」ことが自分の役割だと思っている -会社にしがみつく ○2020年代に生き残る管理職への道 -20代、30代の友達をつくれ -現役感を手放すな -ムカつく奴を使いこなせ -チームの羅針盤をつくれ -ブライトサイド・スキルを磨け
-
3.0
-
4.0「失敗の責任をすべて押しつけられた」「とうてい達成不可能な、とんでもない目標を課された」「不祥事を隠蔽するよう迫られた」etc……。仕事をしていると誰もが直面する「本当にヤバい場面」。本書はそうした「修羅場」の事例を元に、その解決策を探っていくという「紙上ケーススタディ」集。中間管理職ならではの「上と下との板挟み」のケースから、「社内で不正が発覚」「リストラで現場が大混乱」といったより深刻なケース、そして「家庭と仕事との両立」「病気によって休職を余儀なくされる」といったキャリアに関する問題まで、極めてリアルな30のケースをもとに、どのように危機に対処すべきかを説いていく。著者はベストセラー『ダークサイド・スキル』の木村尚敬氏。時には正攻法で、時には「禁じ手」を使ってでも危機を乗り越えていくためのリアルな方策を伝授する。
-
3.3修羅場のプロフェッショナル・冨山和彦氏と 『ダークサイド・スキル』木村尚敬氏のコラボレーション! 乱世の今こそ、古典に学べ! 多くのリーダーが座右の書として挙げるマキャベリの『君主論』。 そのエッセンスを現代のビジネスに当てはめつつ、解説するのが本書だ。 きれいごとではすまされない再生・改革の修羅場を潜り抜けてきた2人が、 その経験をもとにリアルに語る。 第1部では、なぜいま君主論なのか、コロナで一変した日本企業を取り巻く状況と、 リーダーの役割の変化とを関連付けて、冨山氏が解説する。 第2部では、君主論からの重要ポイントを引用し、その意味するところを説明しながら、 実際のビジネスの現場でどのように適用すればいいのか、 木村氏が事例を使いながら紹介する。 第3部は、君主論を体現するリーダーであり、日立の再生を成功させた中西宏明氏の 改革手法について、冨山氏と木村氏が対談形式で語る。 ――マキャベリは「非連続な時代において、国を統治する君主はどうあるべきか」を論じた。それが『君主論』である。 そして「国」を「企業」に置き換えれば、そのまま現代のビジネスリーダーが直面しているテーマと重なる。すなわち「非連続な時代において、企業を統治するリーダーはどうあるべきか」である。 よって『君主論』は、現代のリーダーや次世代リーダーにとって、またとない教科書となる。その内容は500年経っても色褪せない普遍性を備えており、企業経営・組織マネジメントに携わる者にとって必読の書と言えるだろう。――「はじめに」より
-
3.9きれいごとだけでは生き残れない。人を操る「ヒューマンスキル」を手に入れよう! ロジカルシンキング、プレゼンテーション、マーケティング…… MBAで教えてくれるような「正当派のスキル」だけでは、現実のビジネスは進まない。 上司を操り、部下を利用し、時にはさりげなく、時にはわざと衝突しながら自らの意思を通していく。 経営環境が厳しくなればなるほど、そうした「ダークサイド・スキル」が欠かせないのだ。 本書は、リーダーになるために必要な「7つの裏技」を紹介。 「修羅場企業」のコンサルを多数手がけた著者が、実例にもとづき解説する。 良品計画を立て直した松井忠三氏との対談も収録! ◎7つのダークサイド・スキル その1 思うように上司を操れ その2 KYな奴を優先しろ その3 「使える奴」を手なずけろ その4 堂々と嫌われろ その5 煩悩に溺れず、欲に溺れろ その6 踏み絵から逃げるな その7 部下に使われて、使いこなせ
-
4.0新しい「日本の形」をつくる社会変革の書! 少子化・超高齢化のもとでは、労働力人口が減少。それによって日本経済は縮小していく… このままでは成長はおろか縮小均衡すらもできないことは明らかである。 日本経済を再生・成長させるには、労働人口を減らさないことが最重要であり、 そのために実現可能、かつ効果的な政策が本書の主題「40歳定年制」である。 【40歳定年制が成長戦略である理由】 1日本人の働き方が変わる。 240歳で働き直すことでその後高齢(75~80歳)まで働きつづけることができ、キャリアアップがはかれる。これにより今までは破綻必至の年金制度の崩壊が防げる。 3多くの社内失業者が学び直しで活性化する。 4現在の硬直した雇用形態で働くことができない、女性や若者の働く機会が増える。
-
4.2■本当のところどうなのかを解説 仮想通貨を支えるテクノロジー、ブロックチェーンが注目を集めつつある。技術は未熟な面があるが、通貨、金融サービス、契約・取引、IoTなど、経済社会の広範な分野に破壊的なインパクトをもたらす可能性があります。 ■豪華な執筆陣がわかりやすく、包括的に解説。実務的・学術的関心にも応えます。 本書は、金融・フィンテック事情に詳しい翁百合氏、柳川範之氏、岩下直之氏の3氏をはじめ、経済学、法律、銀行、証券、ITなど各分野の実務担当者、官庁の担当者が一堂に会して、ブロックチェーンの可能性を解説します。本書にはつぎのような特色があります。 ★わかりやすさ:本書は、ブロックチェーンを技術面から解説するのではなく、その特徴やメリット。その分類、課題や実践例などを平易に解説し、広く社会への影響をとらえるものです。 ★包括性:ビットコインに代表される仮想通貨、国際送金などの金融サービス、企業のサプライチェーンへの応用、電子政府への導入など、さまざまな応用事例を具体的に、包括的に紹介。日本の実証実験の状況はじめ、海外の事例を豊富に取り上げます。 ★実務的な関心に応える:各分野でブロックチェーン応用の実証実験に取り組んだ当事者が、執筆に参加しています。そのため、実務に即して何が課題なのか、どのような可能性が開けるのか、実践的観点に役立つ内容になっています。官庁の担当者も執筆に加わっているので、日本政府の姿勢もわかります。 ★学術的な関心にも応える:金融政策や金融規制、金融システムとの関連、法的な枠組みとの関係、経済学の契約理論からどのように説明できるのかなど、学術面も含めたより深い知的な関心にも応えるものです。 ★ブロックチェーンが社会を変えていく様を展望した「未来年表」のほか、用語解説集も盛り込み、充実した内容になっています。
-
4.3IGPIのコンサルタントが提言! 「現場再生」のスペシャリストだから語れる4ステップ進化法! AIもIoTも、製造業の競争力向上の要となるテクノロジーであることは間違いない。 しかし、多くの日本企業が、そのメリットを最大限享受するまでには到っていない。 このままでは、グローバル競争に取り残されてしまう危険性も否定できない。 「いかにIoTを活用しようが、ビジネスモデルを進化させようが、 モノづくりの基本ができていないと意味がない」と著者たちは強調する。 本書では、まず「見える化1.0」「2.0」「3.0」というモノづくりの土台を しっかりと築いたうえで、新しいモノづくりの姿である「見える化4.0」を提唱する。 すぐにでも手をつけられる具体的な施策が満載の1冊だ。 【「見える化」進化の4段階】 見える化1.0=儲けの構造の見える化 グローバル化の進展で複雑化する組織・製品をきちんと仕分けて 原価・儲けの構造を解き明かしていく。 「どの拠点、どの顧客、どの製品が儲かっているのか/いないのか」 という一番大事な情報を明らかにする。 見える化2.0=プロセスの見える化 顧客のニーズを製品企画にしっかり取り込むのと同時に、 モノづくりのプロセス全体を一気通貫に見える化して重複や無駄を省く。 見える化3.0=稼ぐポイントの見える化 モノを売るだけでなく、それをサービスモデル化することで、 収益の構造を根本から見直す。 PLモデルから、バランスシートモデルへ、頭を切り換える必要がある。 見える化4.0=リアルタイムの見える化 IoTを活用すれば、各種のデータをリアルタイムで取得できる。 それらを分析することで、バリューチェーンのあちこちに、 それぞれの企業にあった「儲けの戦略」が見えてくる。
-
3.4