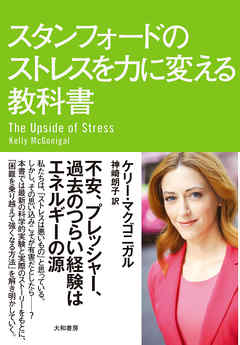感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
・脅威反応場×とチャレンジ反応◎
→どちらが表れるかは対処する自身があるかどうか
→チャレンジ反応=思いやり・絆反応=人の為に頑張る=勇気が出る=大きなものの一員だと思う=身振り手振り大きくなる
・ストレス反応はこう捉える
→力になるもの、身体に良い、役に立つ
・ドキドキはこう捉える
→力が湧いてくる
→成功する、吸収してエネルギーにする
・ストレス
→害ではない、自分を守ってくれるもの
Posted by ブクログ
<要約>
ストレスは役に立つと理解することで、ストレスを受けるほど成果が上げられる。
<感想>
コロンビア大学ビジネススクール行動研究所で行われた実験によると、ストレスに対する考え方1つで健康を害するか、健康を増進するかが決まるということでした。これは本当に驚く内容です。
ストレスによって分泌されるホルモンには、コルチゾールとDHEAの2種類がありますが、前者は心身の健康に害をなしますが、後者は健康を増進するのだとか。
そして、「ストレスは害になる」もしくは「ストレスは役に立つ」と教えられた実験者が同じストレス環境下にさらされたとき、前者はコルチゾールが上昇し、後者はDHEAが上昇したそうです。
また、ロチェスター大学の研究で、試験を受ける大学生に「ストレスを感じるとテストの結果が悪くなるどころか、むしろよくなることがわかっています」と伝えた生徒は、対象群の生徒よりテストで高得点を取ったと紹介されていました。本当に驚かされる内容です。試験前の心構え1つでテストの点数が変わったのですから、試験を受ける学生は是非とも知るべき知識です。
しかも、さらに驚くべきは、その後の追跡調査で本番の試験では、2つのグループの点数の差はさらに大きく広がっていたというのです。
ストレスに対する考え方を変えてくれた本。前著の『 スタンフォードの自分を変える教室』も読んでみたい。
Posted by ブクログ
そう言われてみると、
私も逆境が好きかもしれません(笑)。
困難や試練は、やって来たらチャンスと思え!
というのが私の信条です。
読み進めながら
「ストレス=刺激」
だと、私は感じました。
締め切りまで日にちがあると
進捗が悪いのは、
ストレスを感じていないからにほかなりません。
明日が締め切りだと、火事場の馬鹿力が炸裂!
雑音など耳に入らなくなります。
時間があって、丁寧に仕上げられるような状況では、むしろ雑念が入って内容が散漫になってしまいます。
自信が持てました。
これからも、ストレスを受け止めて、上手に使いながら成長していきたいです。
Posted by ブクログ
2022.4
「ストレスは健康に悪い」と心配し、ストレスのせいで病気になるのを恐れているが、問題はストレスではなく、その考え方であることを、いくつかの研究結果を通して書かれている。
そして、ストレスの考え方しだいで、人々の健康や寿命、幸福感、人生に対する満足度が左右される。
この本の後半では「ストレスを力に変えるエクササイズ」が紹介されており、ストレスをポジティブなものとして捉えるためのマインドセットも行える。
マインドセットの方法自体は、知っているものもあったけど、その根拠(研究事例)までは知らなかったので今までの知識と結びつく感じで読めて面白かった。
Posted by ブクログ
「ストレス=悪」ではないということがいろんな意味でよくわかる本でした。
数年前から「ストレスってたまるとよくない」とは思うけど、「まったくストレスがない状態がいいのか?」と考えるとそれも違うよぅな気がしていました。
「ストレス=害」という思い込みを捨て、「ストレスは役に立つ」と考えてみる。本書にはそれによる効果の体験談がガッツリ載っています。正直、くどいぐらいにw
それによると実際、そう考えている人のほうが人生に対する満足度が高いそうな。なぜなら、そう考える人は
・ストレスを感じた出来事に対して向き合おうとする
・ストレスの原因に対処する方法を考えようとする
・困難な状況において以前を尽くそうとする
から、とありました。
そういえば、ストレスを感じる出来事たとえば仕事で深刻なミスをしたとかそういった時って、お酒ややけ食い、カラオケで気を紛らわせようとしてもダメで、「どうやったらそのミスを防げたのか、今後どうすればミスを防げるのか」を真剣に考えたほうが、ストレスが軽くなったような気がしていました。そうか、こういうことだったのかもしれません。
また、「人に何かを与える・してあげる」ことも癒しになるとの話もありました。ピア・カウンセリングが効果があるのもそのためなのですね。
人のためと言えば、本文では「自分のための目標」と「自分よりも大きな目標」の違いについて書かれてあり、前者は不安や怒り、孤独感にさいなまされやすいのでストレス度が高く、後者は人に貢献しようと考えて動こうとするので人生への満足度が高いとのこと。
ちょうど「キングダム」や「鬼滅の刃」でも同様の話がありました(書ききれないので割愛)。
ストレスは避けるよりも、うまく付き合うほうが人生うまくいくし、楽しいと思えるものかもと思えた一冊でした。ただし、かかるストレスにも限度がありますが。
ただ、登場する体験談が多すぎてちょっとくどく感じたので★-1で。
Posted by ブクログ
医療者のメンタルヘルスについて学びたく本書を手に取りました。
以下まとめ
Part1
ストレスそのものでは死なない。
ストレスは体に悪いと思うこと自体が悪い。つまりすべては思い込み。
ストレスは役に立つと思うと実際にそうなる。
そう介入することをマインドセット介入という。
医療者は職務上のストレスを処理する必要がある。
時に感情をシャットダウンすることで処理する…結果、患者をモノのように扱ってしまうことがある。
またその対処では仕事に意味を見出せなくなりかえってバーンアウトを起こしやすくなる。
→マインドフルネスの状態でそれぞれの体験を語りあい、傾聴しあうワークショップを行った
→ストレスを受け入れ、避けようのない悲しみのなかに深い意味を見出すことでストレスを力に変えた。
ストレスを避けようとすることで孤立的になり、結果うつ病罹患や離婚率が高くなるという結果がある。
避けるのではなく「ストレス」と「意義」には密接なつながりがあることを認識すれば人生は意義深くなる。
Part2
自分のための目標に向かっていると利己的になり、不安や妬みが大きくなる。
自分よりも大きな目標(組織の目標とか)に向かっていると考えると仲間と支えあうことができる。
日常的に人助けを行っている人びとにはストレスによる死亡リスクの増加は見られなかった
→思いやり、絆を大切にしている人々
(それなら医療者は…医療者が問題に対して孤立しないことが大切なのだろう。)
苦しみを抱えているのは自分だけじゃない、力になりたいと示すことが大切
(自分だけじゃない、という言い方は人の苦しみを一般化することではなく自分の共感性を示すこと。
文脈から読まないと勘違いが起こりそうなのであえて記載しておく)
ベネフィットファンディング…苦しみの中の良い面を見つけること。
ただしこれは自分の意思でやらないと意味がない。他者から強制されては効果がない手法。
代理成長…他者のトラウマ経験を通して自己の成長や意味を見出すこと。
心から共感することで相手のつらさ、相手の強さに気づくこと。