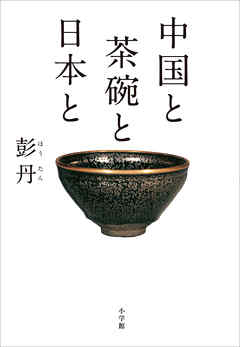感情タグBEST3
Posted by ブクログ
昨年観た東博の「茶の湯」展のおさらいにと思って読みました。
なぜ、中国産の茶碗が日本の国宝として矛盾しないのかなどなど。茶の湯を通して日本文化の奥にある中国文化を中国人の筆者が探っていきます。
中国に天目が残らなかった理由などはゾクゾクする。
Posted by ブクログ
良く「辺境効果」などと言うが要するに文化の中心から離れて外界との接触が少ないとそこには古くから伝わった文化が変化することなく保存されているというもの。これがまさしく日本文化に見られるというのが本書、中国は四川省出身の文化人類学者である彭丹さんの見立てだ。
中国で既に千年も前の古文書に現れるだけとなった「お屠蘇」が日本に根付いているのにビックリしたり、とうの昔に廃れた中国古代の上巳節が由来だという桃の節句が未だにあることに驚いたりもする。その彼女が日本文化を更に知ろうと飛び込んだのが侘・さびの世界の茶の湯だが、そこで目にしたのが国宝とされる中国製陶磁器の数々だ。日本の国宝なのにどうして中国の陶磁器が選ばれているのか疑問に思う一方で、中国は現存しない貴重な陶磁器が日本にだけ存在するという不思議。それらの陶磁器の来歴を探ることで日本と中国の文化の関わりを調べたのが本書だ。
本書以上に惹かれるのが口絵写真で紹介される国宝級陶磁器、8点のカラー写真だ。中でも「曜変天目茶碗」は「お宝鑑定団」風に言えば”実に景色が良い”とでも言いたくなるし、写真で見てもこれはと思える一品だ。曜変というのは元々は窯の中で何らかの予期せぬ炎・温度の変化で茶碗の釉薬が泡立ちそこがなんとも言えぬ味わいを出しているのだが、そもそも皇帝献上品としては規格外でありすぐに廃棄されるべき代物であったのが、どういう経緯なのか日本まで渡り茶の湯で珍重されて今の世にまで残った貴重品だという。
こうした写真を見るだけで本書の元をとったようにも思えるし、その来歴などを知れば知るほど更に今後のお宝鑑定団も楽しんで見れるというものだ。
Posted by ブクログ
根拠がはっきりしない、筆者の推定がかなり含まれるように思う。けれど、中国人からみた日本文化を茶碗からみるという視点が面白い。
青磁茶碗、天目茶碗、祥瑞茶碗の謎。
唐~宋の青磁の中でも、浅黄色の団茶を美味しくみせる気砧青磁が尊ばれる。
その後日本では、中国では雑器とされる灰黄色の珠光青磁が侘び茶の創始者の村田珠光に好まれる。
曜変(←窯変)天目は中国では恐れられ残っていない、また、たい皮天目も派手な文様が中国では好まれないが、それぞれ茶碗の美しさから日本では珍重される。
白い抹茶の泡を美しくみせる油滴天目、禾目天目は、宋が滅びて抹茶の文化がなくなると日本を含む海外に流出。
祥瑞茶碗は、染付けの香炉が日本でお茶に持ち込まれ、小堀遠州が景徳鎮窯に注文して作らせたことで生まれた。
木の文化であった日本において陶磁器は、茶人に求められるようになるまでは大陸から受け入れるもので、命名することで日本文化に取り込んでいった。
中国は王朝が変われば文化も革命的に変わるのに対して、日本では受け継いでいっており、古代の中国の文化が形を変えて日本に残っている。
Posted by ブクログ
著者は中国人であることもあり、おきまりのすべての始まりは中国であるという論調が何となくにじみ出てくる本であるが、中国で忘れ去られてしまった文化が日本に残っていると言う事に著者の詳しさも少しにじんでいるようで、まあ痛み分けという事にしておきたい。
窯変天目茶碗というと日本に3点あるものはすべて国宝指定されているのに、なんと世界にもこの3点しかないのである。しかもこの3点は同然ながら唐物である。
著者は中国製の茶碗を国宝とする不思議さもしくは懐の深さを指摘する。国宝の茶碗は7点しかないが日本で焼かれたものは2点しかないのである。
青磁、天目、祥瑞と言った茶碗の日中での扱いの違い、また龍文がなぜ日本に少ないのか等々日本の茶碗のなぜを考えていく。本当にそうか?と疑問に思うところも散見されるものの、日中の文化の違いと言う事を考えさせられる良書だと思う。
Posted by ブクログ
中国人から見た見方がわかる。他の書籍では得難い中国側の情報もある。
細かい部分を検討しないで断定しているので間違いも見受けられるが、論理としては分かりやすくなっている。
Posted by ブクログ
知識欲を掻き立てられる、なかなか読み応えのある本でした。焼き物から、歴史や日本と中国の違いなど、興味の尽きない方向へ話題が進み、固い話のはずが、すぐに読み切ってしまいました。
Posted by ブクログ
そうなんだよね
日本に昔からあるんだよね
と いわれるものは
たいがい
そうではないんだよね
そこのところが
気持ちよく
分かってしまう
私たちを謙虚にしてくれる
一冊です
Posted by ブクログ
かつて結構勉強したつもりの中国陶磁史。あまりよく理解出来てなかったのを、再確認しました。著書の言うところの、「継承的改良的な創造法」とする日本文化観は、内田樹氏の辺境論とも一脈通ずるところありと感じました。日本の陶磁史研究者による、反論や新見解が、楽しみに思います。
Posted by ブクログ
メモ:
文字が大きいのですぐ読めるかな?と思ったら、読むところの多い本だった。
これだけの内容ならモノクロでよいから、本文まわりに図版や詳細な脚注をもっとつけてほしかった。
ルビも一回目だけでなく、何度かつけてほしい。
編集ももっと力を入れてほしかった。
『日本文化の源流をたずねて』の綛野さんやハラリさん級に推測に次ぐ推測での憶測…な記述や、実証に欠く記述も多いが、歴史を扱う書だとこれぐらいでないと、大胆な仮説も何もも言えなくなってしまうのだろう。
私の勝手憶測、
・1万年前、縄文時代にいた日本人は噴火で西日本はほぼ絶滅
・中国から渡ってきた人々で弥生時代
・朝鮮から渡ってきた人々で弥生後期~古墳時代
なので、文化政治、社会を組織的に管理するツールのルーツはぜんぶ大陸で、その通りかと思う。
日本文化のルーツが中国であり、中国ではゴミ同然のやきものが、海を渡り、高値をつけられて、日宋貿易あたりから日本で出回った…的なことが、何度も繰り返されるのだが、これは、カリフォルニアロールは寿司じゃない!みたいな感じなんだろうか。
受験生時代は、出題されないイスラム史に時間と労力をかけていた私も、朧気な中国史の記憶を引き出しながら、中国文化の懐の深さを、またよくよく知った。
ルーツは大陸であることを強調されるほどに、ドイツが欧州の辺境だったように、日本はアジアの辺境でありながら、独自の文化を育んできた、無資源ゆえの工夫や細やかさや美意識などがかえって際立つ感想を抱いた。
P217
五というものは、君子たる人の盛徳
五はすべてを表し縁起が良い
天帝が兎に賜った天下を治めるための九種法則のうち五のつくもの
五行:水・火・木・金・土~宇宙を構成するあらゆる物質
五事:貌・言・視・聴・恩~行動基準
五紀:差月・日・星辰・暦数~暦法
五福:一曰寿、二曰富、三曰康寧、四曰攸好德、五曰考終命 (書経 洪範)
五倫:仁義礼智信
P274
日本の政治体制は、天皇と将軍が併存し、権威と権力が分離
龍は中国のように政治上の権力よりも強さと力の象徴に変わった
日本では龍は水神など
また蛇のイメージがあり、器に龍を描くことを好まなかった
(追記)
↓たまたま見かけました。うめさん、ありがとうございます。