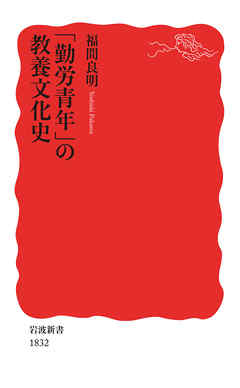感情タグBEST3
Posted by ブクログ
定時制高校へ進んだ動機について、53.6%が「できるだけ教養を高める」と答え、「高校卒の資格を得る」の18.7%を大きく上回ったという(1960年のある調査)。
昭和20~30年代において、高校に進学せず就職・就農した「勤労青年」たちが「実利を超えた教養」を求め、農村では青年学級、都市部では定時制高校、時間・空間の制約がある者は「人生雑誌」という場に集っていた。そうしたコミュニティの成立と消滅についてまとめた一冊。
同時代において学歴エリートの間にも教養主義があった(そして、同じように昭和40年代以降に衰退した)が、非エリート層の大衆教養主義には違った背景もあったことが指摘されている。
高校進学率が低い時代において、経済的な事情で進学できず鬱屈、葛藤を抱えた成績優秀者の代償行為という面もある。
また、定時制高校を卒業しても転職活動において高校卒とみなされない中で「高校卒の資格を得る」ために定時制高校に進んだとは、口にできない・したくない心理もあったのだと思われる(本書ではそこまで踏み込んだ推測はしていないが)。
「人生雑誌」というものの存在を私は知らなかったのだが、『葦』『人生手帖』といった「勤労青年」層を対象にした雑誌があって最盛期には10万部に近い発行部数だったという。
青年学級や定時制高校に通うことが困難(地理的な問題のほか、奉公先の明示的・暗示的な妨害を受ける)な人々が隠れ読むような雑誌で、似たような境遇の人々の投稿を読んで共感するなどしたという。
1960年代後半には高校進学率の上昇という理由もあって「人生雑誌」は退潮に向かい(青年学級も消えつつあり、定時制高校は「全日制に行く学力がない人の学校」とみなされるように変質しつつあった)、雑誌という形での継続的なコミュニティは失われたという。
しかし、かつての「勤労青年」たちは、「人生雑誌」のような大衆教養主義の雑誌ではなく大衆歴史ブームに居場所を移したというのが著者の分析である。彼らが中高年層となって昭和50年代に『歴史読本』『歴史と旅』『プレジデント』などを支える中核となっていたとする。
ちなみに、いまの『プレジデント』しか知らないとピンとこないと思うが、昭和50年代には徳川家康とか山本五十六とかをやたら特集している雑誌だった。
なぜ大衆歴史ブームかというと
「実証史学であれば、古文書を読みこなし、地道に史料批判を重ねる作業が求められるものだが、歴史読み物にふれるだけであれば、そうした労苦を経ることなしに、史的な流れや歴史人物の思考(と思しきもの)を味読することができる。」
と、参入障壁が低いからだという。そしてそこには反知性的知性主義の萌芽があると。
著者はこんなことを書いてはいないが、定年後にネットを見始めて陰謀論を説くようになった高齢者像が目に浮かぶようだ。
著者は「勤労青年」世代の置かれていた状況を振り返っていて、その同情すべき事情も書いているが、それでも対象に対して客観的である。なのでその論考を進めるとこうなってしまうわけで…。
ちなみに本書は世代に注目しているので雑誌メディアにおける「勤労青年」の場がなくなって単行本に移行した後のことは追跡していない。
その点は牧野智和『自己啓発の時代』が述べている。単行本メディアである「自己啓発本」の初期は哲学者や作家が比較的漠然と「生き方」を説いていたが、徐々に実利にシフトしていく様を追っている。
Posted by ブクログ
この本は20世紀半ばから後半にかけて、勤労青年たちにとって「教養」にはどんな意味があったのか、なぜ教養を求めたのか、など当時の社会情勢を描きながら中学を卒業した後すぐに働く青年たちの様々な思いを考察したもの。
当時の高校進学率(全日制)は今に比べて格段に低かった。それには様々な理由があるが、一番の理由は、学費の問題だ。それ故、昼間は働きながら定時制の高校に通う人が多かった。そして定時制に通うほとんどの人たちは良い企業への就職や、転職のためではなかった。(もちろんそういう人たちもいた)
彼らの目的は「教養」を身に着けることだった。彼らは全日制の人たちよりも一足早く社会に出て上司の人たちから理不尽な扱いをたくさんしてきた。勤労青年たちはその不条理な社会に疑問を抱き「人としての生き方」や「社会の在り方」の真理を発見するため定時制に通いだした。
しかし学業と仕事の両立は様々な理由で難しいものだった。(職場環境、人間関係、学習環境、学習内容、健康面など)
これらが理由で「教養」への熱が次第に冷めていった。
そこで勤労青年たちの「学ぶ場」として新しく誕生したのが「人生雑誌」というものだった。彼らは雑誌を通して定時制には無かった「哲学、歴史、思想、社会科学」といった実利的ではないものを学ぶ事ができた。(それらは彼らが求めていたもの)
だが「人生雑誌」も様々な理由から徐々に衰退していく。(それを読むことによって社会から左翼的と思われ悪いイメージがついた)
そして高度経済成長期に入ると段々と経済的格差が無くなって物質的にも豊かになり始めると同時に高校進学率(全日制)も上がった。
また、定時制に通う人に対する社会的評価も変わり始めた。経済的な理由から定時制に行く人が少なくなったが故にそれでも定時制に進学する人は「学力がない」、「落ちこぼれ」などと評価されるようになっていった。
自分の中の結論としては、世の中が経済的に豊かになった行き青年たちの生きがいというか人生での目的が「物質的」に豊かになることになっていったのではないかと思う。心の平安が「教養」ではなく「消費」に代わっていったように感じた。
Posted by ブクログ
アジア太平洋戦争後、全日制高校に進学できなかった勤労青年の間で発生した教養文化について、その消滅までを追跡したもの。進学できなかったことへの鬱屈や、「教養」に触れない人たちへの優越感が、教養文化を支えていたことが浮き彫りにされる。1970~80年代の歴史ブームの担い手を、かつて教養主義をくぐった男性中高年層に見出す個所も面白い。
労働環境の改善や消費文化の浸透という勤労青年にとっての「幸」が、人生雑誌の「不幸」=教養主義の消滅をもたらしたとの指摘は重い。それでもなお教養が流行する社会を是とする説得的な理由を見出すことは、決して簡単ではないと思った。
Posted by ブクログ
竹内洋先生の作品から「教養主義」という主題には興味があったが、これはそれを勤労青年、例えば定時制高校などに通う労働者などに焦点を当てた作品。まだ最初の半分しか読んでないないが、戦争を通じての既存の社会への絶望・農村の閉そく感などと相まって、「教養」への憧憬が強まっていく歴史など、非常に興味深い。
Posted by ブクログ
かつての勤労青年の教養への憧れ、そしてそれがどうして喪失していったのか、若者たちの生の言葉もたくさん引用され、面白かった。
これほどまでに、人生について私は考えたことがあっただろうか…
そんなことも思いながら読んだ本だった。
Posted by ブクログ
幅広く教養への憧憬とその冷却の過程をえがいた秀作。著者の前著に、青年団・定時制を加えて書き下ろされた物でくしくも個人的にヒットする部分が多かった。そのため、定時制についてはやや一面的な部分もあるのではないかと思いつつ、でもああそうだったのかと首肯させてもらうことの方が全体的に多かった。竹内洋の名作教養主義の没落をうまくパラフレーズさせて独自のエッセンスを入れている。改めてこのあたりを学び直したい気分になったし、下村の運動はやや右派の教養主義の運動の系譜ではないかと考えられそうだと思った。何のために学ぶのか、実利でない人文知の価値を深くかみしめたい。
Posted by ブクログ
高校に進学できなかった代償としての文化雑誌についての説明は十分であった。さらに、そのための教養としての文科系学問の重視というのも理解されたが、それがなぜ大学における文系学問の軽視につながるかについては説明がなかった。ただし、教養の断片化としての新書、という考えは賛同できる。
さらに、中高年層からの歴史物語の流行、及び専門家ではない司馬遼太郎の歴史小説としての流行という位置づけは面白い。
Posted by ブクログ
もやもや思っていたことを、わかりやすく文章化してもらったものを読めるという快感があった。『キューポラのある街』をツカミに持ってくるのは、新書の社会科学分野としてハマりすぎみたいだけれど、明快で想定読者層を突き放さない読み物だ、という確かなメッセージにもなっている。
内容で留意すべきなのは、扱っている時代幅が「戦後以降」であるということ。江戸時代、明治・大正という時代を遡って青年層の上昇志向の変異分析といったものとは、明確には接続していない。うがってみれば、敗戦後から1980年頃まで、「勉強しなさい」と大多数の親が怒鳴っていた時代はそれだけで独立して分析対象となりうるということか。確かに、マスとして「勉強」を通じた上昇志向が共有されていたのは、戦後の、それも昭和のある期間だけかもしれない。日本史上においても特異な時代であったのかも。
Posted by ブクログ
エリート層の教養主義については類書も多いが、進学が出来なかった層に焦点を当てて、それぞれの背景や状況をきめ細かく叙述していて、当時が具体的に浮かんできます。バックデータとなっている資料収集の苦労も窺われます。
Posted by ブクログ
ノンエリート層の「教養」について、戦後〜1970年代までを主な射程に、青年学級・定時制・人生雑誌への眼差しをまとめた本。おそらく資料収集に相当力を注いだのではないか。その苦労は察せられるが、引用とまとめが繰り返され、やや冗長に感じた。最後の歴史趣味への論考や、高度成長以降、ノンエリート層から「教養」が如何に見放されたのか、もう少し読みたかった。
Posted by ブクログ
1950年代後半を中心に、上級の学校へ進学できなかった「勤労青年」たちの「教養」への渇望の実相と、何が彼らを必ずしも「実利」と結びつかない「教養」へと向かわせたか、農村では青年団・青年学級、都市では定時制高校や企業の養成所、さらにそれらからはじかれた若者たちの学習欲求の受け皿として機能した「人生雑誌」の盛衰を通して明らかにしている。50~60年代は中学校において「進学組」と「就職組」のコース別学級編成が進行した時期であり、家計の貧困や家父長制の圧迫故に進学できず、差別的待遇を受けることへの不条理に対する後者の鬱屈を重視している。当時の若者の「生の声」を通して見える当時の日本社会の矛盾は、ある意味今日の新自由主義社会における貧困・格差を考える上で依然として参照軸となりうる。
結局、高度成長の開始による所得格差の縮小(高校進学率の急上昇や労働環境の改善)と小市民的な消費文化の隆盛によって、大衆教養主義の支持基盤は(高学歴層における教養主義と同様に)衰退するが、本書では50年代に「教養」の洗礼を受けた世代が、80年代以降の「大衆歴史ブーム」(歴史小説や通俗的な歴史読み物)の担い手となることにその「残滓」を認めている。この点はブームの担い手の階層や世代についての実証を欠いており、そのままでは認めがたい。あとがきでさらりとしか触れられていないが、ある地方の『人生手帖』サークルが同誌の廃刊後『PHP』の読書会に衣替えしたというような事例にこそ、大衆教養主義の変貌を読み解くヒントが隠されていると思われ、より精緻な分析を望みたい。