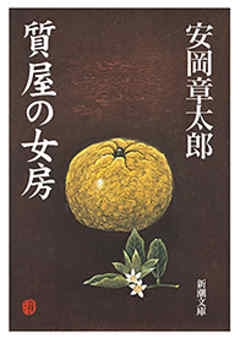感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「ガラスの靴」は前読んだときから随分印象が変わった。以前は主人公の抱く恋愛感情に浮ついた心地よさみたいなものを強く感じたけれど、今度は僕と悦子の間にあるじめじめとした人間の匂いを一文一文から感じた。こんな文章あったっけと思うことが幾度もあった。
「青葉しげれる」「相も変わらず」は、順太郎という主人公の登場する連作で、母との関係が描かれた話。大学生ごろの年齢設定だからか、「三四郎」「それから」っぽさを感じた。
「相も変わらず」がこの作品集の中で一番好き。「悪い仲間」などにもあった、家族から逃れようとするも最後の最後に逃れられないことに気づくという主人公の姿にひどく共感を覚える。さりげない描写にとてつもない文章の力を感じた作品だった。
「質屋の女房」も好き。
Posted by ブクログ
学生時代(出征前)を描いた作品が一番多く、終戦直後がひとつ、戦後10年以上経った時代を舞台にしたものが2つ。芥川賞受賞作を含む。
発表された時期はバラバラ。安岡章太郎の代表作を集めたと言っていいだろう。
「ガラスの靴」は恋愛(それも未熟な恋愛)小説の傑作。若さと才能だけではなく、あの時代に生きていたからこそ書けた。今の上手い作家が同じ時代を舞台にしたところで、これは絶対に書けない。「待つことが、僕の仕事だった。」忘れられない。
代表作だけあって、どれも良かったし、戦争中に浪人していた、母に愛された取り柄のない一人っ子の気分というのは、彼だからこそ書けたと思うが、自分が中年となり、かつては不在ながらも存在感と威圧感のあった父が老いた姿を描いた最後の2作も素晴らしい。
もっと読みたい、安岡章太郎。
Posted by ブクログ
短編集
個人的には表題作の『質屋の女房』よりも、
『悪い仲間』や『陰気な愉しみ』の方が好きで、
社会に劣等感を抱きつつ中々前に進めない登場人物たちに非常に好感が持てます。
『ガラスの靴』も読後感の素晴らしい作品です。
短編で読みやすい作品ばかりですので、是非手に取ってほしいです。
Posted by ブクログ
青春期はある意味、モラトリアムであるとおもいます。
産みの苦しみを経て青年は次のステージへと進んでいくのが一般的な成長だと思うのです。
しかし、ここでの主人公はモラトリアムとも言えない、本当に無駄な時間、糞みたいな時間を過ごしています。
「誇り」も「覚悟」も無いから、女も抱けず、軍人にもならず、学生にもなれず、母親からも独立できずにいます。
こんなクソ野郎が主人公のくせに、苦悩感が薄くさらりと仕上がっています。
でも、それでも苦悩感が残っているんです。
そんなバランスがとても心地よかったです。
Posted by ブクログ
■ガラスの靴
バイトをさぼって配達先のメイドとよろしくやっちゃう話。「魅力のとぼしい」女に惹かれるっていうのがこの作品に共通して不思議なところ。
■陰気な愉しみ
戦争で働けない身体になってしまい、現代で言うナマポ的なものを受け取ることで劣等感を感じる(と、同時にそれを愉しみにもしている)主人公のお話。自分と境遇は違うが、その気持ちは不思議と分かる気がする。
■悪い仲間
伊坂幸太郎が書く型破りな友人キャラに近いものを感じるけど、みんなそれぞれに背伸びしてるところが面白い。
■夢みる女
この本の中で異彩を放つ童話的な話。なんか怖い。
■肥った女
やっぱりここでも外見的には醜い感じの女性に引かれる主人公。お母さんもぼっちゃり系女子(笑)だったようだし、何か母性でも感じちゃうのかしら。このあたりからグダグダ浪人生の話が続く。
■青葉しげれる
落第してもあっけらかんとしてる。どことなく憎めないやつら。
■相も変らず
ほんと相も変らずグダグダしてんなー(笑)
医学部に入ったのに文学部に通うなんてもったいねえよ!! と思ってしまうのだった。
■質屋の女房
おっ……おセンベツ!! 質屋の女房の色気がすごい。
女房もちょっと恋心抱いてたんじゃないかしらなんて思う。
■家族団欒図
ここから2作は戦争が終わって、高知県(K県となっている)のオヤジ登場。ちっとも枯れ切ってない(笑)オヤジもなかなかダメなやつだった。
結末はなかなかハッピーな感じ……かと思いきや。
■軍歌
ついに主人公が大爆発する(いや、短編なので別に同じ主人公とは一言も書かれていないのだけど、作者の私小説風の作品なので)。この大爆発を、学生のころの作者はずっと避けていたような感じがする。そのくせ、親に黙って遊び歩いたり、遊郭に行ってみたり、文科に行ってみたりするんだな。
比喩表現のセンスに脱帽。たとえツッコミ芸人もびっくりだぜ。
Posted by ブクログ
10の短編集。しっかりとした文章が印象的。「陰気な愉しみ」は「檸檬」を彷彿とさせる。他の作品では総じて、母、父との関係、家族であるがゆえの空虚感や重圧感が、苛々と覆ってくる。12.6.20
Posted by ブクログ
母親への義務感と自己嫌悪に苛まれる、童貞の苦悩の結晶みたいな短編集。陰気さと笑いと愛憎のどっちつかずなバランスがおもしろい。処女作「ガラスの靴」の別次元の世界観は、いまなお新鮮で抜群にクール。
Posted by ブクログ
男になるための通過儀礼には二種類あって
ひとつは女、もうひとつは戦争なんだけど
結局、敗戦でなにもかもご破算になってしまったわけで
結局、最後に残された、ギリギリ人間であるための手段は
「裏切り」にあったように思う
母を裏切り、友を裏切り、自分を裏切ることで
かれはこのどうしようもない戦後日本と自分を
やっと相対化することができるんだ
でもそれはやっぱり倒錯でしかないよなあ、とも思った
Posted by ブクログ
初めての安岡章太郎
短編集
「悪い仲間」などの青年ものより、際立つのは「陰気な愉しみ」だ。
傷痍軍人の悲しい愉しみ。
楽しみではなく、愉しみ。
人の目を憚りながら、生きながらえる中に愉しみをも見出せない儚さ。
心の凹凸を顕微鏡で覗くかのように隆々たる山並に変えてみせる、良い作品。
Posted by ブクログ
慶応大学在学中に結核を患い、戦後、脊椎カリエスを病みながら小説を書き始めた著者が、世間に対する劣弱意識に悩まされた経験をベースに綴った10編から成る短編集。
戦中、戦後を哀しく、無器用に生きた学生の自堕落で屈折した日常をユーモアも盛り込んで描く。
標題作「質屋の女房」は、戦時中、外套を質屋に持って行った学生と質屋の女房との関係を甘酸っぱく余韻を含ませて描いたもので印象に残った。学徒出陣で召集令状が来たその学生にとって一度きりの秘め事が結果的にはなむけとなったのだった。
「ガラスの靴」は猟銃店で夜番をしている「僕」が散弾を届けに行った米軍軍医の屋敷で出会った風変わりなメイド・悦子との間に生じた特別な時間が生々しく描かれている。
この他、兵役で病気になり、月に一度生活費をもらいにいく男の屈折した感情、厳格な母親を怖れ、呪縛を感じながらも反発する男子学生や悪徳仲間と現実逃避に終始する学生たちの姿を描く作品が盛り込まれている。
Posted by ブクログ
目次を見て、また読んで、魅力のあるものがほとんどなかった。本作の読書は淡々と作業をする感じであった。特に気に入った作品がなかった。文体は静謐かつ読みやすい。期待したほど、楽しめなかったのが残念だ。
Posted by ブクログ
哀しい、無器用な劣等生は、社会にうまく適応してゆく人々の虚偽を見抜く力をもつ…。先天的に世間に対する劣弱意識に悩まされた著者は、いたずらに自負もせず卑下もしない明晰な自己限定力をもって、巧まざるユーモアのにじむ新鮮な文章で独自の世界をひらいた。表題作ほか、処女作『ガラスの靴』、芥川賞受賞作『陰気な愉しみ』『悪い仲間』など全10編を収録する。
Posted by ブクログ
まぁ上手いんでしょうけど、長旅の中で読むには当方のリズムと合わなかった。それでも後半に収められている表題作はぐっと引き寄せる力がありまする。
しかし吉行淳之介といい、このお方といい、今でいうところの風俗に題材を求めるところを見るに、昔も今も変わらんという陳腐な結論に辿り着いて良いものやら。
Posted by ブクログ
初挑戦の純文学物でした。
読み易く、理解もできました。
短編集なので、主人公は異なり、1編1編は面白いのですが、似たような心情が繰り返されていたので、1冊読み終わる頃には、ちょっと食傷気味な感じになりました。
Posted by ブクログ
悪い奴じゃない、でも、良い人にもなれなかった…。安岡章太郎の小説っていうのは、そういうどっちつかずの人間の悩みが描かれている。さて、そういう半端な人間の王様といえば、やっぱり童貞だ。ここに収録された主人公達も実は皆童貞だ。ものすごく童貞について悩んでる。この本は「童貞傑作選」と呼んでも過言ではない。
それはさておき、中でも安岡は「家族」のうまくいかない感じにわりとこだわっている。この問題、古く見えるかもしれないけれど、全然古くないと思う。と言うのは、確かに父権性とか家族主義っていうのは、昔に較べたらゆるくなってきた。だけど心のどこかで「でもやっぱりおれ家族の中で育ったんだよ」っていう気持ちが、まだどこかに残っている。安岡はそれから逃げれなかった。古くさい家族主義から逃れられずにいる苦しみ。たとえば母親を嫌いつつも、母から離れられない。二人は父を共に嫌うことで、蔭で手を組んでいる…。安岡はやっぱり、微妙な関係を描くのがうまいのだ。
(ただし私小説作家共通の欠点か、たいしたことないのをウジウジ悩みすぎる、という傾向はやはりあるかもしれない。そういうのが苦手な人は、読むのが辛いか)(けー)