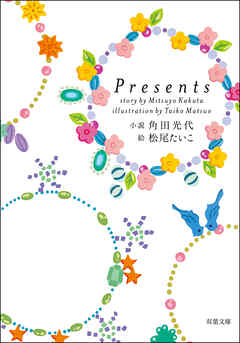感情タグBEST3
Posted by ブクログ
40周年限定カバーになっていて目に留まり、購入しました。
1番好きだったのは『名前』。私も小学2.3年生の時に名前の由来を発表する授業があり、全く同じことを親に言われました。「春に生まれたから」と。弟2人の名前は少し珍しい漢字が使われていて、意味もしっかりあって…。羨ましさもあり、なかなか自分の名前を好きになれませんでした。
でもこの本と出会い、なんだか少し救われました。
出会えてよかった。
Posted by ブクログ
これまでにもらったプレゼントを振り返ってみた。小さい頃に親からもらったずっと欲しかったローラースケートや、オモチャの指輪、大人になってもらったマカロンや靴など色々思いつくけど、物そのものを通して、贈ってくれた人との思い出やその頃の気持ちが物とともに記憶として残っている。
大人になると、物そのもの以外にも、言葉や行動、存在自体が贈り物だなと感じる瞬間と出会うようになった。
プレゼントだと気づかないくらい些細なことから大きな存在まで、心にしみる大事なプレゼントに気づかせてくれる話が詰まった一冊。
Posted by ブクログ
プレゼントに関する短編集
人からもらうものって姿形のあるものだけじゃなく、姿形のあるプレゼントだったとしてもそれと一緒に愛情とか仲直りしようとする気持ちとかが含まれてるみたいな内容でなるほどねえってなった
女性が主人公で大体のストーリーが暗いというか現実的でキラキラしてない現状とかから始まるのも角田光代らしくて引き込まれた
その現実的な退屈とか不満とか色々ネガティブな感情とかがごちゃごちゃな生活の中で立ち止まって考えてみたら、ある物事とか今の状態とかが実はすごいありがたいってこととか、過去のキラキラの思い出が作り出したのが今だって気がつくみたいな現実離れしてないストーリーなのがすごいよかった
Posted by ブクログ
友人がプレゼントしてくれた一冊。本を読むのが苦手で、悩んでいた私のことを考えて選んでくれたのだと思う。タイトルとまさに同じ状況で、「私もこんな粋なことができる素敵な女性になりたい!」と思った。
私は、映画でも観ている途中で最初のほうの話を忘れてしまったりする。この短編小説は、短いからこそ何も忘れないうちに読み終えることができた。どの物語にも印象的なシーンがあり、比喩表現一つとっても洗練されていて、これから先、私が同じような場面に出会ったら、この小説に書いてあるように感じるのだろうと思った。真似したいフレーズもたくさんあったなあ!
物語の一つ一つに感動ポイントがあって、電車で読みながら、涙をこらえるのが必死でした。何年も前に書かれた本だけど、人が感動する場面は変わらないのだなあ。
Posted by ブクログ
私の大好きな大切な本。表紙が綺麗だからという理由で図書室で手に取りページを開いてとにかくのめり込んだ。文章の無駄のなさ、言葉選びの美しさ、本当に全てが完璧だと思った。何度読んでも美しい。6年たった今でも読み返す。どの話においてもその様子や人の顔、家の中や匂いまで全てが想像出来る。挿絵が抽象的で更に想像をかき立てられる。きっといくつになっても手放すことはないだろうと思う1冊。
匿名
贈り物とは何か。
贈り物にまつわる短篇集。次に出てくるのはどんな贈り物なのかとわくわくしながら読んだ。描かれているひとつひとつの贈り物はどれもささやかだけど、どれもかけがえがなくてあたたかい。
ここに出てくる贈り物は実際に手にとることのできる品物でもありながら、それだけじゃない。平凡だけどそれなりに苦しい人生に、それでも誠実に向き合おうと決めたとき、ささやかだった風景が輝き出すこと。それをこそ作者は贈り物と呼んでいる。
Posted by ブクログ
形の有無に関わらず、それによってもたらされた経験そのものがプレゼントの本質なのかもしれないと思った。そもそも人生そのものが両親からのプレゼント。
後書きの「人は贈るより、つねに贈られる方が多い」に、はっとさせられた。
Posted by ブクログ
家族をしていてやりきれない事やそんな中でも日々の幸せを感じられる時が描かれている。
まーいっかと曖昧に思うことや後少しだけやってみるかで、上手くいくかは分からないけれども人と暮らすってそういう事かなと思わせられる。
また、松尾たいこさんの絵がとても素敵な本。
Posted by ブクログ
小中学生の時に表紙と題名に惹かれて買った本。女性が一生のうちにもらうプレゼント(形あるものだけではない)に纏わる短編集。風景の表現が鮮やかかつ分かりやすい、夕焼けに照らされる木々を『金粉をふりかけられたように〜…』って表現したりしている。どの話も良いけどランドセルの話が一番好き。ランドセル貰った当時はなんでも入る!私の全財産(ぬいぐるみとか本とか)余裕で入る!何かあってもランドセルに大事な物詰めて逃げれば生きれる!って思ってたのに大人になってよく考えたらランドセルって一泊旅行の荷物すら入らないよね、当時の身軽さにビックリしちゃう。そんな「分かる〜」って懐かしい気持ちになったり「これから先こんなプレゼントが待ってるかも!」って思えるお気に入りの1冊。
Posted by ブクログ
いろいろな、ほんとうにいろいろなプレセントの形。
あとで考えてみると、自分にとってはとっても大事なプレゼントだったのだろうな、と思い返すような、そんなプレゼントの集まり。すばらしい。
挿絵もほんわかしていて、とてもいいですね。
最後のプレゼントは暖かくて、そして悲しい。
Posted by ブクログ
びっくりした。もはや思い出せるはずがないと思っていた感情が急によみがえってボロボロ泣いた。
もらったもの、してもらったことの短編集。時々、いい話だなーとは思うけどまぁそこまで心に残る感じではないかな、、と思いながら読み進めた。
だけど最後の話になった時、年老いた女性が、夫の昔の浮気相手を思い浮かべて、やっぱり話ぐらいしておけばよかったかな、と、もう恨むことも無くふと考え、夫にしてもらったことで一番うれしかったことは何だった?と会話を空想するシーン。何故かそこで私も、うーーーん、何だったかなーー・・、と自分の夫との昔から今までの様々な出来事を思い返してしまった。
そして思い当たって、そうだったそうだった、本当に好きだった、うわぁ懐かしいな、もう一生そんな気持ちに出会う事は無いだろうと思っていたけど、消し去ってなかったのかと驚いた。
短編集の2つ目あたりで、途中をとばして最後の話を読んだ時は何も思わなかったのに、全部読んだ後だったからか「もらったもの」の定義が一瞬広がっていたのかもしれない。
記憶の彼方にやってしまっていた、自分にとって大切なものを思い出すことができてよかった。
Posted by ブクログ
読みやすさ☆☆☆☆☆
ちょうどいい長さの短編。
読後感もいい。人生の中で出会う悲しみや辛さも、おくりものだと思える一冊。
おすすめ度☆☆☆☆
誰かに差し上げたくなるような、ほんのり温かい優しさを感じられる。
読書が苦手なひとでも読みやすい文章表現。
この本好き☆☆☆☆
今回は全編通して「貰う側」を主軸に置いていたけれど、「渡す側」に立った時の目線もぜひ描いて欲しかった。
きっと、貰う分だけ渡していると思うから。
Posted by ブクログ
女性が一生のうちにもらう贈りもの。それがこの本のテーマです。
表紙や挿絵を担当された、松尾たいこさんのあとがきを見てようやく気づいた。確かにそうだ。女性が産まれてから、亡くなるまでにもらうプレゼントの話なんだ。そんな短編が12話詰まった小説。角田光代さんの小説は比較的悲しく心が締め付けられるようなお話をよく読んできたが、この小説は少し悲しい部分も含みつつも心が暖かくなるお話たちだった。
Posted by ブクログ
贈り物がテーマの短編集
贈り物は物品だけでなく、名前、体験、経験、記憶などの場合も
両親がつけた自分の名前、ランドセルの象徴するもの、引っ越しのときに母親が買ってくれた鍋セット、友人たちの手作りヴェール、子供の書いた絵、家族の作ってくれた料理 等々
贈り物の他にも、親子や夫婦など家族も共通点なのか?と思ったけど、「女性が一生の中で贈られるもの」がテーマらしい
言われてみればさもありなん
短編の構成として、生まれてはじめての両親からのプレゼントとしての名前で始まり、人生の最後にも残るものとしての名前で終わる構成は好き
全体の大きな流れとして、人生のステージの順になっているようにも思える
個人的に共感したのは、鍋セットと娘の結婚を機に離婚を決意した夫婦かな
一人暮らしをし始めてからずっと使っているもの
僕の場合は鍋セットではなく包丁
他にずっと学生のときから同じものはないかな
ヘンケルスの普通の包丁なんだけど、20年以上使っているものなので、自分の手に馴染んでるんですよね
離婚を決めた夫婦に関しては、娘の言葉と母親の両方に思い当たる節がある
僕自身、結婚式で両親に育ててくれた感謝と自分もそんな家庭を作りたいという挨拶をしたので、娘の方の気持ちがよくわかる
それと同時に、僕は離婚してしまった方なので、自分の娘に対しての申し訳無さもあるんだよね
読者の経験によって、どの話に共感するかは結構違ってそうですねぇ
あと、ちょっとしたツッコミを入れるとするなら
小学校で、家族をテーマに靴の絵を描いたからって親を呼び出すか?という疑問がある
もしそんな事で毎回呼び出されるんだとしたら、僕の場合は担任に対して塩対応の親になってるな
Posted by ブクログ
人生にもらう贈りものにまつわる短編集。
贈りものとエピソードという形で
簡潔にまとめられているんだけど、
ほとんどの話で忘れられない景色が語られるのが
印象的だった。
満開の桜、商店街を歩く母のうしろ姿、
夕方の海、靴の並んだ玄関…。
贈りものって、品物そのものより、
それをくれた人、その人との関係を思い出すと
あとがきで角田光代さんが書いていらっしゃるけど
確かに、その品物はなくしてしまっても
心に残り続けるものがある。
強い感慨を持ったこと、
その時目で見たもの、肌で感じたこと、
そんな形のないものたちを象徴するのが
贈りものなのかもしれない。
贈りものをあげるのももらうのも、
自分は結構好きで、特にあげるのが好きで、
なぜかというと、
品物を選んでいる時相手はその場にいないわけで、
なのに贈る相手のことを思い出したり、
たくさん考えないと品物が選べないわけで、
物理的には共有されない、
精神的に強く結びついたその時間が
なんだかすごく尊いもののように感じて、
だから好きなのです。
この作品はもらう側の視点だから
贈りものを選ぶところは描かれないんだけど、
贈りもの以前の関係性が
強くクローズアップされてるのは一緒だなって、
やっぱり贈りものは、その人との時間など
形のないものの結晶だなと思うわけです。
各編の主人公の女性たちは
ままならないこともありながら
ひたむきに考えて、たくましく選んで、
贈りものをくれる人に支えられながら
強く生きていく。
僕ら孤独じゃない、人生捨てたもんじゃない、
この先茨の道でも、切り立った崖でも、
何とか歩き続けていけそうな気に
させてくれる作品でした。
Posted by ブクログ
角田光代の穏やかな文章に癒される一冊。
日常の中にある、プレゼント(贈り物と言った方がしっくりくる?)に焦点をあてているが、12個の短編がこの世に生を受けた時から、死ぬ時まで、一生を辿っているのが面白い。
自分自身が子育て中ということもあって、『絵』と『料理』が良かったかな。
Posted by ブクログ
角田さんの文章がすきだなと改めて実感した作品
’’足をルの字に折って座り’’という表現ってできそうでできないと思う。場面をすごく想像しやすい。
ぺたって座って、太ももにランドセルをおいて、のぞき込んでいる。そんな女の子をふわって想像できてしまう。
’’冷静に、理性的に対応するはずが、口を開いたとたん、よくふった炭酸水の栓を抜いたみたいに、言葉があふれ出した。’’
感情の表現もすごい。
すごいとしか言えない自分。小並感。
松尾さんのあとがきに、表紙は包装紙をイメージしましたとあった。
角田さん、松尾さん、こんなに素敵なプレゼントをありがとうございます。
Posted by ブクログ
プレゼントを題材にした作品。
それは形あるものだったり目には見えないものだったり。
けれどその中には贈った側の色んな想いが詰まっているのがわかる。
読後に色んなものを大事にしたくなる。
Posted by ブクログ
あなたは生まれて初めてもらったプレゼントが何だったかを覚えていますか?
それは、あなたのご両親が『ああでもない、こうでもない』と散々に思い悩み、あなたにいちばんふさわしいと思って与えてくれたものです。それは、あなたがあなたであることの証です。それは、あなたが一生を共にするものです。そう、それはあなたの『名前』です。そんな『名前』をあなたが気に入っているかどうかはわかりません。『もし私が春海という名前だったら、何かもっと違う日々を送っていたような気がする』、というように、一生を共にする『名前』だからこそ、もしそれが違ったものだったとしたら、今までの人生には違う景色が見えていたかもしれません。些細な歯車の組み合わせが変わってしまって、今のあなたの人生は存在しなかったかもしれません。でも、それでもあなたにいちばんふさわしいのは、やはり今のあなたの『名前』なんだと思います。そう、この作品は、〈名前〉から始まって、最後の〈涙〉まで、一生のうちに誰かからプレゼントしてもらうたくさんの贈りものの中から12の贈りものに焦点を当て、その贈りものを感じてゆく角田光代さんの短編集です。
『いちばん心に残っている贈りものはなんですか?』と聞かれて、とっさに答えられなかったという角田さん。『贈りものってなんだろう。私が覚えているのは、品物であり、同時に品物ではない』と思い至ります。『それをくれた人、くれた人との関係。どちらかといえば、そちらをより濃く覚えています』というように、『贈りもの』というのは必ずしもその対象物そのものを指すとは言い切れません。この短編集には、そのことをより強く考えてしまう物語が詰まっています。ここでは、その中から二つ取り上げたいと思います。
まず、一つ目、〈名前〉。『なまえのゆらい、というタイトルで作文を書く宿題があった』という冒頭。『家に帰って、私は母に自分の名前の由来を訊いた』、それに対して『あなたがうまれたのは春だったから、春子なのだと、じつにそっけなく母は答え』ます。『それまであんまり好きじゃなかった自分の名前が、ますますきらいになった』という春子。『春だから春子。なんにも考えていないことがばればれの、頭の悪そうな名前』と自分の名前が余計に嫌いになります。そして『春子という名前は捨ててしまおうと、そのとき決心した』春子。『こっそり、ノートの裏に新しい名前を書いてみた。春菜。春海。春香。春枝。うっとりした』という春子。『今日から私は春海になります』と友達に宣言する春子。『しかし私は春子だった。春子のまま大人になった。地味で、シンプルで、退屈な大人になった』と成人します。そして『結婚したのは三十一歳のときだ』という春子は、『私に負けず劣らず平凡な名前で、ノリオという』夫と結婚し『釣り合いがとれているような気がした』という春子は、『まったく私たちの暮らしは、大いなる平凡、大いなる退屈で成り立っている』という生活を送ります。そんな夫婦に『結婚して一年目に赤ん坊ができた』と生活が大きく変化する機会が到来。そして『私と夫は子どもの名前についてあれこれ考えをめぐらせる』という春子。自分の名前が嫌いだった春子は自らの子どもの名前にどういう結論を出すのでしょうか…。人が生まれて初めてもらう贈りものが『名前』だという考え方。思わず自分の名前の由来を思い浮かべ、親に不満を言ったことを思い出しました。自分の肉体以外で唯一一生を共にすることになるもの、それが『名前』。生まれて初めて受け取ったその大切な贈りものについて、とても味のある納得のいく結末の描かれ方に冒頭からすっかりこの短編集の世界の虜になってしまいました。
二つ目。〈鍋セット〉。『第一志望だった大学に合格した』という主人公は、母親と東京に新居を探しにやってきます。想定した予算では驚くほど狭く、しょぼくれた部屋しかないことに二人は驚きますが、『私鉄沿線の駅から徒歩八分』のアパートに住むことを決めます。引っ越し蕎麦を食べに行こうと出かけた二人。その帰りに『あっ、いやだ、おかあさん、忘れてた』と言う母親は『鍋』を買わないと、と雑貨屋に入り『鍋は大、中、小と三つ』を買い、『私』に持たせます。『鍋なんかいいよ』と言う『私』に『よくないわよ、鍋がなきゃなんにもできないじゃないの』、という母親。そんな『私』でしたが、やがて『この鍋で私は料理を覚えた』、とこの鍋を母親から贈ってもらったことがきっかけで、その先の人生がどんどん開けていきます。『だいじょうぶ、なんてことない、明日にはどんなことも今日よりよくなっているはずだ』という前向きな考え方。そういった気持ちになるには何らかのきっかけを求めたくなるものです。そのきっかけを『鍋から上がる湯気は、くつくつというちいさな音は、そんなふうに言っているように、私には思えた』と
鍋から上がる湯気が背中を押してくれる日々を送る『私』。そんな私は『あのとき、母にいったい何をもらったんだろう?』と、かつて鍋を贈ってもらったあの時のことを振り返ります。使いすぎてボロボロになった鍋を今も大切に使い続ける『私』があの日、あの時、母親からもらったもの。それは単にそのものだけではなく、そのものを贈ることにした母親の深い思いも含めた贈りものだったことに気づく『私』。人生の長い時間を経て、とても奥行きを感じさせるあたたかい短編でした。
『生まれてから死ぬまでに、私たちは、いったいどのくらいのものを人からもらうんだろう』と語る角田さん。この作品では〈名前〉からはじまり、最後の〈涙〉まで色々な贈りものを受け取りながら人は人生を歩んでいく、まさにその姿が描かれていました。そんな贈りものには、単なる品物だけでなく〈名前〉、〈涙〉のように、この作品を読んで初めて意識することになった贈りものもありました。『品物は、いつかなくしてしまっても、贈られた記憶、その人と持った関係性は、けっして失うことがない』と角田さんがおっしゃるとおり、品物は年月が経てば壊れたり、失くしたりと目の前から失われてしまうこともあります。でも、その贈りものにより繋がった何かは、決して失われることなく、その人が生きていく上で一生の宝物にもなりえます。
『私たちは膨大なプレゼントを受け取りながら成長し、老いていく』という私たちの人生。一見全く繋がりのない12の短編がまるで人が生まれてから亡くなるまでを描いた一編の大河小説を読んだかのような読後感に包まれるこの作品。各短編に絶妙なタイミングでアクセントをつける松尾たいこさんのイラストが登場するこの作品。角田さんと松尾さんから文字と絵のとても素晴らしい贈りものをいただいたこの作品。自分自身が受け取ってきたものを思い起こすと同時に、自身も素敵な贈りものを送ってあげられる人でありたい、そんなことも考えさせてくれた作品でした。
Posted by ブクログ
初めて読むのにピッタリだから、と友人に勧められて読んだ最初の角田光代さん作品。
12のお話が入った短編集。そもそも短編集はあまり読まないのだけど、この本はとても良かったです。一つ一つのストーリーが様々な感情を呼び起こす素敵な作品で、それらがプレゼントという一つのテーマで結びついている面白さもあります。
中でも、特に"寂しさ"の感情を描いているように感じた作品「鍋セット」と「うに煎餅」の2作品はすごく心が動かされました。
人間が成長して、大きく変わっていくことは嬉しいと共に、ふと振り返ると寂しさもある。その寂しさは、その時の自分をかけがえなく思えている証でもある…人は、"その時"にしか出せない輝きがあるんだなあと思いました。自分の様々な思い出とも重なり涙が出てしいました。
人は生きて成長していく上で、様々なプレゼントを貰って生きているのだな、と気付かせてくれる素敵な作品でした。
Posted by ブクログ
女性が一生の中でもらう贈り物の短編集。
「名前」「鍋セット」「涙」が特に心に響いた。
プレゼントの話だからといって幸せな話ばかりではなくて苦々しい思い出もあったり。人生って良いことばかりじゃないしそこがリアルだった。
人生の節目に改めて読むと共感できる短編が変わっていそうなのでまた読みたい。
Posted by ブクログ
小説に絵がついているのが可愛い。
形あるものがプレゼントじゃない。ときには形のないプレゼントが、ずっと心に残っていたりするものであったりする。
振り返ったとき、いっぱい人にプレゼントをあげられたと思える人生でありたいな。
Posted by ブクログ
「プレゼント」を題材にした12遍の短編小説。
どの物語も何となく身に覚えのあるような、どこかで聞いたことのあるような、そんな物語。
だからこそ、自分にもあんなことあったなぁーと、共感出来る部分もあった。
特別珍しいストーリーでは無いものの、軽く読めるので暇つぶしにピッタリな一冊。