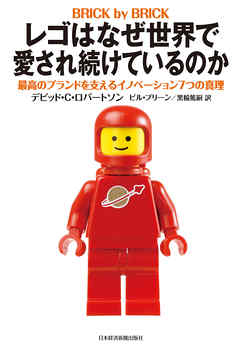感情タグBEST3
Posted by ブクログ
世界的に有名なブロックメーカーであるレゴが、2000年代初頭に低迷期を迎え、それをいかにして乗り越えたかの企業の経営史書的なもの。
内容としては1章から4章で、レゴには6つの基本理念があることの紹介から始まる。
①価値観が肝心
②果てしない試行錯誤が画期的なイノベーションを生む。
③製品ではなくてシステムを作る。
④的を絞ることで、利益の出るイノベーションが生まれる。
⑤本物だけをめざす。
⑥小売店が第一、その次に子ども
その後スターウォーズを受け入れて、様々な改革に取り組んだブローメン氏だったがほぼ失敗に終わり、後ろ盾に創業者一族のケル・キアク、財務のオヴェーセン、クヌッド・ストープという三頭体制で乗り切ることになった。
その中で改革に失敗した7つの方向性をレゴに合う形で行った。
①レゴらしさを取り戻す(イノベーション文化の構築)
②レゴシティーの復活(顧客主導型)
③バイオニクル(全方位イノベーションを探る)
④マインドストームなど(オープンイノベーション)
⑤レゴ・ユニバース(建築などの破壊的イノベーション)
⑥レゴゲームの誕生(ブルーオーシャンに漕ぎ出す)
⑦ニンジャーゴー(創造性と多様性の人材活用)
それらによってレゴが段階的にブランドを復権することができたとしている。改革の失敗の上に成功への導く過程が面白かった。
Posted by ブクログ
40年にわたり遊び続けている、このおもちゃについての成書を初めてしり、読んでみた。歴史から、近年の迷走、そして復帰への道を詳細にルポ。大体の流れは把握しているつもりだったが、多くの事実を新たにしり感動。
アイデアブックや、30年くらい前にあったレゴ新聞なんかが取説以外の唯一の情報だった頃から比べ、今はすごい。改めてネット化後の世界で、これほど多くのファンがいるのを感じ取った。子供がもう少し大きくなったら一緒に遊べるようになるだろうからそれを今から楽しみにしている。5~9歳がメインの製品だったとは知らなかった(他にもシリーズもので15、6歳というのもあるが)。
一方、レゴ社のビジネス的動きを、イノベーションというキーワードで俯瞰するところは、一理あるのだろうが、もう少し詰めた議論、話題があってもよい。組み立てるのは自分自身ではあるものの、ヒントとなるネタはもっともっと同社にあるはず。それをもっと拾ってほしかった(もっと分厚い書籍にしてほしい)。と思いつつも結構触発されているところ・・・。
Posted by ブクログ
レゴのイノベーションについて学んだ。既存の成功体験にしがみつき、何もしないでいるとやがて凋落してしまう。そこから這い上がろう、陥らないようにしようと闇雲にイノベーションを推進し多角的に手を広げても効果は望めない。自分たちの強みとビジョンを明確にし大切なものは大切にし、そこから今までにない価値を見出していくこと、多様性に富んだチームを築いて挑戦すること、自分たちだけでなく外の世界や顧客との関係性から新たな価値を創造していくことが大切だとわかった。うちの会社にも本当に参考になることが多いと思う。
Posted by ブクログ
・一定の枠の中で新しいものを生み出す。制約がはっきりしているため、肝心なことに意識を向けやすく、いいイノベーションが生まれやすくなる
・売上高の10%を占めるまでに成長の見込める新しいチャンスを、一年以内に二つ見つけること
・製品を完成前に販売し、ユーザーの声を聞きながら、販売と並行して製品の改良を続ける
・「まちがいなくレゴだが、今までに見たことがない」製品を開発する
・ブランドの発展のためには、その前に自律的な成長の土台を築くことが欠かせない。健全なバランスシート、持続可能な債務水準、安定した中核事業、利益の出る製品
Posted by ブクログ
複数のイノベーションを同時に実行しようとして2000年前後レゴが低迷していた。そこを救ったのがマッキンゼー出身の30代社長ってのがロマンあるなあ。
Posted by ブクログ
良書。
レゴ、イノベーションの7つの真理
・創造性と多様性に富んだ人材を揃える
・ブルーオーシャン市場に進出する
・顧客主導型になる
・破壊的イノベーションを試みる
・オープンイノベーションを推し進めるー群衆の知恵に耳を傾ける
・全方位のイノベーションを探る
・イノベーション文化を築く
Posted by ブクログ
ブルーオーシャン戦略、オープンイノベーション、破壊的イノベーションの失敗例、成功例をレゴの製品を例にとりながら説明しているので、レゴに親しみのある人にとっては戦略の入門書として非常に分かり易い。
また、レゴは「子どもには最高のものを」という基本理念を大切にするビジョナリーカンパニーであることも本書を読むと良く分かる。
企業研究の書であるとともに、戦略の入門書として良い教科書になると思う。
Posted by ブクログ
多くの人がかつては遊んだであろうレゴ社がいかにして危機を乗り越えて継続的な成長を維持できているかの物語。
お題はイノベーションマネジメント。
時代の流れに乗り遅れないために、かつてはイノベーションをただ目的化することで会社の存続危機に陥るも、新たなリーダーシップの基でイノベーションの管理手法を導入することで再び成長軌道にのったレゴ。
筆者も書いているけど、あくまでもレゴの成功はいわゆる「ストーリー」のなかで成立したものであり、ベストプラクティスとして学べるわけではない。
それでも事実に基づいた成功事例として学ぶところも多く、内容も分かりやすいので、「イノベーションのジレンマ」等の基本書を読んだ上で、この本もお勧めしたい。
Posted by ブクログ
珍しくビジネス書。やはり肌に合わない。しかし、単なる開発物語ではなく、1ページに10回以上「利益」という単語が出てくるところが本書の姿勢をよく表している。レゴって何十年も前からある基本ブロックを作ってデザイナーが適当に組み合わせて売っていると思ったけど、その組み合わせのパターンとブロックのセットを作るのが「開発」でそれに何年もかけているとは意外だった。
Posted by ブクログ
No.666
「ブロックはレゴから。アイデアはきみから」1992年のカタログのコピーが秀逸。
レゴの改革とブランド復権までの道のりが詳しく紹介されています。
レゴ1.0 コストダウン、ビジネスをシンプルに。小売店の利益を増やす。レゴランド売却、キャッシュの獲得を重視。2004年
レゴ2.0 ブロックへの回帰。共通の目標を設定。赤字製品の廃止。2005年末
レゴ3.0 イノベーションマトリックス。レゴ開発手順の見直し。マインドストームに大人のファンを参加。2008年
レゴ4.0 二重焦点の取り組み、今までに見たことがない製品、スターウォーズシリーズ。2012年。アップル、ナイキと比較されるようになる。
レゴ5.0 ビッグバンを得る。レゴフレンズ、女の子向け。ユーザーのオリジナル作品、一万票を獲得すると製品化。
レゴマインクラフトマイクロワールド。
2017.04.09 再読、以下追記
さて、2017年に日本でレゴランドがオープン。巨額の投資と狭いターゲット層のテーマパークはレゴ5.0の先に存在するのか?
Posted by ブクログ
「イノベーション7つの真理」というサブタイトルにあるように、およそイノベーションという言葉がこれでもかと登場する。そして、その7つの真理の実行の仕方で失敗してどん底におち、同じくうまくやって復活したレゴの話。
レゴは、あるときまでうまくいっていたので、経営はけっこう適当だったらしい。置かれている状況に気づかずに自己満足をしていたら、いつのまにやら闇の中。
当初レゴが伸びたのは、小売店を大事にしたこと、そして単なる玩具ではなく、システムをつくったこと。僕もこれで満足すると思う。スターウォーズとレゴは、いまでは当たり前の組み合わせだが、導入には相当な(内部の)障壁があったのだそうだ。
いろんな新しい、レゴではないものに手を出してさらに悪化する始末。成功の参考よりも、典型的な失敗例としても楽しんでしまおう。
イノベーションという言葉がちょっとアレルゲンになりつつあるので、言葉の連発に少し辟易とはするけれど、レゴという玩具のエコシステムに触れられて、ちょっと嬉しかった。
Posted by ブクログ
レゴはどのように失敗し、その失敗をどのように次の成功に役立ててきたのか、その経緯を経営理論に基づいて、というよりもどの流行の経営理論にぶら下がったために失敗したのか、分かりやすく説明。
ただ、残念ながら?(ビジネス書に求めるのは無理かもしれないが)登場人物に感情移入するような書かれ方ではない。
Posted by ブクログ
この本は、経営すらもオープンソースのごとくケーススタディされると言う驚きと、大企業病への処方箋である。
経営は古くは世襲制であり、ごく一部の人がノウハウを独占している秘術のようなものだったと考える。一方現代では、能力があるものが登用され腕をふるえる一方、その秘術を知らないが故に失敗することが多いのではないだろうか。
秘術と言ったが、そのほとんどは失敗の歴史に学んだ教訓だろう。一代ではなかなか失敗•リカバリ•ノウハウ化までは難しい。ケーススタディを読むとだいたいの失敗は先人の経験、教訓を、活かしていないこと。時に非情な教訓にも何らかのキッカケがある。
大企業では、持続的な成長と破壊的なイノベーションのふたつをうまく組み話せていく以外の生き方はない。これら二つは思いの外対処が異なる。故に自分がどちらの問題を解いているのかを理解していない決定は破局を意味する。
これだけの歴史と失敗と教訓を得られる本は貴重た。