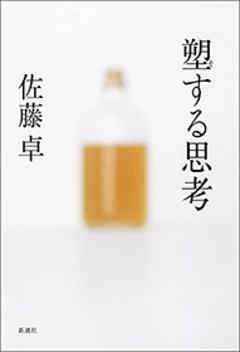感情タグBEST3
Posted by ブクログ
すっごい面白かった。というより、とても重要な視座と言葉をいただいた、という感覚が強いかも。
まさに実用的な視座「構造」と、染み込む言葉の綺麗さ「意匠」を兼ね揃えた本。
物事の本質を「問い」から見出すこと。おそらくそれが、良い意味で自我と戦う一番の術なのかも。
Posted by ブクログ
・元電通のアートディレクター佐藤卓の著書
・「分からない」から全てがはじまる。ニッカウィスキーの自主プレゼン
・柔らかさには2通りあり、弾力性と塑性。外部から力が加わった後のあり方が違う。塑性は粘土のように、力を加えたら戻らない。
・自分の意識がどこから来るのか、その基礎となる自分すら分かっていない中で、自我や自己を固めるよりも、その場に応じて柔軟に変えていく方がよい。
・発想とは、ある目的のために今まで繋がっていなかった事物同士を繋げる試みである。
すでにあるのに気づかずにいた関係を発見して繋ぐ営為とも言える。
・あらゆる仕事の基本は「間に入って繋ぐこと」
・明治牛乳のパッケージ。技術者の牛乳「そのまま」を味わって欲しい想いから「デザインをできるだけしないデザイン」の方向性。
・サーフィン。どれだけ海に通っても、なかなか上達しないが、波に乗り自然と一体になる感覚を味わうだけで充分すぎる。
・サーフィンはあまりに多くのことを教えてくれる。自分の無力さをまざまざと見せつけられ、自分と環境との関係を把握する力も鍛えられる。大きな波が立っている時の海は河のように流れているので、どれだけ自分が知らぬ間に流されているのかを気づかずにいる場合がよくある。ところが岸の景色を冷静に見ていれば、すごいスピードで流されていると気づく。
常に冷静に、できるだけ客観的に自分の置かれている状態を把握していなければ、たちまち危険な状態に至る。
Posted by ブクログ
デザインという仕事から語られた言葉に、仕事への取り組みの本質が溢れていて、経理を仕事にしている私にも多くの気づきがあった。
佐藤卓さんと直接お話しできる機会があったとしてもきっとこんなに深くお話ししていただけることはないわけで…ホントに読書ってすごくオトクな得難いものだなあ…と思いました…
Posted by ブクログ
五輪周辺の不祥事の余波で、なぜかデザインあが放送休止の憂き目に。。追悼の意味で佐藤卓さんの本をよむ。これが素晴らしい出会いになった。
因果応報、人間万事塞翁が馬。
クールミントの2匹目のペンギンの種明かし、積年の謎が解けた。
Posted by ブクログ
自分の中の無責任な「デザインする」意識が変わりました。
私はデザイナーという肩書きで仕事をしているにも関わらず、世の中の著名なデザイナーの方々に関する知見が浅いです。仲間内で「尊敬するデザイナーは誰か」という質問があがると決まって黙り込んでいました。
本書では、世の中に蔓延る無責任で本質を捉え損ねた、一般大衆的な「デザイン」を否定し、デザインの本来あるべき姿を改めて示しています。
誰が何のために何を生み出すのか。
デザインには答えがないよ、正解がないよ、
という人はデザイナーにも沢山いると
思いますが、
定められたルートはないにしろ、必ず達成すべきゴールは決まっています。
こうあるべき、という信念を持ってデザインに向き合うことをエピソードを交えて、しかも読者と近い視点で書いており、
よくあるデザイン思考の指南書よりもずっと参考になると感じました。
私の尊敬するデザイナーは佐藤卓さんです。
Posted by ブクログ
21_21 DESIGN SIGHTのショップでたくさん並べてあったのと、この間までの「グラフィック展」で少し触れられていたので気になって読んでみました。
おいしい牛乳の人だとは知らず、読んで初めて知りました。
デザインを通して仕事、人生、生き方を視ていて気付かされることが多かったです
Posted by ブクログ
塑は「そ」と読む。力を加えても元に戻る「弾性」に対して、相手によって自在に形を変える「塑性」。著者はデザインというものを「塑」であるべきだと考える。
私もデザイナーの端くれなので、著者の言いたいことはよくわかる。著者が自分と同じような考えであることを知って、嬉しくなった。
デザインは自己表現の場ではない。たとえば、商品のデザインを考えてみる。消費者はお店に並んだ商品の中から気に入ったものを選んで買っていく。ならば、商品のデザインは「自分がどうしたいか」ではなく、「みんながどう思うか」が大事である。
この「塑である自我」という考え方が、養老孟司先生の個性に対する考え方とよく似ている。押さえつけていても出てきてしまうのが自我や個性で、そういうものはいい仕事の邪魔になる。なぜなら、仕事は世の中のニーズに合わせて存在するもので、あなたの欲求を満たすために存在しているのではないから。
この本はデザインの本ではなく、デザインそのものについて考えた本である。豆腐屋が「なぜ豆腐を作るのか」と考えるような本である。養老先生も解剖学者でありながら、「解剖とは何か」を考え続けた。そういう意味では、のちにお二人が「虫展」で一緒に仕事をされたのは、必然という気がする。
Posted by ブクログ
著者は、NHK「デザインあ」の総合指導をしている人。
世の中にアイデア出しの本は数あれど、ここまで頭の中の過程を丁寧に解説した本は、珍しいのではないでしょうか。「塑する」とは「柔」につながる意味だそうです。パッケージデザインから、世に言うデザインそのものの謎にも迫っていきます。読めば「デザインあ」が10倍楽しめる。どうしてああいう番組なのかも納得。人生にも確実に効く、考え方の本です。
Posted by ブクログ
デザインとは
きれいなグラフィックや何か施されているものをデザインされていると捉えがちだったが、すべてのものはデザインされているとということが言われてみて初めて気づいた
お箸はナイフやフォークに比べると、チープな印象を抱くかもしれないが、そのシンプルさ故に様々な使い方ができる
自分が普段生活する中でいかに無意識に行動しているかを痛感した
ものを買うときになぜそれを選んだのか、逆になぜ選ばなかったのかなどを意識するようにしたい
Posted by ブクログ
『「付加価値」撲滅運動』とか『「便利」というウィルス』などの章が特におもしろかった。デザインとはそもそも何か、というところから始まり、グラフィックデザイナーの視点から見た現代の様々な側面を、わかりやすい文章で伝えてくれる。
Posted by ブクログ
人間は猿人からの進化で体毛がなくなった。もじゃもじゃの方が怪我もしにくいし暖かいのに。
身体が弱くなった、不便になった。ちょっと転んだだけで擦りむくし痛い。でもその代わりに、全身の末端までに行き届いた神経のお陰か、体の外のことが感じやすくなった。感受性が豊かになったらしい。
不便と口にするが実はそうではないことがありそうだ。
便利だと口にするが実はそうではないことがありそうだ。
何が自分達にとって良いことなのか?
著者は考える。感じている。
最近、これだけ豊かな身体を持ちながら、この身体を使わないことが多くなった。1階から2階に行くにもエレベーターを使ったりする。でも一方では健康に気を使い、大金を払ってスポーツジムに通う。
もしかして我々にとって丁度良い生活とは、身の回りにあることを今一度考え直すことかもしれない。
そして、デザインとは、格好良い形を作るのがデザインではなく、
実は、こんな世の中の問題と思えることを解決することがデザインすることみたいだ。
佐藤卓さんのデザイン道。
「塑」は素直に受け入れること、外部を感じることと解釈。
金属は塑性変形と呼ばれる特徴がある事で様々な形になれます。土はこねることで如何様な形にも。
Posted by ブクログ
養老孟司先生が新聞の書評で「この本を読んで、自分もデザイナーになってみたくなった」と書かれていたのを読み、自分もこの本を読んでみたくなった。
これは、ニッカウィスキーの「ピュアモルト」明治の「明治おいしい牛乳」ロッテの「クールミントガム」などのデザインを手がけ、日本を代表するグラフィックデザイナーの一人である著者が(私は門外漢でお名前を存じませんでしたが)、それらの仕事を通じて思考し、たどり着いたデザイン論である。そのポイントを一言で表すとすれば題名にあるとおり「塑する思考」という著作オリジナルの言葉になるのだろう。「塑」とは、外部からの力に従ってどのような型にもなるが、決して元の型に戻ろうとしない、そもそも元の型というものがないという意味で、同じ「柔軟」ではあっても絶えず元の型に戻ろうとする「弾力」とは分けて考えるべきだという。柔軟に思考することは大切だが、デザインにおいては「塑する思考」すなわち、自分とか個性を表現しようとするのではなく、そのものに内在する価値を引き出すこと、いわゆる付加価値とは逆の発想こそが大切だというのである。和食の職人が素材の味を引き出すとか、仏師が仏様を彫るのではなく、木の中から仏様が現れる、などと語られることがあるように、いわゆる達人が語る言葉には分野を超えて通じるものがあるようだ。そもそもデザインとは絵画とか工芸とかいわゆる芸術の一分野に分類されるものではなく、人が生み出すあらゆるものに関わっており、その意味で人と物を仲介する「水」みたいなものだという。水は方形の器に隨う、たしかに「塑」だし、この惑星では普遍的に存在する生命の源でもあるから、デザインを論じるととても深い世界のことまで想像力が働いてしまう。養老先生がデザイナーになってみたくなったというのも、あながちお世辞ではないと思える。
この本にはグラフィックスという2次元の世界を超えて、奥行きと含蓄に満ちた言葉が溢れている。
Posted by ブクログ
物をつくるなかでデザインが大きく誤解されている。カッコよくすることではない。既存のものとものをつなぐ、物の本質を知る。著者が伝えたいデザインと世間一般で思われているデザインは大きく違う。
物を深く掘り下げてその背景に思いをはせることで、もっと気づかいの出来る世界になるのでは。
塑する思考とはそんな考え方だと思った。
Posted by ブクログ
中盤にあるような、クールミントガムや明治おいしい牛乳、ニッカウヰスキーのデザインを思考プロセスと併せてひも解く部分は読みごたえがあり面白い。佐藤さんのデザインは、一言で言うならオリジナリティの探究だと私は理解した。どうオリジナリティを出すかの研究ではなく、あるものだとして対象を多くの視点から観察することで隠れたオリジナリティを見つけだす探究から、フォルムや表面のアウトプットに繋げていく。今の時代だと良くも悪くも表面的なものに成り下がった引き算のデザインが多いが、真の引き算のデザインはおそらく著者のような思想を持って取り組まれているモノを指すべきだと思う。
反面残念なのは、全編通し細かい部分で思い込みや極度に単純化された知識を元に論理を展開している点が多かったことだ。出典の記載もなく、信頼して読めない印象を持つにいたる。具体的には、進化論の誤用やカロリーベースの自給率で日本はもっと貯水機能を持つべきだ等と批判につなげているところ等で、後者に関してはチェリーピッキングの代表事例のような展開だ。比較対象国との年間降水量の差や、小麦など日本の土壌に適していない穀類がカウントされやすいカロリーベースで自国を批判しつつ重量/金額ベース自給率といった指標には一切触れないのは主観的と言わざるを得ない。また自国の自給率が40%だから単純計算60%他国の貯水機能に頼ってしまっているとし、だから自国でもっと貯水機能を持つべきなのだと言うが、これに関してはもはや何から突っ込んでいいのか、話にならないレベルで論理破綻している。
私は何も偏った言動を慎んでほしいとは言うつもりはない。しかし情報の精度に注意を傾けられないのであれば教育に関わらないでいただきたい、と思う。著者の言う未来を考える場を持つためにはまずフラットな視点で一次情報にあたり適切な発信を努めることからすべきではないだろうか。
Posted by ブクログ
養老ブックガイドから。簡単に使うとたしなめられそうだけど、デザイン職者の手になる読みものを味わう機会はこれまで殆どなかったから、だいぶ新鮮な読書体験となった。
Posted by ブクログ
「明治おいしい牛乳」や「ロッテクールミント」などのパッケージデザインを手がけた、グラフィックデザイナー佐藤卓さん。
「デザインを通して人の営みを考える」ことの面白さ。「日常生活、無意識に触れている事物の中に潜む数多くのデザイン」を紐解いた一冊。
何だか難しそうなタイトルたけど、内容はとても分かりやすく読みやすい。
数々のプロダクトの写真も白黒だけどしっかり掲載されているところもポイント。
・卓さんは、藝大デザイン科に一浪して入学。その後、電通に入社する。面接のときは、幾何学模様のプレゼンをしたという。
(どんなポートフォリオだったんだろう。見てみたいな)
・電通入社後、自身の転機となったのは、ニッカウィスキーの商品開発の自主プレ案件。
依頼ではなく、自主プレのため、商品の容量や値段、パッケージ、ネーミングも全て卓さんが検討したという。
空き瓶を二次利用してもらうことも考え、シールを剥がしやすくした、というアイデアも良いなと思った。(意図的にぼかされているけど、表紙で使われている商品です)
無事展開され、ウイスキーの瓶が青山のブティックのウインドーでディスプレイとして二次利用されているところを見たときはとても嬉しかったという。
・デザインの起源を遡る記述も興味深かった。
印象派の時代に印刷物としてのポスター制作を行なっていたロートレックの存在がデザインの歴史を辿る上では大きいという。
そして、ロートレックと同じ時代に活躍した印象派画家達に影響を与えたのは江戸時代の浮世絵だという。
・「クールミントガム」
これは卓さんを語る上で外せない。卓さんのデザインした商品の中で、個人的には一番好きだ。(2枚目)
電通を通じてガム全体のリデザインの依頼があり、7社ほどの競合コンペで勝ち取った案件とのこと。
店頭でガムがどのように見えるかを考えたとき、正面だけでなく、天面も重要だと気づき、そこに、既存で入れていたペンギンくんを配置した。
そのペンギンくんの人間のような感じが良いんだよな−。
「デザインがあまり変わり過ぎて欲しい商品を見つけられなくなったら本末転倒。」という考えに納得。
リニューアルという考え方は、さじ加減が難しい。既存のペンギンくん(3枚目)を残してリニューアル感を出したところはさすがだと感じた。
(ただ、2014年再リニューアルで卓さんデザインのパッケージは姿を消したようです。残念。。)
・「明治おいしい牛乳」
明治から出てきた、絞られた3案のネーミング案は卓さんは最初、どれも気乗りしなかったという。
ただ、実際に手を動かしてデザインに当てはめたとき、その中の一案の、「明治おいしい牛乳」というネーミングをしていないような、演出を感じさせないネーミングが力を持ち始めたという。
必要以上に施していないデザイン。演出をできるだけ抑えること。
・「デザインの解剖」
この企画も、卓さんの代名詞の1つですね!
身近な物事をデザインの視点で解剖しようとした試み。
「多くの人が何気なく使っている大量生産品を介して、いわばデザインとは何であるかを考えるきっかけが作れないか。」
と考えたことから始まった。
自身がパッケージデザインを担当した「キシリトールガム」や「おいしい牛乳」(4枚目)。
「写ルンです」では、カメラの断面などを見せて構造を紐解き、
「リカちゃん人形」では、「眼」の変遷などを通して、時代の化粧を反映していることがわかることを解説。
・「21_21 DESIGN SIGHT」
東京ミッドタウンの一角にある展示場。
三宅一生氏が発起人で、卓さんと深澤直人氏が組んでそこで行う展示を計画。建物は安藤忠雄氏が設計。
久々に行ってみたくなった。
・「デザインあ」
デザイン教育に力を入れ始めた卓さんは、「にほんごであそぼ」のアートディレクションを経て、「デザインあ」の制作を進める。
身の回りに潜むデザインをどうすれば面白いと感じてもらえるか、その考えを膨らませて番組が出来上がったという。
デザインあ。
毎回録画するほど好きな番組だったので、今休止となってしまったのがとても残念です・・・。
早く再開してくれますように。