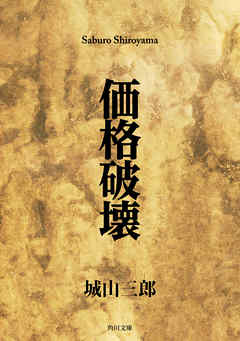感情タグBEST3
Posted by ブクログ
流通業界のカリスマ中内功さんをモデルにした小説です。メーカーとのし烈な闘いは読む人をは引き込みます。私も流通業界で働く事を夢みてダ⚪エーの入社試験を受けましたか見事にご縁がありませんでした(笑)
Posted by ブクログ
城山三郎は明言していないが、主人公のモデルはダイエーの創業者中内功であることが、本書から読み取れる。フィクションではあるが、スーパー「アロー」とメーカーとのせめぎ合いが妙に生々しい。できる限り商品を安く提供することで消費者からの支持を得、事業を大きくしたいスーパーと、取引のルールと価格を守り、ひいてはブランド・イメージを維持したいメーカー。双方の立場ともに理解できる。しかし、本書で描かれていることは、流通革命という、日本の流通史・商業史上もっとも重要な出来事の1つである。流通業を志す者、流通分野での研究を目指す者にとって、必読の本である。
Posted by ブクログ
BtoC (大衆相手)から BtoB(企業相手)の商売に手をだして、本来の才能や神通力などが失われることもある。評判だったお好み焼き屋のオヤジがナイロン工場を始めて失敗する。「大衆は海である。焦れば溺れるが、身を預ければ浮かばせてくれる。機械を相手にせず、大衆相手に生きるべきだった。大衆を相手にする商売だからこそ花開いたのだ。大衆を捨てて、神通力が失せ、自分も捨てられる羽目になったのだ。」 古い本だけど、今も十分通じる。安売りの薬屋から年商500億のチェーンスーパーに育てる主人公は、ダイエーの中内功がモデルらしい。後半、”平安”電器とダイエーとの再販価格をめぐる争いも描かれています。
Posted by ブクログ
子供の頃にNHKのドラマで観た記憶があったので古本屋の店頭で見つけて即買いしました。
時代はグルグルグルグル回りますが、そこに生きている人たちも巻き込まれて右往左往して大変だ。
巻き込まれるより巻き込みたい。
独立した一本どっこの渦になりたいのです。
Posted by ブクログ
フィリピン、ルソン島で地獄を経験した矢口は日本に帰り、「どうせ一度は死んだ体」と割り切って会社を辞め、「価格破壊」を標榜しスーパーマーケットを立ち上げる。
従来のメーカー⇒卸⇒小売という商流の中にあった慣れ合いや癒着を一切排除し、次々と常識を打ち破っていく矢口の言葉・行動は力強くて圧巻。
常識を打ち破る姿が痛快で、文章の歯切れはいつもの城山三郎のように非常に良く、読んでいて本当に気持ちがいい。
モデルは誰だろうと思って調べるとやはりダイエーの中内功であった。
原体験のある人は強い。自分にはそんな強烈な原体験はないけれど、この本だって原体験になりうる。だから小説でも読書はやめられない。
Posted by ブクログ
久しぶりに驚くほど引き込まれ、一気に読んでしまった一作であった。
価格破壊というタイトルからは想像できないような奥深さ。主人公のモノ売りにかける執念は、並々ならぬものがあったと思う。
少しずつ店が大きくなっていく様子も見ていて爽快であった。
社会に反抗する主人公の姿が今でも心に焼き付いている。
Posted by ブクログ
これは、ダイエーの創始者の中内功氏の伝記的小説となっていると思う
確かに、現代の歴史の中では価格破壊的商法は一時代を築いたのだと思うし
現在もそのモデルに則って行われているビジネスがあるのだろうが
その場合、果たしてみんなが幸せになるモデルなのだろうか?
フェアトレードを最近聴くようなったが、多くの場合
貧困国からの搾取を言っているようだが
国内を見渡しても搾取の割合がおかしくなっているのではないだろうか(利益の再配分の方法といってもいい)
それの一因として価格破壊のような正当な価格を引き下げる方向の力が働いていることがあるのではないかと考える
Posted by ブクログ
名前からして、おもしろくなさそう。経済小説?なんてジャンル、聞くからに興味なかったのですが、一気に読めました。
城山三郎氏は、やっぱり戦時の荒波にもまれた人なのでしょう。主人公は戦時中の地獄生活に比べればすべて天国だと、逆境に打ち向かっていきます。
しかし、価格破壊にそこまで入れ込まなくてよくない?と思うけど、一生懸命だからこそ、話がおもしろくなります。
やはり、おもしろいのは尾頭家との関係。美人で聡明なのに若くして、いろんな判断と苦労を強いられます。
最後には、主人公がすごい大成功を収めて終わるハリウッド的なハッピーエンド物語。
Posted by ブクログ
戦後のエコノミックアニマルを活写した、ある意味ロビンソンクルーソーのような行動小説。商売繁盛の為の徹底したハングリー精神の出発点は戦場での臨死体験にあるというのがいかにも戦後というべきか。死にそうな思いをした人は強い。
主人公は信念に突き進んで行く行動の塊で、葛藤らしい葛藤も無いのに対比して、妻や部下など彼を取り巻く人物の揺れ動く内面描写は、丁寧に描かれている。この辺りがさすがというものか。
Posted by ブクログ
貪欲に成功を求めるなら、綺麗事だけでは済まされない。小説読んで人生が学べます。大事なのはまず行動!いつの時代もハングリーを求める方は必読です。軋轢に負けそうか貴方にもオススメ!VeryGooです!
Posted by ブクログ
ダイエー創業者・中内功をモデルに描いた小説。
経済小説を拓いた城山三郎の真骨頂。
流通革命、価格破壊を目指した中内は、日本中を安い物で満たすことを目指した。そのルーツは戦争にある。日本は物量でアメリカに負けた。戦友がバタバタと死んでいく中、それでも、中内は生き残った。
戦後、中内は価格破壊を掲げ、流通革命を起こしていく。そして、一代でダイエーを築いたそのパワーに圧倒される。
この小説は、ダイエーの基礎をどうやって築いていったかの軌跡がよく分かる。家族も省みず、ひたすら仕事に打ち込み、社会のひずみと戦った。
いかに安く消費者に提供するか。いかに安く提供する仕組みを作るか。そのために、松下電器とも戦った。プライベートブランドも作った。
メーカーではなく小売が値段を決める今の社会は、中内が拓いたものに他ならない。
Posted by ブクログ
「この経済小説がおもしろい!」に紹介されていた本。
城山三郎さんは企業小説の分野では著名な作家さんですが、
著書の本を読むのはこれがやっとこさ2冊目。
しかし、期待以上の面白さにぐいぐい引き込まれてしまいました。
ストーリーはダイエー創業者の中内功さんをモデルとした
スーパーマーケットの企業物語。
「安い商品を買う」という行為は
ごく当たり前のことだと思っていましたが、
昔は物の値段は統制されていたんですね。。
そんな基本的なことから知らなかった自分でも、
主人公がどうやって創造的価格破壊をもたらしたのかが、
ストーリー形式でよく理解できました。
主人公の熱意というか執念が伝わってきます。
この小説を読んで、ウィキペディアで中内さんのことを調べてみました。
小説内で出てきた家電メーカーとの争いは、
ダイエーv.s.松下電器の戦いのことだったのかとか、
色々知ることができて勉強になりました。
経営の神様といわれていた松下幸之助も
家電製品の価格を守るために中内さんと対立していたのか。。
(もちろんどちらが正しいかというのは、
松下側の言い分も確認する必要がありますが。)
スーパーマーケットの歴史を疑似体験できるという意味で、
本当によい小説だと思います。
Posted by ブクログ
城山三郎著『価格破壊』角川文庫(1975)
当時の流通機構、再販価格に執拗に挑戦し、流通革命を目指す男の一生を描いている。この小説のスーパーマーケットにおける流通革命の実態はダイエーが元になっているようだが、当時の経済の側面を的確に捉えた内容であり、傑作。主人公の信念、情熱が心に焼きつく。
Posted by ブクログ
今でこそ、薬品の安売りはめずらしくなくなったが、昔は定価というものが存在していた。主人公は流通機構や再販価格にまっこうから風穴を空けようとする旗手である。
メーカーや弱小小売店を敵にしても、最後は消費者のニーズに答えるために自分の信じた道を突き進むのは、読んでいて胸がスカっとする思いである。
この本で学んだこと
1.どんなに追いつめられても諦めない。
この本にも出ている「あと、もうイーチャン」という姿勢は見習いたい。
2.自分の信念を曲げない
自分たちの売るものは自分たちで値段を決める!買収されそうになっても、自分の信念を曲げなかった。
3.買った瞬間からくさりはじめる
妻の「くさらないものはないの」という質問に
主人公の矢口は「動いているもの、流れているものは、くさらない。くさるより早く流れてしまう。人生だって、絶えず流れて走っていなくちゃ」と答えている。
Posted by ブクログ
横並びの価格が当たり前だった時代に不断の努力で低価格を武器に挑戦する戦争帰りの男のビジネス小説。
時代設定が相当古いので、現在にそのまま通用するような戦略はあまり無いが、過去にこうした時代があったことを知ることができる。
やむを得ないと思うが、どうしてもビジネス小説は内容が薄く感じてしまうのが残念。
Posted by ブクログ
解説の小松伸六氏は、スーパーマーケットの経営者矢口にモデルがあるのかどうかわからない。なんて書いていましたが、どう考えてもこれ、中内功がモデルでしょ。
ルソン島での戦争体験、薬局で闇商売、スーパー設立、生きた牛肉を買って自らで加工販売、大手電器会社(松下電器)と再販(独占禁止法)をめぐり長期にわたる裁判等々。どこをとっても中内功物語だ。小説内では、裁判の結末は政治による裏の力が働いて、電器会社側の勝利となっているが、実際には松下電器側が折れる形で和解したらしい。
スーパーマーケットのパイオニアであり、一時代を築いたダイエーは、今はもうどこにもない。中内氏がワンマン過ぎ、社内にはイエスマンしかいなくなり、時代の流れに乗り遅れていったのだ。いまやダイエーのライバル会社イトーヨーカ堂ひきいるセブンイレブンが日本を席捲している。小説ではその凋落まで触れていない。
神戸出身の私としては、ダイエーの文字が世の中から消えてしまったのはとても寂しい。
Posted by ブクログ
流通の仕組みと闇、価格の裏側を解りやすく描きながらも、説明調に終始しない確かな筆力。
また主人公の戦争体験についての描写も強烈に鮮明で、彼の切迫感がひしひしと伝わり、城山三郎氏ならではの作品だと感じた。
主人公矢口はダイエーの創業者をモデルにされているらしいが、彼の人生を追うのではなく、あくまでも物語の中心を貫くのは「価格破壊」の灯火について。
価格破壊=たたき売り、ではない。
価格を破壊できる体制を整え、勝負する。
矢口の行動を見るにつれ、発想の転換、忍耐力の重要さをより認識する。
教科書的な本にもなるが、彼とは対極に位置するメーカーに在籍する身にとっては苦々しい気持ちにもなった。
Posted by ブクログ
ダイエー創業者、中内功をモデルにしている。スーパーマーケットという業態がどのように市場を席巻していったのか、知ることができる。一人のカリスマ経営者の信念が一時代を築いた。流通業界に与えた影響は計り知れない。
Posted by ブクログ
本棚の整理中に手に取り読んでしまった。今から見ると古く当たり前なところがあったりはするし現実を脚色してるんだろうなというところもあるが、とはいえそれ以前と比較すると大きな契機が描かれているしまあそこそこ。城山三郎にしてはもったいないかなあとは思う。
Posted by ブクログ
中学生だったかそれくらいの時に父親からもらって初読。
何かの折に何回か読み返していたけど、今回は結構久しぶり。
(モデルとされている)中内功氏の話に触れる機会があったので再読。
装丁が変わっていることにちょっと驚き。
(従前はもうすこし劣情をそそる感じの装丁でした)
また中身も記憶にあるほどバイオレンス的(例えば「週刊大衆」のような)ではありませんでした。昭和のお父さんが好みそうな描写も若干ありますが。
今回読み直して思ったこと。
・主人公は戦地で死にかけたので、「死ぬことより辛いことはない」「青春は鍛えるためにある」というロジックでどこまでも「メーカー希望(指定)価格」という暗黒大陸に陽を灯すべく、突き進む。
消費意欲はどこまでも高く、給料が上がり続けた、モーレツな昭和。良いか悪いかはわかりませんが、こういう時代もあったということ。
・また、組織の求心力や突破力を高めるためには、志や信念が必要、ということも再認識。信念のない安売りは永続せず。
というか改めてこれを子供に読ませる、草葉の陰のお父上もお父上だけど、読んでる方も相当なマセガキだな。おかげで流通にハマることができました。
Posted by ブクログ
主人公がえらく自己中心的に思える。流通業に風穴を開けるといっても、やってることはつまり他人を犠牲にしての自己利益の追求。それが資本主義のビジネスの世界だと言われればそれまでだが、あまり読んでていい気はしなかった。そんな自分はやはり保守的な人間なのだと思わされた。
Posted by ブクログ
経済法の教授がオススメしていたので、少しでも経済法の理解の足しになれば…と思い、読んでみました。
簡単にいうと、独占禁止法の「不当廉売」の話です。不当廉売からのし上がっていく主人公と、それを阻止しようとする大企業との闘い。講義を聞いたり、法律の条文を目で追ったりするだけでは、決して分からない当事者(被害者・加害者)の心情・息遣いが伝わってきます。
個人的には、「経済法の理解」に重点を置いていたので、その点では物足りなかったので、この評価です。しかし、小説に「経済法の理解」を求めすぎるのも筋違いかなとも思っています。
物語としても面白いと思います。自分のように勉強の理解のために…と欲張るのでなければ(笑)オススメです。