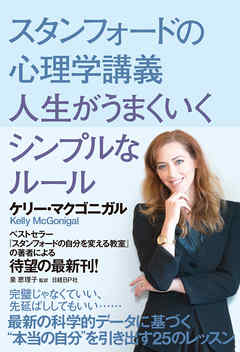感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
価値観をしっかりと持つことが大事なのはわかっているが、その価値観の見つけ方が分からないので困っている。
要は心の持ちようが大事だということ。
人間関係を大事にし、そのためにはインフォーマルなコミュニケーションが人間関係の構築に役立つ。
ヤル気とは「ある」「なし」ではなく、心の持ちよう。関係性、自主性、熟練が満たされると、モチベーションが高まる。そして、「自発的なモチベーション」として自分を高める目標(結果ではなくそのプロセスが大事)を立てる。
不安やストレスは成功へ導くためのエネルギーであることを理解して、それらを取り除くのではなく、受け入れることが大事。
これからのリーダーには「思いやり/共感型リーダーシップ」が必要。高い地位に着くとこの機能が損なわれて、部下の状況を思いやることが出来なくなってしまうので、注意が必要。
・「成長型マインドセット」とは、自分自身に挑戦することでしか潜在的な能力を発揮できないという考え方です。難題に直面した時は、成長する絶好のチャンスです。失敗したり、目標を達成できなかったとしても、それはあなたが無能で力不足なのではなく、振り返って反省し、成長へ向けて前進する必要があるということなのです。「成長型マインドセット」の持ち主は、困難を耐え抜き、仕事に意味を見いだし、長期的に成功する傾向にあらそうです。
「固定型マインドセット」とは、能力・知性・才能をあなたが持っていようといまいと、それらは固定的であり、変わらないと信じる考え方です。この「固定型マインドセット」の持ち主は、例えば試験の成績が悪かったりすると、もともと自分には素質がなかつたのだと考えます。この人が挫折を経験すると、ほとんどの場合は諦め、すぐに成功できる「別の何か」を探し始めます。そして自分の得意分野を探すこしや、失敗、苦労を避けることが、人生の目標になってしまうのです。
・私たちは自分の仕事を「何をしているか」で捉えようとする傾向がありますが、私たちの精神面の健康や幸せは、「何をしているか」よりも、「一緒に働く人に対してどう感じるか」によって決まるからです。たしえ1分という短い間でも人を1人きりに$せて、思考が散漫になるし、ほとんどいつも、何らかの形で「社会的なストレス」を感じ始め、それが不眠の原因になります。
・「社会的な対立」と上手につき合っていくための第一歩は、「それ(社会的な対立)がどれほど私たちに影響を及ぼすか」認識することです。これはただ単に、人間の性質(たち)なのです。「あなたの思考はほとんどいつも、どんなちょっとした対立(操め事)でも、拡大・誇張して捉えている」し認識することも、役に立ちます。脳はどんな些細な社会的ストレスでも敏感に探知するこしができるため、大したことのない「不確かなこと」を、壮大なドラマ(事件)に変えることがでさます。職場での人間関係の対立に参っていると気づいたら、「脳の「社会的な本能」が過剰反応しているのかもしれない」と、考えてみてください。
・職場での人間関係を改善するポイントは3つあります。
①サボートが必要な人が周囲にいるか考える
②「職場での親切」を実践する
③他人の「貢献」を認め感謝する。
・「インフォーマルコミュニケーション(休憩スペースでの雑談など、組織や集団内で行われる何気ない会話・コミュニケーション)」が、生産性を回復させ、職場での人間関係を強めるのに決定的な役割を果たしていることが分かっています。
・ソーシャルキャピタル(社会関係資本)とは、他者と積極的に交流することで得られる、ある種の信頼や尊敬のことです。ソーシャルキャピタルは、誰かを助けたり、仕事で好ましい印象を与えた時に得られるものですが、信頼関係や友情を築いたり、人に善意を示したりして「人と交流する」ことによっても得られます。職場の冷水機周辺で交わされる会話のような、仕事に直接関係のない「交流」は、ソーシャルキャピタルを築くのに特に効果的です。仕事の重圧から解放されている時に、同僚の違う一面を知る機会を得られるのです。
・ー日に何度も出かけていって邪魔するようなことはしたくないでしょうが、会って話す方が、仕事に関係のない簡単な会話を交わす機会が増えます。特別に関係を築きたい人がいるなら、メールで連絡を取る代わりに、顔を合わせて直接話す時間が取れるか確かめましよう。
・スマートフオンや携帯電話を手に持っていたり、ただ机の上に置いて見えるようにしているだけでも、精神的にも、視覚的にも気が散ってしまい、会話することで生まれる共感や信頼を損ねかねないことが分かっています。
・同僚と信頼関係を築く最も簡単な方法の1つは、「あなたの話を確かに聞いていた」と相手に示すことです。前に話した会話をフォローしましょう。
・ポジティブな噂話をした相手(個人やグループ)にその言葉が直接届かなくても、それを聞いた人はあなたのこしを、「職場を大切にし、貢献する人」と見るようになることが分かっています。いい噂話を広める人は、「サポートを受けるべき人」として認められるようになうます。そして、あなたがその(いい噂話を広めるという)習慣ガを身につけたなら、必要な時に他人が助けてくれたり、守ってくれたりする可能性が高まるのです。
・自分の価値観をはっきりさせ、熟考すれば「道徳的な偽善」は減ることが分かっています。これを毎日繰り返すことが大事です。自分の価値観を思い出させてくれる”モノ”を身近に身に付けることで、「言行が不一致だ」ということに気づくのを助け、「自分の理想に背くような決断を下そうとしている」ことに気づくのを助けてくれます。
・「やる気(モチベーション)」とは、ものではなく、ましてや、なくしてしまえるようなものでもないことが分かっています。やる気とは「ある」ものでも「ない」ものでもないのです。
・「仕事をやる気が起きない」と不満を言う時は、大抵の場合、自分が持っている強い意欲・やる気を満足させる具体的な方法を見つけられないだけなのです。すべての人が持っている「最も基本的な、前向きなモチべーション」は、次の3つです。
①関係性:他者やコミュニティー、大切にしている大きな目的・目標とのつながりを感じること。
②自主性:人生の質を左右するような行動や選択を自由に取れること。自分の意思で取つた行動や選択が、大切にしていることと一致していれぱ、目標を達成する助けになる。
③熟練:取り組んでいることに対する能力があり、貢献できるものがあることが自分でも分かっていて、個人的に満足できるような上達や学びがあること。
・「根本的で、前向きなモチべーション」に加えて、人間は、とても強い、相反するモチべーションに突き動かされることもあります。「不快なことを避けたい」「すぐに満足したい」という、相反する欲望です。これは基本的な生存本能に基づくモチべーションで、根本的な人間の要求を満たすことと関係のある「大きな意義や幸福」よりも、「その瞬間の痛みや喜び」に焦点が当たっています。
・仕事で「やる気が出ない」と感じる時、大抵の場合は、自分の根本的な欲求の1つ、あるいは複数の欲求が職場で妨げられている(阻害されている)と感じているものです。根本的なモチぺーションが満たされないために、「ラクになうたい」「すぐに満足したい」という。相反する衝動。が、一層顕著になります。「関係性」「自主性」「熟練」を経験する具体的な方法が見つけられないし、不必要な努力やストレスを避けたいと、さらに強く思うようになるのです。不快なことを避けて、喜びを最大限引き出そうしする「基本的な衝動」が優位になってしまう。「やる気をなくした」というのは、多くの場合、この状態になっていることを指します。
・対照的に、仕事への努力やストレスが、少なくとも「根本的で前向きなモチべーションいの1つとつながっていると感じ大時、その仕事が耐えられるものになるだけでなく、やりがいのあるものにもなります。実際、根本的な欲求が満たされると、ある種の特別なエネルギーが解き放たれるようなのです。身体が活性化する感覚、楽観的になる感覚、意欲など、「やる気をなくした」という時に、多くの人に欠けているエネルギーです。
・「自分の能力」「人との関係性」「自主性」といった欲求を満たす仕事や職場、同僚を持つのは、言うまでもなく理想的なことです。しかし、必ずしもそうとは限りません。やる気がない人のほとんどが、「職場は自分の欲求を満たしていない」と言うでしょう。しかしそれは、「やる気がない」ことしは全く違うのです。やる気不足が問題なのではなく、「自分の欲求を満たす方法を見つけることが大事なのだ」とひしたび気づけば、本当の問題に取り組むことができるようになります。なぜなら、たとえ仕事に満足できなくても、仕事に対する考え方や、仕事への取り組み方を変えることで、そうした要求を満たすことができるからです。
・やる気が起きるカギになる「3つの質問」があります。
①職場で一番大切な人間関係は何ですか。その関係を深めるために何ができますか。職場での人間関係をじっくり考える他の方法は、同僚を知る機会を進んで探し、後輩を指導し、仕事で出会う人の役に立つようにすることも含まれます。
②仕事で、あなたの個人的な貢献によって支えられている「目的」「ピジョン」「大きな計画」は何ですか。言い換えるなら、メールに返信したり、報告書を提出したり、数字を計上したり、会議に参加したりする時、その作業の裏にある「なぜ」に対する一番いい説明は何ですか。特に、恐ろしくストレスが多く、平凡な日常的作業では、この種のことを考えることが、職場での自主性を高めます。
③自分のキャリアをどう育て、どう伸ばしたいですか。そうするための一番手っ取り早い方法は何ですか。
この間いに答えるカギは、具体的に考えることです。何かを選択したらすぐに、上達したいと欲しましょう。コミュニケーションであろうと、時間管理であろうと、チームマネジメントであろうと1日々の仕事を、学びや成長の機会と捉えるのです。
・目標を立てる時には、「何を達成したいか」ではなく、「誰のようになりたいか」「どんな自分になりたいか」を、自分に問いかけてみてください。何か特定の成果が繰り返し頭に浮かんできたら、「どんなプロセスでそこにたどり着けそうか」「どんな選択が必要か」「自分のどの部分を強化したらいいのか」、自分に問いかけるのです。変化や成長のプロセスが大事であり、成果はその結果としてあとからついてくるもの。
・「良い目標」には必ず、「行動する」というコミットメントが伴います。つまり、あなたが目標に近づくためにしようとする、何かしらの行動のことです。ただ、その行動を起こそうとする前に、あなた自身がなぜそれをするのか、その意義をきちんと理解しておききしょう。これ以上「なぜ」と聞くことができないところまで、「なぜ」と問い続けてみてください。そうすれば、あなたの目標の裏に隠れている大きな「なぜ」に突き当たります。「その”変化”を求めている「深層心理にあるモチぺーション」が何かを突き止められれば、目標によりコミットできるようになるだけでなく、その目標をあきらめることが少なくなる」ことが分かっています。
・本当に新年の目標から離れずにいたいのであれば、その目標に近づくために考えられる”最も小さな一歩”を踏み出すことから始めてもいいのだと、自分に言い聞かせてください。その小さな一歩が「今日あなたがしていること以上の何か」である限り、正しい方向に進んでいるのです。たとえ「これは十分でないような気がする」と感じたとしても、あなたの大きな夢に合った”小さな一歩”を選んでみてください。
・「自分の強みを思い起こすことで将来の忍耐力と意思の力が強められ、過去を振り返ることで将来の幸せが増す」ことが分かっています。将来の目標について考える時、私たちは「過去に自分がどれだけ至らなかったか」と、ラ点にフォーカスしがちです。自分に自信を持ちましょう。自分に対して寛容の精神を持って、自らの人生を素直に見つめれば、自分がどれだけたくさんのこしを成し遂げてきたか、分かるはずです。自分の進歩を認識すると、新年に向かってやる気も湧いてさます。
・「自発的なモチベーション」は、等感を感じないようにしたり、周囲から認められたいというような「外(部)からの報酬」を求めるものではありません。それどころか、変わりたいという深い欲求の表れなのです。自分にとって何が大事なのか、どんな人間になりたいのか、目標に向かつて前進させてくれるものは何かを、反映しているもの(モチべーション)なのです。
・白分の目標について考えてみてください。あなたがどれだけ変わりたい、改善したい、成長したいと思っているか。そして自分に問いかけてみてください。「なぜこの変化を望んでいるのか」「なぜこの目標を達成したいのか」、と。その回答が次の3つのどれかに当てはまるなら、買われる可能性が高いのです。
①生活の質を改善しますか?そのモチべーションは、健康や幸福感、仕事への満足感を高めたいといった、長い目で見て「生活の質を向上させるもの」ですか?
②「なりたい人物像」を反映していますか?そのモチべーションは、あなたが高めたいと思っている「積極的・肯定的な自己認識や性質」と関係がありますか?その変化は、「表面的ではなく、心の底からなりたい人物像」を反映していますか?
③本質的にやりがいのあるもの、楽しいと思えるものですか?その変化は、あなたの幸せにすぐに影響しますか?例えばそのモチぺーンョンは、楽しむことが出来たり、自然に興味が持てるようなものですか?大切な人やコミュニティと時間を過ごすことが出来るものですか?
・挫折を感じているなら、「このゴール(目標).役割、関係が、なぜ大切なのか」、思い出してみてください。それは、なぜ大切なのですか?現状で、本当はどうしたいですか? こう考えることで、心理学者の言う「目先の日標より大きな目標」に集中する助けになります。「目先の日標より大きな目標」とは、称賛や報酬といった「個人的な達成や成功」の尺度を超えた目標のことです。
・「有能で信頼できる」と周囲の人に思わせ、勇気が持てるようになる「3つのルール」
①自信のなさや不安は、自分自身を気にかけ、べストを尽くせる人間として信頼できるサインとして受け止めきしょう。自信のなさや不安を、「準備不足や覚悟ができていないことへのサイン」として捉えないこと。
②大切な会議や話し合いの前に、その会議や話し合いがなぜ大切なのか、数分間考える時間を作る。
③心を開き、周囲の人の言うことに関心を持つ。
この3つの秘訣に共通することば何でしようか。自信があるかのように見せるために自分の行動をコントロールしようとしたり、「自信があるんだ」と自分に言い聞かせたりするのではなく、「もっと深いレぺルの自己信頼を呼び起こすマインドセット(心の持ち方・考え方)」を選ぶ」ということです。
・人が陰口を言う対象は、同僚であれ、ライパルであれ、自分に対して力を持つ人物であれ、「自分の目標に限りなく近い人物」についてだということが分かっています。実際、「ライバルだと認識されている人物」が、そうした噂のターゲットになりやすいのです。陰でライバルの悪口を言うことは、自分の自尊心を高め、ライバルと比較きれる時に自分を良く見せることができる「一番手っ取り早い方法」だからです。多くの人が、自分の不安感や自信のなさを処理するために、ネガティブな噂話をします。
・「不安というものは、私たちが全力で頑張れるように仕向けてくれるものである」ということです。「不安によって引き起こされるこうした身体的な症状が、パフォーマンスの邪魔になる」とほとんどの人が信じているにもかかわらず、実は緊張している状態の方が、完全にリラックスしている状態よりも、いいように見えます。
・不安に乱されず、逆に不安の力を利用するためには、「あなたが不安をどう考えるか」が、すべてのカギになります。「不安に邪魔されている」と感じる人は、不安を抑えることにエネルギーを費やしてしまう傾向にあります。不安を抑えようとするのは、気が散るし、難しいものです。落ち着こうとすればするほど緊張してしまいます。不安が障害になると信じていると、自信を失って、無力だと感じやすくなるのです。逆に、最新の研究によると、不安を受け入れ、さらに一歩進んで不安を積極的に受け入れられるようになれぱ、困難に立ち向かう助けになってくれるのです。
・不安を受け入れ、「不安は自分の助けになる」と言い聞かせれば、人は自信を持ち、いい結果が出せるのです。体が発するサイン(症状)がどんなものであれ、それを消し去ろうとすることに、心を砕くのではなく、不安があなたに与えてくれるエネルギーを使って何かを成し遂げようとすることに、もっと集中してください。「自分の目標を達成するために、今この瞬間に、私が取れる行動や選択は何だろう」と、自問してください。この方法は、人生で不安を感じ取った時にいつでも使うことが出来ます。
・「あがり症」を克服するためには、観衆が自分に対して肯定的か批判的かという現実よりも、発表者自身が彼らをどう見ているかの方が、重要だからです。大抵の状況では、観衆の考えているこしを察することなどできません。その代わり、その人自身の普段のマインドセット(心の持ち方・考え方)が影響するのです。「他人が応援してくれる」と、普段から考え、自分自身も他の講演者に自信を与える観衆になるように心がけるのです。
・「注意回復理論」と呼ばれる、とても興味深い認知心理学の理論があります。この理論では、「集中力は有限のカ・才覚で、定期的に補充される必要がある」ことが分かっています。ある仕事に長いこと集中しすぎると、物事をこなす能力が低下します。休憩が必要なのではと感じるのは、正しいことなのです。休憩を取り、集中力が回復することをしたら、前よりもっとエネルギーと集中力を持って仕事戻ることができるでしょう。。集中力を回復させるはかの行動・動作として、「身体運動」「呼吸に意識を集中$せるこ上「膜想」のほか、「笑いや畏敬の念、愛情の念を起こさせるようなビデオ(かわいい動物など)を見ること」が挙げられます。
・「ストレスは悪いものだが取り除くことができない」と考えていること自体が、不安や憂惨(気分の落ち込み)を引き起こす「特に有毒な処方範」になってしまっているのです。米エール大学の研究によると、「ストレスを害だと思っている人」は、「ストレスがポジティブな力になり得ると思っている人」よりも、気分が落ち込む傾向があることが明らかになっています。そういう人は同時に、腰痛や頭痛のような「ストレスからくる健康問題」を、他の人より多く抱えているといいます。
・不安や憂穆(気分の落ち込み)を和らげ、そこから回復する力を生み出すのに最も効果的なのは、運動やスポーヅ、散歩、友達や家族・ぺットと過ごす時間、マッサージ、膜想、ヨガ、お祈り、祭北への参加、ボランティア活動や他人の手助け、クリエーテイブな趣味に費やす時間だということが、科学的に証明されています。こうした方法は、飲酒やテレビ鑑賞といった「典型的なストレス解消法」と、何がそんなに違うのでしよう。飲酒やテレビ鑑賞といった「逃避する方法」と違って、前述した「効果的な方法」には、「自分自身へのセルフケフ」や「自己よりも大きな存在とつながること」が関わっています。それらが「人生の意義」や自己超越の感覚をもたらしてくれるのです。「人生の意義」「自己超越」「自分自身へのセルフケア」が幸福や回復のために必要な「重要な力の源」なのです。
・ストレスに対処する「最善の方法」は、ストレスを減らそう、避けようとするよりも、ストレスについての考え方を改めて、ストレスを受け入れることなのです。
・ストレスは、自分が仕事を大切にしているからこそ表れる「サイン」だと考えると、いいでしょう。ストレスを感じるのは、「自分の仕事に対して思い入れがある」ことの証しで、一生懸命やっているからこそ、誰かのことを思っているからこそ、ストレスを感じるのです。ストレスは誰もが感じることであると知り、「ストレスの味」を自分なりに変えることによって、ストレスとのつき合い方を変えることができます。
・大事なのは、何かが起きた時に、「なぜ私にこんなことが起きたのか」と考えるのではなく、「何のために起きたのか」と考えるのです。「なぜ」ではなく「何のために」と考える。これこそが「成長思考」です。逆境は起きてほしくないと思っても、実際には起きてしまっているわけですから、それを一旦は受け入れる。そしてその経験から、自分自身がより良い状態になるためにどうしていくのか。あるいは、その経験が、他人を助けるためにどう役立つか。そうやって考えていく方法です。そのためにも、「書く」ことが大事です。自分の経験を書く行為というのは、ヒーリング効果が最も高いやり方なのです。感じていること、起きたことを「言葉にする」ことは、癒やしの効果があると、研究で分かっています。そこで大事なのは、「感じていることをただ綴る」ということです。この時に注意しないといけないのは、「あの時は大変だった、でもよかったんだ」というところからスタートしないことです。「自分にどんな辛いことが起きたのか」ということを受け入れながら、「ありのままに自分が感じたこと」を書くことが大切です。何度も書いていく中で、自然発生的に、「前向きなエネルギー」が生まれてくるのです。
・リーダーシップには二面性があることが分かりました。人を見下す傾向にある人、優しく思いやりを示す人、どちらも素晴らしいリーダーの素質があるという結果でした。もちろん、思いやり/共感型リーダーシップは「優しい笑顔があれぱいい」といった単純なものでないことは分かっています。、思いやりを構成する要素として以下の3点を挙げています。
①他者の要求、要望、苦難に対する配慮。
②他者との相互依存の気持ちを持ち、相手を思いやり、強い関係を築くこと。
③他者の必要を満たし、苦しみを軽減させ、幸福のための支援をすること。
・「自分の価値観について考えることが、思いやりのある行動にっながる」ことが明らかになっています。それはあなたが「他者、あるいは自分よりも大きな何かとつながっている」と実感させてくれるからです。価値観について考えることは、新しい情報を受け入れる時や周囲からの様々な反応に対して、広い気持ちを持って対処するのにも一役買ってくれます。「自分にとって一番大切な価値は何か」を意識することとは、リーダーだけでなくすべての人に有益です。学び、成長するために大事な要素だからです。
・最後に、自分自身に対して心を配ることも、思いやり/共感型リーダーシップには大切なことです。企業の重役や上級管理職の人間に聞くと、「自分を思いやるのが一番、難しい」と、誰もがロを揃えて言います。「他の人を思いやる方がまだ易しい」と感じる人が多いのです。しかし、自分に対して思いやりの気持ちを持つことは、力強さの源泉であり、サービス精神を発揮するための源です。最も素晴らしいリーダーは、自分の幸福を大事にする人だと断言できます。
・神経科学者によれば、共感を感じる脳の最も基本的な組織、他人が何を考え、何を感じるか理解するのを助ける神経細胞「ミラー細胞」、は、高い地位に就くと、その権力が恋意的なものであろうが一時的なものであろうが、機能が損なわれることが分かつてきたのです。高い地位にいる人は、他人の感情を認知する能力が低いのです。同様に、地位の低い人が直面する困難に対して同情する気持ちが少なくなり、助けようとする気持ちは薄れていきます。この「共感力の欠如」は、意図的に、非倫理的ではない選択につながることもありますが、他人への影響力を顧みないことで、周囲に害を及ばすこともあります。例えばマネジャーの地位にある人は、自分のチームが直面しているプレッシャーが分からないかもしれませんし、本人の批評がチームのやる気や成果を削いでしまっていることが、分からないのです。
Posted by ブクログ
成功のカギとなる成長型マインドセット、成長を阻む固定型マインドセット。能力より、努力を誉める。
アヒル症候群=周りから努力していないようにみせかけて、アヒルの足のように一生懸命努力している=ストレスをかかえやすい
完璧にやらないことがすべてをこなす秘訣。
人間は忙しいほうが幸せを感じる。
生産的先延ばし=先延ばししている間にアイデアが浮かぶ
講師の服装がきちんとしていれば、学生は熱心に学ぶ。
服装は、なりたい自分を表現できる。
パワーポーズを作る=無気力感を自信に変えられる。
脳には社会的な対立を見つけて悩む仕組みが組み込まれている。
他人がどう思うか、を正しく気にする方法は、すべての人を満足させることはできない、目標自体は他人に相談しない。
言行一致はレジリエンス(精神的回復力)の源になる。
毎日、自分の価値観を思い出す。
やる気をどう高めるか。やる気がないのは具体的な方法がわからない、だけ。
新年の目標設定=どう成長したいか考える。なにを、ではなくなぜ、を考える。具体的な行動目標を設定する。
新年になる前にする5つのこと=今年起きた一番好きな思い出をリストアップする、人生で感謝しているリスト、をつくる。新年のハイライトを想像する。再来年1月1日付で、未来の自分から今の自分宛に出紙を書く=来年の目標を達成した、という立場でその年を振り返っているところを想像する、来年の努力できたことに感謝する。新年の目標に、他人へのかかわりを含める。
何らかの成果を達成することは目標にしない。
自己効力感を持つ=自信と謙遜をバランスよくもつ。
妬みをプラスに変えるルール
誰かに気持ちを打ち明ける=サポートが得られる
妬みは欲しいものを知るサインと知る
妬ましくても、成功を祝う
妬みを行動を起こすきっかけにする
不安は成功へと導くエネルギーである。
TEDの赤い点に立つと、パニックになるのが普通。
応援されている、と考えると不安がパワーになる。
誘惑に触れる前に、大事なことを一つする。
注意回復理論=集中力は有限、45分集中したら15分休む。
ストレスにもいい面がある。