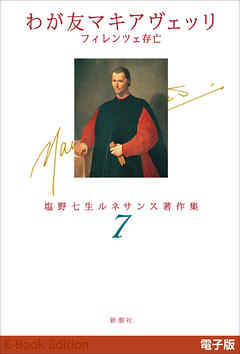感情タグBEST3
Posted by ブクログ
「君主論」の作者で、マキャベリズム、マキャベリストなどの言葉の元になったニッコロ・マキアヴェッリの半生を、豊富な資料を元に描いた歴史読み物的作品。マキャベリスト(権謀術数主義者:目的達成のためには手段を選ばない人)の筆頭かと思えば、冷徹な思想家は彼の一面に過ぎず、実際には誠実な実務家であり、ユーモアをそなえた戯曲家であり、愛国心厚い歴史家でもあった。人間味あふれるマキアヴェッリの素顔に迫った読み応え十分の一冊。
Posted by ブクログ
愛すべきマキァベリ!
本題からは逸れますか、有名なゴンドラの唄のルーツは、ヴェネツィアではなく、フィレンツェの偉大なるロレンツォに辿られるとのこと。
勉強になりました。
またルネサンスの都フィレンツェに行きたくなる一冊。
Posted by ブクログ
チェーザレの連載再開を祝うに当たって、やっぱりもっと勉強しないとなぁと思って手にした一冊(全三巻だけど)
やっぱり塩野さんはおもしろい!!
ローマ人は途中で自分が何巻読んでんのか分からなくなって辞めちゃったけど、これはなんといってもルネサンス!
1巻はまだそんなにボルジアは出てこないけど、それにしたって、この時代背景にはゾクゾクせずにはいられないよねー。
もし、好きな時代に生まれられたなら、この時代に生まれてみたかったかもしれない。
(いや、そう簡単には言えないか)
Posted by ブクログ
細川選。
フィレンツェ共和国みたいですね。うちの部は。
サヴォナローラ該当者が多すぎますけどね。
もちろん中道主義者・大統領ソデリーニとか気狂いピエロも…
Posted by ブクログ
塩野七生 「 わが友マキアヴェッリ 」
マキアヴェッリ の政治思想「君主論」の思想背景を紐解いた本。
君主論の目的は ロレンツォの死により滅亡の道を進むフィレンツェを救うために、チヤーザレボルジアが行ったような 市民兵による自力防衛を実現すること。
マキアヴェッリは フィレンツェ市民兵による イタリア統一まで視野に入れているとし、マキアヴェッリのイタリア統一の野心は スペインによるローマ略奪を持って 終了したとする構成。
君主論やマキアヴェッリを スペイン台頭など国際関係の変化、フィレンツェ人の気質、グイッチャルディーニ との比較から捉えている。著者しか書けない視点で面白い。
全体を通して、鋭すぎるマキアヴェッリの時代感覚と 鈍すぎるフィレンツェの時代感覚を 感じる。ルネサンスにおけるフィレンツェの成功体験が 時代感覚を鈍らせたように思う。
この本の最終章が マキアヴェッリやフィレンツェのことでなく、「ルネサンスの終焉」としたことは、フィレンツェの滅亡やマキアヴェッリの死を 一つの時代の終わりと見ているから?
君主論の面白さ
*権力を獲得するためには 冷徹しかない〜善や悪は関係ない
*政治に倫理を求めていない〜しかし 人間が悪とは言っていない
*時代の変化に対応するには 共和制より君主制の方が望ましい
*人間は自然を模倣するものだが、その自然は多種多様が当たり前〜多様は非難されるべきではない
Posted by ブクログ
マキャヴェッリ これまでは「君主論」の著者ということくらいしか知らなかった(もっとも、君主論だっていまだ読んじゃいないのだが。。)。
ふーん、もともとはフィレンツェの敏腕官僚&外交官なんだね。それも相当な労働中毒だ。
42才の時クーデターが起き、それまで活躍しすぎていたこともあって、あえなくクビ。収入の道を絶たれ、生きがいも無くし、失意の中で「君主論」など後世に残る著作を次々とものにする。人生、何が不幸なのか、何が幸いするのかわからないもんで、このクビがなければ後世これほどマキャヴェッリの名前が残っていないはず。
マキャベリズム 辞書によれば「目的のために手段を選ばないやり方」とある。いささか印象が悪い。これも後世の人々の誤解や歪曲がかなり入っているらしい。聞いて見なけりゃわからんもんだ。とはいえ、塩野先生はほれ込んだらあばたもエクボっぽく書くので、塩野説を100%信じてもいないわけだが。。。。
Posted by ブクログ
いつか読もうと思っていた塩野七生の本を初めて読んだ。
マキャベリズムという言葉で知られる、君主論を執筆したマキャベリについて徹底的に深く描かれている。マキャベリはどういう時代に育ち、書記官時代に何をして、そしてフィレンツェ追放後、物書きとして何を考えていたのか。
マキャベリは誠心誠意祖国のために尽くしてきたが、不当に祖国を追放された、そこにはどのような怒りがあったのか。活かされなかった天才の姿と、天才を活かさなかった時代が圧倒的な質量で書かれていてとても面白かった。
経営層に塩野七生が好まれるのが分かる気がする。交渉のやり方、それぞれのひとの立場の想い、攻略方法、経営戦略にも繋がりそうな政治の世界に触れることが出来る。
でも、天才マキャベリの無邪気さ、自由奔放さ、そういった人間味もしっかり描かれているのが、ただの歴史本で終わらない醍醐味を与えてくれる。
Posted by ブクログ
この本の狙い通り、「君主論」により目的のためには手段を選ばない冷徹な人間像からはかけ離れた人間ということがわかった。むしろ人間味のあふれた、俗っぽさが伺えた。残念ながら時代には翻弄されたがその中で「君主論」等を表すに至った洞察力で、指導者に下記の者を望んだのである。
ヴィルトゥ(才能、力量、能力)、フォルトゥーな(運、幸運)、ネチェンタ(時代性、時代の要求に合致する)
この本を読んで彼の生きた時代を考慮するとこれらを選ぶ理由が分かった。
Posted by ブクログ
著者のマキアヴェッリに対しての贔屓、いや愛が存分に伝わる1冊。著者自身が自分が書いたマキアヴェッリの友人たち(ヴェットーリやグイッチャルディーニなど)と、どちらがマキアヴェッリを理解しているか張り合ってるところが面白い。塩野作の他作品を読んでいてフィレンツェほどイタリア統一の足を引っ張っている国は無いなと感じていたが、視点がフィレンツェに移ると、ヴェネツィアや法王陣営、その他の小都市国家も三者三様だったんだなと。
Posted by ブクログ
「夜がくると、家にもどる。そして、書斎に入る。入る前に、泥やなにかで汚れた毎日の服を脱ぎ、官服を身に着ける。
礼儀をわきまえた服装に身をととのえてから、古の人々のいる、古の宮廷に参上する。そこでは、わたしは、彼らから親切にむかえられ、あの食物、わたしだけのための、そのためにわたしは生をうけた、食物を食するのだ。そこでのわたしは、恥ずかしがりもせずに彼らと話し、彼らの行為の理由をたずねる。彼らも、人間らしさをあらわにして答えてくれる。
四時間というもの、まったくたいくつを感じない。すべての苦痛を忘れ、貧乏も恐れなくなり、死への恐怖も感じなくなる。彼らの世界に、全身全霊で移り棲んでしまうからだ」
人間性の現実を冷徹に見極める彼の思想哲学とは裏腹に、なんと人間臭い人物だったのだなと、ほほえましく感じる。
いや、そういう人間だったからこそ、あの『君主論』を著すことができたのだろうか。
実に魅力的に描かれていて、彼のことがたまらなく好きになる。
Posted by ブクログ
読んでいると作者が女性だということを忘れる。繊細さや柔らかさにですら潔さが漂う感じ。
フィクションなんだかノンフィクションなんだか、この人の話を読む時は読んでいると境界が分らなくなる。
じっとり染み込んできて、拾い読みが許されないくらい濃密な厳しさみたいなのを感じる。
それでいてすごく艶かしい文章を書く人だなあというのをいつも思う。この人の作品って大抵そう。
「ルネサンスの女たち」が一番好きなのだけれど、この本はハードでもお構いなしに鞄に押し込んで読み漁った。凄く楽しかった。
余談だが、この人が物凄く好きだったので、受験中世界史の問題の全てに私はこの表記を使い通した。
Posted by ブクログ
君主論・戦略論などを書いた権謀術数の大家のイメージが強いマキャヴェッリの若い日から、フィレンツェのメディチ家に対する反乱(ロレンツォの弟ジュリアーノ・メディチの死)、そして一代を築いたロレンツォ・メディチの死後僅か2年後のメディチ家の衰退、サヴォナローラの台頭と失脚、チェーザレ・ボルジアなどの興亡、そしてメディチ家の復活などを見、そして自ら失脚し失意の晩年。彼の人生を通して変転に満ちたフィレンツェの歴史を描く。著者も書いているとおりもう一方のイタリアの大国ヴェネツィアと比較し、なんと一貫性のない歴史なのか。その背景の下でマキャヴェッリが生まれたということも頷けます。マキャヴェッリに対する愛情に満ちた視線が印象的です。
Posted by ブクログ
塩野七生「我が友マキアヴェッリ」の文庫本3分冊を読み、ついでに勢いで、武田好「マキャベリ『君主論』」を読む。
高校時代、世界史は大学入試のために勉強した社会科目のうちの一つだった。もちろん、マキアベリの名前は、その著作「君主論」とともに出てきて、国の統治には権謀術数を駆使し、冷酷に徹して、目的のためには手段を選ぶべきではない、などと学んだような気がする。マキアベリ自身もそれを実践した人物で、マキァベリズムとは、そんな恐ろしい政治思想だとも・・・・。
塩野七生さんの「我が友マキアヴェッリ」によれば、マキアベリは、フィレンツェ共和国のノンキャリア外交官とでもいうべき地位に過ぎないわけだが、フィレンツェ政府がとり続けた優柔不断、日和見的な外交に対する憤慨がこの「君主論」を書かせたということのよう。国を統治する上では、時と場合により冷酷とでも思えるような手段も必要、思い切った手段を採る決断をしなければならない、のだという。実際に他国にチェザーレ・ボルチアというモデルもいて、その人物に刺激されたことでもあるようだが・・・・。
でも、こんな話は現在から見ると当たり前のことだろう。特に企業経営に当たってはその心構えは当然とも云える。もちろん不法、不当な手段を使ってはならないが、最近よく見られる工場閉鎖、人員整理など、心を鬼にして決断すべきことは多い。そういう意味では、「君主論」は経営者のバイブルとしてもいいくらいかも知れない。
これまで実際には「君主論」も読んだことも受験勉強以上のことをしたこともなかったが、今回初めてマキアベリのことを読んで、少し本当のところを教えられたようなことだろうか。このマキアベリという人物、仕事人間ではあるが不埒な遊びも無縁ではなかったよう。お堅い著作だけでなく喜劇もいくつか書いていて、特に代表作「マンドラーゴラ」は芝居で上演され人気を博していたのだとか。いわば愛すべき人物で、だから塩野さんも「我が友・・・・」としたのだろう。知れば知るほどに真実が見えてくるというところだろうか。
最近つくづく思うのは、ある歳とってからの読書というものは、子供のとき或いは学生時分に上っ面だけを撫でてきたこと(それが勉強だと思っていたが)を、自分の眼と頭で改めて見直し、自分自身で思いを巡らせて見る、考えてみるということではなかろうかと。源氏物語のような古典、宗教や倫理、社会問題、今回のような歴史、それらすべてについて云えることなのだが・・・・。