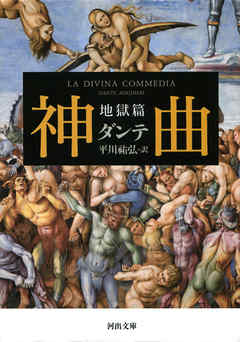感情タグBEST3
このページにはネタバレを含むレビューが表示されています
Posted by ブクログ
ご存知でしたか?
これは詩なんです。
一応ダンテが実体験したことになっていますが、生きたまま地獄を巡るわけです。
当時はキリスト教が法王派と教皇派に分かれて争い、法王派であったダンテは政争に敗れて追放されていました。
そんな失意のダンテの前に、古代ローマの詩人ウェルギリウスが現われ、神が創りたもうたこの世界を見て、この世の人たちに正しく伝えるように言うのです。
で、まず地獄から。
文字を読める人が少なかった中世の頃、夜、薄暗いろうそくの明かりの下で武器や農具の手入れ、織物などの手作業をしながら誰かに読んでもらって聞く地獄の様子は、それはそれは恐ろしく感じられたと思います。
死ぬほど地獄に行きたくない→神様の教えに従って、善い人生(正しい人生)を送らなければならないと思うのは、自然な流れでしょう。
そういう意図をもって書かれたのが、この神曲。
だから地獄の住人たちは歴史的に有名な悪人だったり、個人的にダンテが気にくわないヤツだったりとかなり恣意的。
もちろんキリスト教ができる以前にお亡くなりになった人は天国へ行けません。
でも、地獄にはいますけれども罰は受けていません。善い人は。
天国へ行くための第一歩は善い人であることではなく、洗礼を受けることなのです。
小難しい理屈もありますが、詩なのでテンポがいいです。
そしてダンテは、庶民に受け入れられやすいようにラテン語ではなくトスカーナ地方の方言で書いたそうなので、余計に耳から入りやすかったのではないかと思います。
“ゲルマン人のゲーテの『ファウスト』と異なって、ラテンの人ダンテの『神曲』は非常に緻密に構成された芸術作品で前後照応する場合が多く、それが精読の興味にたえる理由の一つともなっている。”(訳者あとがき)
ゲーテ、ディスられてる。
目に浮かぶような描写で地獄の様子を、罰を受けている人々の様子を、延々と語ります。
キリスト教の教義では魂は不滅です。
生まれ変わることもありません。
だから永久に罰を受け続けなければならないのです。
反省したから許されるとか、水に流すなんてことは一切ないのです。
泣いて罪を悔いても、一度やっちゃったことは取り返しがつきません。
最後の審判の日まで、地獄に落ちた亡者は苦しみ続けます。(地獄に落ちちゃった人が最後の審判の日に救われるとは思えないのですが、そこのところはどうなんでしょう。とても気になります)
この容赦のなさが、私には何より恐ろしかったです。
「罪を犯したことのない人だけが罪びとに石を投げてよい」とイエスは言ったのじゃないの?
なぜ許さん?
一章ごとに一編の詩。
詩の前にまず内容が書いてあって、全体像を念頭に置きながら詩を読み進めます。
その後には詳しい訳注。
何行目の○○について、一編につき20~30ほどの注。
それが34章。
あちらを読んだりこちらを確認したりと、思いのほか時間のかかる読書でした。
ダンテが付けたタイトルは『喜劇』
後の人たちはこれを『神聖喜劇』と呼びました。
日本語タイトルの『神曲』は、森鷗外がつけたらしいです。
キリスト教にほぼ初めて触れたであろう明治の文人たちは、この作品のどこに心を打たれたのでしょう。
作品の文学的な部分なのか、信教の厳しさなのか。
私はこの本を読んで、どうせ落ちるなら仏教の地獄に落ちたいものだと思いました。
とりあえず蜘蛛には親切にしておきます。
そして、糸が切れそうになっても皆を励ましながら、心をひとつにして極楽をめざそうと思います。←お釈迦さま、その際はよろしくお願いします
Posted by ブクログ
なんかもっと深遠な、とてつもない哲学が語られるのかと思っていたが、何のことはない、上方落語にもある地獄めぐりの物語だ。それに付け加えるものがあるとすれば、ふんだんに登場する実在の人物たち。彼らの生前の所業を断罪するその手際が当時の人々の目からすればジャーナリスティックに映ったのかもしれない。
ただ、ディティールの表現は確かに秀逸。蛇が人間に、人間が蛇になる描写など、さしずめSF映画のようにビジュアルに訴えかける。想像力をかきたてる描写は圧倒的。
Posted by ブクログ
左手の堤へ鬼たちは向かったが
出かける前にみな自分たちの隊長に向かって
合図にしたでべえをして見せた。
すると隊長の方は尻からラッパをぷっと鳴らした。
時代を超えて読まれる名著中の名著。お堅いのかと思いきや、放屁場面が出てきた…。ルネッサンスの時期に、キリスト教の世界がどのように思われていたかがよくわかる本。口語訳である上に、背景が注に書かれているので分かりやすい。地獄、煉獄、天国編があるのだが、登場人物が実話や神話に基づいているのに驚いた。つまり、ダンテが地獄に落としたいと思っていた人は見事に地獄でお会いすることになる。マホメットはキリスト教を信じていたが、そこから分裂してイスラム教を作ったなど、古代の常識や慣習を知ることができるのも魅力の一つ。相当の知識がないと読み砕けないので、博学になってから読むのでも遅くはないと思った。
Posted by ブクログ
ダンテ『神曲』地獄編,河出書房,2008(初版1966)
再読(2009/8/12)。基本的にはウェリギリウスに導かれて、ダンテが地獄を旅する話である(ちょっと『西遊記』みたいだ)。
ダンテ(1265-1321)はフィレンツェに生まれ、法王党として政治にかかわり、1302年、故郷を永久追放された。『神曲』は1300年頃の設定で書かれており、ダンテの敵が地獄で手ひどく罰せられ、大便のなかでのたうちまわっていたり、自分の首を提灯のようにさげて彷徨っていたりする。師匠がじつは男色の罪を犯していて、引かれていく途中だったり、亡者が地獄の鬼(悪魔?)に鞭打たれていたり、貪欲な亡者がぐるぐる回って、ぶつかって罵りあったりと、地獄はまあそんな所である。冷たい雨が降ったり、火の粉が絶えず降ってきたり、空気がくさっていたり、ときどき、ケルベロスだのミノスだのミノタウロスなどの怪物や、巨人がでてきて、悪態をついたり、予言をしたりする。キリスト教徒じゃなかったホメロスは辺獄(リンボ)の片隅で淋しくしている。マホメットやアリーは二つに裂けている。キリスト教を分離させた者に応報の罰らしい。
たぶん、現代の映画なんかで消費しつくされたイメージだからだろうか、偉大な作品ではあるんだろうが、内村鑑三のように身の毛がよだつこともなく、こんな所かと読んでいる。地獄編が面白くないのは、ダンテが敵をいじわるく痛めつけているからもあるけど、そこには人間の「生活」がないからだと思う。ちなみに地獄でも、派手に痛めつけられている「主人公」は大悪人で、凡人は地獄に落ちても脇役である。悪人としては、恋に身を忘れた者から、偽金作り、裏切り者までたくさんいて、みな因果応報の罰をうけている。貪欲なものは生前自分がサイフにつめこんだように、地獄では自分が穴に詰め込まれていて、足だけでていたりする。
ウェルギリウスとダンテは地獄を底まで下りていき、地球の重力があつまるところで、悪魔大王(ルシファーとかベルゼブルとよばれる)をみる。大王はキリストを裏切ったユダと、カエサルを殺したブルータスとカシウスを三つの首でかみ砕いている。彼らは悪魔大王の毛をつたって、南半球にでていくのであった。
「神曲」の「神」は形容詞で、「神のごとき」の意味で、後に冠せられた。もともとの名称は「コンメーディア」とのこと、「ハッピーエンドの話」の意味だったが、のちに転じて、「喜劇」の意味になった。「光も黙る」とか「年老いた裁縫師が針に糸を通すような目つき」とか、うまいなと思う比喩はある。
『神曲』はイスラム圏では悪魔の著らしい。平川祐弘(『マテオ・リッチ伝』の著者)による注釈は詳細、カーライルやブルクハルト、正宗白鳥や内村鑑三、与謝野晶子などの意見を事細かく、引いてくれている。訳としてもよみやすい。『神曲』はその後の地獄のイメージなどに影響を与えた作品で、中国に宣教したイエズス会士などの頭にもあった作品だろうと思う。