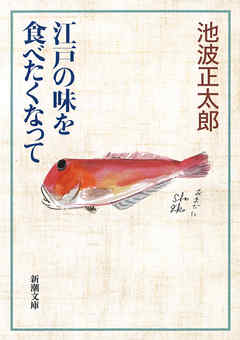感情タグBEST3
江戸の味を食べたくなって
池波正太郎さんの小説よりも「美食家」としてのエッセーが大好きです。特にこの書籍は決して高価ではなく庶民的な食材の(とても懐かしいものばかり)文書、しかも池波先生の人を引き付ける筆致であっという間に、一気に読んでしまいました。
最近はこういう名文家が少なくなって寂しいが霧です。
Posted by ブクログ
過日、書生だった佐藤隆介さんが亡き師を思い、味を再確認するエッセイを書かれた本を読んだ。
これは、池波正太郎氏がエッセイを書き、まとめたものです。
第一部 味の歳時記
タイトル通り、一月から十二月までの、旬のものを扱ってまとめたもの。読みながら、その料理を思い描き、口中に唾が出る。
第二部 江戸の味、東京の粋
食を通しての書く著名人との対談をまとめたもの。
作家の山口瞳氏との対談は、考えさせられるものがある。122ページの、池波氏の言葉が忘れられない。
第三部 パリで見つけた江戸の味
パリへ取材を兼ねた旅行でのあれこれ。同行者や、パリ在住の日本人写真家とのやりとりが楽しい。中でも、写真家が紹介してくれた酒場〔B・O・F〕のことが多く語られる。
老亭主と奥さんとで切り盛りする酒場を、池波氏は『まるで、むかしの東京の下町になったような』と表現する。それほど、気に入ってしまい、パリ滞在中に四度ほど訪れている。
最後に、この酒場をモチーフにした短編小説と絶筆小説が掲載されている。愛していた酒場〔B・O・F〕は、読んだものに強い印象を残してしまう。
この酒場名は『忘れられたる佳きフランス』というような意味だと、作中に書かれているのもまた、印象深い。
Posted by ブクログ
この本に限らず、池波さんの食に関するエッセイを愛読しています。池波さんの「おいしい」の基準が好きで好きで……。ただ単に味が好みってだけじゃなく、料理人さんの考え方・お店の人たちの人柄・お店が背負ってきた歴史すべてひっくるめて好きだから、「おいしい」。『鬼平犯科帳』の食事シーンが活き活きしてる理由がわかります。
Posted by ブクログ
本当は『鬼平犯科帳』とかメジャーな作品から攻めなきゃダメなんだろうけど、タイトルの茶目っ気ぶりにしてやられた。
一番にお金をかけるべきは食だという考えにシフトしつつある。お金があればまずは美味いものでも食いに行くというのが理想だけど、写真にでも残さない限り食べたものの記憶は簡単に残ってくれないのが現状。最近食べたなかで一番美味しかったものですら即座に出てこない…
その点池波さんの食の記憶は味も思い出も鮮明で、話だけで空腹になってくる。鮮明なのは時代的なものもあると思うけど、食べるとは本来噛み締めることなんだと実感した。
プロの料理人との対談は勉強になるし食べるということへの教訓にもなる。
それにしても偏食気味な幼少期から、のちにメディアが注目するレベルの食通にまでなったきっかけが太平洋戦争なのは意外というか、皮肉というか。
後半はエッセイや短編小説がパラパラと。
全体的に好きなものを寄せ集めた仕上がりで、前に聞いたエピソードが2−3回再登場することも。
小説はご自身の体験を思いっきりベースにされていた。代表作とも言える時代小説群は悲しきかな読んだことがないけど、何だか景色が心に沁み渡りもっと読んでいたくなる。
「死ぬために食べる」
佐藤隆介氏が綴ったあとがきで知った池波さんのその理念と自分が感じた「食べる=噛みしめる」がリンクしたように思えた。
自分は恥ずべき食べ方をしていないか。
今一度胸に手を当てて考えると、「そんなんじゃいけねぇよ」って声がこだました。
Posted by ブクログ
果たして本書のタイトルが相応であったかは疑問であるが、久しぶりに池波氏の文章を楽しんだ。味の歳時記では、江戸から東京へと引き継がれ、そして今は味わえないような食材の話も交えて四季が語られる妙味。第二部の対談では江戸っ子の会話の雰囲気を堪能。第三部ではフランスが舞台となっていたが、エッセイ、語り下ろし、小説と同じ素材を使い回したような構成だったが、これも絶筆を盛り上げんがための趣向なのだろう。
Posted by ブクログ
池波正太郎の食に関するエッセイ集。いきつけのお店に行く心境や、その食事の描写は心に響くと言うか、胃が刺激されると言うか。自分も季節の旬のものをめでてみるのもいいなぁと、かなり刺激を受けました。
食べ物で四季を感じる、いまの社会では薄れてしまった感覚ですが、自分で実践してみるのも一興だと思える一冊でした。
Posted by ブクログ
この一冊は「味の歳時記」、「江戸の味、東京の粋」、「パリで見つけた江戸の味」の三部で作られている。「人は死ぬために食べている。しかも明日が最後の日ではないという保証はない。だから、今日の一食一飲が大事」という池波氏の死生感が本の根底に。
歳時記に書かれている「小鍋立て」今や我が家の冬の定番です。豆腐、油揚げ、大根、浅蜊、今晩は何にしましょうか?
Posted by ブクログ
「昔は食べものと季節が、ぬきさしならぬものになっていた」との言葉にハッとする。
旬の食材を年中 食べられる時代になったけど、そのせいで旬の食材を味わう楽しみがなくなってしまった。
昭和時代の方が、旬の食材を味わう楽しみと豊かさがあったとは、なんたる皮肉。
Posted by ブクログ
『グレーテルのかまど』で紹介されてて、ずっと気になっていた。日本の味とフランスの味が紹介されている。どちらも失われた、もしくは失われそうになっている風景なのだなぁ。古きよき時代というもの。
Posted by ブクログ
随筆集ですが、いろいろ混じっています。好きな方はどうぞ。って感じですが、結構焼きまわしのがありますが、作者さんが、なくなっていますので、仕方ないかと。
個人的には底本ほしいんですが、高価だし、それよりも見かけない。う~ん、ちょくちょく検索しているんですけどね。
Posted by ブクログ
グ、グルメレポート!なんて美味しそうなんだ!小鍋だてとかたまらないです。
私のような現代人は、戦前というとろくな食べ物なかっただろうし今と全然違ったんだろうな、と思いがちですが、そんなことないんですよね。池波さんは戦前の東京で普通に枝豆をツマミにビール飲んだりしている。今と全く変わらない。
というか若いうちから金使って遊んでます、池波さん。その最たるは吉原!戦前が青春だと最後の吉原を知ってる世代なんですねぇ…。
Posted by ブクログ
最近池波正太郎のエッセイを読むようになった。若い頃に学べなかった作法や考え方がすごく納得がいく。先達の言う事は聞いておくものだとしみじみうなずく事しきり。
Posted by ブクログ
食エッセイとフランス旅行記。山口瞳や職人さんとの対談が面白い。
「芸者遊びは駄目だ、直接の金のやり取りがあるから。その点、吉原はいい、置屋を通すから遊女との間に金が入らない」なんていう台詞読んでると、江戸のイナセとか遊びっていうのが現代では成り立たないのがよく分かるは。