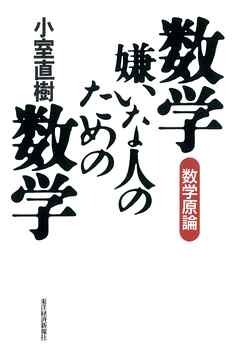感情タグBEST3
Posted by ブクログ
ボクが初めて読んだ小室さんの本。依頼、小室ファン。
タイトルに"数学"をうたっていながら、読後に得たのは新しい社会的見地。世界の見え方が本当に変わった。
Posted by ブクログ
数学とは神の論理なり
数学と近代経済の関係をものすごく簡単に書いてあります。
ものすごく難しい事をものすごくわかったような気分にさせてくれます。
Posted by ブクログ
本書を購入したのがいつ頃か覚えていないが、長らく本棚に並んでいたものを読んだ。
1932年生まれの著者が東京大学で法学の博士号を取得したのは1974年だが、もともとは京都大学理学部数学科を卒業している。その後、大阪大学大学院で経済学を学び、ハーバード大学では心理学と社会学を学んだ。帰国後の1963年に東京大学大学院法学政治学研究科に進み、1967年から「小室ゼミ」を開催していた。1970年に経済史の大家・大塚久雄について学んだ後、上記博士号を取得する、という経歴だ。
万般を修めた小室直樹の著書は、その広汎な知識と「小室節」で、縦横無尽に語るところに特徴がある。
本書では前半の「論理は神との論争から生まれた」の件が斬新で、目から鱗の内容であった。後半の経済学との絡みは私の知識不足でイマイチ理解ができなかったのが悔しい。経済学の基礎を学んだ上で、再読したい。
Posted by ブクログ
最近機械学習関連で数学を学んでいるが、著者である小室氏がその数学についてどんな論を展開するのか、興味があって手に取った本。
結果、すごくタメになった。
通常の数学本には数式がかならず出てくる。
著者は物理学や数学を大学で学ばれているので、そういう本にも出来たはず。しかし、この本では数式はほぼ出てこない。
なぜ、数学が西洋(宗教)から生まれたのか、ここまで発展したのか、などが簡易な文章で語られている。1つ1つの論はそれほど詳細ではないけれど、神との対話で生まれた(形式)論理学が、数学を理解する上での要諦だということは腑に落ちた。たしかに需要だ。
日本の数学教育では、命題や同一律・矛盾律・排中律、対偶・逆・裏、必要条件・十分条件などの論理に関してはほぼ時間を割かない。自分も勉強した記憶がほぼない。良く考えれば、なぜ高校数学の授業で命題とかをやってたのか不思議だったのだが、この本読んでその理由がはっきりとわかった。むしろ、数式を覚えるより、この論理を覚えた方が社会に出たとき数倍役に立つ。数学を学ぶと論理的思考が身に付くのも、結局この形式論理学の基礎を数学を通して無意識に学んでいるからなんだろう。
また、西洋と東洋の論理の違い、そして日本の論理がさらに異なることなども興味深い。宗教的バックボーンが薄い上に、仏教の空思想がなぜか好きな日本人に、西洋の論理が根付かないのはたしかに納得できる。玉虫色が好きだもんね、日本人って。要するに矛盾してるってだけなんだが。。
空思想から数字のゼロが生まれたのかな?
西洋の数学にゼロを混ぜると、色々と矛盾が出てくるもんな。分母がゼロだと分数も崩壊するし。
なお、後半に書かれていた資本主義や経済学の話は、小室氏の別の本と内容が被っていたので、ここではあまり触れないことにする。
物理学・数学・経済学・法学・政治学・社会学など、本当に幅広い学問を学ばれた著者だからこそ書ける本。まさに「数学原論」。専門知に埋没して勘違いしているその辺の学者には絶対書けない。
こういう知的探究心を持って幅広い学問を学んでいる人って、少しずつ少なくなってきている気がする。最近の所謂括弧付き「学者」って本当に信用できないし。。
著者がご存命のうちに、直接学びたかった・・本当にそう思います。
Posted by ブクログ
元々私も「数学嫌い」の一人である。本書は数学に興味を持つきっかけの一冊である。数理論理学すなわち形式論理学の分野を扱っているため数式もほぼ登場しない。数学知識は不要だが、史学や哲学といった文系的素養は要求される。背理法や対偶が原論の範疇かという気がしないでもないが内容は面白い。
小室氏は数多くの「原論シリーズ(?)」を出版しているが、本書も思想としては左寄りでやや過激、些か偏ってる感は否めない。それゆえ読んでいて極端で面白いともいえる。本書で述べられる「絶対的唯一神との対話」という概念理解が出来るかが論理学のポイントだろう。神視点からの演繹的証明と、聖書視点での帰納的証明の不完全性の指摘などはなかなか興味深い。
中等・高等での数学教育は、具体性ある算数教育から急に、抽象的な数式や公式へ移行するため興味を失いやすい。私がそうであった。本書のような尖った人間臭さがわかったほうが、多少回り道になったとしても数学に興味を持てると思うが、どうだろう。
Posted by ブクログ
数学嫌いな自分ではあるが、その原因は数学に対する根本的な理解がかけていたからだと思う。個人的な経験談ではあるが、大学に入るまで数学の重要性や意義を誰も教えてくれることがなかった。特に高校数学においては基本的な公式、定理をとりあえず覚えてから論理展開を行うというのが一般的なやり方であるが、そもそもなぜいきなり前置きもなしに公式を覚えさせられるのかという疑問が常にあった。もちろん数学に限らず、基本的事項はとりあえず覚えるということはいずれにせよ必要ではあるものの、それらがなぜ重要でどのような意義があるのかという理由はもっと厳密に私達の思考と連関があるように思われる。本書は数学を一神教、論理学、歴史という例を持ちながら数学的概念の日常例、思考の規則、そして数学の普遍性といった出来事を面白く解説している。
「ゆとり教育」の弊害として再び教科書のページが再び増量されている。このこと自体に問題はないのだけれども、単純にやることを増やすだけでは余計に学問離れが促進するだけであるように思われる。そもそも、学問の面白さを伝達する知的好奇心の育成こそが学業におけるもっとも重要なテーマであり、それを養うことによって主体的な探究的な勉強を独創的な見地から行うことができるのである。教科書の付録にでも本書の内容のような本質的な事柄が書かれていれば、学問をする意義というものが早いうちからわかってもらえるのではないだろうか。
Posted by ブクログ
本書のタイトルに「数学」とあるが、いわゆる数学の専門書ではない。数学の基盤となっている思考方法が社会とどのように関わっているかを説いている。著者は社会科学系学者の小室直樹氏。哲学、宗教、法律、経済と幅広い領域にわたって数学との関わりを解説している。数式はほとんど出てこないし、数式を解説することが本書の主眼ではないのでタイトルにあるように数学が嫌いな人にとっても読みやすいだろう。一方で、いわゆる理系の人にとっては本書で述べられている数学的素養は当たり前のことのように感じるかもしれない。しかし、数学的思考と社会との関わりという視点は新鮮に映るだろう。その意味で本書は数学嫌いな人よりも学校教育で数学が得意だった人こそ読者にふさわしいだろう。
Posted by ブクログ
うーん、私も数学は大っ嫌いだし興味もないのですが、小室直樹氏の著作なので、つい魔が差して買ってしまいました(苦笑)。
ただ、数式などはほとんど出てこないので、なんとか読めるかもしれません(自爆)。
評価は小室氏の本というだけで最低でも4はつけちゃいます(笑)。
目次
1 数学の論理の源泉―古代宗教から生まれた数学の論理
2 数学は何のために学ぶのか―論理とは神への論争の技術なり
3 数学と近代資本主義―数学の論理から資本主義は育った
4 証明の技術―背理法・帰納法・必要十分条件・対偶の徹底解明
5 数学と経済学―経済理論を貫く数学の論理
Posted by ブクログ
「数学」がタイトルにつくが数学的な内容はほとんど出てこない。数学と論理学、宗教学、経済学などとの関係や矛盾、必要条件、十分条件、証明などの話が例えや歴史的な経緯を踏まえて解説してある。著者特有の表現もあるため、そこは好き嫌いが分かれるかもしれない。
Posted by ブクログ
必要条件、十分条件を理解している人間は意外と少ない。これがわかるだけでも本書には価値があるといえるだろう。
猫は哺乳類である。というとき哺乳類であることは猫であることの必要条件であり、猫であるとこは哺乳類であることの十分条件である。わかってしまえば簡単でこれだけのことであるが、わかってない人間にはわからないのである。
また矛盾律、同一律、排中律についても解説。
Posted by ブクログ
内容的に特に真新しいものがあるわけではなく、数学入門書と位置付けられる。それよりも気になるのは、数学原論を説明するにあたって行っている筆者の論理展開の方法である。全体を通して、筆者の「自分勝手な思い込み=事実に即しない」と「自分に都合の良い強引な論理展開=論理の破綻」で貫かれており、論理を語っている本の著者と思えないことは言うに及ばず、学者としての資質さえ疑いたくなってしまう。結論は学問として既に(著者ではなく)先人が築いて来た内容なので問題はないのすが・・・。小室氏の本は初めて読んだのですが、大きく失望しました。左翼活動家や左翼学者と言われる人たちは自分の考え方を相手に理解してもらうのに論理立てて説明するという手法を取らず、とにかく押し付ける、思いこませるという手法をとりますが、手法だけを取り上げれば非常に似ていると言えます。
Posted by ブクログ
「数学とは神の論理なり」・・・神がいるかいないか、という命題を解くために発達したというくだり、これを先に知っていればもっと数学が好きになれたのに、と思う。こういうことを数学の先生は隠して教えているのだろうか?それとも知らずに教えてるのか?
ある問題に対し、「かならず正しい答えがある」と信じて解明の努力をするのが西洋人。「答えが無いということもある」と達観して細かなプロセスを踏まないのが東洋人。単純だがバイタリティがある西洋と、賢いが泥臭さや生命力の薄い東洋といった構図か?
数学だけでは所詮世の中すべてのことなど解明できない。けれど、「所詮・・・」という考え方が好奇心の芽を摘んでしまってはもったいない。数学に興味を持つことで、細かなプロセスへの興味と興奮を生むことこそ醍醐味だと思う。