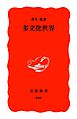青木保のレビュー一覧
-
異文化理解とは何か自分の中で定義ができるきっかけとなる本だった。
異文化理解とは、自分の殻から出て、その国に染まること。そして自分の国をみて理解すること。
それぞれの国には必ず急所のような部分があり、そこを押さえることでスムーズな理解ができる。(タイ→仏教など)Posted by ブクログ -
前に読んだ「異文化理解」に続く、文化人類学者・青木保先生の一冊。こちらでは、ジョセフ・ナイのソフトパワー論に触発されて「文化は力」と唱えていますが、刊行から15年たとうとしている日本では相変わらず理解されない思考なのが残念です。Posted by ブクログ
-
ちょい堅苦しいタイトルの割りに、わかりやすい内容!新書のイメージ変わりました。
「その文化の価値とか象徴を理解するところが異文化理解のひとつの大きな困難であると同時に、大きな課題なのです。」Posted by ブクログ -
これも大学の授業のテキストだったわけですが、面白かったのでいまだに読み返しています。体験出家エピソードと、そこから感じる国民性とか、現地の人たちの宗教のとらえ方がいいなあ。Posted by ブクログ
-
文化人類学ってのがそうなのかもなんだけど、なんだかフワフワしてよく掴みにくい本だった。けど文化都市とかブランド国家とか東アジアと南アジアの発展の仕方の違いって指摘はハッとさせる物がある。Posted by ブクログ